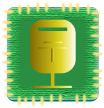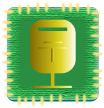
迷惑メール メッセージが届きました
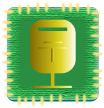
迷惑メール メッセージが届きました
![]() 1
1 ![]()
それは帰省することに躊躇する程短い、正月休みのことだった。 「うわー、さむっ!」 緩くウェーブする黒髪に、ラテン風味の堀の深い顔、人を小馬鹿にするような表情ばかりを浮かべる彼、渡辺庵(わたなべいおり)は、似合わない半纏を着て炬燵に潜った。買い換えたばかりのスマートホンで確認すれば、氷点下七度という数字が表示された。これは外に出たくない、と寝転んだままスマホをいじる。惰性で、友人と共有でアカウントを持つ画像投稿サイトを開くと、メッセージが届いていた。 『突然すみません。メラーと申します。テントさんの水車のある風景画に一目惚れしました。どうしたらあのような絵が描けるのか教えていただけますか? よろしくお願いします。返信待っています』 テントとは庵たちのアカウント名だ。某国立の美術科に通う大学二回生である彼と友人は、授業の合間に描いた趣味の絵をここに投稿していた。 庵の眉間にシワが寄る。送られてきたメッセージは、丁寧な文体だが、質問の仕方が回答者に頼りすぎていると感じた。例えるなら、勉強を教えろ言ってきた友人に、分からないところが分からないと言われるような腹立たしさだ。 しかし庵は逡巡した後キーボードを叩き出す。遊び感覚で相手をしてやろうと思った。ここは自分だけのアカウントではないし、友人だったらどう返すかを考えながら、最近嵌っている紳士キャラで返事をすることにした。 『こんにちは、テントです。私の絵を気に入って下さり、光栄に思います。メラーさんはデッサンの勉強をされたことはお有りですか? 私は基本に忠実に、そこにあるものを見たまま描いただけですので、申し訳ありませんが特別にお教えできる技術はございません』 『すみません、デッサンの経験はありません。基本とは何ですか? また、特別なことをしていないと言われますが、テントさんの絵には他の人にないものを感じました』 子どもか、と思う。デッサンの仕方なんて、ネットや図書館にいくらでも転がっている。自分で調べればすぐに出てくるものを、ネットで見知っただけの自分に聞いてくるなんて。 いや、もしかしたら本当に子どもなのかもしれない。小学生がケータイを持っている時代だ。誰でも簡単にネットにアクセスできる。 『デッサンの基本はよく見ることです。描いていてうまくいかない、と感じる時は、どこに違和感があるのかを考えて、目の前の風景と異なる点を根気強く修正していきます。ですので、もう直すところがない、というところまで描けた絵は、自分の目に映った光景そのものということになります。枚数を重ねることで目が鍛えられてよりリアルな絵が描けるようになります。 私の絵に特別なものを感じてくださったということですが、絵描きはそれぞれ特別で、例えデッサンであっても全く同じ絵を描ける人はいません。目で見たものを描くと言っても、その目と、風景を捉える心と、指先を動かす筋肉が違うのだから当然です。私の絵は参考程度に捉えて欲しいですね。 基本的なことならここで聞くよりインターネットや図書館で調べる方が早いと思います。ネラーさんが学生なら、学校の先生に聞くのも良いと思いますよ。こうしてメールでやり取りするより、実際に指導していただいたほうが分かりやすいでしょうし』 『丁寧にありがとうございます。絵の勉強をすることは大変ですか? またテントさんはご自身のサイトを持っていますが、サイトはどうやって作りますか? いろいろ質問してしまってすみません』 庵は文章に違和を感じて首を捻った。質問ばかりすることを謝りながら、こちらの意見に返しがない。しかもその質問も、庵が答える必要があるのか、と言いたくなるようなものだ。サイトの作り方だって、調べればいくらでも出てくるだろう。今さっき送ったメッサージを読んでいるのか疑いたくなった。 『絵の勉強を大変と感じるかどうかはその人次第だと思います。学校の勉強にも好き嫌いはあるでしょう? メラーさんは意欲があるので大変ではないと思います。 サイトはHTMLで作りました。私が参考にした作り方のサイトを紹介します。http…』 『サイトのつくり方、ハッキリ言いますがよくわかりません(笑)お願いなのですが、テントさんが代わりに作ってくれませんか? それから、テントさんの絵は油彩ですよね? 僕も油絵具を使える環境にあるのですが、どうすれば上手に描けるのかわかりません。よかったら教えてください』 ああ、これは向こうも遊んでいるな、と確信する。 いきなり砕けた文章でこちらを煽ってきているし、庵が紹介したサイトはHTMLについて手順を追って丁寧に説明しているのだから分からない筈がない。その上今度は油絵の上手い描き方を教えろ? 自分で調べろという話だ。 『そちらと素材のやりとりや意見を交換することが難しいので、私がサイトを作ることはできません。期待に添えずにすみません。また、油絵具はただの画材です。うまく描こうというなら、まず基礎の画力を上げるしかありません。メールで細かく伝えるのはなかなか難しいですね、やはり図書館で絵の教材などを探すのがいいと思いますよ』 『そうですね。いろいろ頑張ってみます。僕は学生なので、美術室に行ってみようと思います。それから、質問なのですが、HTMLとはなんですか?』 おちょくってんのか。しかし、ここまでくるとキレたら負けな気がする。俺には最後まで紳士でいることが求められているのだ。 『いままでに貼ったサイトは見ていただけましたか? HTMLは「ハイパーテキストのための、文書に目印を付ける方法を定めた文法上の約束」と訳せます。サイトを作るのに一番基本的なものです。「HTMLってなに?」で検索をかければすぐに調べられます。 メラーさんは自由にパソコンでネットが使えませんか? ケータイサイトしか見られないなら難しいかもしれません』 『へぇ、そうなんですか(笑)ネットは自由に使えます。でも学生なので良く分からないですね(笑)』 『質問するにも、先に調べておいて、どうしても分からないことがあったら質問するという形を取ったほうが効率的です。「数学教えて」「どこがわからないの?」「どこがわからないかわからない」では、何を教えるべきかわかりませんが、具体的な問題を持ってきていただいて、「この問題がわからない。途中式はこうして解いたけれど、どこが間違っているのか」と聞かれれば答えようがあります。 ネット社会では調べれば分かることを聞くなという意味で、よく「ググレカス」という言葉が使われます。メラーさんはネットの初心者のようなので、これから気を付けてください。黒歴史になってしまいますよ。 ホームページの作り方や絵の描き方だけでなく、知りたいことは検索してみてください。私がメラーさんとのメッセージのやり取りでお教えしたことは、ネットで得られる知識が大半だった筈です。 学生だから分からない、と投げてしまわないで、学生だからこそ勉強しましょう? 手間はかかるかもしれませんが、難しいことではないので出来ることをやってみてください。応援しています』 メッセージを送り、しばらく待ってもメラーからの返信はない。庵は「勝ったな」と鼻を鳴らし、餅でも焼くかとようやく炬燵から抜け出した。 ****** 「あれ、庵。今日は早いな。休み明けで張り切っちゃったの?」 ガッガッと机を引きずる音のする洋画室に入ると、例のアカウントを共有する友人である坂本優斗(さかもとゆうと)が、机やイーゼルを授業の配置に整えていた。 洋画室は、絵画系の授業をする教室だが、洋画専攻の一二回生が個人制作をする作業室でもある。机もイーゼルも連休の間に教室のあちこちに散らばっていた。 「お前いつも一人で準備してんの?」 「いつもはもう二三人居るんだけど、庵とは逆に正月ボケかな」 言いつつ、優斗は机を班ごとに固めていく。不満も言わずに自分ばかり動く彼を、お人好しだと思った。 「自分の場所だけやれば良いだろ」 庵は自分の班の準備を終えて適当に寛いだ。 「嫌だよ、準備ができてないと先生の機嫌が悪くなるじゃない。気まずいのは勘弁だな」 ああそうか、と納得した。遅れてやってくる学友のせいで労働をしなければいけない彼が、不満を感じていない理由が分かった。強制されたわけではないから他の生徒に不満が無い、自分の学習環境を整えるためにしていることだから不満が無いのか。 彼は、人のための行動を自分のための行動に置き換えることが上手い。彼を見ていると、この世に理不尽なことなんてないのではないかと思えてくる。人生楽しそうだ。まあ、見習うかどうかは別だが。 庵はそんなことを考えて、あのメッセージのことを思い出した。 「なあ、お前サイト見た?」 「ああ、なんかたくさんやり取りしてたよな。庵だったらすぐに『ググレカス』って言いそうなのに」 「お前だったらどうしてた?」 「あの口調よりはもっと砕けた感じで同じように返したと思うよ。もしかしたら頭が緩いだけで本当にファンかも知れないし。てか、エセ紳士庵、胡散臭すぎ」 クスクス笑う優斗にニヤリと笑う。庵は彼ならどう返すかをシュミレーションしながら返信していた訳だが、正解だったようだ。しかしこれには続きがある。 「昨日以降は見たか?」 「見てないけど、返事きたの?」 「どうやらメラーさんには胡散臭く思われなかったようで」 そう言いながらスマホを見せると、優斗は「あれまぁ」とメガネの奥の目を瞬いた。 『メラーです。ご無沙汰しています。先日の失礼をお詫びいたします。それで、本当によければなんですけど、直接会っていただくことはできないでしょうか』 『どうしてでしょう?』 『テントさんになら、僕の悩みを相談できると思いました……』 『悩み、ですか……。それはメールではできませんか?』 会話はそこで途切れている。 「返事無いね」 「お前ならどうする?」 「会うと言ったら庵は会うの?」 「会う」 その答えを聞いて優斗はスマホを受け取り、返事を打ち出す。 『すみません、悩みなんてはっきりしないものをメールで相談するのは難しいかもしれませんね。プロフィールのとおり、私は都内に住んでいるのですが、メラーさんがこちらを訪ねてくると考えて宜しいのでしょうか?』 「こんな感じ」 優斗が確認を求める。 「でも会う理由は?」 庵は質問しながらも彼の返答に当たりを付けていた。お人よしの彼は「友達が増えるから」とか「人に親切にすると気持ちが良いから」とか、そんなことを考えているのだろうと。しかし、 「恩を売るところから始める、自分より下位の知り合いが出来るよ! やったね庵!」 反ってきた予想外の言葉に、戸惑った庵は彼から目を逸らした。 「……俺に合わせて捻くれた答出しただろ」 「結果は同じだよ」 優斗は笑いながら、逸らされた目に視線を合わせようと、庵の顔を覗き込む。庵は楽しそうな彼の額を叩いて、送信ボタンを押した。
2
女顔は生れつきだった。でも、一緒に遊ぶのは男の子だったし、体を動かすことも大好きで、性格だって女らしいところなんて無いはずで、女みたいだなんて言われたこともなかった。 だからそれは本当に突然で…… ある日学校に行くと、ざわついていた教室がシンと静まった。普段そんなに仲良くしているわけでもない騒がしいタイプの男子生徒が「おはよう、今日も可愛い顔してるね。元気~?」なんて馬鹿にするような口調で話しかけてきた。 前日まで仲の良かった友人はやけに大人しく周りの様子を窺っていて、話しかけると慌てた様子で目を逸らされた。 「女顔」「ぶりっこ」「気持ち悪い」と顔を見てはクスクス笑われて、反発すれば「べつにお前のことじゃないし」「自意識過剰なんじゃないの」とさらに笑われた。 どうすることもできなくて、我慢しているうちにいつしか顔を上げられなくなった。「急に大人しくなっちゃって」「暗い」「不気味」と原因になった人たちにこそこそ言われて、頑張って顔を上げたら「元気すぎる」「自分がクラスの中心だとでも思ってるんじゃないの」と嘲笑された。 一つ一つの行動を否定されて、いつしか身動きができなくなって…… 休みがちになると、担任の先生が気にしてくれて、目立つ生徒を注意してくれたけど、すこしふざけただけだと茶化すばかりで「甘えてる」「贔屓だ」と陰口のレパートリーが増えただけだった。証拠がないから先生も強く言うことができなくて、その様子を見るうちに、自分自身、これは虐めじゃないのかもしれないと思い始めた。 でも、そうしたら自分は生徒のひとりひとりにただ嫌われていることになる。自分の何がいけないのか、指摘されても直せなくて、顔や性格、仕草の一つ一つを笑われたら、人前に出るのが怖くなった。 学校に行けなくなって、家から出られなくなって。両親は学校なんて行かなくても良いと言ってくれたけど、不安そうだった。行かなくても良いなんて言っても、行ったほうが良いに決まってる。 無差別に迷惑メールを送り始めたのは、行き場のない気持ちを晴らすためだったと思う。いっそあからさまに嫌われる行動をすれば、自分の思った通りの返しが来る。嫌がらせメールを送って罵倒が返ってくることに安心してしまっていた。 「メラーさんですか?」 「はい。テントさんですよね?」 待ち合わせた駅前のファーストフード店。声を掛けてきた男性はメールの印象通りシックな装いに穏やかな笑みを浮かべる、紳士のような人だった。 「メールでは失礼しました。改めまして、メラーです。本名は永井柳と申します」 「はい、初めまして。私は渡辺庵です」 彼は恐縮する柳に微笑むと、ダークブラウンのPコートを畳んで端に置く。 「考えて話す人なんですね。そんなに緊張なさらないでください」 「あ、いえ。これは」 一連の動作をじっと目で追っていた柳は慌てて視線をテーブルの紙コップに移した。 「こんなにかっこいい人だと思っていなかったから、思わず見惚れてしまいました」 正直にそう漏らすと、彼はややたれ目がちな瞳を細め、薄い唇に弧を描く。 しっかりした体躯の長身に、日本人離れした堀の深い顔立ち。端々に育ちの良さを感じさせる仕草も相まって、物語の世界から抜け出してきたかのように見えた。 「永井さんも、整った顔立ちをされていると思いますよ」 「あ、ありがとうございます」 長い袖から指を出して、コップに触れることで緊張を紛らわす。すごく久しぶりにまともに褒められた。 「それで、相談があるということですが」 促されてつばを飲み込む。 「はい。あの……」 口に出した言葉が震える。ここに来るまで何度も整理したはずなのに、話そうとすると頭がぐちゃぐちゃになってしまった。 「……実は僕、もう半年も学校に通えていないんです……」 「――そういうわけで、憂さ晴らしにあんなメールを送ってしまいました」 話を聞き終えた庵は心中で「ふん」と鼻で一笑した。 柳を一目見たときから、味方も敵も多そうだと感じていた。可愛いというよりは美人という言葉の似合う女顔に、大きすぎる白いカーデガンにうす茶色のダッフルコート。自分の容姿を理解して、自分だから許される可愛さを演出している。素直に可愛いと評する者もいれば「あざとい」「うざい」と感じる者もいるだろう。庵は後者だ。 萌え袖から指先だけを出して、両手でコップを持つ。疑問を提示するときに小首を傾げる。苦しい心情を話すときに緩く握った拳で口元を隠す。初対面の同性に対して「見惚れる」だなんて歯の浮くような台詞を言える。俗にいう小悪魔を具現化したようなやつだと思った。弱そうに見せているが本当の彼は相当強かだろう。大人しくしていれば許される、弱ければ助けてもらえる、と計算して動いている。 「顔を上げてください。べつに怒っていませんから」 しかし庵は考えたことを全て隠して、俯いてしまった彼にふわりと微笑んでそう言った。向こうが腹芸をしているなら、こちらも腹芸で返そうというものだ。 「僕は、どうすれば良いでしょうか……?」 ゆっくり顔を上げた柳に縋るような視線を向けられて、喉の奥がむず痒くなった。また質問か、と。 「メラーさんはおいくつですか?」 「あ、僕はオレンジジュースなので砂糖は……」 「年齢の話です」 「す、すみません! 十七歳、高校二年です」 「なるほど」 庵が高校二年のこの時期は修学旅行の計画を練り始めていた。友人と呼べる人がいないのは辛いだろう。でも、それはこいつが逃げていたからだ。 「そういう人たちは、何にでも文句をつけてくるんですよ。あなたが悪いわけじゃない。きっと誰でも良かったんです。標的にする理由なんて、ちょっと目立つからとか、そんな些細なことで良いんです。何をするにしても良いと思う人、悪いと思う人はいます。確固たる正解がないのなら、貴方の正しいと思うことをすれば良いんですよ」 穏やかな口調で諭すと、柳の目が不安げに瞬いた。 「あの、それは学校に行けということでしょうか?」 その通りだ。 彼は頭が悪くない。何重もオブラートに包んだ言葉の真意を受け取れる。しかし、 「メラーさん自身で答えが出ているなら、私の意見は意見として頭の隅にでも置いていただければ結構ですが」 不満気に顔を曇らせる彼に言い添える。最初から、彼の中で答えは出ているのだろう。せっかく意見を出しても響かない。 「……私に決めてもらうのではいけませんよ」 こんな相談なんてしても彼が変わろうとしなければ意味が無い、と庵は言い渡した。 ****** 「と、いう流れだった。けど」 庵は回想を終えると、ふーっと長く重い溜息を吐いた。 「あいつマジでぶりっこだよ」と。 庵たちの通う大学では講義が行われる教室がいくつかの棟に分かれており、敷地の中央に全課共有のA・B・C棟、それらを囲むように美術棟や化学棟などの専門の棟が建ち並んでいる。 全国でも有数の生徒数を誇る大学だが、休憩スペースの席数は少なく、庵と優斗は昼を挟んで講義のある日は専ら、美術等に近いC棟の空き教室で昼食をとっていた。 「完全にいじめっ子の味方じゃないか。というか庵そんな服持ってたの? お前こそブリッコじゃん!」 サラサラ落ちてくる横髪を耳に掛けながら優斗が笑う。前髪をゴムで纏めていたり、髪の手入れを怠らなかったりする彼だが、庵は彼に対してはぶりっ子だと思ったことは無い。 なんだろうな、柳の場合は第一印象が悪かったからなのだろうか。 「ボロ雑巾みたいなモッズコートとジーンズの紳士はいないだろ」 どうせ汚れるからと頓着しない庵の普段着は、着古してボロボロのヨレヨレで、絵の具やオイルの匂いが染みついている。制作時にツナギでも着れば良いのだろうが、嵩張るし夏は暑いしで、庵はあれがあまり好きではなかった。 「そう言えばどうして紳士なのにファーストフードなの?」 「先払いだから。絶対奢らない」 「あー、ね」 「というかあいつ、メールの時から質問だらけでムズムズするんだよ。ちったぁ自分で考えろ! って」 「メールは悪戯だったんだから、おいておこうよ。……それに、考えても抜け出せなかったんじゃないかな」 生協でセール品だったツナパンを齧って二の腕を擦る庵に、インスタントのスープを啜っていた優斗が苦笑いする。 「庵は、メラーを学校に行かせたいと思ってるよな」 「思ってるさ。だって、世の中もっとひどい環境の中でも毎日登校している生徒はたくさんいるだろ。イジメの証拠がないから何もできないって言うけど、証拠が残る余地もないことしかされてねぇんだよ」 あいつを見ていると甘えている気がして、どうしても思考が攻撃的になった。 優斗は「うん」と頷くと、言葉を探すようにゆっくり続ける。 「学校の先生は、学校に来なくて良いなんて言えないよね。いじめを解決できないから、出て行ってくれって、追い出すようなものだもの。親だって、学校に通えるようになるのが一番良いと思ってる。でも、メラーの気持ちを考えて、行かなくても良い、と言ってくれる。 そうしたら、メラーの思考は、『行かなくちゃいけない。でも行けない』でずっとループして答えは出ない。罪悪感と劣等感ばかりが募っていく」 「……でも俺は一人しかいないから、意見は一つしかない。俺は、あいつは逃げているだけだと思う」 「せやな。そしたら僕も意見を出したら良いね」 そう言うと、優斗はスマホを取り出して操作した。 「俺はさ、心の強さは身体能力とか学力と一緒で個性だと思うんだよな。庵が強くてメラーが弱いってのは変えようがないわけ。強い方に弱い方が合わせるのは無理なんだよ。そりゃ、みんな強くなれれば良いけどさ。立ち向かえない人はいるよ」 柳に対する自分の対応を責められている気がして、庵は気まずさにストローを摘んで潰す。優斗は単に意見を言っているだけだ。罪悪感を覚えさせているのは優斗ではなく、言葉を受け取った庵の方だろう。そう考えると、柳のために自分を責めたという事実にもやっとした。 「あいつはそんな弱そうに見えなかったけどな」 「そっか。俺は会ってないから分からないんだね」 ちっと舌を鳴らして言うと、優斗がきゅっと肩を縮める。庵が優斗の発言に腹を立てたと思ったのだろう。別にそんなことはないのに。 庵が優斗の横髪に指を通して梳くと、彼はご機嫌取りのスキンシップにふにゃりと笑って、操作していたスマホの画面を見せてきた。 『テントです。今日はメラーさんとお会いできて嬉しかったです。学校に行くかどうか、決めるのは自身でないといけないと言いましたが、選択しやすいように、私の意見を纏めてみました。 もちろんできるなら高校に通い続けるのが良いと思います。でも、どうしても無理なら逃げても良いと思います。しかし、逃げる場合はその後のことを考えてください。 転校するのか、高校中退の経歴で就職先を探すのか、高校卒業資格を取るのか、大学は受けるのか、一生ご両親に寄生し続けるのか。他にも選択肢があるかもしれません。 どれも簡単なことではありませんが、自身にとってどれが良い選択なのかを考えてみてください』 そこに打ち出されていたのは、優斗の意見だったけれど、庵が譲れない「自分で考えろ」という気持ちもちゃんとあった。 「どうだろうか」 「良いんでなかろうか」 「紳士口調もOK?」 「まぁOK」 納得して送信する。 「これ、最初からお前が相談に乗るべきだったんじゃないか」 「それはないよ。俺は相談者の擁護一択だもの。もし彼が『親の金と生活保護で生きていきます』とか言い出しても、『はい、そうですか』ですませる自信があるし。それに、メラーは庵に言われたことをよく考えたと思うよ」 優斗は早口でそう言うと、むっと唇を尖らせる。 「おまえなんかイライラしてないか」 「……イジメる側は逃げられるのに、イジメられる側は逃げ道塞がれるなんて、ムカつくじゃん!」 バンバンと机を叩いてコミカルな動作で苛立ちを表現する彼に、庵は今更かと思う。どうも優斗は負の感情を自覚するのに時間がかかるらしい。というか、 「……やっぱ俺の意見に反対なんじゃねぇか」 「庵にじゃないもん、世の中のルールにだもん」 「しょぼんとするなよ」 ぷくっと膨れた頬をつまむ。庇護欲を刺激されて構いたくなるような仕草はこういうことをいうのだろう。柳もこいつみたいにすれば良いのに、と、二人のどこが違うのかを明確に分からないまま、庵は漠然とそう思った。
3
「お前、まともな格好すると腹が立つ程見栄えがするな。爆発四散して召されれば良いのに」 柳に会ったあと、その服装のまま登校した庵に、C棟仲間の川島が物騒な言葉を吐いた。緩い七三にメガネをかけた彼は、真面目そうな髪型とメガネと服装で清楚系女子をつろうと目論んでいるが、中身がアレなのですぐに逃げられる残念な男だ。庵は似非紳士を気取るために、彼から服を借りていた。 「お前の服、良い感じに胡散臭くて好評だぞ」 「誰にだよ」 「どこぞの女子だよ」 「はあ!? 俺の服なのに!? 俺はその服を着て褒められたことがないのに!?」 声を荒げる川島の肩を彼の友人がポン、と叩く。 「しゃーない。顔だよ顔」 「神は俺を見捨てるのかぁぁああ!!」 大げさなリアクションを取る彼に、その落ち着きのなさがモテない原因なんじゃないかと庵は思うが、面白いので指摘はしない。 「そんなことより」 庵は頭を抱えて絶望する川島に数学のテキストを開いて見せた。 C棟空き教室は、美術科の研究室から近いため、美術科の学生が多いが、もちろん他の学科の学生もいる。しかし、優斗が持ち前のコミュニケーション能力を発揮した結果、男はもれなく友人同士、女もつられて友人同士になっていた。 「というかだな、これとか直接教える方が良いと思うんだけど」 シャーペンでメモ書きつつ川島が言う。 このテキストは、大学を受験したいという柳の話をした庵に、数学科の川島が勧めたテキストだ。早いことに、始まりのメールから半年以上が過ぎて、外では煩く蝉が鳴いている。 優斗のメールを見た柳は、高校を中退し、高校卒業資格試験を受けて大学に進むことを決めた。相談や勉強の質問と称して、彼は月に二回ほどのペースで庵に会いたいと持ちかけてくる。その度庵は紳士キャラに磨きをかけた。 「笑わないでいてくれる?」 「何に」 庵は、普段人を小馬鹿にするように歪な弧を描いている口元に、春風を感じるような穏やかな笑みを浮かべ、半トーン上げた済まし声で丁寧に言葉を紡ぐ。 「先日永井さんに質問された問題ですが、友人に協力をいただいて解いてきました。メモを見ながら解説致しますね」 「……サブイボ立った」 川島はふるりと身を震わせて、剥き出しの二の腕をさすった。 「まあ、分かりやすく質問してくれてるから、別に良いんだけども」 彼の言うとおり、柳の質問は庵に注意されたからか、とても答えやすい。 「でも、どうしてキャラ作りだなんて、そんな面倒なまねをしてるんだ?」 「……ネカマ感覚で始めたらやめ時を失った」 一拍おいて答えた庵に、川島が「馬鹿だなぁ」と呆れて言った。 「永井さんは、塾や家庭教師は利用なさらないんですか?」 ファーストフード店で待ち合わせた柳に庵が尋ねると、彼は視線を彷徨わせてか細い声を絞り出した。 「その、……迷惑だったでしょうか」 言いにくそうに指先で口元を覆い、儚げに目を伏せる。その言い方は卑怯だ。 弱さを演出することで迷惑だという答えを封じ、質問で返すことで答えをうやむやにして、会話の流れを都合の良い方に運ぼうとする。 「いえ、もしかして人に会うのが辛のかと心配になりました」 「いえ、そんなことは……」 柳は驚いたように目を瞬いて言葉を切る。ついで、ほっと息を吐くと眉を下げて微笑んだ。 「すみません、多分そうです。渡部さんと会話をしている時が一番落ち着くことができます。勉強も、渡辺さんに見ていただくと気を張らない分すっと頭に入っていくんです」 「それは嬉しいですね」 濁されたが、彼は実際庵以外の誰かに指導を受けているはずだ。そうでなければ彼の学力の向上を説明できない。どうして隠してまで無理に会おうとしてくるのか。庵には彼が何を考えているのか分からない。キャラづくりについて、川島には「やめ時を失った」などと言ったが、本当は柳を信用していないだけだった。 柳に接するとき、庵はいつかのルールを設けている。隙を見せない・本音を見せない・興味を持たない・個人情報を明かさない。 別れる時は念を入れて彼を最寄駅まで送り、自分の後をついてこないよう見届けた。午後に会うときは帰宅にかかる時間を聞いて、遅くならないうちにと嘯いて、絶対に終電に間に合うように帰らせた。そんな上面だけの関係が続いていた。 ****** 画面に、その数字の羅列を見つけると、体の奥からじわりと喜びが溢れ出した。 庵と出会ってから一年と三ヶ月。インターネットで大学合格を確認した柳は、誰に報告するより先に庵宛のメールを作成する。指先が震えて、何度も誤字を修正して、短い文章に長い時間をかけてやっと送信した。 『第一志望の大学に合格しました。その報告と、それから…… 渡辺さんに直接会って伝えたいことがあります。また、お会いできますか?』 柳の生活は彼と出会ってから一変した。学校を辞めたい、でも大学に行きたい、と自分で選択肢をもって両親に話したとき「良かった」と嬉し泣きされて、柳まで泣きそうになった。目標が見つかると、やるべきことが見えてきて、灰色だった世界が色を取り戻した。生きていて良いのだと思うことができた。 柳がここまで来られたのは彼のおかげだ。きっかけもそうだが、その後も、彼に呆れられないように、彼に見合う人間になれるように、と彼を理由に努力を続けられた。 彼と会うのはいつも駅前のファーストフード店で、彼に釣り合わないその選択に、自分に合わせてくれているのだと思うと嬉しかった。彼はいつも最後まで話を聞いて、柳の言葉が足りないところも丁寧に聞き出して、理解してから意見をくれた。帰りの時間を気にして、必ず改札まで送り届けてくれた。彼はいつも車道側を歩いて、人ごみでも庇ってくれた。 少し前、そんな好意が嬉しくて、とびきりの笑顔で「渡辺さんは本当に優しんですね」と気持ちを伝えると、彼は「永井さんは人を褒めることがお上手ですね」とはにかんだ。彼と一緒にいると、自分が特別な人間になったように感じられた。 「渡辺さん……」 柳は悩ましげな吐息を漏らして、左胸をそっと押さえる。彼を思うと胸が切なく高鳴った。 自分が更正できたのも、大学合格を両親や心配してくれた高校時代の恩師に報告できるのも彼のおかげだ。感謝が積もって、一人では抱えきれないくらい、彼への気持ちが育ってしまった。 大学合格の報告メールの後、都合を合わせたその日。どうしても他に人の居ない場所で話がしたいのだと、柳は初めて庵をファーストフード店から連れ出した。 告白に最適な場所は事前に調べてきた。駅に程近い場所にある公園の、桜並木の奥。遊歩道ともボートのある池とも離れたその場所は、都会の中にあるのにとても静かだった。 「恋愛対象として、渡辺さんのことを好きになってしまいました」 泣いても笑ってもこれが区切り。拒絶されるかもしれない。でも、気持ちを抱えたまま平気な顔をして過ごすことはもう出来ない。柳は声が震えてしまわないように、彼にきちんと伝わるように、その瞳を見つめて想いを伝えた。 「好きだとか……」 庵はぎゅっと瞳を閉じると、低い声で呟く。 ああ、これがエンディングかと遊びの終わりに納得し、同時に苛立った。 「好きだなんて、そんな簡単に言ったらいけませんよ」 「簡単になんて言ってません! 僕はあなたのおかげでここまでこれた。もし、あなたと出会えていなかったら、僕はずっと部屋に引きこもっていたかもしれない。あなたが、真摯に僕の話を聞いてくれたから……」 「私があなたに何を見せましたか」 庵は拳を握って高ぶる気持ちを押し殺す。こいつは何も分かってない、と。 「人には良い部分も悪い部分もある。全部合わせてその人ができている。表に出ているところは綺麗かも知れない。でも、表に出るまでに複雑な思考がある。それを全てひっくるめて、それでも愛しいと感じたことがありますか」 見せなかったのは自分だ。でも、それに気づかずに告白したのは彼だ。それを浅はかだと感じた。 「すみません。感情的になりすぎました」 庵は額を抑えて俯いた。 柳は、ただショックだった。彼に否定的なことを言われたのは初めてで、混乱する。 彼は僕の気持ちが本物じゃないと言いたいのか? でも、彼の気持ちは? 彼の伝えたいことが分からない。でも、分からないで終わらせたら駄目だと思った。「考えろ」と何度も彼に教わったから。 「渡辺さんは、すごく優しく接してくれるけど、頭の中ではそれだけじゃない、たくさんのことを考えていて、僕に対してふさわしい対応を選んでいる。だから僕は渡辺さんの全てを知っているわけじゃないけれど、全てを受け入れて欲しい。――ということですか?」 柳は探りながらそう返した。 「……そう聞こえましたか?」 庵は長い溜息を吐く。的外れにも程があった。 「ハズレです。あなたの気持ちは受け取れないということです。私でなくても、あなたが求めれば助けてくれる人はいくらでもいたでしょう。例えば、私と一緒に魅力的な女性があなたの相談にのっていたら、きっとあなたは女性の方を好きになった」 「そんな、もしものことなんて分かりません」 柳は緊張に冷えた指先を胸の前で握った。 男同士だとか、そんな葛藤はずいぶん前に乗り越えていた。そんなことでは割り切れないほど、たくさんのものを彼からもらったのだ。柳を救ってくれたのは、「もしも」居たかもしれない女性ではなく、目の前の彼だ。 しかし、柳が「もしも」を否定しても、庵は首を横に振った。 「すみません、今のは私の気持ちではなく、あなたの気持ちを納得させるために言いました。誤解させたなら謝ります。『もしも』など関係なく、私の答えはNOです。永井さんに恋愛感情は持てません」 最終宣告だった。 「……分かりました。はっきり言ってくれて、ありがとうございます」 庵への想いで、伝えたいことはまだたくさんあった。でも、柳は気がついてしまった。彼が初めて感情を乱し、柳を否定した理由に。 (あなたにも、好きな人がいるんですね。裏も表も好きになる程素敵な人が……) 「今まで、ありがとうございました。今日は一人で帰ります……っ」 一人になりたい、とそう言えば、庵は何も言わずに去っていった。 「あぁ、あぁ……っ!」 言葉にならない気持ちが溢れ出す。柳は蹲り、地面に向かって嗚咽を漏らした。
4
庵は美術棟入口前の段差に腰を下ろしてシャボン玉を吹かした。 この春、庵は三回生に進級した。一二回生に比べ必修の講義が少なくなり、制作に掛けられる時間が増えた。時間に囚われずに制作に没頭することができるのは、嬉しいが、ふと区切りをつけた時に感じる疲労は大きい。 シャボンとその向こうに見える空の青さに、疲れた心と目が癒されていく。シャボン玉遊びは、初めは優斗が遊んでいるのを見つけた。その時は、また変わったことを始めたな、と思ったのだが、そのうち他の生徒がしているのを見るようになり、いつの間にか大学生協にシャボンセットが置かれるようになっていた。 「あの、すみません。道をお尋ねしたいのですが」 空に向かっては弧を描いて落ちていく虹色を眺めていた庵に、背後から声が掛かる。聞き覚えのある声にハッとして振り返えった庵は、その人物に目を見開いた。 「「え」」 二人の声が重なる。一か月前に終りを言い渡した少年――柳がそこに居た。 「道って」 「あ、はい。C棟に行きたいんですけど」 「それならここから見える隣の建物がC101で、それ以外の教室はその奥の三回建ての建物……です」 口調を迷った結果、取ってつけたような敬語になってしまったが、あれこれ考えるのも面倒くさいと舌を鳴らして言葉を崩した。 「毎年新入生が道に迷う。分かりづらいのは講師も分かってるから、迷ったと言えば大丈夫だろ」 もう講義は始まっている時間だ。庵は戸惑いと焦りに、講義棟と庵の間で瞳を彷徨わせる彼の背中を押した。柳が慌てて走り去る。庵はその背中を見送って、「まじか」と呟いた。 「どうした柳ちゃん、そんな難しい顔して」 「川島さん」 行間休み、隣で授業を受けていた学科の先輩に声をかけられて、柳は慌てて表情を繕った。 「大丈夫です。すこし考え事をしていただけなので」 「そう? ところで次の講義の場所は大丈夫?」 「嫌だな、からかわないでくださいよ」 彼とは、新入生歓迎のイベントで知り合った。一二回生中心のイベントに現れた三回生の彼に、第一声で「男じゃないか! 美人が居ると言うから来たのに!」と叫ばれたのは衝撃だったが、それでも彼は柳を気に入ったのか、履修計画を立てる際などいろいろ助けてくれた。 柳は川島と分かれると、ポケットの中のケータイを弄んで思考した。……彼は、本当に渡辺さんだったのだろうか、と。 ヨレた服を着て地べたに座りシャボン玉を吹く彼の後ろ姿は、紳士然とした渡辺さんとは違った意味で浮世離れして見えた。服の汚れから美術科だと分かり、やはり芸術家には変わった人が居るのだな、と思ったのだが、まさか振り返った顔が渡辺さんと瓜二つで、驚いた。でも、その顔に浮かぶ表情と自分に接する態度は全く違うから、似ているだけの別人なのかもしれない。 そんなことを考えていると、手の中のケータイが震えた。画像投稿サイトにメールが届いたという通知だ。 『今日は何限終わりだ? 話がある』 至極簡潔なそれは、テントからの初めてのお誘いメールだった。 講義室前まで迎えに来た庵は、大学敷地内にある広場まで柳を連れ出した。 (ここ、大学の敷地だったんだ) 柳は気づいて落胆する。 水車のあるその場所は、柳が惹かれた彼の絵の風景と同じ場所だった。しかし、水車の下を流れる川は自然のものではなく、すぐそばの水道から流れる人口のもので、どこまでも続くと思われた森は、すこし視線を上げればさっきまでいた講義棟が見える程に小さい。彼の絵の中ではとても素敵な場所に思えたのに、実物はとてもチープだった。 「単刀直入に言うが」 「はい」 景色に気を遣っていた柳は、話しだした庵に身構える。 「俺は今までお前で遊んでいただけだ。鬱憤を晴らすために利用した。俺は紳士じゃない」 「な、え……。なんですか、それ」 突然のカムアウトをうまく飲み込めなかった。 「お前のことはいけ好かないやつだと思ってた。あんなメールを送ってきたかと思えば、手のひらを返したように俺の顔色を窺って、作ったような仕草ばかりする。正直信用ならなかった。だから、お前がどうなろうとどうでも良かった。高校中退しただとか、大学に合格しただとか聞いても、現実味が無かった。そもそも、会いたいと言われたあとの了承のメールも、逃げる選択支のメールも、考えたのは俺じゃない」 ――私があなたに何を見せましたか あの言葉は、こういうことだったのか。でもどうして、 「どうして今になって、そんなことを言うんですか」 「同じ構内にいればすれ違うこともあるだろう。それでお前が声をかけてきても、俺はもうキャラを作らない。面倒なことになる前にはっきり言っておきたかった」 「それだけ、ですか……?」 「ああ」 柳は、涼しげな庵の顔を見て泣きたい気持ちになった。言われなければ気がつかないでいられたのに、と。 「じゃあ、俺戻るから。時間取らせて悪かったな」 庵はそう言いおくと、地面を睨みつける柳に使いかけのシャボンセットを握らせて立ちさった。 ****** 「あれ、シャボンセットじゃん」 柳のカバンから覗いたそれに、気がついた川島が言った。 授業の中には、隔年開講のものや、取りたい資格によって他の授業と被ってしまい、対象学年の間に受けられないものがある。そういった授業は次年度に繰り越して受けることができるため、一年対象の授業でも上級生がとっていたりする。彼もその例で、いくつかの講義を柳と共にしていた。 「貰ったんです」 答えた柳に、川島は「どこぞの美術科みたいだな」と返した。 「はい、美術科の方に頂きました」 流行っているのだろうか? と不思議に思いながら柳は答える。 「あ、そうなんだ。じゃあC棟行く? 昼休みだし丁度いいだろ」 「C棟?」 「うちの大学の食堂、生徒数に対して席が少なかっただろ? みんなサークルとか自分とこの研究室とか空き教室で食べてるんだよ。それで、C棟の空き教室は美術科が主に使ってるんだけど、俺もよく行くんだ」 「え、でも僕は」 「まあまあ、美術科連中癖はあるけど悪い奴じゃないし、他の学科もちらほら居るから」 「いや、そうじゃなくて」 川島は渋る柳の腕を引いて半ば強引にC棟に向かった。 連れて行かれた空き教室は講義等角の日当たりの良い場所で、中に入ると先に居た人たちが口々に「おつかれ」と声を掛けてきた。川島がそれらに「おつかれ」と返す。柳も習おうとするが、視界に映った人物に、ひうっと喉がしまって言葉にならなかった。 「柳」 「わ、渡辺さん」 身構える柳に遠慮なく近づいてくる庵に「なに、知り合い?」と川島が尋ねと、庵は柳を指して言った。 「川島、そいつメラー」 「え!?」 その発言に川島が声を上げる。 「柳、お前に数学教えてたのこいつだぞ」 「え!?」 続いた言葉に今度は柳が声を上げる。そうしていると「メラーだって」「実物見れた」「ようこそ我が校に」と上級生たちに声をかけられて、思わぬ歓迎ムードに柳は戸惑いを隠せなかった。 シャボン玉は気持ちを切り替えるために使えるのだと、C棟で聞いた柳は早速三限で授業が終わる水曜日に、人気のない場所を探した。シャボン玉を人前で吹くのに抵抗があったからだが、人が全く居ない場所はなかなか無く、結局水車のあるあの広場の前まで来てしまった。この場所に良い思い出は無いが、寧ろ都合が良いかも知れない。 柳が、気分を変えたい、と思ったのは庵のせいだ。自分は彼に裏切られたのだと思ったし、彼は自分を嫌っているのだと思ったのに、彼は何事もなかったかのように接してきた。そんな彼の意図が解らなくて混乱して、自分は彼への気持ちを消化できていないのに、と思うと辛かった。 「あれ、柳君だ」 広場に踏み入ると、地面にイーゼルを突き立てて色鉛筆でデッサンをしていた先客が声を掛けてきた。長い前髪をちょんまげに結び、赤メガネをかけた彼は、C棟で顔見知りになった川島と庵の友人だ。いつもビビットカラーの水玉模様のパーカーを羽織っている彼を、柳は勝手に美術科でもサブカルチャー方面の人だろうと思っていたから意外だった。 「えっと、坂本さん?」 「そうだよ、坂本優斗だよ」 彼はそれだけ言うと画面に向き直る。特に柳に構うつもりはないらしいので、柳も気にせずに彼の視界に入らない場所でシャボン玉を吹いた。 「あ」 そうしたら、加減を間違えたシャボン玉が、優斗の元まで飛んでいってしまった。 「シャボン玉するの?」 「あ、すみません」 「どうせなら画面に入るようにやってよ! 綺麗だから!」 邪魔にされるかと思いきやの発言に、柳は雑草の茂った地面を鬱陶しいと感じながら場所を移す。どこでシャボンを飛ばしても、広場はどこにでもあるただの広場だった。 「あの、渡辺さんってどういう人なんですか?」 なんの感慨も得られないままシャボン液を使い果たした柳は、思い切って優斗に尋ねた。 「どうって?」 「えっと、坂本さんは渡辺さんと僕のやり取りを知っているんですよね?」 「ああ、本当はあんなでびっくりしたでしょ?」 「はい。それもありますけど……」 「庵に何か言われたの?」 どこまで言っても良いものかと、柳は言葉を濁らせたが、優斗に促されて続ける。 「遊びで相手してただけだけだとか、僕のことは信用してなかったとか。僕の思っていた渡辺さんって何だったんだろうと思うと……」 そこまで言って、こんな話をしたら庵の友人である優斗は気を悪くするのではないかと思い、顔色を伺う。しかし彼はそんな様子もなく 「別に良くない?」 とキョトンと首をかしげて言った。 「どういう意味ですか?」 聞き返すと、彼は考えるように唸って続ける。 「だって、永井君も庵も何も悪い目に遭ってないし、どっちも何も悪いことしてないよ。柳君を信用して相談に乗ったのでも、信用しないで相談にのったのでも、結局行動は同じってこと。今だって柳君は庵のおかげでこうしてここに居るでしょ?」 優斗の言い分に柳は、それで良いのか、と納得しかけて首を振る。確かに彼の言うことは正しいのかもしれないが、自分が言いたいのはそういう事ではなかった。だって、 「それでも、僕の知っている渡辺さんは居ないんです」 自分が恋した人は実在しなかったのだ。その事実がこの心を蝕んでいるのだと、今気がついた。 「……庵って面倒見良いよね?」 沈黙の後、優斗が口を開く。考えてみれば、彼は面倒見が良かったかもしれない。大学で初めて会った時も、道を教えてくれた上に、焦る柳を励ましてくれた。 「柳君の知ってる紳士な庵も面倒見良かったでしょ? 態度はだいぶ違うけど、柳君が知ってる庵も本当の庵と変わらないよ」 柳ははっと瞳を輝かせ、白い頬を淡く染める。彼の言葉に視界が開ける気がした。 優斗は喜色をあらわにする柳に微笑むと、一度タッチを描き足して鉛筆を置き、描き上がったそれを柳に見せた。 何度も色で描いて消してを繰り返した痕の見えるそれは、泥臭さの中に温かみのある、そんな絵だった。 「すごい。この場所なのに、ここじゃないみたいだ」 「えへへ、ありがとう」 「渡辺さんのとは全然違うんですね」 彼の絵は油彩だったが、もっとシャープで清廉された美しさがあった。画材だけ見ると反対になりそうなものなのに、不思議だ。 「絵は描き手の心を映すんだよ。俺は見えたものを全部描いちゃう。それも、やりたい放題のぐちゃぐちゃに。でもなんとか形に収めようとしてる。対して、庵は欲しいと思ったものをとっても綺麗に描いて、要らないと判断したものはすっぱり切り捨てる」 柳はその言葉にまたはっとして、広場を見渡した。 「僕、始めてここに来たとき、がっかりしたんです。絵ではとっても素敵だったのに、って。でも違いました」 瞳を閉じて、素敵だと感じたあの絵を今見た景色に思い重ねる。 彼の絵が綺麗なのは、彼の心が潔いいから。彼が自分を切り捨てないでいるのは、きっと自分を惜しいと感じているから。 「今は、本物の景色を見られて良かった、って思います」 それがどんな意味でも嬉しかった。
迷惑メール メッセージが届きました<完>