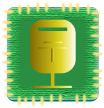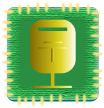
迷惑メール 交錯する想い
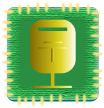
迷惑メール 交錯する想い
![]() 1
1 ![]()
居慣れないベッドの隅で膝を抱えた柳は、悶々とシャワーの音を聞ながら、自分の置かれた状況を必死で整理しようとしていた。 (……どうしてこんなことになってしまったのか……) 家具が少ない割に雑多なもので賑やかに見えるここは、前にも一度来たことのある庵の家である。もちろん今シャワーを浴びているのも彼だ。ちなみに先に身を清めた柳は前回同様ダボダボの服を借りて彼を待っている。 (まさか、さっきの今でことに及ぶなんてことはないよな? ないよね!?) ぐるぐると迷走していると、引き戸が音を立てて開いた。そんな些細な物音にびくっと肩を縮めて反応した柳は、部屋に入ってきた庵の姿を見てさらにぎょっと心臓を縮める。 「な、なんで裸なんですかぁ!?」 「どうせすぐ脱ぐからだけど」 タオルを腰に引っ掛けただけの姿で脱衣所から出てきた彼は、電気のスイッチを切って歩み寄ってくる。真っ暗で何も見えないなか、彼の気配を追っていると、ぎしりとベッドが軋んだ。「柳」 「は、はい」 肩を掴まれてびくりと震える。押し倒そうとしてくる彼に抵抗して壁に背中を寄せると、彼は顔の横に肘をついて迫ってきた。 「……力抜け」 「い、いや嘘でしょ!? いきなりこんな……」 庵は鼻先が触れ合うほど近くまで迫り、筋張った手を柳のシャツに侵入させる。 「まだ、心の準備も出来てないのに……っ」 湯上りの、暖かくしっとりした掌が、ひたりと柳の肌に触れる。 「心臓ばっくばくだな」 「~~っ!」 胸に手を当てて指摘する庵の肩を、柳は掌で思い切り叩いた。 「って、ちょ!」 しかし庵は無表情のまま、その手を取って柳を引きずり倒し、マウントを取る。 「目、慣れてきたな」 柳を見下ろして目を眇める彼の顔が、柳からも見えた。 筋肉質な身体、風呂上がりのしっとりした素肌。生乾きの髪が彼の頬や首筋に吸い付くように散らばって、匂い立つような色気を放つ。 「これでも我慢したんだ。前に泊めた時だって」 庵は柳の綺麗に浮き出た鎖骨から首を指先でなぞり、耳たぶをつまむと、反った顎の下に歯を立てる。 「食っちまいたかった」 ――ゾクゾクッ 柳の背筋に、寒気に似た衝動が走る。雄々しく光る眼光に捉えられて、いっそひと思いにヤられてしまいたいと思ってしまった。 「あ、ん……っ」 無骨な指が、柳の鎖骨から胸、腹を撫でていく。指を追うように唇が触れていく。否応なく高まる熱に、柳は腰をもぞりと動かした。庵は彼のズボンを引き下ろしながら、ヒクヒク震える太ももを一撫でして、臍に舌をねじ込ませる。 「ひぁっ!」 「柳」 庵は筋肉を収縮させて逃げた腰から手を離し、高く声を上げた彼を抱きしめた。高ぶった中心を柳の太股に押し当てると、彼は驚いて目を見開く。 「い、庵さ……ひゃんっ!」 胸の突起をいじられて、柳は再び声を上げた。頭の芯がもやもやするような初めての感覚に困惑する。 「ここ、感じるのか」 「ちがっ、だって、庵さんが……っ」 気持ち良いとかではなく、男の自分のペタンコなそこを、庵がわざわざ触れているという事実に居た堪れなくて、逃げ出したい気持ちになった。 「やだ、やめてください……っ、そんなところ触っても面白くないでしょ!?」 枕を掴んで訴えるのに構わず、庵はニヤリと笑って、柳のそこを指先で抓って引っ張る。 「ひぁああ!?」 「お前の反応見るのスゲー興奮するけど」 「い、意地悪い……っ!」 柳は、熱い舌で乳首を押しつぶされて身をよじった。 「う、わ……っ」 「もっと色気ある声出せよ」 「だって」 舌先で擽られてビクビク震える。じゅうっと乗せられた唾液ごと吸われて思わず彼の腰に足を絡めた。 「あ、あ、あ……っ、吸わ、ないでっ」 柳は目を瞑って顔を逸らす。胸に顔を埋める彼を見ていたらおかしくなりそうだった。でも、視界が効かなくなると、そこに触れる唇や舌の濡れた粘膜の感触が生々しく伝わってきて余計にダメだ。 「い、おりさん……っ、もう……っ」 柳が庵のくせ毛に指を入れて頭を掻き抱くと、庵はがばっと身を起こしてカーテンを開け放った。煌々と降り注ぐ月光が彼の横顔を白く浮かび上がらせる。柳がその光景に息を飲んでいると、振り返った庵は柳を見下ろし、 「絶景」 と、唇の端を釣り上げた。 「へ……」 柳は状況を飲み込めずに間の抜けた声を出した。 庵の視線の先で、瞳を蕩けさせて顔を紅葉させる彼は、Tシャツをたくし上げられ、大きすぎるズボンを膝までずり下ろされて、扇情的な姿を無防備に晒している。 「し、閉めてください! やだ……っ」 やっと庵の視線の理解した柳は、慌てて身を隠そうとシャツを下ろすが、直ぐに股間を揉みしだかれて動きを止めた。 「え、うそっ、や、ぁあっ」 「これ、誰の下着だか分かるか?」 あ、あ、と甘い吐息を漏らす柳に庵が尋ねる。 「お前が俺の下着こんなに濡らしてるの、分かるか?」 「あ、ひ……っ、ごめんなさ……っ」 「良いよ。許してやる」 泣きながら謝る柳に、庵は胡散臭い柔らかな笑みを向けると、ぐにっと先端に指を押し付けた。 「ああっ! だめ、それ、だめ……っ!」 「どうしてだめ?」 手のひらを押し付けるようにして全体を擦りながら先端を爪で引っ掻くと、柳は面白いようにビクビク体を跳ねさせる。 「ひぅっ、い、いっちゃう……っ」 シーツを蹴って身悶える柳に、庵は一層にんまり口元に弧を描いて、「へー、そう」と手の動きを早めた。 「ぅ、ぁあ……っ!!」 柳は下着越しの彼の手になされるがまま、丸めた指先まで痙攣させて熱を放った。 庵は、肩を上下させて呼吸を整える柳の下着を下ろして、その蕾をゆるりと撫でる。 「へ、うそ」 「ちゃんと丁寧にやるから心配するな」 「そんな……っ」 庵は怯える柳に嘯いて、慎ましやかなそこにつぷっと指先を挿入した。 鳥の鳴き声とともに、緩やかに意識を浮上させた柳は、傍らの体温にぽっと頬を染めた。 「た、食べられちゃった……」 昨夜のことを思い出すと、むず痒くて恥ずかしくて、居た堪れなかった。 今は夢の中にいる彼は昨晩、口は悪いし態度も相当だったが、最後まで至極丁寧に柳を扱ってくれた。腰にも違和感はあるが切れてはいないし、痛くもない。半端でなく恥ずかしかったけど幸せだった。 「ん……」 小さく唸った庵の腕が柳を捕まえる。しなやかな腕と胸板に抱き寄せられて、柳はもごもごと唇を動かした。 (庵さん、もう、全部かっこいい……っ) 一人身悶えていると、庵は眉を寄せてまた小さく唸った。起きるのかな、とその顔を覗き込むとゆっくりと唇が開いた。 「……ゆう、と……」 その呟きに、全ての感情がさっと引いていく。柳は一言も発することができずに呆然とただ彼を見つめた。 ****** 柳と庵の距離は、付き合い始める前よりも近くなった。休日は二人で過ごすことが増え、学校にいるときでも机の影で手を繋いだりと、浮かれた恋人気分を味わった。しかし、柳はこのままじゃいけないと思い始めていた。 庵はどこに出かけても、優斗と来た時にはそこで弁当を広げて食べたのだとか、優斗とはカラオケの選曲がいつも被るだとか、彼の名前を話に出した。 初めての朝のあの寝言を、柳は深く考えないようにしていた。きっと彼はただの夢の登場人物で、寝言で名前を呼ばれたのは、たまたまなのだろうと。確かに、庵は優斗のことを好きだったと言ったが、今は自分のことを好きでいてくれているはずだと。 でも、それにしても庵は彼を気にしすぎていた。そういえば―― 「気になっていたことがあるんです」 麦茶のコップを両手で持ち、立てた膝に乗せて口に運んだ柳は、意を決して口を開いた。 「最初のころ、鬱憤を晴らすために俺の相手をしたって言ってましたよね。鬱憤って、何ですか?」 床に寝そべって寛いでいた庵が、億劫そうに顔を上げる。 「そんなこと今更聞いてどうするんだよ」 「聞きたいんです」 あの日、柳が最初に庵に告白した日、彼が想っていたのは優斗だった。他に想う人が居る彼が、柄にもなく柳を気にかけてくれたのはどうしてなのか知りたかった。 「……坂本兄弟の仲を取り持ったんだよ」 庵が苛立たしげに吐き捨てる。柳はその答えに妙に納得してしまった。 優斗さんに振られてメールに応えて、優斗さんに言われて僕に会って、優斗さんを理由に僕を振って、それなら…… 今、僕と付き合っているのは、優斗さんに振られたからってことですか?
2
柳は無機質な机に突っ伏して重い溜息を吐いた。今日、庵と優斗が連れたって校内でキャンパスを広げているのを目撃した。彼らは美術科、自分は数学科。立場の違う柳は、二人が一緒にいるとき声を掛けられないことがあった。一緒にいても、二人が話し出すとついていけなくなる時がある。庵と付き合い始めて三ヶ月が過ぎ、恋人として大学生活初めての夏休みを過ごした。その間、気が付けば自分たちだけの世界を作ってしまう庵と優斗に疎外感を感じ、自分は彼らにとって何なのだろうと、幾度となく考えた。 「どうした柳ちゃん。悩み事か?」 「川島さん……」 同じ学科の先輩に声を掛けられ、縋る視線を向ける。 「僕を川島さん家の子にしてください」 「お、お、どうした川島さんの魅力に気がついちゃったか」 「川島さん~!! 僕は非常に寂しいんです~」 唇をきゅっと引き結んだ柳は、両手を広げた彼の胸に飛び込んだ。 「あの、川島さんは庵さん達三人の関係を知っていますか?」 傷心の後輩を学生寮の自室に上げた川島は、後輩柳の言葉にカチンと笑顔のまま硬直した。 「川島さん?」 「……関係、関係か」 ベッドに腰掛けた川島を、カーペットにぺったり座りこんだ柳が見上げる。チワワのように庇護欲をそそられる悩ましげな瞳で窺われた川島は、顎に手を当てて「うーん」と唸った。 あの三人の関係を、川島は良く知っていた。それどころか、その修羅場に巻き込まれることも数知れず。だからあのグループには関わりたくなかったのだが、そんなことを今まさに相談を持かけようとしている後輩に言えるほど、彼の血は冷たくなかった。 「知ってるんですね」 「……あー、まあ」 確認されて渋々頷く。 「それで僕、庵さんとお付き合いしているんですけど」 「うぉおおぅ……っ」 予想外の言葉に変な声が出た。 「どうして優斗さんは圭斗さんなんでしょう」 「話が一気に飛んだな、おい」 川島は高速で進む話に頭を抱える。 「えーと……。弟が兄と付き合ってるってのは、お前に関係あることなの?」 「すごく関係あります」 「どうして」 「……庵さんじゃダメだったのかな、とか」 「柳ちゃんは渡辺と一緒にいるのが辛いの?」 「……少し」 「その理由が分からないから弟の意見が聞きたいってこと?」 「いえ、理由は分かってるんです」 「えー、よく分からないな」 言葉を探りながら話す柳の意図が分からず、川島は頭を掻いた。柳は何か言わなければと口をもごもごと動かしては眉を潜める。自分には言えないこともあるのだろうと、川島は深く考えることを諦めた。それに、他人のいざこざにあまり首を突っ込んでも良い事なんて無い。 「柳ちゃんの悩みを解決するために、弟がどうして兄を選んだのか知りたいってことなのかな」 「そうです」 「まあ、そう言われても俺に弟の気持ちは分からないんだけどね」 「まあ、そうですよね」 話を終わらせた川島に、柳ほっと息を吐いて緩く微笑んだ。 「でも僕、こうして川島さんと一緒にいると落ち着きます。ありがとうございます」 柳と川島の関係は、柳と庵、庵と川島には無いものだ。庵と優斗が学科での繋がりによって、柳の知らない関係を作るのと同じように、柳自身もこうして彼らの知らない関係を作っている。そう思えるだけで気持ちが楽になった。 「わー、嬉しい。でもそれ絶対渡辺の前で言わないでね」 「……嫉妬なんて、してもらえますかね」 引きつった笑みを浮かべて二の腕を摩る川島に、寂しく笑う。 柳が庵達に嫉妬したことと、同じ状況を作っているのは、心の底では彼に嫉妬して欲しい、自分を見て欲しいと思っているからに他ならない。でも、もしかしたら彼は、自分が川島や他の誰かに靡いてしまっても、何も感じてくれないかもしれない。そう考えると、この気持ちを素直に受け入れてしまうことが辛かった。 「はー、でもそうか。弟か」 川島は呟いて、壁に耳を当てた。 「よし、居る」 「え、居るって何が」 川島は戸惑う柳を引き連れて部屋を出ると、隣室の扉を叩いた。 「兄~、弟貸して~」 慌てて腕を引っ張ってくる柳にニッと笑う。 「ここ、兄の部屋だから」 「はい! 優斗君です!」 川島の言葉を飲み込む前に彼が飛び出して来たので、柳は咄嗟に川島の背中に隠れてしまった。 「お二人は仲が良いですよね」 麦茶のグラスを両手で抱えた柳は「それでそれで」と優斗の物言う視線に切り出した。 ちなみにこの麦茶、圭斗が「あいつん家と違って麦茶ぐらい出せるからな」と言って出してくれたものである。柳は優斗を意識しているが、彼も相当庵を意識している。「最近は麦茶作ってくれてますよ」と返す柳に、「オレンジジュースでも常備しようか」と舌打ち混じりに答えていたから相当だ。 「俺と圭斗? 仲良いよ」 「あの、優斗さんは圭斗さんのどんなところが好きなんですか?」 柳が麦茶から視線を外して優斗を見ると、彼は照れくさそうに眉を下げていた。彼は隣の圭斗を窺って頬を掻く。 「一番は、俺の顔色が読めないところかな」 「それ、良いところじゃないだろ」 憮然とつっこんだ圭斗に「そんなことないよ」と笑う。 「俺、教員免許取りたくて、青少年の心理学とか、カウンセリング技法の授業を受けてるんだけどさ、そういうの勉強してると思うんだよ。今この人は俺を肯定してくれているけど、それは対人関係を良好にするためのただの技術で、心の中では反対のことを思っているかもしれない、とか。普通だったらただ嬉しい、良い人だって感じる筈なのに」 優斗は忙しなく指を動かしながら続ける。 「でも、圭斗は心理学専攻だから、そういうことをたくさん勉強している筈なのに、日常に全然取り入れようとしないんだ」 「あー、何か面倒くさいんだよな」 「それに俺、直ぐに感情が顔に出るからカードゲームとかすぐ負けるのに、圭斗とは良い勝負になったりして。そういうところが好きかな!」 言い切った優斗は「あー、もう! なんか恥ずかしいな!」と膝を叩いて身悶える。 「俺はお前の全部が好き」 「それはずるいだろ!」 横から抱きついて囁く圭斗にケラケラ笑った。 「でも、庵さんだって良いと思うんです」 じゃれあう二人を前に、柳は口を開いた。 優斗は圭斗の好きなところを教えてくれたが、柳だって庵の好きなところを挙げられる。庵だって十分魅力的なのに、どうして、と。 「そうだね、庵もかっこいいよね。あのアバンギャルドな感じは憧れる」 「ただ、捻くれてるだけだろ」 「圭斗だって庵のこと好きなくせに」 「気色悪いこと言うなよ」 クスクス笑う優斗に、圭斗は眉を顰めて立ち上がる。 「どこ行くの?」 「便所」 「素直じゃないなぁ、もう」 圭斗が逃げるように部屋から出て行くと、柳と優斗の二人きりになった空間に、妙な空気が流れた。 「優斗さんは、どうして庵さんじゃダメなんですか」 沈黙を破った柳に、ようやく優斗はそういうことか、と納得する。 「いくら好きになる要素があっても恋にならなければ恋じゃないんだよ。柳くんは庵のことそういう意味で好きなんだね」 優斗の言葉に、柳はぐっと押し黙って俯いてしまった。殺風景な部屋にウィンウィンと、冷蔵庫の音がやけに大きく響く。何となく、優斗も黙ってしまうと、間もなくして帰ってきた圭斗が「何話してたんだ」と声を掛けてきた。 「今、柳くんに庵を勧められてた」 冗談めかして笑う優斗を圭斗は抱き寄せ、柳に視線を投げる。 「あのさ、永井」 名前を呼ばれた柳が顔を上げる。 「優斗は俺のだから」 柳に強い視線を向ける圭斗に、優斗は「そうだね」と微笑んだ。腰に回された腕に手を重ね、そっと撫でて宥めても、彼は力を緩めなかった。 ****** じめじめと湿気を持った鬱陶しい残暑の中、柳の悩みは解決しないまま鬱々と時間ばかりが過ぎていく。そんな中柳は、庵が優斗の話をするのはもはや癖なのだと思い始めていた。つい、名前を出してしまうほどに、彼の心の内を占めているのだろうと。 嫌なら指摘すればいいじゃないかと、他人は思うかも知れない。でも、彼は優斗の話をしながらも、柳のことを見ていてくれる。すぐ近くを自転車が通れば肩を抱いて守ってくれるし、歩幅も合わせてくれるし、柳が立ち止まれば直ぐに気づいて振り返ってくれる。口を開けばいつも酷いことしか言わない癖に、そうして柳を離してくれない。 だから、言えなかった。 『優斗さんの話ばかりするんですね』 でも彼は無意識だろうに、自分が言って直るのか分からない。直らなかった時が怖い。 『本当はまだ優斗さんのことが好きなんじゃないですか』 そうだ、と言われたらどうする。そうでなくても、口ごもられただけでも、それは肯定になるじゃないか。 『僕は優斗さんの代わりですか』 聞いてどうする。自分は代わりじゃ嫌なのか。それは嫌だ。嫌だけど、代わりでも良いとは思わないか。だって、どうせ優斗は庵のものにはならないのだから。 それに、こんなことを聞いて、彼に面倒くさいやつだと思われたくなかった。優斗の話が頻繁に出てくるだけで、他の関係は良好だ。それが、この質問一つで壊れてしまうかもしれない。 「柳、言いたいことがあるなら言え」 ぐるぐると巡る思考を、庵の言葉が遮った。 場所は庵の自室。何の予定も無い休日は、何をするでもなくこうして一緒に過ごすこともあった。 「別になんでもありません。それより、あの絵も良いですね。これも構内ですか?」 柳は努めて冷静に応えて、壁に立て掛けられた真新しい絵を指す。 「少し行ったところにある美術大学で、そこの学生と一緒に描いた。そもそもそいつは優斗の知り合いで、あの日は三人で会う予定だったんだ。でも優斗がバイトに急に呼び出されて来られなくなって、初対面同士で顔つき合わせて。そうそう、何話して良いか分からないから、結局優斗の話ばっかりしてたな」 「それは、災難でしたね」 「でも、友達増えたでしょ。なんて優斗は言うし」 「はは……」 また彼の話かと、柳が乾いた笑いを漏らすと、『ピンポーン』とレトロな呼び出し音が響いた。 「庵、どうしよう~!」 扉を開けた庵に、着の身着のままカバンも持たずにやって来た優斗が縋り付いた。 「なんだよ、また逃げてきたのかよ」 「そうだけど~!!」 「とりあえず中に入れ」 通された優斗は、机を挟んで柳の向かいで膝を抱えて座り込む。庵はてっきり彼の方に座るものかと思ったが、お茶だけ出して柳の隣に腰を下ろした。 「何があった」 「……進路で揉めた」 優斗は庵に促されてゆっくり話しだした。 「圭斗の進路は前から聞いてたんだ。院に行きたいんだって。その話を聞いた時に、俺はどうするんだって聞かれて、まだ分からないって答えた」 その話に柳は首を傾げる。 「教師になるんじゃないんですか?」 「良いなとは思うんだけど、採用厳しくて。就活も考えてるかな」 優斗は苦く笑って答えた。どこでも就職するのは大変なようだ。 「それで、もし教師になるとしても、こっちより地元の方が採用試験の倍率が低くて。もしそっちしか受からなかったら地元に戻ることになるんだけど、両方受かった場合も地元に戻るかもしれない。親兄弟が戻って来いって言ってるから」 言葉を切って溜息を吐いて続ける。 「それをどう間違えたか、俺が卒業後に地元で就職するって話が圭斗の耳に届いて……」 「それ、誤解解けば良いだけの話じゃないのか」 庵の指摘に「わー」と叫んだ。 「そうだけど~話したくないんだよ~」 「なんでだよ」 「だって、圭斗が俺を甘やかすから」 優斗がぶすっとむくれると、庵は柳の髪を梳いて頬を撫でる。 「もう少し自分で考えて、全部決めてから話したいんだ。俺は、圭斗と対等でいたいから。よく、恋人同士支えあう、とか言うじゃんか。でも、それで上手くいくのは出来る人同士に限った話で、俺みたいなやつはそんな考え方じゃ甘えるだけのダメ人間になっちゃう」 庵は片手で柳を構いつつ、もう片手でケータイを操作した。 「もしもし坂本兄?」 「って、ちょっと庵!?」 慌てて身を乗り出した優斗を無視して通話を続ける。 「弟がまた電波なこと言い出したんだけど」 「電波じゃないよ!」 『んだとてめぇ、優斗と一緒に居んのかよ、ふざけんな』 電話越しに聞こえた怒号に、庵はこちらに乗り出している優斗の頭を掴む。彼に手を離された柳は完全に蚊帳の外になってしまった。 「うわぁ。理不尽すぎて思わず弟の頭掴んだわ。てめぇがふざけんな」 『いいか、絶対優斗に手出すんじゃねぇぞ! 絶対だからな!』 「もう出してるんだって。鷲掴んでるんだって」 『首洗って待ってろよ!』 「言ってろ」 通話を終えた庵は鷲掴んだままの優斗の頭に「兄来るって」と伝える。 「自分の考えを話すのは甘えじゃないだろ」 「そうかな」 「そうだよ。まったく、変なプライドでこじらせてるなよ」 そう言って、突き放すように頭から手を離した。 「うん。ごめんね庵、ありがとう」 ふにゃっと笑う優斗に、フンと鼻を鳴らして柳の肩を抱く。そんな庵に柳は、少し嬉しいと感じる傍ら、もしかしてこれは優斗と圭斗の仲を取り持たなくてはならなくなったことに対する行き場のない感情を、自分に触れることで紛らわしているだけなのではないかと考えてしまう。彼にとって、自分は優斗の代わりであり、彼に対する想いを殺すための道具に過ぎないのではないかと。 「柳君もごめんね。突然押しかけて」 「いえ、それは大丈夫です」 圭斗が迎えに来ると、二人と一緒に柳も庵の家を出た。普段ならまだ帰る時間ではないが、今は彼といるのが辛かった。 「あの、圭斗さんは優斗さんといて不安に思うことは無いんですか?」 柳は雑談の合間に質問した。さっき、庵は優斗に『また逃げてきたのか』と聞いていた。こいうことが過去に何度かあったのだろう。 優斗はキョトンと目を瞬き、圭斗は目を鋭く光らせる。しかし、柳には二人の反応を気にかける余裕がなかった。 「優斗さんはこうやって相談しに来るのに、庵さんじゃダメなんですか?」 続けて問う柳に、やっと意図を理解した優斗は不安に瞳を揺らす。 自分のせいで、圭斗が不安に思っているかもしれない。いや、かもしれないではなく絶対そうだ。自分は彼に甘えたくないと言いつつ、無意識のうちに彼に甘えて傷つけている。こんなことでは愛想を尽かされてもしょうがない、と。 「優斗!」 じわじわと表情を曇らせる優斗を圭斗が呼ばった。 「来い」 両手を広げた彼に優斗が抱きつく。 「こいつは面倒くさいところばっかりだけどな、別れたいなんて思ったことは一度もない。優斗も、あいつじゃなくて俺を選んだ。そうだよな」 圭斗が柳を見据えて宣言すると、優斗は圭斗の胸に顔を押し付けたまま頷いた。 「永井」 冷たい熱を持った声に呼ばれて、柳はびくりと肩を震わせる。 「俺は今お前を嫌いになった」 圭斗の言葉に、優斗がショックを受けて目を見開く。柳は足元が崩れる錯覚をした。
3
しとしとと秋雨の降る早朝、優斗は住宅街を横切る小川沿いの道を歩いていた。カーテンを開けたまま眠り、朝日に起こされて朝の空気を吸いながら散歩に出るのが優斗の日課である。じじ臭いと言われることもあるが、澄んだ空気を肺いっぱいに吸い込むと、それだけで滅入った気持ちが軽くなる気がした。 しばらく歩いていると、川に掛かる小さな橋の上で、手すりに肘を掛けて川を眺めている人が居た。犬を連れているわけでもない、若い男だ。朝に散歩に出ている人は、優斗の他にも居たが、元より中高年層や犬のリードを引いている人が多いため、今日のような雨の日に人と出会うのは珍しかった。 「あっ」 優斗が男の横を通り過ぎようとすると、彼が短く声を上げた。 「え、毒島……?」 その顔を確かめて、思わず口走る。 「永井の学校の人っスよね」 ばっちり目を合わせてくる彼に、今更他人の振りはできなかった。 雨の中で立ち話もなんだろうと、最寄りのファミリーレストランに入った二人は、飲み物を注文して腰を落ち着けた。 「台風が近づいてるらしいね」 「そういえばそんな時期っスね」 「毒島君は結局今年どこを受験するの?」 「……あの」 窓の外を見ながら、世間話を始めた優斗を、毒島は遮った。 「なに?」 「他に聞きたいことって無いんスか。どうしてあんたのこと知ってるのか、だとか。一応俺たち初対面っスよ」 「いやぁ、別に身元隠してるわけじゃないし、良いかな、と思って」 優斗はハハッと笑って頭を掻いた。 「柳君のことが気になって様子を見に来てたりしたの?」 こくりと頷く毒島の目の下には濃い隈が出来ている。 「それで、あんたのことも」 「そっか」 優斗はしおらしい彼の様子に、あの頃とは随分変わったな、と感心した。 「なんというか、毒島くん丸くなったよね」 「丸く、っスか」 「前見たときはもっとつっぱってた。でも、今は丸くなったけど元気も無いね」 「前……」 「ああ、そっか。オープンキャンパスの時、ギャラリーの中に居たんだ、俺」 毒島は俯き、拳をぎゅっと握る。 「俺、自分がクズ過ぎて情けなくて」 そこから先、言葉を切って黙り込んでしまうと、丁度そのタイミングで飲み物が運ばれてきた。それを受け取ってから、彼はやっと口を開いた。 「あれから、もうあいつとの関係はどうにもならないのに、気になって気になって勉強も手に付かなくなって。あいつの大学を覗きに行って、あの庵とかいう人と一緒にいると嫉妬して……そんな資格もないのに……。順調に大学生活を送るあいつを見て、自分はまだ受験生活から抜け出せないのに、とか、永井の癖に、とか思って、そんな風に今でもあいつを下に見てる自分が嫌で……」 彼の話に「うん」と頷いて、優斗は彼の言葉を補完する。 「毒島君は、柳君にしてしまったことを反省して、それはもう取り返しのつかないことだと認めるてるんだね。でも、どうしても彼が気になって、様子を見に行っては嫉妬してしまう自分を嫌な奴だと思っちゃうんだね」 「俺は、嫌な奴だから……」 「そうなんだ」 穏やかな口調で肯定されて、毒島は「え」と口を半開きにして固まった。優斗はそんな彼を気にせずに続ける。 「人は他人の気持ちに沿うことはできても自分の立場からでしか物事に対応できないんだ。俺は永井君の友達だから、君を肯定することは彼への裏切りになるから出来ない。でも、君は君の立場で物事を見て良いんだよ」 そう言って優斗は暖かいレモンティーを口に運ぶ。どう言えば彼に伝わるのか、考える時間が欲しかった。 「嫉妬は誰でもするよ。人の良いところは本当に羨ましく思うもの。でも、その羨ましく思うものを、彼はどうやって手に入れたの?」 「それはあいつが努力したから……」 「そう思うなら、欲しいなら真似をして。そうして柳君のことからはもう卒業しなくちゃ。忘れるんじゃないよ、卒業するんだよ」 糾弾されているつもりでいた毒島は、その言葉に目を瞬く。優しそうな人だからと思い切って相談したのに、まさかの手のひら返しをされたと思ったのだが、違かった。 「なんだか甘いものが食べたくなっちゃった。毒島君も何か食べる? 三百円以内ならおごってあげる」 いそいそとメニューを開く彼の笑顔を眩しく感じながら、毒島は『卒業』の言葉を噛み締めた。 ****** いつからか、優斗の表情が陰りだしたことに庵は気がついた。人と話しているときはそうでもないが、話の途切れた瞬間や、一人でいる時に眉間に薄い皺が寄る。その上、庵が話しかけると目を泳がせ、話を短く切り上げては、早々に庵の元から立ち去った。 彼に避けられるようになると、学校生活が一気につまらなくなった。庵と優斗は学科ではにこいち扱いで、ちょっとした時間は一緒に過ごしていたから。 庵は、外の空気でも吸って気分を変えようと、油臭い制作室を出た。美術棟の一階に降りると、特徴的なちょんまげ頭が、廊下の隅でケータイを耳に当てているのが見えた。 「――うん。それじゃまたね、毒島君」 にこやかな声で会話を終えた彼は、こちらを振り向き、庵を視界に入れて表情を凍らせる。 「今の、何」 「何が」 「毒島って、あの毒島か」 「――だから?」 優斗は泳がせていた目をきつく瞑り、再び開いた瞳で庵を見つめた。 「俺が毒島君と関わって何が悪い? 俺は、庵でも柳君でもない」 庵は大股で彼に歩み寄り、小さく震える手首を掴んで、揺れる瞳を覗き込む。 「お前はそんな奴じゃないだろう」 彼が理由もなく、自分や柳を裏切る筈がないと信じていた。理由があったとしても、自分たちを見限れる筈がないという確信があった。そうでなければ、こんなに不安定な顔をする筈がない。 「……だって、どうすれば良いか分からなくなったんだ」 優斗は庵の強い視線に肩を震わせ、瞳に涙の膜を張った。 「俺たちが嫌になったわけじゃないんだな」 「そんなわけない!」 「分かった。じゃあゆっくり話せ」 優斗は唇を噛んで涙を拭って話だす。 「俺は、庵も柳君も友達だと思ってる。二人共大切で、でも、圭斗が……」 言いかけて、今求められている話はこれじゃない、と首を振る。 「毒島君とはたまたま会って、話をしたんだ。それから何度か連絡を取り合ってるけど、柳君とは関係ない。俺の新しい友好関係だ」 「でも、俺のことを避けてただろう」 言い返されてぐぅっと喉を鳴らす。庵を避けてしまっていたことを、バレないはずがないのに、脳天気にもバレていないと思っていた。いや、指摘されないと高を括っていた。 「さっき何を言いかけた」 「俺は……」 口の中がパサパサに乾燥して声を出すのが辛くなる。その続きをどうしても言いたくなかった。柳に言われたことを彼に言いたくない。自分の言葉で二人の関係を壊したくない。口は乾くのに視界は滲んだ。 毒島に優斗自身が言った言葉が頭をよぎる。 『人は他人の気持ちに沿うことはできても自分の立場からでしか物事に対応できないんだ』 彼に言いながら、自分に言い聞かせた。圭斗を裏切らない、と立場を決めた。 柳のことは大切な友人だと思っている。一緒にいれば楽しいし、好みや行動のフィーリングも合った。けど、柳と圭斗を天秤にかけたらやっぱり圭斗の方が大切で…… 「俺は、二人も大事だけど、圭斗を一番大切にしたいから……っ」 柳を切り捨てるなんて嫌だ。そんなことをすればきっと彼は傷いて、彼自身を責めるだろう。でも、彼は優斗と圭斗の関係に刺を刺した。今までどおりの関係でいることは、彼を突き放した圭斗の気持ちを裏切ることになってしまう。 「柳が何か言ったのか」 核心を突く庵の言葉に、優斗の瞳からぼろっと涙がこぼれ落ちた。 「優斗」 もう、言わなきゃいけない。逃げられない。 「柳君は多分俺と庵が付き合えば良いと思って……」 しかしそれを言ってから気がついた。彼は庵を好きな筈なのに、それはおかしいと。彼は優斗と庵に恋人同士になって欲しいだなんて言っていない。優斗と圭斗に別れて欲しいとも言っていない。 「……そうだよ。柳君は俺に、どうして庵じゃなくて圭斗を選んだのかって聞いたんだ」 庵は優斗の言葉に、ぐっと息を飲んだ。 「庵?」 「分かった。ちゃんと話すから、もう余計なことを考えるな」 庵は物言いたげな優斗の頭を軽く叩いて、メール制作画面を開いた。
4
学校最寄りのJRの駅を柳は毎日利用している。ある日、その北口周辺の商店街で、笑顔を交わす二人を見てしまった。ちょんまげにした前髪に、赤い眼鏡がトレードマークの彼と、柳のトラウマ。 どうして貴方がそいつと一緒に居るんですか。僕のことはもう、見限ってしまったんですか……? 「柳ちゃん、最近ちゃんと眠れてる?」 余りにも顔色の悪い彼を自宅に連れ込んだ川島は、青白い顔に濃い隈を浮かべる柳に熱いお茶を差し出した。残暑がやっと収まって、一気に肌寒い気候になったこともあるが、今の彼に冷たいものを与えたら、血液までキンキンに凍ってしまいそうだ。 お茶を受け取った柳は、一息吐く間もなくケータイの着信音に肩をビクつかせた。 「それ、庵からじゃないのか」 「多分……」 川島の指摘にケータイをとって確認する振りをする。 昼間、庵から『話がしたい』とメールがあった。それに答えてもいないし、その後のメールや電話も確認していない。きっと別れ話だと思った。優斗と庵は今でも仲が良い。優斗は、自分が彼と圭斗に言ったこと、二人と決別したことを話しただろう。毒島のことだって、彼の口から聞いたら庵の気持ちは変わるかも知れない。 「柳ちゃん?」 「……僕、壊しちゃたんです」 柳は震える声を絞り出した。 自分の人間関係はグチャグチャになった。自分で壊した。でもどうして良いか分からなかった。壊したくないから動かないでいた筈なのに壊れてしまった。 「大事なものを全部無くしたんです……っ」 泣いても仕方ないと思うのに、目頭が熱く滲んだ。 「やっと手に入れたのに、頑張ったのに、僕、僕が自分で、壊して……っ! 僕のことなんか誰も好きになるはずない……っ、あのまま部屋から出なければ良かったんだ!」 こんな自分を彼が好きでいる筈がない。優斗が良い人過ぎて、彼と比べたら……僕なんて、妥協されただけじゃないか…… 「おーよしよし。辛かったな。でも誰も好きにならない、なんてことはないぞ。俺は柳ちゃんの先輩で良かったと思ってる」 川島は、黒目がちな瞳からボロボロ涙を零して言い募る柳の背中を撫でて言った。 「ほ、本当ですか……?」 「本当だよ。だからそんなに泣くんじゃないよ」 「僕、川島さんを好きになれば良かった……っ」 柳は彼の胸に額を付けて縋る。その時、大きな音を立てて部屋の扉が開け放たれた。 「随分無用心だな、川島」 地獄の底から響くような重低音に、川島は全身を震わせる。恐る恐る振り向くと、鬼の形相の庵と、その後ろでケータイを掲げてピースをする圭斗の姿があった。 「じょ、常識ある人間は鍵が開いててもノックするんだよ!」 言い返すと、真っ黒い顔の庵がズンズンと大股で近づいてくる。すごく怖い。良かったな、柳お前ちゃんと愛されてるよ。そう思ったが、肝心の彼は処刑を待つ囚人の如くその身を震わせていた。 「返せ」 庵は柳の手を引いて無理立たせると、よろけた彼を受け止め、そのまま抱きしめる。庵の腕の中にすっぽり収まった柳は、状況を理解できずに硬直した。 「しっかり話し合ってこい」 「待って、俺も連れて行って!」 扉を閉めようとする圭斗に川島が突進した。 二人きりになった部屋で、庵は柳を抱きしめたまま深い溜め息を吐いた。 柳の様子がおかしいのは気がついていた。けど、どうしたのかと聞いても誤魔化すから自分には話したくないことなのだろうと思って深追いしなかった。 柳が優斗にどうしてあんなことを言ったのか、そんなの嫉妬に決まっている。庵は自分が優斗にどれだけ依存しているのか理解していた。でも、それは友情であって恋愛じゃない。 「俺はちゃんとお前が好きだ」 柳の頬に手を添えて顔を上げさせて告げると、彼は理解できない、と目を瞬いた。 「じゃあ、どうしてお前は優斗を好きにならなかった」 くすんだ瞳を見つめて尋ねる。この目が光を失ったのは、いつぐらいからだっただろう。 「今だから言うけどな、俺がお前に会ったのは優斗に言われたからだし、お前が俺に救われたと思ってる、あの選択肢をお前にやったのも優斗だ。もっと言えば、紳士の俺の言動は全部、優斗だったらこう言うだろう、こうするだろうと考えてした。お前が好きになるべきなのは俺じゃなくて優斗なんだよ」 「でも、僕は卑怯なんです。庵さんの言葉は強くて潔くて、そんな庵さんの後ろに隠れてその言葉にスカッとして気持ちよくなってるような卑怯な男なんです!」 「そんなのは分かってんだよ。俺の質問に答えろ!」 柳は怒号に驚き、身をすくめる。それでも、瞬きを繰り返して彼の言葉を飲み込んだ。 (僕が好きになるべきは、優斗さんだった? でもそんなこと言われても……) 既に柳は庵の紳士じゃない部分も含めて好きになっていた。今更そんなことを言われても関係ない。 「僕は庵さんの嘘をつかないところが好きです。言葉がきつい時もあるけど、言われたことは全部本当だから安心できます。優斗さんじゃなくて貴方が良いんです」 「そんなの優斗だって嘘をつかないし、言葉だって優しいだろ」 「そんなこと言ったら、もう理由なんて、無い……。それでも、僕が好きになったのは他の誰でもなく庵さんです」 あの絵を見た時から好きになっていたのかもしれない。彼にメールを送る切っ掛けになったあの絵に、彼の心を見て惹かれたのだ。 「俺も同じだ」 きっぱり言われて、柳は踊りそうになる胸を必死で抑えた。 「悪かったな。俺が、優斗の名前ばかり出したから、不安になったんだろ。お前をあいつの代わりにしたんじゃないかって」 庵は、徐々に光を取り戻し始めた柳の瞳を見て頬を緩める。 「俺も最初そう思った。だから確かめるみたいにあいつをお前に重ねた。でも、そうじゃないと分かった。お前も、俺の本性を知ってもまだ俺のことを好きだと言った。だからお前の気持ちに応えたんだ」 柳は再び熱くなった涙腺に、戸惑う。信じたい、でもまだ信じきってしまうのが怖かった。「でもその後だって」 「どうしてお前なのか考えてたんだ。お前と優斗はどこか似てる。でも俺はお前を好きになった」 庵の言葉に簡単に甘く痺れてしまう心に、いやいやと頭を振る。庵の口から「好き」という言葉が出るたびに、心が疼いて切なくなる。 「僕と優斗さんは違いますよ。全然……」 「そうだな。あいつは元の甘えたな性格を隠そうとしてる。お前は元の冷たい性格を隠すために無意識に甘えてる。表に出ている分には似ているけど、優斗は努力、お前は打算な感じがする。総合するとお前の方が性格が悪い」 柳は俯いてしまった頭をがばりと上げて目を見張る。ショックと怒りに唇が戦慄いた。 「でも俺はそんなお前が良い」 「は……ふぇ……」 しかし続く言葉に一瞬にして筋肉が緩む。どんな顔をしたら良いか分からなくなって、そのまま顔をくしゃくしゃにして泣いてしまった。 「もう俺以外の前で泣くなよ」 「庵さんが泣かせてるのに、理不尽です……っ」 「うるせぇ犯すぞ」 「合意での行為は抱くって言うんですよ!」 庵は宝物を扱うように、大事に彼の頭を胸に抱く。柳の大粒の涙は、辛い気持ちと一緒に瞳のくすみも流していった。 コッチコッチと時計の音が響く。川島・圭斗と同階にあるカラフルな自室で、優斗は落ち着着なく体を揺らした。 「今ごろ二人で何話してるのかな」 「俺には関係ない」 ベッドの上で向かい合って座る圭斗にすげなく返されて、優斗はしゅんと眉を下げる。そんな彼の様子に、圭斗は片眉を下げてクッションを叩いた。 柳に『嫌いだ』と告げたのは、単純に腹が立ったからだ。彼の言動は何となく優斗に似ているところがあったから、人から嫌われるのは応えるだろうと思った。思惑通り、彼は子供騙しの一言で、世界が終を迎えたような顔をした。 本当のところ、それだけで圭斗は溜飲を下げていた。それを柳に言わないにしても、とばっちりで気を病んだ優斗には伝えるべきかも知れない。 (でも今更なぁ……) 悪いと思いつつ、優斗が自分のために他を捨てようとしてることが嬉しくて、放置してしまった。 「優斗ぉ」 「どうした圭斗」 クッションを離して優斗を横から抱きしめる。それだけでふにゃっと笑み崩れる彼が可愛くて仕方ない。今回のことは、庵を呼んだことでチャラできないだろうか。 「おーい、お前ら。俺が居ることを忘れるな」 床に座る川島が胡乱な視線を投げる。 「川島うるさい」 「部屋を占領された俺を少しは気遣って!」 優斗の肩に額を押し付けたまま言い捨てる圭斗に川島が訴えていると、コンコンと扉がノックされた。 「はい、開いてます!」 優斗が答えると、扉を開けた庵が、気まずげな柳の背中を押した。 「優斗さん、圭斗さん、変なことを聞いてすみませんでした」 柳に頭を下げられて、優斗は圭斗を窺う。 「良いよ」 圭斗の言葉を聞いて、優斗は柳に飛びついた。 「せわになったな」 帰り際、庵は川島を見据えて言い捨てた。川島にしたらとんだ災難だ。自分は女の子が大好きなのに、彼らといるとホモの修羅場に巻き込まれる。 川島は、泣き疲れてくったりした柳を連れて出て行く背中に「もう巻き込むなよ」と言い返した。 ****** 「ん、ぁ……っ」 柳は下半身に与えられる甘い刺激に、暗闇に濡れた声を溶かした。上体をシーツに沈める柳の太ももの間に自らのたかまりを挟んだ庵は、柳の蕾をいじりながら腰を揺らす。そのたびに柳の脳が揺さぶられた。 「やぁっ……」 節立った指に内壁を擦られた柳は切ない叫びを上げる。 「庵さん、もう……っ」 「もう?」 庵は蕾から指を抜いて、物欲しそうにヒクつく蕾を撫でる。それだけの刺激で柳は腰を震わせて、顔を埋めている枕の端を握り締めた。 「庵さんの、入れてください……」 羞恥に耐えて懇願すると、直ぐにそれを蕾に当てがわれる。 「ふ、ぁあ……っ」 皮膚を広げながら侵入してくる熱の塊に、柳は熱い吐息を漏らした。挿入を終えた庵は柳の腰をそっと撫でて、彼の呼吸が整うのを待った。 「動くぞ」 彼が頷いたのを確認して律動を始めると、腰を引く度に柳の中が吸い付くように蠢く。彼の吐息、熱、全てが庵の官能を刺激した。 「柳お前、俺のことすげぇ好きだろ」 「ん、ぁあっ!?」 「お前の中、俺のこと喰ってるみたいに動いてる」 「そ、んなのっ」 意地悪く指摘する庵に柳は反論しようとするが、募る快感がぞわぞわと全身に駆け巡り、言葉にならなかった。 「ひっ、もう……っ!」 「柳、愛してる」 庵は限界を訴える柳の背中を抱いて、言葉と吐息で彼の耳を犯す。庵の下で柳が全身を震わせると、張り詰めた熱を最奥に押し込み、会陰を押し付け同時に果てる。がくがくと震えてながら白濁を放つ柳は、自身から熱が溢れるその感覚と、注がれる熱の感触に翻弄される。抑えられない嬌声が、八畳の城に響いた。 鳥の鳴き声とともに、緩やかに意識を浮上させた柳は、傍らの体温にぽっと頬を染めた。昨夜、言葉と行動、自分を包む庵の全てから、無愛想で取っ付きにくくて皮肉屋な彼の、めいいっぱいの愛を貰った。初めての朝と同じ暖かさがこの心を満たしている。 「……やなぎ……」 幸せな気持ちで庵の寝顔を眺めていると、規則正しい呼吸の合間に彼が言葉を紡いだ。 (今度は寝言も僕だ……!) 嬉しくなった柳は勢いのまま彼を揺すり起こし、不機嫌な顔で瞼を持ち上げた彼に尋ねる。 「庵さん、僕は夢ではどんな配役だったんですか?」 じっと柳を見つめた庵は「……夢」と呟いて、柳をきつく抱き締めた。 「夢か」 「庵さん?」 「お前がただ泣いてるだけの夢だった」 柳は彼の胸から顔を上げ、眉を寄せる彼の顔を覗き込む。 「庵さん、僕、今幸せですよ」 そう言って微笑む柳の瞳はキラキラと澄み渡っていた。
エピローグ
青い空に、陽の光が眩しく光る秋晴れの京の都。紅葉の時期にはまだ早いが、シルバーウィークの中日であるこの日、各寺院は観光客で賑わっていた。 「カップル、子供連れ、男女混合グループ旅行……。盛んだね、楽しそうだね、やぱり男はそうあるべきだ。なのにどうして」 境内を見渡した川島は、目の前で地図を広げる坂本似非兄弟に視線を移して溜息を吐いた。「俺の周りは男しかいない」 「柳の大好きな先輩だからだろ」 「危うい発言やめろ。渡辺に恨まれたらどうすんだ!」 川島は圭斗の発言に冷や汗をかきながら反論した。数週間前、柳の相談にのっていた川島に向けられたあの視線を、思い出すだけで恐ろしい。柳はもっと早くあいつの独占欲に気づいているべきだった。 川島は今、柳の計画した親善旅行に来ている。メンバーは、柳、庵、優斗、圭斗と川島の五人。仲直りの記念の旅行だと思うのに、自分は関係ないだろうと、川島は言ったのだが、可愛い後輩にどうしてもと頼まれたら断りきれなかった。というか、柳の後ろの庵に凄まじい形相で「来るよなぁ?」と地を這う声で脅されたら来るしかなかった。 「俺は可愛い女の子が大好きなのに……」 「可愛い子なら優斗と柳が居るだろ」 地図と格闘する優斗を楽しげに眺めながら圭斗が言った。 「男はお呼びじゃねぇんだよ! というか、柳ちゃんはともかく弟は可愛い系じゃないだろう」 「はあ!? 優斗めちゃくちゃ可愛いですけど!?」 「ちょっと圭斗、大声で変なこと言うのやめろよ!」 圭斗が声を荒げると、優斗が慌てて彼の背中を叩いた。 「あっち、楽しそうですね」 売店の巫女さんからお守りを受け取った柳は、後ろを振り返って呟いた。 「何やってんだあいつら」 言いながら庵が振り返ると、二人の視線に気がついた優斗が手を振ってきたので振り返す。 「そういえば、よく圭斗さんが言ってる前科一犯ってなんなんですか」 庵に向かって圭斗が威嚇するような視線を送ってきたので、何となく思い出した。彼は庵が優斗を構うと、決まってこのセリフを口にする。 「あー……」 ボリボリ頭を掻いて言いにくそうにしながら、庵が口を開いた。 「俺が酔ったふりして優斗にキスぶちかました、ってやつだな」 その言葉に、柳はしゅんと項垂れる。 「やっぱり、優斗さんの方が良いんだ」 「やめろぶりっこ」 庵に頭を叩かれて、ぷくっと頬を膨らませた。 「どうせ僕はぶりっこですし。素で可愛い優斗さんの方が良いんでしょ」 「なにお前、そんなに好きだって言わせてぇの?」 「そ、そんなんじゃありませんっ」 膨らんだ頬を摘んで潰される。そのままそこを撫でられて、むず痒い感触にぞわりと産毛が逆だった。 「布団の中でたっぷり言ってやるから待ってろよ」 低い声で囁かれて、ぶわっと視界が桃色に染まる。 「――っ、い、いりません!」 柳は火照った頬から彼の手を振り払い、優斗達の方に走った。 「どうしたの柳君、また庵に何か言われたの?」 「ほんとあの人の頭の中どうなってるんですかね」 優斗に尋ねられて、柳は真っ赤な顔のまま、ぎゅっと眉を寄せた。 「あーあ、あれだ。怒ったときは『不如意』だよ。不如意です! って言ってみてよ! 可愛いから!」 「庵さん! 不如意です! 馬鹿! 不如意です! 不如意!」 「やめろ」 柳の後を悠々と歩いてきた庵は、振り返った柳に涙目で「ふにょい」を連呼され、慌ててその頬を片手で挟んで口を塞ぐ。赤面涙目でふにょふにょ言うな。 「兄は何してんの?」 柳と庵を睨みながらブツブツ何事か唱えている圭斗に、川島が尋ねた。 「あいつらが破局しないように念送ってんだよ。俺と優斗の邪魔されてたまるか」 同性カップル二組に挟まれた川島は「あー、そう……」と力なく返した。 「あ、そうだ優斗さん。これ」 柳が先程買った学業守りを優斗に渡すのを見て、庵は首を傾げる。 「受験生の知り合いでもいるのか?」 「優斗さんから毒島に渡してもらおうと思って」 「はあ!?」 「別に許したわけじゃないですよ。でも、これくらいは良いかな、って思ったんです」 スッキリした顔で言う柳は、諸々のことを吹っ切ったのだろう。それは良いことに違いないが、庵の気持ちは空かない。 「不如意ですか?」 「調子にのるなよ」 「いひゃい、いひゃいです! ふにょいです!」 だから、誇らしげに笑う彼の頬を伸ばして泣かせた。 澄み渡る空の下、柳の生活はこうしてどうにか軌道に乗る。
迷惑メール 交錯する想い<完>