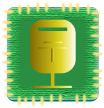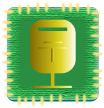
迷惑メール 付きまとう影
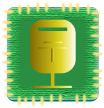
迷惑メール 付きまとう影
![]() 1
1 ![]()
「柳君は学科に友達できた?」 「連絡取れる人はいますよ。でも、優斗さん達と話している方が落ち着くんです」 サンドイッチを頬張りながら言う優斗に、弁当の副菜のポテトサラダをつまみながら答える。口達者な柳に優斗は「やだ、嬉しい」と頬に両手を当てて喜んだ。 昼休みのC棟空き教室は、今日も賑わっている。高校までのように学級という単位の無い大学では、学科以上にサークルや研究室での所属意識が強くなるようで、そのどちらにも所属していない柳は、すっかりC棟空き教室の住人になっていた。 「そんなこと言って、お前が同級生と話してるところ見たけど、楽しそうだったじゃねぇか」 「ひとりひとりが特別なんですよ」 柳が庵のツッコミにすまして答えると、庵は「はん」と乾いた笑いを零して、ああ言えばこう言う、と彼の丸い頭を小突いた。 態度を取り繕うことをやめた柳は、生意気にも八方美人を極めた。顔色を窺う云々の、庵の言葉は意図とズレた解釈をされたようだが、これはこれでまあ良いかと庵は思っている。 「痛い、酷いです」 大げさに声を上げた柳がしゅんと眉を下げて目を伏せた。 「表情作ってんじゃねぇよ、女優か。俺が悪いみたいになるだろう」 「僕そんなつもりないのに、酷いです。それに僕男ですし」 「うるせぇよ」 柳はしおらしくするのをやめて、仏頂面を作る。その膨れた頬を庵が摘んで伸ばすと「うぬー」と唸った。 「おい渡辺、優斗に悪さしてねぇだろうな」 柳が庵に遊ばれていると、湯気の立つカップ麺を持った茶髪の学生が声を掛けてきた。 「やっほー、圭斗!」 優斗が手を伸ばして彼にじゃれつき、庵は「お前じゃないんだから」と挑戦的な目を向ける。 優斗の隣の席に腰を下ろした彼は、坂本圭斗(さかもとけいと)。優斗のいとこである。二人は苗字が同じため、川島や庵は「坂本兄」「坂本弟」と呼び分けているのだが、本当の兄弟ではないのにややこしいということで、柳は二人共下の名前で呼んでしまっている。そのついでに庵のことも名前で呼ぶようになった。 「前科一犯」 圭斗が庵を睨み返すと、庵はべっと舌を出して答えた。彼はたまにこのセリフを使う。柳には良く分からないが身内ネタなのだろう。 柳はここに来ると大体このメンバーで集まっている。柳がここに来るきっかけになった川島は「あいつらに関わると碌な目に合わない」と最低限の関わりしか持つ気はないらしい。しかし、頻繁に合コンの誘いを持ってくる彼の、最低限のボーダーはどこなのかは微妙なところだ。 「優斗お前また、そんな少しで足りるのかよ」 「朝ごはんガッツリ食べたからね! 麻婆豆腐!」 「重い」 心配げに言う圭斗に優斗はガッツポーズをする。彼の今日の昼食は角形中サイズのタッパーに入れたサンドイッチとインスタントのカップスープ。彼はいつもこのタッパーに焼きそばやら中華丼やら一品を詰め込んで、生協でカップスープを買って昼食にしている。圭斗はその時の気分で決め、柳は今のところ、とりあえず生協オリジナルの商品を制覇しようと考えている。 「それにしても庵さんはよく食べますね」 菓子パンの空き袋を量産する彼を見て、柳は感心した声で呟いた。 庵は別段甘いものが好きなわけではなく、量を食べたいがために安いものを選んだ結果こうなっている。 「育ち盛りなんだよ」 「それは嘘だろ」 庵のボケに優斗がケラケラ笑ってツッコミを入れた。 「柳、こいつに合わせて大食い御用達の店とか絶対行くなよ。死ぬからな」 圭斗の忠告に「気を付けます」と本気で答える。 柳の学校生活は順調に進んでいた。 5月に開かれるオープンスクールは、一・二回生が中心になって企画をするイベントだが、暇そうな上級生がいれば、手伝いに駆り出される。 制作をしている学生はその例ではないが、見学者がいる中で描き続ける者はほぼ居ない。そのことを忘れて、登校してしまった庵は、どうしたものかと構内をうろついていた。 「永井!」 正門から続く掲示板の並ぶ通りで、見知った顔を見つけた庵は、声を掛けようとしたが別方向からの声に先を越されてしまった。 「永井、俺だよ! 覚えてるか!?」 「毒島(ぶすじま)君……?」 毒島と呼ばれた彼は思わぬ再会に喜んでいる様子だが、柳は顔面を蒼白にして身を固くしている。 「そうだよ。お前、あれからどうしてたんだ? 心配してたんだ」 覚えられていたことが分かると、毒島は快活に笑って柳の肩に手を伸ばす。触れられた柳は息を飲んで一歩後ずさりした。 「柳?」 「い、おり、さん……っ」 流石におかしいと思い庵が声をかけると、毒島から離れた柳が庵の着古したパーカーの裾を握る。事情を察した庵は例の紳士な笑顔を作って、毒島をうかがった。 「失礼ですが、どちら様ですか?」 「自身から先に名乗るのが礼儀じゃねぇの?」 睨みつけるように二人の様子を見ていた彼は、腕を組んで挑発的に答える。 「これは失礼。私は柳君と一緒にこの学校に通っている、彼の友人の渡辺と申します」 庵の言葉に、彼は小さく目を見張った。 「永井、この学校の生徒なのかよ」 「そうですよ」 「何でだよ、お前、学校中退したじゃねぇか」 「一般人でも大学は受けられますよ」 「あんたには聞いてねぇんだよ!」 庵の服を掴んだ手を見つめたまま言葉を発せないでいる柳の代わりに答える庵を、毒島は苛立たしげに怒鳴りつけた。 大学の名前が印字された手提げは、正門の受付で配られる学校案内のパンフレットだ。今年の受験は失敗したのだろう。見学に来たここで、自分と同じ境遇、あるいはそれ以下だと思われる柳を見つけて思わず声をかけた。しかし彼は実はこの学校の生徒で、そのことに納得がいかない――というところか。 (クズ野郎だな) それは失礼、と庵は毒島への評価を笑顔の下に隠した。 「ところでまだ、お名前を伺っていませんが」 「そいつの高校の友人の毒島だけど? 話がしたいからどいてくれねぇ?」 「どうしましょうか」 柳を伺うと、彼はパーカーを掴む力を強くして庵に身を寄せた。 「柳君は私に居て欲しいみたいですよ」 「永井っ!」 気色ばむ毒島に、柳は「ひっ」と短い悲鳴を上げる。庵は彼を背中に隠すように後ろ手で抱き寄せて、毒島に向けてふんわり笑みを作った。 「私、柳君が高校生の頃から相談を受けているんですけど。部外者でしょうか」 「あれは……」 庵が事情を知っていると分かると、彼は途端に居心地が悪そうにたじろいだ。 「本当はあんなことがしたかったわけじゃないんだ。ただ、ちょっと柳について言ったことが誤解されて、気づいたときにはもう皆変わってたんだ。だから……っ」 目を泳がせながら早口でそう言い募る。 「あなたが原因だったということですか?」 「そうじゃなくて! 柳って、女々しいところあるだろ? それがこう、もやっときて。俺はそれだけだったんだ」 「そうですか」 言い訳にしかならない言葉たちを、庵が切り捨てるようにそう返すと、彼はぐっと息を詰めた。それでも柳からの答えを期待してじっと見つめる彼に、柳は口元を抑えた。 「……きもち、わるっ」 「はぁ!?」 毒島が顔をしかめて声を上げる。まるでヤンキーの威嚇のようだ。 望んだ答えじゃないと受け入れられないのか、と庵はこれみよがしな溜息をついて、頭の悪い彼に説明してやった。 「貴方の言い分は分かりました。でも、それを素直に受け入れることはできません。貴方が嘘を言っているかもしれないですし」 「俺は嘘なんか言ってない! 証拠もないのに疑って避けるのって道徳的にどうなの?」 「柳君が学校をやめた理由は分かっているでしょう? でしたら彼が簡単にはあなたを信用できないのも理解できるはずです。信用を得たいならそれなりの誠意を見せてください」 「そんなこと、できるわけないだろ!」 「それなら、このお話はここまでです」 「なっ」 「あのね。今弱い立場にいるのは貴方の方なんですよ?」 言い負かされた毒島は、それでもまだ何か言いたげに、庵の影に隠れる柳を見つめた。 「弁解する気があるなら、私の連絡先をお教えしますが」 このまま放置したら柳に直接何かしてきそうだ。それならこう言ってしまえば、中途半端な気持ちでは連絡できないだろう。それにもし相手が本気でも自分が対応できる。 庵がケータイを出して提案すると、彼も渋々それに応じた。 悲しそうな目で庵を見た柳が「なんで」と小さく呟く。弁解なんていらない、ここで終わりにしたい、と。庵はそれにべっと舌を出して答える。お前も調子に乗ってんなよ、と。 「ところで」 庵は毒島に視線を戻して切り出した。 「ずいぶん悪目立ちをしてしまったようですが、さっさと帰られたらいかがですか?」 柳が口元を抑えた辺りから、立ち止まって様子を窺う人が増えてきていた。庵が、数人のギャラリーを指して言うと、毒島は顔を真っ赤にして走り去った。 「弟!」 庵がギャラリーの一人になっていた優斗を呼ばうと、飛び出してきた彼が勢いよく庵の肩を叩く。ついでに呼んでもいない圭斗も寄ってきた。 「ひ、ひやひやさせる寸劇はやめろ!」 「でも柳はもっとしゃべれよな!」 二人の言葉に柳は「へ」と困惑の声を上げたが、こちらを伺っていた人たちは、彼らの言葉で興味を無くして散っていった。 「似非紳士なんてお題で和やかな劇になるはず無いだろ」 「なら今日作戦会議だ」 ため息混じりの庵に、優斗が強い視線を向ける。庵は彼を一瞥すると、 「俺んち」 と、ぶっきらぼうに返した。 「俺も行くから」 「兄はいらない」 「んだとてめぇ」 「じゃあ柳君、そういうことだから」 優斗はそう言いおいて、庵と言い合う圭斗を回収して去っていく。辺りはすっかりいつもの様子を取り戻していた。 「柳、大丈夫か?」 「あ、はい。もう離してください」 こちらもいつもの調子を取り戻したようだ。庵は抱き寄せたままだった柳の肩から手を離すと、生意気を言う彼の口を、頬を摘んで伸ばしてやった。 ****** 柳にとっての大学は、努力の末に勝ち取った、自分の居場所であり誇りだった。高校時代の自分を捨てて、自分を認めてくれる、受け入れてくれる人達と新しい関係を築いていた。それなのに、彼に会ったことはそれだけで、やっと取り戻した自尊心を引きちぎられる心地がした。 『心配してたんだ』 と言う彼に、どの口が、と疑った。 毒島は、高校時代ああなるまでに一番仲良くしていた友人であり、一番関係が変わった相手でもあった。無視したのはお前じゃないか。陰口の中心に居たのはお前じゃないか。俺に話しかけようとしたクラスメイトに圧力をかけていたのはお前じゃないか。 今更何がしたい。何をしようとしてる? 捨てたはずの思い出を、そんな風に投げつけられて、どうすればいい? 目をつぶって忘れた振りをしていたのに、お前が蒸し返さなければ見ない振りが出来たのに。 『柳って、女々しいところあるだろ』 頭がどうにかなりそうだった。 柳はぎゅっと目を閉じて、庵に抱かれた肩を掴む。あの場で発狂しなかったのは、崩れ落ちてしまわなかったのは、彼が支えていてくれたからだ。 あの後、数学科に割り当てられた教室に戻ると「お疲れ様」と労われた。自分は他学科の先輩の遊びに付き合わされた、苦労人ということになっているらしい。 毒島のせいで壊されると思った生活は、実際は何も変わらなかった。でも、 『弁解する気があるなら、私の連絡先をお教えしますが』 また、会わなければいけなくなるかもしれない。どうして、と見つめた庵はべっと舌を出して柳を嘲笑った。 柳は自身の肩を掴む手に力を込める。 (肩、熱い……) 彼が何を考えているのか分からなかった。でも、すがりたいと思ってしまう。 「永井、外で渡辺って人が待ってるけど」 「はあ!?」 オープンスクールの片付けを終えて黄昏ていた柳は、学科の友人に声を掛けられると、慌てて教室を飛び出した。 「庵さん!?」 「おせぇよ」 窓に寄りかかってぶっきらぼうに言葉を投げてくる彼に、遠目で見ていた女の子達が「きゃっ!」と、黄色い悲鳴を上げる。こんなボロ切れみたいな服を着ているのに顔とスタイルが良いからやたらにモテるのだ。雰囲気イケメンなんて言葉が流行る時代に雰囲気ぶち壊しの格好でも絵になるなんて、努力している人に謝ってほしい。 「迎えに来てくれたんですか。わざわざ」 なんだか腹が立って、刺のある言い方をしてしまった。 「お前は本当に可愛くねぇなぁ。お前が俺の家を知らないから迎えに来てやったんじゃねぇか。わざわざ」 庵は失言に顔を曇らせる柳の髪の毛をグシャグシャにかき混ぜた。 古びた車体がガタンゴトンと音を立てて揺れる。年季の入った商店が窓の向こうを流れていった。 「東京にも田舎ってあるんですね」 「そりゃぁな」 「僕ここに来るまで東京の人ってどこに住んでるだろう、とか思ってました。ビルかな、とか」 「笑い取ろうとしてんのか?」 「いえ、べつに」 庵の家へ向かうローカル線は、通勤時間からずれているためか、席もそこそこに空いていた。扉近くの席を陣取り手すりに腕を掛けて寛ぐ庵の隣で、柳は所在無く拳を握る。 「昼間、どうして庇ってくれたんですか」 「何となく」 庵は柳を横目で一瞥して答えた。 「僕、何も言えないでいたのに。庵さん、そういうの嫌なんじゃないですか」 「俺だったら言い返してた。あの時動けないでいたお前の気持ちは分からない」 「だったら」 庵は、大きな瞳をぎゅっと顰める柳の、その瞳を隠してしまいたくなった。紳士をやっていた時なら、こんな表情でこんな質問をする彼を、言葉を否定して慰めて欲しいだけの甘えた野郎だ心中で罵っただろう。でも、今の彼は庵が優しい性格をしていないことを分かっている。自分が苦しくなると予想しているのに、追求してくる彼を哀れだと思った。 「――俺には分からないけど、お前にはどうしようもないことだったんだろ?」 溜息混じりに言ってやると、柳はぱっと表情を輝かせて庵を見つめた。彼の方が背が低いために自然と上目遣いになる輝く瞳に、根っから捻ている庵はうっと言葉に詰まってしまう。 「……心の強さは個性だって、優斗が言ったんだからな。俺じゃない。俺は単純にお前よりもあの毒島とかいう野郎の方がムカついたから叩いてやっただけだ」 庵は熱くなった目尻を隠すようにプイと横を向いて言い訳をした。 「それでも嬉しかったです」 返ってきた柳の生暖かい声にはもう答えなかった。 「――い、庵さん」 しばらくだんまりを決め込んでいると、うわずった声で名前を呼ばれて、彼に視線を戻した。 「どうしましょう……っ」 あうあう、と困り顔の彼の肩に、女子高生が寄りかかって眠っていた。 「……役得じゃねぇの」 「困ります……」 柳は庵側の拳で自身のズボンをぎゅっと握り、庵の方へ体重が傾かないよう意識する。気を抜くと彼女に押されたまま彼に寄りかかってしまいそうで緊張した。 「しょうがねぇな」 しかし、そう呟いた庵は柳を横から抱きしめるように腕を伸ばしてきた。気づいたときには至近距離に彼の顔があって、思わずそれを直視してしまって、心臓が飛び出すかと思った。 庵は女子高生の頭を少し浮かせて、柳の肩と彼女の頭の間に手を入れて、元の位置に座り直す。 (悪化した……!) 彼と接触しないようにと思って緊張していた筈なのに、何故がすっかり肩を抱かれてしまった柳はこの状況に戦慄した。 「い、庵さん!」 「なんだよ」 「……なんでもありません」 「あっそう」 目的の駅まで後どれくらいだろう。赤くなっているだろう顔を俯けて、柳は意識を彼から離そうとする。 「お前、肩熱いな」 「そういうこと言わないでください!」 「うわ、ばか」 デリカシーのない彼の発言に思わず顔を上げると、バシっと掌で前を覆われた。目隠しをされる直前、彼の顔が見えたがそれも真っ赤で、 「……こっち見るんじゃねぇよ」 「……庵さん、照れてますか?」 消え入るような声で言った彼にそう聞くと、目隠しを外されてそのまま頬を抓られる。 「お前が可哀想なくらい意識してくれるもんだから伝染っちまったんだろうが。赤面症」 「赤面症なんかじゃありませんよ!」 「じゃあなんでこんなに真っ赤なのかな? 心臓もバクバク言ってんじゃねぇか」 「それは……っ」 貴方が相手だから、貴方がこんなに近くにいるから、こんなふうになってしまうのに…… じんと目頭が熱を持つと、覗き込んでいた彼がうっと顔を顰めた。 「あ! うわっ、すみません」 停車駅のアナウンスとともに扉が開くと、肩に凭れていた女子高生が慌てて飛び起きて電車を降りて行った。 庵は柳から両手を離して、扉側の手すりに身を寄せる。柳も腰をずらして彼から距離を取った。
2
二本の線路を大きなコンクリートの台で挟んだだけの小さな駅を降りて、商店街をしばらく進むと、白を基調とした比較的新しいアパートが見えてくる。共用の洗濯機を備え付けた学生専用のそこが、庵の住まいだ。 「あ、庵と柳君!」 アーチ型の門を潜ると、良く通る声で名前を呼ばれた。 すぐ近くの扉の前で、圭斗に後ろから抱きつかれた優斗が二人に手を振っている。 「どうしてそんなに密着してるんですか?」 柳が聞くと、優斗は腰に回された腕をぎゅっと握る。 「優斗が肌寒いって言うから」 「圭斗暖かいよ! 快適!」 「鍵開けたからさっさと入れ。弟には羽織るもん貸してやるから」 口々に言う彼らを庵が促した。 「庵優しい」 「そういうの要らないから」 「いや、貸さなくていいから。というか優斗に構うな」 胸の前で指を組んで感動する優斗に庵がシッシと手を振ると、優斗を抱き込んだまま圭斗が威嚇した。 冷蔵庫、ベッド、本棚、ラック、ローテーブル。最低限の家具しか置いていない八畳の部屋は、目立つ家具が少ないにも関わらず、床やテーブルに放置された資料や雑誌、空のペットボトルや出しっぱなしのグラスのせいで、ごちゃっとして見えた。 「そこら辺の雑誌寄せてスペース作って座れ」 言いながら庵はペットボトルとグラスをシンクに運ぶ。すぐに、水しかないから何も出さない、と言って庵が戻って来ると早速優斗が切り出した。 「それでは毒島について考える会を始めます。が、進行とかできないので雑談形式です」 「「大丈夫だ。求めてない」」 断りを入れる彼に圭斗と庵が口を揃えた。 ところでこの優斗、今現在も圭斗に後ろから抱かれ、彼を背もたれにして座っている状態だ。C棟でもやたら距離が近いと柳は思っていたけれど、椅子や机という障害物が無くなると、こうなってしまうのか。 「なんていうか、仲良いですね」 「うん。仲良いよ」 柳が感想を述べると、優斗は何でもないようにカラッと笑って答えた。眩しい。彼らを穿った目でみてしまうのは自分が庵のことを好きだからだろうか…… 「あいつらはあれが通常運転だから放っておけ」 逡巡する柳の思考は庵によって断ち切られた。 「そんなことより毒島のことだが、俺はあいつの言っていることは本当だと思う」 「俺は怪しいと思うけど。始終態度悪かったし」 庵の言葉に圭斗が意見すると、庵はフンと鼻で笑って彼を挑発する。 「俺はどこかの無能な心理学科と違って顔色読むのが得意なもので」 「なんだとコラ」 「誰もお前のことだなんて言ってねぇけど」 テーブルを叩いて身を乗り出す二人に柳がひやひやしていると、乗り出した圭斗に半ば潰された優斗が「仲良いな~」と呑気に呟いた。 「というか顔色読むのが得意だって言うなら、メラーの顔色も読めたはずだろ。信憑性が薄いんだよ」 「こいつの場合は第一印象が最悪だったからからな」 二人に指を指された柳の肩がびくりと震える。 「二人共雲行きが怪しいよ」 「自業自得だろ」 優斗の宥める声に庵は反射でそう返し、しかし隣で居心地悪げに俯いて縮こまってしまった柳を見てバツ悪く口を噤んだ。 「というか、毒島が本当のことを言ってるかどうかなんて、俺らが考えることじゃないだろ。あいつが信じさせてくれるかどうかだ」 同じく柳を責めるのは筋違いだと、圭斗が話を戻す。 「庵は信じるためにどんな材料が必要だと思う?」 「署名とか日記、あと誰かに相談しているならその記録とかかな」 庵に伺った優斗は、その答えに頷いた。 「署名は難しいよね。それやったらもし嘘でも本気は信じる」 「じゃあ、そう伝えとく」 「親切なの?」 「ハードル上げるだけ胸がすくだろう」 「またそうやって悪がる」 意地の悪い笑みを浮かべる庵に優斗がクスクス笑った。 しかし話が進んでいくほどに、柳の心は暗くなる。毒島から連絡があることが前提になった話し合いは、連絡があることが決定事項になったようで辛かった。 「あ、アイス食べたい。コンビニ行ってくる」 話し合いもそこそこに、各自でのんびりしていると、唐突に優斗が立ち上がった。 「お前一人じゃ迷うだろ。俺も行く。俺も食べたいし選びたい」 「はあ? お前と優斗二人にするわけねぇだろ。俺が行く」 それに続こうとする庵をすかさず圭斗が追いかけると、何故か優斗一人が戻ってきた。 「俺カップのバニラだったら何でも良い。柳君は?」 「え、俺ですか。じゃあ、優斗さんと同じでいいです」 玄関に向かって声を掛ける彼に続いて柳が答えると、庵と圭斗は言い合いながらも二人で出掛けて行った。 「なんだかんだ言って、あの二人も仲良いですよね……」 「うん! 二人って仲良いよな。当人同士は否定するんだけど、やっぱり仲良いよな!」 優斗の無邪気な声が柳の不安を煽る。 「あの、庵さんは僕のことが嫌いなんでしょうか……」 自分のことを好きだったら良いのに、との思いから出た質問だった。 「嫌いだったらこんなことしてないでしょ」 優斗の答えは柳にとって嬉しいものだ。しかし、だからこそ疑問が浮かんだ。 「そうですよ、どうしてそんなに真剣に考えてくれるんですか? 優斗さんにだって関係ないのに……」 瞳に不安の影を落とす柳に優斗はふわりと笑った。 「柳君に好きになって欲しいから」 「え!?」 「もー、柳君可愛いなぁ。その首引っこ抜いて持って帰っちゃいたい」 「だ、だめです」 「えー」 「えーじゃなくて……」 赤いメガネを揺らしてケラケラ笑う彼に、からかわれたことを知った柳は小さく溜息を吐いて眉を下げる。 「不安なの?」 しゅんと項垂れる彼に優斗が優しい声で尋ねた。 「……だって、毒島に会って、証拠を見せられて、どうすれば良いんですか……」 柳の言葉に優斗はキョトンと首を傾げる。 「どうして何かしなくちゃいけないの?」と。 「柳君は高校時代辛い思いをしたんでしょ? それが自分に悪いところがあったせいかもしれないって、思ったらもっと悲しかったんでしょ? だから俺は、実際は何が原因でそうなったのか知りたい」 優斗は神妙な顔で話を聞く柳にふふっと笑って続けた。 「毒島の話が本当なら柳君は何も悪くないね。土下座でもさせちゃえば?」 柳は彼の話を飲み込んだ。それでも納得いかない。 「そうしたら、許せますかね」 (許さないといけないんですかね……) 許したくなんてなかった。だって、彼のせいで自分の人生はめちゃくちゃになるところだったのだから。高校だけじゃない、今日だってそうだ。彼に会って、心が潰されるかと思ったのに……。もしここで彼を許して関係が修復したと思われて、また会いたいだなんて言われたらどうする? 彼が自分の生活圏に入ってきたらどうする? そんなのは耐えられない。もし彼が平気な顔をして優斗さんや圭斗さん、まして庵さんと話していたら、僕は…… 「別に、謝罪なんて向こうの自己満足でしょ。柳君が答える必要なんてないよ。柳くんは自分のためだけに毒島と話をすれば良い」 ぐるぐると巡る思考を、優斗の言葉が断ち切った。 「俺たちは毒島じゃなくて、柳君の味方なんだよ」 はっとして顔を上げる。柳の抱えていた不安は霧になって消えていた。 シャッターが閉まった商店街に、ぽつんぽつんと街灯が灯る。二人分の足音が肌寒い空気に溶けていく。 「お前、柳のこと好きなわけ?」 「……お前に関係ないだろ」 コンビニからの帰り道、圭斗の質問に庵はおざなりに返した。 「前科一犯」 「優斗はお前にやっただろ」 ――前科一犯――庵は酔った振りをして優斗の唇を奪ったことがあった。しかしそれも過去の話だ。 「でもお前、スキあらばって、思ってたんじゃねぇのかよ」 「……そうだな。でもそれを決めるのは俺でもお前でもない。優斗が心底お前に愛想をつかせて俺の方に傾くようなことになったら、遠慮なく掻っ攫う」 庵の言葉に圭斗の瞳が鋭く光る。空気がキンと緊張した。 「――と、思ってた」 しかしその一言で元の安穏な空気が戻ってくる。 「……なら良い」 「お前に許される筋合いはない」 「可愛くねぇな」 二人は軽い言い合いをしながらアパートに戻った。 「なんでこの短時間で……」 部屋に入った圭斗は、寄り添って寝息を立てる二人を見て呟いた。 「お前、弟起こしてアイス食べさせたら連れて帰れ。柳はここに泊めるから」 ベッドを整えながら庵が言う。 「いくら何でも手が早すぎるだろ」 「泊めるだけに決まってんだろ」 軽口を叩く圭斗に庵は枕を投げつけた。 ****** 風呂から出た庵が部屋に戻ると、柳が辺りをキョロキョロ見回していた。 「起きたのか」 「あの、二人はどこに?」 「帰った」 教えてやると、柳は「起こしてくれても良かったのに」と慌てて身支度を整え始めた。 「良い、お前は泊まっていけ。この暗い中、送り届けるのとか面倒くさい」 「一人で帰れますよ」 「一人で帰すわけないだろ」 庵はそう言ってタオル投げ渡す。 「風呂入って来い。大人しく俺の服を着て出て来いよ」 にやっと弧を描く口から飛び出したセクハラまがいの発言に、柳はぼっと顔を赤く染め上げた。 「庵さん、これブカブカなんですけど」 「はーん。思った通りガリガリのチビだな」 スウェットのウエスト部分を掴み、裾を引きずりながら出てきた柳に、庵は意地悪く言ってその姿をまじまじと眺める。下もそうだが上も大きく、半袖Tシャツの袖は彼の肘まで、裾は太ももまでを覆い隠していた。 「失礼ですね! て、ちょっと!?」 布の向こうの腰を掴むと、彼はびくっと跳ねるように後ずさり、声を上ずらせた。 「まあ寝るだけだし。履かなくても良いけど」 庵は唇引き結んで震える柳を解放してベッドに寄って布団を捲る。 「客用の布団とかないからここな」 「え、一緒に寝るんですか?」 「そう言ってる。お前壁側な。無駄に遠慮して端に寄りすぎて落ちそうだから」 動かない柳を「ほら、早く」と促すと、彼はやっとベッドに上がって横になった。続いて庵も隣に入れば、狭いベッドで肩が触れ合う。しばし沈黙が訪れ、柳は緊張に身を縮めた。 「お前今日優斗と何話した?」 「……首」 「首?」 「僕の首を引っこ抜いて持って帰りたいって」 ぎしりとベットが軋む。庵は身を乗り出して柳の細い首に手を触れ、サイズの大きなTシャツから晒された鎖骨に手を滑らせる。 「それだけか?」 ふるりと肌を震わせる柳に囁いた。 目を覚ます前と後、明らかにこいつの顔色が変わっていた。何か重圧解放されたような…… (あいつに嫉妬する日が来るとは思わなかった) 庵は無表情のまま、息を詰めて健気に睫毛を震わせる彼の、触り心地のいい頬を指先で撫でる。 「まあ、顔だけは良いしな」 「もう、さっさと寝てください!」 手を離すと、直ぐに拳が飛んできた。 (この人寝付くの早いな……) 規則的な呼吸を繰り返す庵を前に、柳はひとりごちた。 こっちは衣擦れの音にまでビクついて、ずっと心臓がバクバクいいっぱなしで眠れないでいるのに……。彼の触れた肩や腰が熱い。首筋がじくじく疼く。あんなセクハラまがいのことを平気でして、僕が告白したことを忘れてるんじゃないのか。 壁に背を付けて、憎たらしい顔を睨みつける。高い鼻をへし折ってやりたいと思った。 「くしゅんっ」 冷たい壁に体が冷えたのか、くしゃみが出てしまった。 「ん……っ」 彼が眉を寄せて身じろいだ。起こしたか、と思うと同時に、伸びてきた腕に抱き寄せられる。 「え、ちょっと!?」 「……冷たい」 小さな舌打ちが耳元で響いた。柳がおろおろしている間に、庵は柳をすっぽり腕の中に収めたまま、再び穏やかな寝息を立て始める。 首筋に吐息がかかってこそばゆい。触れている部分が多すぎて、全身の神経が敏感になる。布団の中、篭った彼の熱に抱かれて、息をすれば彼の匂いが胸いっぱいに広がる。同じシャンプーを使った自分も彼と同じ匂いがしているかもしれないなどと考えたらもう訳が分からなくなって、 (庵さんが、庵さんが、庵さんが……っ) 柳は意味もなく頭の中で、彼の名前を連呼した。
3
初めは、男のくせに整った顔をしているな、とその程度にしか思わなかった。けど、ふとある時、彼と目が合ってから、その瞳がとても綺麗なことに気がついてしまった。豊かなまつ毛に覆われた、すっと切れ上がった輪郭に浮かぶ海より深いその色は、ゆらゆらと波打ち瞬く度に光の粒を溢れさせる。 それから、彼の動作の一つ一つが気になるようになった。居眠りを起こされて指先を丸めてぐずる時、寒いと眉を潜めてマフラーに顔を埋める時、体育の後に不機嫌に汗を拭う時、彼を目で追っては胸が高鳴るのを感じて、おかしいと気がついた。 「永井って可愛いよな」 それを言ったのは、そう思っているのが、自分だけじゃないと言って欲しかったから。でも、相手は眉を潜めて、えっ、と引いた声を出した。 「いや、ていうか可愛くみえる仕草してるじゃん?」 「ああ、そういうことか」 「確かに」 慌てて言い直せば納得されて、その時はうまく誤魔化せたと安堵した。自分はやっぱりおかしいんだ。この気持ちは知られたらいけないんだと、蓋をした。 けど、次の日から学校がおかしくなった。 クラス中が彼を意識しているのに、誰も彼に話しかけようとしなかった。遠目で眺めて、ひそひそひそひそ。何を話してる? いつの間にこうなった? 「あ、毒島おはよう。そう言えば知ってる? 永井のシャーペンってピンクなんだぜ。ピンクなんて女の持ち物だよな」 「見ろよ、毒島。今日の永井は大人しいんだ。しかもよく見ると少し内股で、気持ちわるいよな」 状況を飲み込めないでいると、前日話をしたクラスメイトとその友人にそんなことを言われて、愕然とした。 「あ、毒島君」 「~~っ」 だから、彼に話しかけられて、逃げてしまった。 もしあの時誤魔化さないでいたら、ターゲットになったのは自分だったのだろうか。今彼をかばったら、自分の気持ちはばらされて、晒し者にされてしまうのだろうか。 怖くて何もできないでいる内に、彼は学校を休むようになった。 「毒島がお前のことをぶりっこだって言ったんだぜ。一人で友達面してたなんて可哀想だな。でも、付きまとわれてた毒島だって可哀想だと思うだろ?」 誰かが言ったその言葉に、彼ははっとして俺を見つめた。綺麗だった瞳は輝きを失って、澱んだその色を見ていられなくて、俺は何も言えずに目を逸らした。それが、彼を見た最後だった。 ****** 「証拠みたいなものはこれしか用意できなかったけど、信じて欲しい」 毒島は、ファーストフード店の奥まった席で、向かいに座る二人にレコーダーを差し出した。 庵と柳と毒島三人の予定を合わせた六月上旬のこの日、外ではしとしとと雨が降り出していた。 「これは?」 「本当の主犯との通話を録音した」 庵に聞かれてそう答える。柳に連れたってきた彼は、大学で会った時と違い、綺麗めのシャツにチノパンというきちんとした服装をしていた。はじめ見た時は、汚い身なりで胡散臭い男だと思ったが、今は紳士然としている。 「他の証拠が無いということは、今まで貴方は誰にも相談することもできずにただ一人で悶々としていたということですか」 「……」 確認されて押し黙る。穏やかな口調で微笑む彼の笑わない瞳に寒気がした。 「とりあえず聞いてみましょう」 庵はイヤホンを片耳に付けて、もう片方を柳に手渡す。彼の準備ができたことを確認して、再生ボタンを押した。 オープンスクールで柳と再会した毒島は、その日のうちにクラスメイトに電話をした。日を開けてしまえば、また気持ちが揺らいでしまうと思ったから。 「もしもし毒島だけど」 『毒島? どうした卒業以来だな』 「永井のことなんだけど」 『ああ、あのぶりっこがどうしたの』 早速切り出すと、彼は笑い混じりにそう返した。 「大学見学で会ったんだ」 『それで?』 いじめのターゲットに再会したのだと言っているのに、能天気な声色を変えない彼に苛立つ。 「……俺、あいつのことぶりっこだなんて言ったことないよな」 低い声を搾り出すと、彼は『は?』と怪訝気な声を上げた。 『言っただろ。可愛い子ぶってるって』 「俺は、あいつが可愛く見えるって言ったんだ!」 『は、ホモかよ』 「そうだよ!」 一気に冷たくなった声に勢いで返した。 「俺はあいつが好きなだけだった。それなのにお前らは、あいつのことを避け始めて……」 『何、そんなこと言うためにわざわざ掛けてきたわけ? そんなの今更だし、どうでも良いんだけど』 「なっ」 『大体お前がどう思っていようがあいつがぶりっこなのはクラスで万条一致だっただろ。だからああなったんだ。お前があいつを好きだから何? キモい奴が増えただけなんだけど』 散々なことを言われているのに、何も言い返すことができなかった。 『用件それだけなら切るからな。……たく、今更蒸し返してんなよな』 舌打ちとともに通話が切られ、毒島の胸に言いようのない嫌悪感だけが残る。 どうして彼にそんなことを言われなければいけないのだろう。自分は彼に何を期待していたのだろう。そこまで考えて、彼に電話をかけた理由を思い出した。 (そうだ。俺は永井に認めさせるために話をしたんだ。無駄に嫌な思いをしたわけじゃない) そう自分に言い聞かせて、冷たい受話器を置いた。 録音を聞き終えた庵は、隣でショックを受ける柳の肩を抱いて眉間を押さえた。こんなものを聞かせて、こいつは馬鹿か、と。 「……信じてくれたか」 縋るような瞳で見つめて尋ねる毒島に、柳はびくつきながら頷いた。 「……じゃあなんでそんなに嫌そうな顔してんだよ」 「ひっ……」 柳は逃げるように彼から視線を外して、庵の与えてくれる体温を意識する。 彼の――毒島の目が気持ち悪くて仕方なかった。 「それは貴方が、柳君のことを思い遣っていないからですよ」 「はぁ!?」 声を荒げる毒島に、庵は首を振って続ける。 「さっきのテープで分かったことは、『貴方は柳君に恋をしていた』『本当の主犯は開き直っている』『柳君がぶりっこなのはクラスで一致した意見だった。だから仲間はずれにされても仕方ない』……少し考えれば柳君が傷つく内容だと分かるでしょう? 柳君を想うなら、信じてもらえたかを伺うより先に、ぶりっこなんて思っていたのは一部で、他は空気に流されただけだと言いおくべきなんじゃないですか」 「俺は、ただ信じてもらおうと思って……」 毒島が口を開くたびに、柳は胸に黒く重い何かが渦巻くのを感じた。 庵は一つ溜息を吐いて続ける。 「信じましたよ。貴方は何もしていない。きっかけを作った癖に見て見ぬ振りをしていただけなんでしょう?」 「だって、どうしたら良かったんだ」 毒島は胸の痛みに眉を潜める。言いたいことは山ほどあるのに、言われっぱなしではいたくないのに、彼の一言一言が胸に刺さって、何を言えばいいのか分からなかった。 「だって、でも、分からなかったから、動けなかったから、自分は何もしていないから。――言い訳をしたって過去は変わらないんですよ。いつまで自己保身を続けるつもりですか」 「だから悪かったって言って」 「言ってません」 言葉を遮られてハッとする。 「あなたはこれまで一言も『悪かった』だなんて言っていません。ただ、自分の罪がどれだけ軽いかを主張しただけです」 自分は、その一言すら言っていなかったのか、と。 毒島は改めて、柳の顔を見た。彼の瞳は、今も濁ったままだ。 学校見学で彼を見かけたとき、彼の表情が昔に戻っていた気がして嬉しかった。構内歩く彼の瞳は前と同じ輝きを持っていた。だから、高校時代のあれは、ただの過去の出来事なのだと、今はもう関係ないのだと思ってしまった。でも、自分と話す間に彼の瞳はどんどん曇っていって…… 永井が俺を許さないのは俺のせいなのに、永井の瞳を曇らせているのは俺なのに、心を開かない永井が悪いのだと思い込んだ。分かっていたのに我が身かわいさに見ないふりをした。俺は柳を好きだと言いながら、自分のことしか考えていなかったのか。 「……永井、ごめん。悪かった」 最低すぎる自分に幻滅して、声が震えた。 「……うん」 「永井! だから!」 機械的な返事をしたまま何も言わない柳に、どうしようもなく詰め寄ると、柳はガタンと音を立てて立ち上がった。 「……分かった。分かったから! もういいだろ!?」 柳は声を荒げると、机の上の拳を強く握った。やっと顔を上げた彼の瞳は涙で揺れている。 「庵さん、ごめんなさい……」 「どうして謝るんですか」 庵は項垂れる柳の頭にポンと手を乗せて宥め、柳の行動に固まっている毒島を諭すように口を開いた。 「毒島君、私が貴方と柳君を会わせたのは、苛めが柳君のせいじゃないと証明されることが柳君のためになると考えたからです。決して、柳君に無理やりあなたを許すと言わせてあなたの気持ちを楽にするためじゃありません」 柳を促し、席を立つ。 「そんなっ」と、呼び止める毒島に、顔だけで振り向いた。 「そういうわけで、お話はこれでお仕舞いです」 寄り添いながら二人が出て行くと、賑やかな店の隅に、毒島一人が取り残される。雲の切れ間から覗いた太陽が、彼の頬を白く照らした。 ファーストフード店を出てしばらく。人気のない通りに出ると、柳は隣を歩く庵を引き止めた。 「あの……庵さん」 服の裾を掴まれた庵は立ち止まり、振り向く。 「僕、やっぱり庵さんのこと……」 柳は溢れる想いを口に出しかけて、彼の目を見て飲み込んだ。 だって、伝えてどうなる? なんのために伝える? さっき、毒島と彼の会話を聞いていて辛かった。彼の言葉は、毒島だけじゃない、後ろめたい気持ちを持つ柳の心にも突き刺さった。 ――過去はなかったことにはできない。 柳が庵に送ったメールも、なかったことにはできない。彼に嫌われていても仕方ない。一度振られているのに、しつこく告白したって迷惑がられるだけじゃないのか。 毒島に好きだと言われて、吐き気がした。そんな目で僕を見るな、と叫びたかった。彼だって同じだ。 「いえ、なんでもありません。……今日はありがとうございました」 醜く歪んだ顔を隠して頭を下げると、暖かい体温に包まれる。 「頑張ったな」 ぎゅっと抱き絞められて、そんな優しい言葉を掛けられたら、もうダメだった。 「……好き、です」 ついに、言葉にしてしまった。 自分は今日だって何もできなかったのに、本当は自分が彼に立ち向かわなくちゃいけなかったのに、良いところなんて何も無いのに、最低だ。 「ごめんなさい、僕なんかが好きでいてごめんなさい……っ」 柳は突き放されることを覚悟して身を固まらせた。 「あのさ」 しかし庵は、びくっと肩を震わせる彼を一層強く抱き締める。 「俺も好きかもしれない」 「は?」 「付き合うか」 「え?」 柳は耳に響く彼の言葉が瞬時に理解できずに、呆けたままぼろぼろ涙を零した。頭では理解できないのに、心はもう嬉しくて嬉しくてたまらなくて、溢れるそれを止められない。 「あ、ばか泣くな!」 「だってぇ、庵さんがぁ……っ! 曖昧なことを言って僕を弄ぶからぁ……っ!」 「ああ、うん。ごめん。悪かったって。好きだよ、泣くな?」 「もっと言って下さい~っ!!」 「気色悪いな」 庵は言葉ではそう言いながらも、柳の横髪を避けて、耳元に唇を寄せて囁く。 「柳、好きだ」 甘く響く重低音に、柳はゾクリと肌を震わせた。つま先まで痺れが走る。 「は、はいぃ!」 「気色悪い声出すなよ」 庵は、瞳を蕩けさせて声を裏返す柳を罵りながら、彼のサラサラの髪を梳いた。 「優しくするなら最後までちゃんとしてください!」 「ちゃんと優しくあやしてやってるだろ。俺が泣かせてるらしいし」 「……っ、すみません涙止まりません……」 「ああ、もう良いから泣いとけ」 鼻声の柳の顔を肩に押し付けて背中をさすってやる。しばらくそうしていると、やっと泣き止んだ彼が顔を上げた。涙は止まったが、鼻も額も赤くした不細工な顔だった。 「僕、庵さんは優斗さんか圭斗さんを好きなんだと思ってました。――ってすごい顔してますよ」 その上やっと口を開いたかと思えばそんな突拍子もないことを言う彼に、庵は盛大に顔を顰めた。 「弟はともかくどうして兄が出てくる」 「だって仲良いですよね」 「良くない!」 真剣に言っている彼を叩いて頭を掻く。 「あれはあの二人ができてんだよ」 「あ、そうなんですか……」 柳は噛み締めるようにゆっくり瞬きをして、また大きな瞳できゅっと視線を合わせてきた。これはまだ何か言ってくるな、と身構える。 「あの、じゃあ優斗さんが好きなんですか……っ!?」 庵は彼の顎を掬うと、くだらないことばかり喋る口を唇で塞いだ。
迷惑メール 付きまとう影<完>