
科学者の恋人

科学者の恋人
![]() ロボット爆誕
ロボット爆誕 ![]()
雨風吹き荒れる嵐の夜、小さいながらも、最新機器を取り揃えたラボで、台に横たわる女性を前に白衣の男が呟いた。 「完成だ……」 男の名前は増見智恵理(ますみちえり)。齢二十歳ながら、世界から注目される若き天才科学者である。 横たわる女性は、彼の持つ技術のすべてをつぎ込んだアンドロイド “真理” 。柔らかな肌に、緩く波打つ粟色の髪、関節の柔軟性から肌の質感まで丁寧に丁寧に仕上げたそれは、本物の人間、それも見目麗しい美女にしか見えなかった。 智恵理はうきうきとステップを踏みながらコンピュータに向かう。モニターに並ぶ数字とアルファベットは、彼女の行動のすべてをつかさどるデータだ。優しく大らかという “性格” に加え、年相応の “生活知識” と “学力” 、疑問を持ったら首を傾げる、困った時には眉を下げるといった “感情に対する反応” 、自分の意思で行動し、新しい知識を蓄える “学習システム” が詰まっている。 「後はこのボタンを押すだけ。そうすればやっと、やっと女性から解放される……!」 アーッハッハッハッハッハッハ!! 智恵理は笑い声を高々と響かせボタンを押した。その時、轟音が響くと共に智恵理の体にビリッと電気が走る。驚いて叫び声を上げた瞬間、電気系統が一斉に落ちた。 「な、なんですか!? 雷!?」 掌を動かしてみると、若干痺れは残るものの問題は無いようだ。 しかし智恵理自身に問題は無くとも、ロボットは様々な機械に繋がれている。雷によってそれらが誤作動を起こせば、ロボットにも影響が出てしまうだろう。 「このラボは雷ごときで機能しなくなるようなものではない筈なのに……っ」 ロボットの様子を確認したいが、窓の無いラボでは目の前に翳した自分の手すら見えない。じりじりと焦りを感じていると、やっと自家発電に切り替わり、照明が復活した。 「真理!」 智恵理は慌てて振り返り、目を見開く。そこに真理の姿は無く、代わりにギンと目つきの鋭い裸の男が座っていたのだ。 「は、な、な……っ! 不審者! 不審者!!」 「ああん?」 上擦った声で騒ぐ智恵理に、男はどすの利いた声で返した。堅気とは思えない眼力と声の迫力に、智恵理は「ひぅぅっ」と空気が抜けるような声を出した。しかし、怯えている場合ではないと、及び腰ながらも拳を握りしめる。 「ま、真理を、僕の真理をどこにやった!?」 「はあ? 俺が真理だろうが」 「はあ!?」 「ああん!?」 再びの「ああん!?」に、びくっと体が跳ねる。なんなんだこの「ああん!?」の威力は、どうしたってその道の人だろう。 「そ、そんなわけ……」 それでも智恵理は男の体を目で確認した。男の裸何て見たくはないが仕方ない、別に女の裸なら見たいのかというとそうでもないが、とにかく見た。 「はぁぁああああ!?」 驚いて、思わず男に駆け寄る。男の体には真理に繋いでいたはずのコードが繋がっていた。 『白百合の魔法使い』 それが白百合大学に在籍する智恵理の通り名だ。 幼いころから神童と呼ばれた智恵理は、提示された問題はどんなものも特に悩むことなく答えを出すことができた。特に数字が好きで、無心で数字を追うことに楽しみを見出した。そんな中、彼は科学と出会う。数字によるデータを集めて、たくさんのことを知り、生み出す。独創的な発表を繰り返す彼は、いつしか魔法使いと呼ばれるようになった。 しかし、そんな彼にも悩みがあった。 ふわりと緩くカールする艶々の黒髪に、キュッと綺麗に釣ったアーモンドアイ、肌理の細かい白い肌、すらっと伸びた四肢。将来を約束された才能に加えて、器量にも恵まれた智恵理には、言い寄ってくる女性が多すぎた。キャンパスを歩けば囲まれる。静かな空間が好きな智恵理にとって、騒がしい女性の甲高い声は耳障りだった。加えて、恋に狂った人間は怖い。 その気が無いと言えば、「でも、付きあってる人が居るわけじゃないんでしょ?」などと迫り、「実験に集中したい」と言えば、それでも良いと粘る。なし崩しに付きあえば、「愛が無い」とか「恋人なのに」とか「実験と私どっちが好きなの?」なんて、最初から気持ちは無いと言っているのに詰ってきて。酷い時には、誰それを傷つけやがってと、第三者に罵られもした。 「――大体、近頃の女性は押しが強すぎるんです! 僕は恋愛には興味が無いと言っているのに!! 色恋沙汰に巻き込まれるのはこりごりなんですよ!」 智恵理はバンっとテーブルに手を突いた。ちゃぶ台だったらひっくり返しているところである。 突如現れた不審な男を真理と認めた智恵理は、彼を地下ラボから居住空間に上げ、衣服を着せてソファーに座らせ、状況の確認をしていた。 「そんなことより、この部屋変な匂いしねぇか?」 「そんなことよりとは何ですか! アロマですよ! 一応初対面ですから、リラックスできるようにと焚いたのに。良いですよ、嫌なら消しますから」 「嫌とは言ってないだろ。変って言っただけで」 「我慢してもらわなくても結構です」 智恵理はむすっとする真理を無視してアロマポットに蓋をした。イライラするべきはこちらの筈なのに、真理が機嫌を悪くする理由が分からなかった。 こっちは自分の作ったロボットだからとそれなりの扱いをしているのにこの男ときたら、やれ服の趣味が合わないだ、やれ家具が乙女趣味で気持ち悪いだ、やれハーブティーは好かないだと、さっきから失礼極まりない。 「とにかく、そういう訳で女性から逃げるために貴方を造ったんです。いっそ恋人を作れば誰も寄ってこないと思って、それなのに……」 智恵理は身を乗り出して、テーブルを挟んで向かいに座る真理の顎を掴む。 「大きなつぶらな瞳は何処ですか、ふわふわの頬は? 手に馴染む髪は? ふくよかな胸は? くびれた腰は?」 「あんた本当は結構女好きだろ」 捲し立てる智恵理に真理が呆れて言うと、彼は真理を突き放して仁王立ちで腕を組む。 「お黙りなさい! 恋人のふりをさせるのですから、女性にするに決まっているでしょう! 女性が好きとかいう話ではありません」 智恵理の指がせわしなくコツコツと二の腕を叩く。それを見て真理は、さっきのアロマやっぱり焚いたままの方が良かったんじゃないか、と思った。 「でもさ、男の方がいっそう女が寄ってこねぇんじゃねぇの? ゲイってことだろ?」 「なっ!?」 真理の言葉に智恵理が目を見開く。 「……貴方、意外と賢いですね……」 生みの親に対して何だが、「あ、こいつ馬鹿だ」と真理は理解した。 ****** 「真理、真理!」 「う、ん……」 揺すり起こされて吐息で答える。 シャッとカーテンを開ける音と共に差し込んだ光に目を顰めて身じろぐと、真理の細く真直ぐな髪が枕に散った。 「まったく。休みだからといって、いつまで寝ているおつもりですか。ちゃっちゃか起きなさい、ちゃっちゃか。布団片づけて顔洗って、朝ご飯食! 貴方が食べないと片付かないんですからね!」 「……休み……?」 口うるさく喚かれて、真理はしぶしぶ身を起こした。昨晩智恵理から与えられたベッドは清潔で、ふわふわな布団はとても心地よくて、いっそ彼ではなく布団の恋人になりたいと思った。 「ああ、まだ日にちの感覚がありませんか。ゴールデンウィークですよ」 「……じゃあ」 「布団に戻るな!」 再び布団に潜ろうとしたら、その布団をはぎ取られた。 食卓には、焼き立てのパンに、生野菜のサラダと、ふわふわのオムレツとカリカリのベーコン、オニオンスープが並べられていた。 「……これ、普通に食べて良いのか?」 「大丈夫ですよ。恋人として一緒に食事ができるように造ってありますから。味も感じますし、稼働エネルギーにもなります」 「へぇ」 真っ白い器に盛られたそれらは、彩りも鮮やかで、香りも豊かでとても美味しそうだ。作り物の体ながらに食欲をそそられて、本当に自分の体は良くできていると感心する。 トーストに卵を乗せて食べると、ふわふわとろとろの卵と、さくっと香ばしいトーストが口の中で魅惑のハーモニーを奏でた。 「美味い」 思わず出た真理の素の感想に、智恵理はふふんと得意げに笑う。 「この僕が作ったのですから当然でしょう」 真理は、しゃららと効果音が付きそうな仕草で前髪を掻き上げる彼の、その髪を一房手に取った。 「な、何ですか!?」 「なんか、今日、昨日と違うな……」 いきなりの接触に、智恵理は弾かれるように真理の手を振り払うが、意図が分かると気を取り直して自身で髪を梳いた。 「ふふん。真理のくせによく気が付くじゃありませんか。今日は快晴ですからね。僕の美形が際立つでしょう!」 「あー?」 美形うんぬん関係なしに思ったままを口にしただけの真理は、突然上機嫌なった彼を変な奴だな、と思った。 「雨の日は髪がまとまらなくていけませんね。髪型が決まらないと気分も落ち込みますから、始終イライラしています」 「女子かよ」 「失礼な。どこからどう見ても立派な日本男児でしょう」 「?」 真理の思う日本男児は決して彼のような人ではない。自分の知識のデータは彼が入力した筈なのにおかしい。 「そんなことより、今日は貴方の動作テストをしますから、しっかり食べて頑張ってくださいね」 智恵理はやはり日本男児にあるまじき優雅な仕草で癖毛を耳に掛けて、スープを口に運んだ。 「サボるな!」 モップの柄に顎を乗せて息を吐く真理に智恵理の叱咤がとぶ。 朝食を食べ終えた真理は、ジャージとマスクを渡され、手始めに食器の片づけ、そのままキッチンの掃除、次に廊下と部屋の掃除と、散々にこき使われていた。 「あ、今不満そうな顔をしましたね。生意気な」 智恵理は腰に手を当てて真理を一睨みする。 「動作テストって、ただの掃除じゃねぇか」 「もともと真理には生活に必要な動作データしかインプットしていませんから。これで良いんです。あ、そこ角までしっかり! 横着しない!」 言葉だけ聞くと、シンデレラをこき使う意地悪な継母のようだが、割烹着と三角巾とマスクというフル装備の智恵理は、真理以上に働いていた。だから、真理も文句は言いつつも手を動かしているのだが、自分はしっかりやっているつもりなのに、文句ばかり言われれば腹が立つ。 「細けえんだよ、潔癖症か。て言うかなんで、そっち拭いてんのに、こっち見えてんだよ……」 「……何か、言いましたか?」 「潔癖症! 地獄耳! 千里眼!」 真理がぶつぶつ文句を言っていると耳ざとく聞き返された。思っていたことをそのままぶつけると、智恵理は無言で物を投げてきた。ヒステリーだと思った。 「まあ、こんなものですかね」 「こんなものって、十分すぎるだろ……」 肌を気遣いながらタオルで額の汗を叩いて満足げな智恵理に対し、真理はジャージの裾で乱暴に汗を拭って息を吐いた。 あの後結局、ガラスも磨いて、風呂場タイルのカビ取りまでしたのだ。住居空間は隅々まで綺麗になった様に真理には思えた。 「おや、もうこんな時間ですか。真理、昼食を用意してください」 時間を確認した智恵理が、床に座り込んで休む真理に言った。 「はあ!? まだ働かせるのかよ!?」 「当たり前でしょう。恋人(仮)なんですから。朝ご飯は僕が作ったんですから、お昼は貴方が作ってください」 「はー……」 「はー、じゃないでしょう。はい、でしょう」 「ハイ……」 真理は渋々腰を上げてキッチンに向かった。 「どういうことですか」 出された料理を見て智恵理は神妙な顔で呟いた。 献立はいたって一般的な合挽き肉のハンバーグとサラダと野菜スープ。だが、ハンバーグは周りが真っ黒に焦げているのに中は生焼け、ソースとスープは色々な調味料の味が混ざりすぎて匂いからして気持ち悪くなる、という粗悪品だ。 「見たまま」 「……どういうことですか」 「るっせぇな! 失敗したもんは仕方ねぇだろうが!」 じっとりと見つめてくる智恵理に、真理は怒号で返した。ドスの効いた巻き舌での反論に彼がびくっと身を縮める。 「し、しかし、料理の仕方もインプットした筈だったんですけどねぇ……」 それは真理にも分かる。何も知らなければ、野菜は切れなかったし、フライパンをコンロにかけることもしなかったはずだ。だから、自分が思う通りにやればできると思ったのに、結果はこれだ。 「まあ、良いです。きっと雷の影響でしょう。作り直しますから待っていなさい」 智恵理がサラダ以外の料理を盆に乗せて席を立つ。それを目で追って、真理は「あ……」と声を上げたが、地獄耳の筈の彼は振り返らない。 真理なりに栄養バランスを考えて、味付けも工夫して一生懸命作ったはずだったのに、きっとあれは捨てられてしまう。たかが一食分の料理だが、生まれたばかりの真理がしたことはまだ、掃除とこの料理だけ。だから、たかが一回の料理を無駄だと言われることをとても空しく感じた。 「あ! ジャガイモも人参も、皮を厚く剥き過ぎですよ!」 「うるせぇな!」 (それだって、うまくいかなかったんだから、仕方ないだろう) 「真理、できましたよ」 「……」 「何変な顔してるんですか」 「うるせぇ」 智恵理が持ってきたのはスパイスの香るカレーライスと、厚く剥き過ぎた皮を揚げた野菜チップスだった。 「さっきの……」 「全部煮込みましたよ。食材がもったいないでしょう」 それを口に運んで智恵理が笑う。 「いつものカレーとは違った風味です。真理の味付けが良い隠し味になったようですね」 真理はもやっとした気持ちに顔を顰めて、ご機嫌な彼からそっと目を逸らした。何故だか胸がむかむかした。 「データに問題は無いみたいですね……」 地下のラボで、智恵理はモニターから目を離して寝台に横たわる真理を覗き込んだ。 「なのにどうして、こんな野蛮で大雑把な性格に……」 「昼の失敗を全部煮込んでカレーにした奴に言われたくない」 真理は、大概失礼な彼にそう返した。 「誰の所為ですか、誰の!」 途端に彼はプリプリ怒り出す。自分から話題を振ってきたのに変な奴だ。 「どっか間違ってんじゃねぇのか」 「僕が間違えるわけがないでしょう、まったく。料理はできないし、掃除も言われたことしかできない。きっと部屋が散らかっても、埃が溜まっても気にならないんでしょう? 信じられない。言動にも知性が感じられませんし、これでは記憶力や学力の方も心配ですね」 「あんたさ……」 真理がじっと見つめると、智恵理はびくっと肩を跳ねさせた。 「な、何ですか。僕は事実を口にしているだけですからね」 真理はただ見ているだけなのだが、とにかく目つきが悪いために睨みつけられたと勝手に勘違いした智恵理は、思わず声を上ずらせる。 「……あれだな。しゃべり方マダムだな」 「誰がマダムですって!?」 智恵理の怒りの声が響いた。んもー! と牛のように唸る彼に、真理は「思ったことを言っただけなのに、何を怒ってんだ?」と不思議に思った。
科学者の夢
――待って、行かないで! 彼の背中を追いかけて手を伸ばす。追いかけなければいけない。でも、追いつけない。手が届かない。 もっと早く足を動かせ、もっと大きく声を張れ。 気付いて、振り向いて、止まって、待って、僕を置いて行かないで……! 彼との距離が徐々に縮まる。その背に手が届いた。彼に触れた指先から感情が溢れ出ていく。ピンクとも、黄緑とも言えない、オーロラ色のそれが、ぶわっと智恵理の体を包んだ。 ――やっと捕まえた。手が届いた。やっと、やっと……。 智恵理は目を覚ますと、天井に手を伸ばして泣いていた。 「……顔、浮腫むじゃないですか……」 智恵理は物心の付いた頃から、同じ夢を見続けていた。 毎日夢で、見知らぬ男の背中を追いかけ続けた。ただ、追いかけなければいけないと思った。捕まえたいと思った。でも、どんなに足を動かしても、大きく声を張り上げても、彼に届くことは無く、毎日目が覚めると焦燥感に胸が押しつぶされそうになった。 現実では神童と呼ばれ、科学に嵌った。それから、知識を蓄えるごとに夢の背中が近づいていることに気が付いた。きっと、この後ろ姿は、科学の心理そのものなのだと思った。 もっと勉強すれば、きっとこの背に手が届く。この背に届けば、きっとこの胸の痛みが無くなる。 そうして智恵理は、いつしか魔法使いと呼ばれるまでに成長していた。 女に興味は無かった。だからと言って男にも興味は無かった。どんな相手を見ても、夢の中の背中の方が魅力的に思えた。この胸の痛みを恋と呼ぶならば、自分はずっと彼一人に恋をしているのだろう。 「ちょっと貴方、もっと優雅に食べられないんですか。カチャカチャカチャカチャ食器を鳴らして」 「細けぇな」 「マナーの問題です」 音を立てずにスープを口に運ぶ智恵理を見て、真理は訊いた。 「なあ、あんたさ。何で俺をスクラップにしねぇの? 失敗作なんだろ?」 「貴方、壊されたいんですか? 変わっていますね」 智恵理に適当に流されて、むっとする。真理は、彼の真意を測りかねて、そのすました顔を見つめた。 「……夢見が良いんです。どうだって良いでしょう」 智恵理は彼の視線から逃れるように目を伏せ、今朝の夢を思い出す。 (真理を作ったその日から、あの背中に手が届くようになったから……) 長い睫毛が、柔らかな頬に影を落とす。心ここにあらずの智恵理を、真理は訝しげに眺めた。 ****** 智恵理のセンスは世間一般から外れている。 彼は男のくせに、女でも着ないようなフリルのシャツやバラ柄のシャツを好んで着た。しかし、智恵理には何故かそれらが似合った。ふわふわのフリルも、エレガントなバラ柄も、彼のために作られたのかと思うほどにしっくりきた。 そこらを歩いている人が、彼と同じ服装をすれば、笑い話にしかならないだろう。だから当然、それらを真理が着ればただのセンスの悪いそれになり下がった。 「真理にはどんな服が似合いますかね」 智恵理はそう言って何着も試着させ、いくつも店を梯子して、両手にいっぱいの服や小物を買った。次々商品を選んで渡してくるのは智恵理だが、最終的に選んだのは真理だ。華やかな智恵理と対照的に、黒を基調にしたシックなコーディネートにまとまった。真理が選ぶ服は、絶対に智恵理の趣味ではないだろうに、智恵理が文句を言わないどころか、似合うなどというものだから、真理はカレーの件に引き続き、また胸がムカつくのを感じた。 服や小物など、真理の為の買い物を一通り終えた二人は、遅めの昼食を取りに、智恵理行きつけのカフェ、「お菓子の庭」にやってきた。 たくさんの花が植えられた花屋のような庭から、ガラス暖簾を潜って店内に入る。 「あ、増見だ。久しぶり~」 店主であり、智恵理の幼馴染である花名荘一郎(はなそういちろう)が空気の抜けるような声を掛けてきた。 「先週も来たはずですけどね」 「でも、昨日は来なかったよ?」 毎日来なければ久しぶりになるのだろうか、彼の感覚は幼馴染の智恵理にさえ良く分からなかった。 「Aランチ二つ。飲み物は後で決めます」 智恵理は注文をして適当なテーブルに着いた。 「智恵理さん智恵理さん、明様がさくらんぼ持って来てくれたんですよ!」 「甘いですよ」 カウンター席に座る二人の女性が智恵理を振り返った。 「って、あ! 美人がイケメン連れてる!」 「絵になりますなぁ」 頭の悪そうなツインテールの女性、綾坂まゆみが真理を見て言うと、その隣で丸顔ショートカットの桜井美樹がむふふんと笑った。 「さくらんぼですか」 「うちで採れたさくらんぼよ」 肩にかかるふわふわの髪の女性、愛場明が振り返る。鼻筋の通ったきつめの美人だ。彼女はまだ来たばかりの様で、ショルダーバックを肩に掛けたままだった。 「たくさん頂いたので、明日はチェリーパイを作ろうと思います」 荘一郎の腕の中で、籠いっぱいのさくらんぼが、宝石のように艶々と輝く。 「お礼にケーキセットをサービスしてくれても良いのよ」 「もちろん。ケーキと飲み物は決まってますか?」 「ガトークラシックと、飲み物は……そのさくらんぼで何か作ってくれない?」 「かしこまりました」 荘一郎が厨房に引くと、明は智恵理たちのテーブルにやって来た。 「同席させて下さらない?」 「もう座っているじゃありませんか」 「私と貴方の仲じゃない」 自由に振舞う目の前の美人を、智恵理は溜息一つで受け入れる。 白いクロスのかかった丸いテーブルには、椅子が四つ並べてあり、三人で食事を摂るのにスペース的には問題無い。 「どんな仲だよ?」 いきなり初対面の女性に同席された真理が当然の質問をすると、カウンター席の二人が振り返った。 「明様は『山百合の魔女』なんですよ」 「山百合の魔女?」 「あれ? 智恵理さんが『白百合の魔法使い』って呼ばれてるの知りません?」 「二人とも世界に注目される天才科学者で、白百合大学に通う智恵理さんは、『白百合の魔法使い』山百合大学に通う明様は『山百合の魔女』って呼ばれているんですよ。――ハ!」 美樹と交互に紹介していたまゆみが、閃いた! とツインテールをぴょんと跳ねさせた。 「ちえり、ちぇり、チェリー……チェリー!」 「誰がチェリーですか!」 キタコレ! と瞳を輝かす彼女を智恵理が一蹴した。 「嫌なの? チェリー」 「なんか、こう……嫌です」 瞳で笑う明に、歯切れの悪い返事をする。 「チェリーボーイみたいだもんね」 「な、な、な、荘一郎!!」 智恵理はランチセットのサラダを運んできた荘一郎の言葉に、顔を真っ赤にして取り乱した。 「チェリーの癖に」 真理が真顔でボソッと呟くと、智恵理はバンとテーブルに手を突いた。 「真理!! 貴方たち、淑女の前ですよ! 自重なさい!!」 「あー、ごめんごめんチェリーさん。ランチセットのサラダです」 荘一郎は彼の怒りをしれっと流す。 「もー!! まったく、んもー!!」 「牛か」 唸る智恵理に真理がつっこんだ。 「誰が牛ですか!」 「まあまあ、チェリーさん。そんなに興奮しないで」 明がひらひら掌を振る。 「チェリーと呼ぶのをお止めなさい!!」 三人におちょくられて、智恵理の血管が切れそうだった。 真理は生ハムのサラダスパゲッティを頬張った。シャキシャキと歯ごたえの良い瑞々しい野菜と、濃いピンクに艶めく生ハムが華やかな色彩を生む。あっさりした特性ドレッシングに、生ハムの塩気が絡んで深い味わいを生み出していた。 「美味い」 「ああ、ほら。そうやって一気に口に運ぶと口の周りが汚れると言っているでしょう? はしたない」 「ん」 智恵理はナプキンを取って、口いっぱいのパスタをもきゅもきゅ食べる真理の、口元のドレッシングを拭ってやる。その一連の動作を見た美樹とまゆみが「うぉぅ」と声を漏らした。 「何です?」 二人の視線に智恵理が気付いて声を掛けると、まゆみは「仲が良いんですね!」と胸の前で拳を振った。 「家じゃもっと口煩いぞ」 「煩いとは何ですか」 真理の言葉に智恵理が反論する。 「家で一緒にご飯食べてるんですか?」 「俺、こいつの恋人だから」 「えええええ!! うっそおおおお!!」 「ああん!? 嘘じゃねぇよ!!」 ツインテールをぶわっと広げて叫ぶまゆみに、真理がドスを効かせる。 「ガラが悪い!」 咄嗟に智恵理が彼を叱った。 「ちっ、否定されるとムカつくんだよ」 「ごめんなさい。でも何で!? 何でチェリオさんとそうなったの!?」 「チェリオ?」 舌を打つ真理にまゆみは素直に謝ったが、彼女の「チェリオ」呼びに智恵理が首を傾げる。 「チェリーがダメならチェリオかなって。智恵理さん男ですし」 IQが20違うと話が合わないと言うが、本当に彼女の思考は分からない、と智恵理は思った。 「チェリオさんのどこを好きになれたの?」 「チェリオと付きあうなんて……お母さん穢してる気分にならない?」 しかし、天然なのか悪乗りなのか、美樹と荘一郎まで彼女の付けたあだ名を使い始める。 「貴方たち大概失礼ですよ! 特に花名! 誰が貴方の母親ですか!」 「チェリオさんの良いところなんて、顔に決まっているじゃない」 と、明まで。しかもその内容が酷い。 「顔しかないみたいに言わないでください!」 「俺、顔の良い悪いは分からない」 「じゃあ、無い」 真理の言葉に、明は「顔が無いなら良いところなんて無い」と言い切った。 「無い!?」 「こいつの好きなところ……」 真理はショックを受ける智恵理の顔をじっと見つめて顎に手を当てる。 「悩むな!」 智恵理は熟考して黙り込む彼の腹に手刀を入れた。 ****** 真理が来てから、夢の彼の背中に触れることができるようになった。それから、徐々にもっと近づけるようになった。肩を掴めるようになって、体に腕を回せるようになって、今日は遂に抱き締めた。どうしようもなく、この人が好きなのだと感じた。一歩進むごとに、ふわふわした幸せが心を見たす。でも、それだけじゃ足りなくなった。 顔が見たいと思った。でも、回り込もうとしても、そこに壁があるかの様に進めない。こちらを向かせようとしてもびくともしない。 足りない、足りない。好きなのに、好きなんだ。顔が見たい。名前が呼びたい。 ギュッと、彼を抱く手に力を込める。すると、彼が振り返った。その腕に抱きしめられる。嬉しい。温かい。しかし、その顔は黒く塗りつぶされていて分からなかった。 「……だれ?」 自分の声で意識が浮上する。ぼんやりと瞼を持ち上げると、すぐ目の前に真理の不機嫌そうな顔があった。 「うわっ」 何故か同じベッドに入っている彼に悲鳴を上げる。 「どうして、一緒に寝ているんですか!?」 「恋人だからだろ」 「いやいやいやいや!」 「うるせぇな。魘されてたから来てやったんじゃねぇか」 真理はベッドの端に逃げようとする智恵理が、ベッドから落ちるのではないかと思い、咄嗟にその腰に腕を回して引き寄せた。 「ちょ、何っ!?」 「あんたさ、仕草が色っぽいって言うか。例えば飯食う時とか髪を耳に掛ける仕草がこう、くる」 「は!?」 突然、密着するような体勢でそんなことを言われ、智恵理はぶわっと頬を染めて目を見開いた。 「その顔、初めて見た。顔の優劣は分からないけど、表情が変わるのが面白いとか可愛いとかは思う。ビビったり、怒ったりするタイミングは訳分かんねぇけど、どんな顔してても面白れぇな、って思う。あ、こら逃げんな」 「な、んで……いきなり」 真理は逃げようとする彼の手首を掴むと、その手がすごく熱いことに気が付いた。 「あんた、熱いぞ。大丈夫か?」 指摘すれば、かっと充血した瞳が睨みつけてきた。 「だ、れの所為ですか!」 智恵理は見下ろしてくる真理の視線から逃げるために顔を背ける。男に組み敷かれる日が来るとは思わなかった。しかも、自分の作ったロボットに。 「バラ柄のシャツとか、センスおかしいと思ったけど、あんたが着ると悪くないと思うから、すげぇと思う。そのフリルのパジャマも、女みたいで絶対おかしいのにあんたが着ると色っぽく見えるから、すげぇと思う」 「お待ちなさい! 僕と貴方は恋人(仮)であって恋人ではありませんから!」 「それがどうした?」 「で、ですからこういうことはちょっと……っ」 「こういうこと?」 真理は、自分の下で震える智恵理の頬に、掌で触れる。 「ひぅ……っ!?」 「いつも手入れしてるから、髪も肌も綺麗だし。撫でて気持ちが良い」 しっとりと手に馴染む髪と肌は、もっと触ってくれと真理を誘っているようで、感触も温度も気持ち良い。すっと綺麗な形の鼻を軽く摘まむと、彼の腕がびくっと跳ねた。昼間見た時から艶々と潤っていた唇は、やはり柔らく弾力がある。 「や、ちょっと……」 ふにふに指先を押し付けると、彼は真理の手首を掴んで切なげに睫毛を震わせた。 「あとはそうだな。文句言いつつも色々教えてくれるし、服も俺の趣味で選ばせてくれるし、なんだかんだ俺をスクラップにしない。あと、カレーが美味い」 「ん?」 あわや貞操の危機かと身構えていた智恵理は何かおかしいと思い、自分を組み敷く男を改めて見上げる。相変わらずの真顔で何を考えているのかよく分からないが、その目に劣情の色は皆無だった。そもそも感情や趣向のデータは人間らしい反応をさせるために入力したが、性欲なんてデータは入れていないのだからそんな感情が湧く筈が無いのだ。 「……何の話ですか?」 「だから、今日訊かれただろ。あんたの好きなところ」 智恵理は真理の腹に手刀を入れると、「ぐふっ」と声を漏らす彼をベッドから転がり落とした。 「いってぇ、何しやがる!」 「う、煩い! 自分のベッドに戻ってさっさと寝なさい、馬鹿!」 「ああん!? 何で褒めたのに怒ってんだよ!?」 「知りません!」 掛布団を頭まで被ってしまった智恵理に、やっぱり怒るタイミングが分からない、と真理は釈然としないまま自分のベッドに戻った。
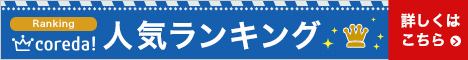

ざわつく
ゴールデンウィークが明けて、最初の実技の授業の時間は生憎の曇り空だった。空調の効いた室内での実験だから、天候は関係ないが気分は良くない。 「増見、彼女出来たんだって? 実際どうなの? 順調?」 何となくつまらないなと思った畔戸琉惺(くろとりゅうせい)は、同じ班になった恋愛下手をからかってやろうと、そう尋ねた。 「今日も花名の店で一緒に食事をする予定ですが、一緒に来ますか?」 「は!?」 しかし彼の答えはまったく予期せぬもので、琉惺は目を見開いて絶句した。 「白百合の魔法使い」に恋人ができたと噂が立つのはすぐだった。 頭脳、容姿、研究による財力、ついでに奇抜な服装。様々な点で目立つ彼に関する情報が回るのは早い。しかし、それを聞いた生徒の反応は、「また適当な奴と付きあったのか」「どうせまた放っておくんだろう」「今度の被害者はどれくらいもつか」と、冷めたものばかりだった。 智恵理と同じ研究室に所属する琉惺は、彼とそれなりに仲の良い位置にいると把握している。だから、彼が色恋沙汰を疎ましく思っていることも知っていた。 彼は、恋人のことを訊くと、いつも渋い顔をした。「好きで付きあったのではありません」だとか「あまりしつこかったので、勝手にしろと言っただけです」だとか言って完全放置で。たまに彼女が研究室に来ても相手にせず、待っているにも関わらずやりたいだけ作業をし、終いには「遅くなると危ないから帰りなさい」などと、一人で帰らせてしまう。 彼女がそれでももう少し一緒に居たいから、と残ろうとすれば「自衛できない人って、迷惑ですよね」なんて冷めた目で返すのだから、本当に酷いと思う。彼女は、遅くなってあわよくば一緒に帰って欲しいなどと思っていたのだろうに。 彼は泣きながら帰る彼女を見て、苦虫を噛み潰したみたいな顔をして「だから初めから言ったんです」なんて呟く。傷つけておいて、自分が傷ついているんだから、本当に色恋沙汰に向いていないと思った。 だから、そんな彼がまともに恋愛らしいことをしていることが、琉惺には信じられなかった。 「増見真理です。僕の遠い親戚で恋人です」 「……は?」 紹介された男を見て、琉惺は再び目を見開いた。智恵理より背は高いわ、がたいは良いわ、目つきは悪いわ、無表情だわで、隣に並ぶ美人系の智恵理がよりか弱く見える。 「何て言うか、あんた、男でもいけたんだな。そんで普通に紹介しちゃうのな」 智恵理に向けた琉惺の言葉に、真理が首を傾げる。 「女はいけるのか?」 そう言えば、琉惺は彼が女を好きになった話も聞いたことは無かった。 「……ゲイ、なのか?」 琉惺が恐る恐る口にすると、智恵理は指先を口元に当ててふむと声を漏らす。 「考えたこともありませんでしたね。そもそも恋をしたことがなかったので」 「マジかよ……でも、それにしても水臭いよな」 「何がです?」 「お前、友達俺くらいしかいないじゃん。なのに真理さんのこと何も聞かされてなくてさ」 「失礼な、友人ぐらい他にもいます」 彼の反論を琉惺は心中で否定した。本当に彼に友人がいるなら、彼に言い寄ってくる女なんて激減する。世話焼きで時にヒステリックな女みたいな男なんて、まともな女が好きになるわけがない。 智恵理は高根の花だから、同じ研究室の人間からも一歩距離を置かれている。嫉妬も妬みもあるだろう、同級生や先輩には忌避されて、後輩には別次元の人と認定されて遠巻きにされる。その上、媚びへつらう輩は彼の方がお断りだから、彼の周りはいつもざわめくのに、彼の居る中心はとても静かだった。 「真理さんは増見のこと、小さい頃から知ってんの?」 「いや、この前初めて会った」 「ゴールデンウィークに親戚で集まりまして。その時に」 琉惺は二人の答えに思わず声を荒げた。 「はあ!? まさか一目惚れとか言うんじゃないだろうな!?」 「そうです」 「ありえない」 「ああん!?」 「真理!」 否定されて威嚇する真理を智恵理がいさめる。その様子はつい最近出会ったばかりとは思えない。 「……お前らおかしいよ」 琉惺はごちゃごちゃした感情で締まってしまった喉から、やっとそれだけ絞り出す。 外ではぽつぽつ降り始めた雨が庭の草花を濡らしていた。 「白百合の魔法使い」がゲイだという噂は、彼に恋人ができたという噂以上に早く回った。 下世話な話はすぐに広まる。特に智恵理の場合は、彼のことを良く思わない人が多すぎた。彼に嫉妬する者が、弱みを握ったと思い、貶めようと吹聴したのだ。まあ、それは予定通りだから良いのだが。 智恵理の当初の目的通り、女性からのアプローチは少なくなった。しかし、しつこい人は「本当に彼氏がいるの?」だとか「どんな人なの?」だとか詮索に余念がなく、鬱陶しいことに変わりなかった。声を掛けられなくなるまでにはもう少し時間が要るのだろう。 「大丈夫か?」 「何がです」 真理はじっとりとした視線と、自分たちを見てはヒソヒソと囁きあう気配を感じて眉を寄せる。 「……嫌な感じ」 「真理のくせに繊細なんですね」 智恵理は、そんな彼の視線を挑発的に見返して、彼の大きく筋張った手に指を絡める。周囲のざわめきが大きくなった。 「遠巻きにされるくらいが丁度良い」 「コミュ障か」 失礼な言葉にはごすっと腹に手刀を入れて応えた。 「ただいま帰りまし、ひっ」 智恵理は帰宅すると、迎えてくれた真理の形相に身を縮めた。 「何かあったのか?」 「べ、別に何もありませんが」 「でも何か、あんた、小さいぞ」 真理は智恵理の頬を両手で包んで、その顔を覗き込む。智恵理はその鋭い瞳を直視できずに目を伏せた。 本当に、特に何かがあったわけではなかった。ただ、周囲の反応にいちいち腹を立てて疲れただけだ。 昼に真理と一緒に居るところを見せたため、噂に信憑性が増したのだろう。その後、研究室に行くと遠巻きにする視線に、好奇と軽蔑の色が混ざっていた。嫉妬の視線の中に、侮蔑の色が混ざっていた。 「あれは絶対増見が女役」「美人だから、男の方がお似合いなんじゃねぇの?」「どうやって落としたのかねぇ」構内を歩けばわざわざ聞こえるような声量で噂された。 智恵理は、同性同士で愛し合う事がマイノリティであることは分かっている。しかし、それは当人たちの問題であるのに、そんな風に見下す下衆な輩に腹が立った。 「やっぱり何かあっただろ」 真理は黙り込む智恵理を促した。 目を伏せたことで、智恵理の白い頬に影が差し、元から黙っていれば儚げな美人顔の彼が、より儚げに見えた。 「放しなさい」 「智恵理!」 真理が彼の目を見たまま呼ぶと、手に挟んだ彼の頬がじわじわ熱を持つのが分かった。 「いきなり呼び捨てとか、頭が高いですよ……」 智恵理は眉を顰めて呟くように吐き捨てた。 「智恵理、さん?」 低い声が、智恵理の耳に馴染む。彼に改めて呼ばれて、居た堪れなくて、智恵理は無理やり彼の手を引きはがして彼から離れた。 「少し、疲れただけです。今日は早めに寝ます」 そう言い捨てて風呂場に逃げ、自身の二の腕をぎゅっと握った。もう、さっきまでのイライラは消えていた。 寝支度を整えて寝室に向かう智恵理に、真理も着いて行く。学費を免除され、特許での収入もあるとはいえ、贅沢をしているわけではない智恵理の家は、部屋数も少なく、二人は寝室を共有している。 部屋の端と端に置かれた二つのベッドの内、智恵理が窓際のベッドに潜ると、真理も当然のようにそこに入ろうとした。 「俺も寝る」 「は!? ちょっと、何でこっちに入って来るんですか!」 「疲れてるのストレスだろ。ハグはストレスを和らげるって、データにある」 「け、結構です!」 真理は逃げようとする彼を無視して、彼を押しつぶすように抱きしめた。嫌がることを無理やりすれば、ストレスを和らげるどころか、それ自体がストレスになるかもしれない。しかし、と考える。 さっきだって、辛そうに縮こまっていた彼が、自分が近づいたらこっちを向いたんだ。触れたら、顔色が変わったんだ。だからきっと間違えてない――と。 「……っ、ハグ、しましたよ。出て行ってください」 苦しそうに息を詰める彼を見て真理は、自分が乗っているから重くて苦しいのだと思い、体勢を変えて横から抱きしめた。しかし「ちょっと!」と抗議する彼がまだ苦しげなのは、なぜか分からなくて首を傾げる。 「恋人なんだから、一緒に寝ても良いだろう?」 「恋人(仮)です! スクラップにしますよ!」 「すれば良いだろうが。寧ろどうしてしない」 「は?」 「あんたが面倒くさい目に遭っているのは、よく分からねぇけど俺が男なのが悪いんだろう? だったらちゃんと女のロボットを作り直せば良いじゃねぇか」 智恵理は真理の目をじっと見つめた。 真理は、智恵理のために智恵理が作ったロボットだ。雷の所為でイレギュラーが有ろうと、智恵理のためにという思考回路は健在だったらしい。 (僕の為なら、壊されても良いのか) 智恵理は、寝返りを打って真理に向き合う。相変わらず目つきが悪いし、何を考えているのか分からないその顔に手を伸ばした。 頭部は彼の心臓だ。身体は直せても、イレギュラーが多すぎる脳の回路はもう智恵理には直せない。 「……貴方、僕が貴方をなんだかんだスクラップにしないところが好きだと言ったじゃありませんか」 「それは俺の都合だろ」 「……嫌ですよ、新しいロボットなんて。それこそ面倒くさい」 自己犠牲と言ったらきっとおかしいのだろう。意思が有るくせに大事なものは他人に決められているなんて、なんて悲しい。自分は、何て面倒なものを作ってしまったのだろう。 「もう、勝手になさい」 智恵理はそのままそっと目を閉じた。 ****** 朝の花は一層美しい。澄んだ空気と青い光を浴びて、一番純粋な色で輝く。 開店前の「お菓子の庭」に押しかけた琉惺は、コーヒーとサンドイッチを頂きつつ、のんびり庭の手入れをしている荘一郎をテラスから眺めた。 「花名さんって増見の幼馴染なんだよな」 「そうですよ」 「真理さんの話、よく聞くの?」 「いつも二人で来られるので、聞くというよりは見てますかねぇ」 「増見から直接話は聞いていないと?」 「他にお客さんがいない時なんかは三人で話したりもしますよ」 庭いじりをしながらだからだろう、普段から忙しないという言葉とは無縁のようにみえる彼の言葉使いが一層のんびりに聞こえる。 「あの二人見ててどう思った? というか、どんな話してるんだ?」 「えー……特に何も思わないというか、話……なんの話したかな……ごめん、あんまり覚えてないや、ません」 「同い年だし、敬語外して良いよ」 敬語のはずれかかった彼に提案した。そもそも開店前に押しかけるような奴は客扱いしなくて良いだろう、と思う。 「あはは、ごめんね」 「いやぁ、それくらい俺とも打ち解けちゃったってことでしょ?」 「話してて楽だとは思うよ」 その返しに琉惺は目を細めた。 「てか、花名さんふわふわしすぎ。その受け流す姿勢は嫌いじゃないけどさぁ。もっと気にならないもん? 幼馴染って」 「んー? 興味ないわけじゃないけど、何でも知りたいわけじゃないというか、そこに居れば『ああ、居るな』って。『せっかくだから絡んじゃおうかな』てくらい」 「それ、全然じゃん」 「あはは」 棒読みの笑いは何を考えているのか分からない。いや、きっと何も考えていない。 「俺、花名さんの条件反射で笑うところも嫌いじゃないよ。でもさぁ、もっと他人に興味もって行こうぜー。あいつ今ちょっと大変そうだし」 「大変?」 「世間体がどうのこうの。まあ、周りが騒いでるだけだけど」 「心配?」 「あんたは心配じゃないのかよ」 「心配だよ」 手を止めないまま、声のトーンを変えずに淡々と受け答えする花名に、琉惺は苦笑いした。 「思って無さそう」 「ばれた? やだ、怖い顔しないでよ」 「してねぇよ。せめてこっち見てからそういうことを言え」 やっと顔を上げて琉惺を見た荘一郎は「怖い顔してるじゃん」と嘯いた。 「だって、僕が心配したってどうしようもないじゃない。味方ではいるし、何かあれば力になっても良いと思うけど、自分にどうにもできないことで、やきもきはしたくない」 その返しに、琉惺はおっと目を見張る。 「通じあってんね」 「今のでそう思ったの? すごいね」 だって、きっとそれは増見も同じだ。彼は自分の所為で、友人がどうにもならないことに心を曇らせることを良く思わないだろう。 琉惺はへらへら笑う彼を流して話を戻した。 「男同士って、もっと葛藤とかあるもんじゃねぇの?」 「増見達のこと?」 何気なく訊かれて、琉惺は一瞬息が詰まった気がした。 「いや、それ以外にないでしょ、何で訊いたの」 「ふふ、何でだろうね? 何となく?」 荘一郎は琉惺の質問を笑顔ではぐらかして、再び庭いじりに戻った。琉惺は彼を追って、カップ片手に席を立ち、テラスの手摺に肘をついてのりだす。コーヒーを一口啜る。息苦しい気持ちを、ほろ苦さとほんの少しの酸味で流して話を続けた。 「……男に一目惚れなんて、早々認められないだろ。それなのに、すぐに告白? 断られる可能性の方が高いどころか、完全に拒絶されるかもしれないのに。万が一告白が成功したとして、祝福される関係でもない。それに男女だって、そんな軽率な告白しないだろ。ナンパ男じゃあるまいし。特に増見は……あいつは良くも知らない人間と付きあったりしないだろ」 「そう?」 「あんた、幼馴染ならさすがに知ってるだろ?」 荘一郎は雑草を詰めた袋と、選定した花を詰めた袋を片手で持って立ち上がる。 「僕は、増見が僕に見せてくれたことしか知らないよ。でも、そうだな。彼って結構ロマンチストなんだ。――だから、やっと会えたのかな……って」 そう言ってふわっと笑った顔は、いつもの適当な笑顔なんかではなくて、見惚れた。 「ねぇ、僕は君の頭の良いところ、嫌いじゃないよ」 その笑顔に固まる琉惺に、歩み寄った荘一郎は、赤い花弁を一枚とって琉惺の唇に押し当てる。 「花を食べる人って、綺麗だね」 花弁を押し当てられた唇がひくっと震える。 「何それ、かっこいーい」 それでも、なされるがままにそれを咀嚼した琉惺は、軽い口調でそう返した。
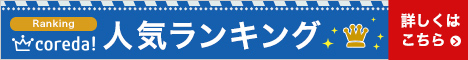

兄弟
カーテンの隙間から射す朝日に目を顰め、小さく唸り声を上げて瞼を上げる。身体を起こすと、肩に乗っていた腕が白いシーツに落ちた。隣で眠る真理はうつ伏せに顔を枕に埋めていて、起きる気配は無い。 真理にハグされたまま寝て、朝はどこかしら触れられた状態で起きる。今日は肩を掴まれていたようで、重さの無くなったそこが何となく寂しかった。 ****** 温く柔らかい液体の中に浮遊していると、ずるっと何かを脱がされる感覚がした。 それでも液体の中に浮遊し続ける。身体の自由は利かないし、自分がどんな状態なのかも分からないけれど、苦しくは無い。寧ろ心地いい。 そのまま、目を開けているのか閉じているのかも分からない状態でゆらゆら漂っていると、すぐ隣で何かが生まれる気配がした。 暖かそう、柔らかそう、優しそう、楽しそう。ふわふわと柔らかく光るそれに手を伸ばした。 「真理、起きなさい。朝ですよ。ちゃっちゃか起きて朝食を食べてしまいなさい」 エプロン姿の智恵理に揺すり起こされた真理は、枕から顔を上げて「まただ」と呟いた。 「何がですか?」 「毎日同じ夢を見るんだ。夢は記憶の補完だから、同じ夢ばかり見るのはおかしいのに」 どうしてだろうと智恵理を見上げると、彼は難しそうな顔で真理を見つめていた。 「……おい?」 「……ロボットなのに、夢、見るんですか?」 朝食後、二人は食後のコーヒーを持って、ダイニングから続くソファセットに移動した。ローテーブルにノートとペンを用意した智恵理は「では」と正面に座る真理に切り出す。ちなみにもしもの時のために、実験のデータはデジタルとアナログの両方で記録している。 「まずは夢の質問からいきますよ」 「おう」 「どんな夢ですか」 「なんかこう、水の中みたいな。でも呼吸はできるし苦しくない。寧ろほっとする感じ」 「お風呂のような?」 「いや、もっと柔らかい」 「つまり中にいろいろな成分が入っている不純物だらけの溶液ということですね」 「あんたよく俺のこと情緒無いとかセンス無いとか言うけど、あんたも相当だと思う」 智恵理はとりあえず、ノートに夢の特徴を書き出しておく。 「毎日同じ夢を見ているんですよね、いつからですか?」 「生まれた時から」 「……データ処理じゃないでしょうし、ロボットって夢見ますかねぇ……」 「実際見てんだよ」 疑うように眉を顰める智恵理に真理は唇を尖らせた。 「あとは、そうだ。貴方、性欲あります?」 「性欲……両性の性器をめぐる機能とその活動の中で生じる快感を求める欲求(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より)……」 「あ、無さそうですね」 すぐに結論を出されて真理は「ん?」と首を傾げる。性欲やら欲求やらをいまいち良く理解できなかった。 「あと気になるのは趣向ですかね。僕と恐ろしく合わない」 「あんたの趣味はおかしいよ」 「失礼な、貴方には少し高貴過ぎて理解できないだけですよ。ですが、貴方の趣向は本来ならば僕と変わらない筈なんです」 智恵理はノートをぱらぱら捲り、以前に取ったデータを見返した。 「以前も言いましたが、性格と料理の腕も、頭脳データを解析してもおかしなところは見られないのに、貴方はイレギュラーが多すぎる」 彼の言葉に真理の眉間に皺が寄る。殺し屋もかくやという恐ろしい形相だ。イレギュラーが多いから悪いと言われれば、自分の人間性(ロボット性?)を否定されたようなものだった。 「……何でそんな険しい顔をしているんですか」 「ああん!?」 「ガラが悪い! とにかく、頭は大事になさい。もう、僕には直せませんから」 パタンとノートを閉じた智恵理を前に、真理はキョトンと目を瞬いた。胸のムカつきを感じて、智恵理の頬に手を伸ばす。 「ちょ、なんでふか!」 両手で頬を挟まれて無遠慮にぐにぐに揉まれた智恵理は、滑舌悪く抗議する。真理の胸のムカつきは軽くなった気がした。 ****** 智恵理が大学に通っている日中、真理は「お菓子の庭」で荘一郎の手伝いをすることになった。 テラスに繋がる大きな窓から入る、さんさんと輝く太陽の光で明るく照らされた店内。カウンター席奥の厨房で、真理と荘一郎は並んで食材の下処理をしていた。 「真理さんは何処の出身なんですか?」 「ブルガリア」 バラの花びらを砂糖とレモンで煮込みながら訊いてきた荘一郎に、真理はヨーグルトをボウルにあけながら答える。 「お菓子の庭」で手伝いをするにあたって、荘一郎との会話が増えることは必然だ。開店前の準備の時間や、客足が途絶えた時などは二人きりにもなる。荘一郎は智恵理の幼馴染なのだから、真理に色々訊きたいこともあるだろう。そう思って、真理は智恵理と、彼に何かを訊かれたらどう答えれば良いのかを事前に話し合っていた。智恵理曰く「あれは何を言っても適当に受け流すだけですから、どう答えても大丈夫ですよ。何も疑いませんが、信じ切りもしない」とのこと。 「へーそうなんだー」 彼の言った通り、荘一郎は驚くことも聞き返すこともなく、そう返した。 「いつごろこっちに来たの?」 「5月」 「ふーん。それですぐ増見と付きあい始めたんだ。もうずっとこっちに居るんですか?」 「おう」 「そういえば今どこに住んでるの? 近い? あれなら交通費出しますけど」 「智恵理さんの家」 「え、一緒に住んでるんだ」 さすがの荘一郎もこれには驚いたような声を出した。 「やっぱり気になるか? 幼馴染って。俺には居ないから分からない」 「いや? 無言になるのもどうかと思って訊いてるだけで、割とどうでもいい」 真理は、彼の言葉に何とも言えない気持ちになった。智恵理の学校の人たちのように他人のことに面白がって影でこそこそ言うのもどうかと思うが、そこまで興味が無いものどうなのだろう。 「……俺、ブルガリア出身じゃない」 「へーそうなんだ。じゃあ、どこですか?」 「じゃあ、ブラジル」 「オレンジ! でも残念、そのオレンジは南イタリア産でした!」 オレンジの皮を剥きながら真理が答えると、荘一郎はその手元を覗いて笑って返した。 「増見は家ではどんな感じ?」 (でも、訊いてくるのはあいつのことなんだな……) 「朝俺より早く起きて飯つくって、俺を起こして一緒に食べる。学校行って、帰って来て、飯食って風呂入って寝る」 「真理さん全然言葉足りなーい。ほとんど分からない。逆にすごい。あ、それ白い部分残らないようにね」 荘一郎はコンロの火を止め、ふう、と一息吐く。 「でもさ、君たち恋人って言うより、親子とか兄弟みたいじゃないですか。……それ、どういう顔? 怒ってます? ただきょとんとしてます?」 じっと見つめてくる真理を、ははっと笑う。 「悪い意味じゃなくてね。増見、お兄ちゃん子だから」 そんなとりとめのない会話をしていると、シャラシャラ揺れる硝子暖簾から、飄々とした顔が覗いた。 「開店前にお邪魔~。あれ、真理さんじゃん」 「いらっしゃいませ。モーニングメニューはサンドイッチ一択ね」 荘一郎は、開店前にやって来た琉惺を、怒ることもなく笑顔で迎えた。 空き時間に智恵理を見つけた琉惺は、嬉々として彼に絡みに行った。学校に居れば研究室に籠っているのが常な彼が、校内をうろうろしているのはとても珍しい。 「チェーリオ! 何してんの?」 智恵理は琉惺を認めると、綺麗な顔を盛大に顰めた。 「綾坂さんですね」 「そう、まゆみちゃん。良いんじゃない? チェリオ可愛いじゃん」 「貴方に言われると馬鹿にされているようにしか思えないのですけど」 「えー、何それ言いがかりも甚だしいんだけど。で、何してんの?」 再び訊くと、彼は額に手をやって軽く息を吐いた。 「異様に班員に絡まれるんですよ。おそらく貴方の所為で」 「で、研究室から逃げてきたわけ?」 琉惺はじろりと睨みつけてくる彼の腕を掴んで歩き出す。 「ちょっと、何処に連れて行くつもりですか」 「カフェテリア。お茶しましょーよ」 琉惺は渋々ついて来た智恵理に、自販機のコーヒーを渡した。その場で入れる本格ドリップのコーヒーだ。舌の肥えた智恵理は缶コーヒーやジュースなんかは絶対に飲まなかった。 「その人たちに何を言ったんですか」 「それがさぁ、お前に友達がいないせいで、俺、あらぬ疑いを掛けられたんだよね」 窓際のスツールに並んで座る。小さくて足の長いそれの、座り心地はあまり良くはない。 「それがさぁ、俺とお前が浮気してるんじゃないかって言うんだぜ? とんだ言いがかりだよな。男二人いりゃ掛け算する性根腐った腐女子じゃあるまし、頭の中お花畑かっていう」 琉惺は窓ガラスに薄ら映る室内の様子に眉を顰める。チラチラと窺うような視線と、ヒソヒソ囁かれる声に苛ついた。 しかしまあ良い、どうせただの好奇心だ。視線は監視するものではないし、聞き耳をたてられてもこちらの会話は聞こえないだろう。ヒソヒソ声も聞えよがしに吐き出される嫌味よりよほど善良だ。 「だからさ、言ってやったんだよ。『あいつと俺が? 冗談じゃない。そんなデマが流れてんのか、それは迷惑だ。何とか誤解を解かないと。ああ、きっとそんな風に言われるのはあいつが俺とばかり話しているからだ。あいつに友達が居ないからだ。なんて可哀そうなんだ。おっと、そう言えば俺の目の前にはおあつらえ向けに俺らと同じ研究の班員が居るじゃないか』と」 「色々言いたいことはありますが……、それで?」 「それで、お前今日俺にフレンチトーストをくれただろ? そう、俺が前から頼み込んで作ってもらった奴だ。それをそいつらに差し出した。『これは増見がお前たちのために作ったフレンチトーストだ。あいつも不器用ながら仲良くしたいと思ってるんだ』と」 「よくもまあ、そう舌が回りますね」 身振りを交えて話す琉惺に、智恵理は呆れた声で言った。 「それから俺は訊いたんだよ。『この中に増見とちゃんと会話をしたことがある奴は居るか?』って。『居ないならなんてもったいない。あいつはマダム口調で喋るんだ。とても面白い、爆笑ものだ』と。ところで俺、結局フレンチトースト食べられなかったからまた作ってよ」 「誰がマダムですか! 僕は美しい日本語を正しく使っているだけです! 絶対作りませんからね!」 「えー、でもさ。研究には信頼関係・協力体制、必要だと思うじゃん。俺頑張ったじゃん。ご褒美ちょうだいよ」 智恵理はにやにや笑って掌を出してくる琉惺のその手をぺちんと叩き落とす。 琉惺は叩かれた手をひらひら振りながらにっこり笑った。 「ところでさ、俺らが浮気してるなんて噂が立ってたわけじゃん。根も葉もないけど」 「噂というほどもない、ただの嫌味でしょう」 「まあ、それでも良いけど。そういうの、真理さんどうなのかなって」 「別に、事実無根なんですから、何も思わないでしょう。あとその顔気持ち悪いです」 「ふーん」 「なんですか」 「淡白なんだな、と思って」 琉惺が、何となく窓の外に意識をやると、男同士がふざけ合ってお互いの頭を叩いたりしているのが見えた。 「お前らなんか、恋人っぽくない。親友か、兄弟って感じ」 「そうですか?」 「そうですよ」 茶化して彼を真似た敬語でそう返すと、智恵理は「兄弟ねぇ」と嬉しそうにふわりと笑った。 「今日は……萎れてるな」 ぐったりした様子で帰って来た智恵理を見て真理が言った。 真理が初めて学校について行った日、智恵理はすごく小さくなって帰って来た。それから、徐々に環境に慣れたのか、彼が帰って来た時に見せる疲れた表情は薄くなっていた筈だった。それなのに、今日はやけにぐったりしている。 「何かあったのか?」 「別に。お風呂湧いてます?」 「おう」 「頂いてきますね」 前は心配したら怒られたので、今日は何もしないで見送った。それに、疲れて見えると言っても、前は小さくなっていたが、今日は萎れているからきっと違う。前は顔色が暗くて、ショックを受けている感じだったが、今日はただ疲れているだけのようだから、きっと大丈夫だと思った。 「今日、店はどうでした?」 ソファの背もたれに肘をついて、何となくバラエティ番組を眺めていると、湯気を纏った智恵理が向かいのソファに座った。お気に入りのバラの入浴剤を使ったのか、顔色も機嫌も香りも良い。 「花名さんが始終ふわふわしてた」 「そうでしょうね」 席を立って彼の隣に移動する。やっぱり華やかで甘い香りがした。 真理が座るスペースは十分あったのに、智恵理が端に移動する。それに何故か苛っとして、その手を掴んだ。 「ちょっと、何するんですか」 彼の顔が嫌そうに歪む。それを見て気付いた。 (俺、こいつの嫌がることするの結構好きだ) 「もしもし?」 智恵理は黙り込んでしまった真理の顔の前で、自由な方の手を振った。 「俺、性格悪いかもしれない」 真理が、訝しげに覗いてくる智恵理の瞳を見て言うと、彼の目じりがひくりと動く。 「一応訊きますけど、それ、睨んでいるわけではないんですよね?」 「睨んではないな」 真理がキョトンと首を傾げると、それに合わせてサラサラの髪が揺れる。可愛らしい仕草だが、目つきの悪い男がしても怖いだけだった。 「貴方の性格が悪いなんて、最初から分かっていましたけど」 「マジかよ」 それを聞いて、真理は彼を抱き寄せた。 「は!?」 「俺があんたの嫌がることをしたくなるのも、知ってたのか」 「っ、何……」 フローラルな香りのする首筋に、頬をすり付けると、ぶわっと彼の産毛が逆立って、体温が上がる。 「お止めなさい!」 「あんた、相変わらず触り心地良いな」 「知ってます!」 智恵理は真理を突き飛ばすと、気まずげに目を逸らした。 「……僕、嫌がってます、よね……?」 真理はこくりと頷く。 体を強張らせて止めろというのだから、嫌がっているだろう。伏し見がちな瞳が潤んでいたり、目じりが赤くなっていたりするのは嫌悪感で泣きそうになっているからに違いない。それを見てもっと触りたい、むしろ泣かせたいと思ってしまう自分はやはり性格が悪いのだろう。 「とりあえず離れなさい」 真理は大人しく彼から離れた。性格が悪いことは認めるが、性格が悪いことを良いこととは思わない。ややこしいがそういうことだ。 「そういえば、あんた、お兄さん居たんだな」 「は? いませんけど」 真理が気を取り直して、昼間の会話を思い出して言うと、予想外な返事が帰って来た。 「花名さんが、あんたはお兄ちゃん子なんだって」 「あれは本当に適当なことを言いますね」 智恵理はボケボケした幼馴染の顔を思い浮かべて、呆れて溜息を吐いた。 「まあ兄は、居ないこともないんですけど。母は、僕を生む前に一度流産しているんですよ。それをずっと昔に花名に話したことがありまして。もしかしたら、『兄がいたら楽しかっただろう』などと言ったことがあるかもしれませんが、それだけですよ」 それだけ言って、お茶を淹れようと席を立つ。 「貴方も飲んでみますか? オレンジピール。初心者向けの飲みやすいハーブティーです。はちみつを入れるときっとよく眠れますよ」 真理は、自分はいつもよく眠れているのだけど、と思いつつ、爽やかな香りのそれを飲んでみることにした。 今日も二人は同じ夢を繰り返す。
作り物の感情
智恵理が真理を作ってから三ヶ月、初夏から晩夏に季節も移り替った。周囲も落ち着いて、女性に言い寄られる頻度と、これ見よがしに聞こえる陰口も少なくなった。 真理との関係も相変わらずで、朝起こして、朝食を食べさせて、マナーや態度を注意して、と、兄弟か息子と暮らしている心地がしている今日この頃、智恵理は真理と一緒に、荘一郎のバースデーパーティーに招かれた。 間接照明のみ明かりを灯した店内は、昼とは違うムーディーな雰囲気を纏っている。 招待されたのは、常連客の明とまゆみと美樹、幼馴染の智恵理と、バイトの真理と、 「ちわーす! ヒーローは遅れて登場!」 それから琉惺。 片方の肩に鎖の紐の付いた大きく襟の開いた黒いシャツに、黒いダメージジーンズ姿の相変わらずチャラついた格好の彼が登場すると、ロリータ一歩手前のピンクのフリフリワンピース姿のまゆみが「きゃー!」と黄色い声を上げた。 「畔戸さん! 今日真っ黒ですね! クロちゃんさんじゃないですか!」 「ちゃんとさん両方付けちゃうんだ」 いきなりテンションマックスの彼女に、琉惺はニシシと歯を見せて言った。 「クロちゃんさん、まゆみの隣空いてます」 「まゆみちゃんはクロちゃんさんお気に入りだね」 ポンポンと隣の席を叩いて誘うまゆみに、美樹がくすくす笑った。 「私、男の趣味悪いから」 しかし、誘いに乗って隣に座った琉惺は、彼女に言葉にこけそうになる。 「どういうことだよ、おい」 「あー、そうなんだ?」 「ふふふ」 なにやら通じ合っている風に笑うまゆみと美樹に、琉惺は「おーい」と再び声を掛けた。 琉惺、まゆみ、美樹、明、真理、智恵理、一つ飛ばして琉惺、という並びで二つ繋げたテーブルを囲む形で落ち着くと、普段後ろで一つ縛りにしている髪を、ツインテールにした荘一郎が、鮮やかなバラ色のグラスを持ってやって来て、彼を見た琉惺が吹き出した。 「ぶっは! 花名さん何その髪!」 「まゆみちゃんがやってくれた」 「まゆみとお揃いなんだ! それより、花名さんそれ何ですか!」 「バラのリキュールですよ。去年二十歳になってから色々口にしてね。自分でも勉強してみたんです。今日はみんなお客さんじゃないから、味見してもらっても良いよね」 「お客さんの時でも喜んでしますよ!」 美樹とまゆみがきゃっきゃと燥ぐ。彼女らを見て、智恵理は「少々騒がしいですが、女性がいると華やかで良いですね」などと色事が苦手なくせに評価した。 「あんた、人に花食わすの好きな」 「そのままズバリを食べさせたのは、君にだけだけどね」 置かれたグラスに苦い笑いを浮かべる琉惺に、荘一郎がふふっと笑った。 「で、まゆみちゃんはこっち。ノンアルコール、特別ね」 一人未成年なまゆみにウインク付きで渡す荘一郎に、彼女は胸の前で手を組んで瞳を輝かせた。 「きゃぁあっ! 花名さんイケメン! 好き!」 「浮気が早いな、おい」 琉惺のつっこみに、まゆみと美樹が一緒になってキャッと燥いだ。 「それじゃあ」と、智恵理と琉惺の間の席に着いた荘一郎が音頭をとる。 「僕の僕による僕の為のバースデーパーティーに集まってくれてありがとう! 乾杯!」 「乾杯! 花名さん誕生日おめでとう!」 「おめでとう!」 八月七日、花の日に生まれた荘一郎は、今日で二十一歳になった。 「俺もお呼ばれしちゃって良かったの?」 「うん。クロちゃんもお得意様だもの」 チンと荘一郎とグラスを合わせた琉惺が、流し目で尋ねると、荘一郎はいつもの眠たげな瞳を一層うっとりと溶かして返す。 「早速クロちゃん呼びかよ」 琉惺は、はは、と笑って気が付いた。 「……なあ、花名さんや、ちょっと俺の名前言ってみ?」 いきなり神妙な空気を作って尋ねる彼に、荘一郎は「え?」と首を傾げる。 「どうしたの、急に」 「今俺は花名さんに一度も名前を呼ばれたことが無いことに気が付いた」 「そ、そうだっけ?」 「花名、貴方まさか……」 冷や汗をかいて歯切れ悪く受け答える荘一郎を、智恵理が覗き込んだ。 二人に冷たい視線を向けられ、荘一郎はパンと手をうち頭を下げる。 「ごっめーん! クロちゃん! でもでも、黒が付くのは分かるよ! えっと、黒何とかだよね!」 打った手をそのまま顔の横に持っていき小首を傾げる可愛らしいポーズだが、言っていることが全く可愛くない。 「はぁぁあああああ!? 言っとくけど白黒の黒じゃないからな!?」 「……花名、それは流石にドン引きですよ」 「え、待って! 引かないで! 他は覚えてるから! まゆみちゃんと明様と美樹ちゃんとえーと……」 「真理ですよ! どんなけですか!」 「ど、ど忘れだよぉ!」 慌てる荘一郎に琉惺は顔を手で覆って、テーブルの角に額を押し付けた。 「クロちゃぁん……」 しゅんと肩を落とした荘一郎が情けない声を上げる。 「何デスカ」 「人間得意不得意はあるじゃない……」 そんな彼を琉惺はじと目で見上げる。瞼の厚い三白眼のじと目は割と怖い。荘一郎を非難する瞳であるが、荘一郎は何を思ったか彼の肩をポンと叩いて言った。 「花名さんに名前覚えられてなくて、ドンマイ!」 琉惺はへらっと笑う彼の肩をガッと掴んで、ゴッと頭突きを食らわせた。 「いったぁい!」 荘一郎が悲鳴を上げるが、琉惺だって予想外に痛かった。 「畔戸、それ花名にはいくらやっても良いですけど、真理にはやらないでくださいね。馬鹿になりますから」 「ひっどーい! 僕は馬鹿になっても良いって言うわけ!?」 「貴方は元から馬鹿です」 智恵理はツンと返して真理の頭をポンポンと軽く叩いた。 料理が粗方片付いて一息つくころ、「花名さんのアルバム見たいです! 智恵理さんも写ってますよね!」というまゆみのリクエストで、皆でアルバムを見ることになった。 「あっはは! 懐かしい!」 一ページ目の写真を見て、花名が声を出して笑う。生後間もない赤ちゃんが二人、荘一郎が智恵理の足を食べて智恵理が大泣きしている写真だ。 「懐かしいって、覚えているわけがないでしょうが」 智恵理が幼馴染を呆れた声で諭す。そんな感じでどんどんページを捲っていった。 「あー、これ初めての幼稚園だ」 荘一郎は、ママと離れたくないと泣く智恵理を放って荘一郎が庭に突撃している写真を指す。 「この後、増見が泣きながら僕の後を追いかけて来るんだよ」 「チェリオさん可愛い!」 「ねー、チェリオ可愛いですよねー」 壮一郎はまゆみに笑顔で返して、次いで、遠足でふらふらどこかに行こうとする荘一郎を智恵理が引っ張っている写真を指した。 「この頃から増見は僕のお母さんだった」 「誰が貴方のお母さんですか。いい加減ふらふらするのをお止めなさい」 軽口を叩く荘一郎を智恵理が小突く。 「今もふらふらしてるんですか?」 「してないよ?」 まゆみの問いに荘一郎はきょとんと返した。 「……先月、二股疑惑の修羅場を作った挙句、僕に投げましたよね」 「そっちのふらふらかよ」 じっとりとした声で智恵理が非難すると、琉惺がこれまたじっとりした瞳を向けた。 「僕はどっちともお付き合いしてた訳でもないのに、おかしいよね」 それに対しても荘一郎は軽い口調で返す。 「貴方はいちいち行動が思わせぶりなんですよ」 「ホントニネ」 「クロちゃん片言かーわい」 琉惺は自分の方に伸びてきた壮一郎の手を、ぺしんと叩いて落とした。 またしばらくページを捲っていくと、そっぽを向く智恵理に、荘一郎が腕を無理やり絡めてダブルピースをしている写真が出てきた。二人は違う色の鉢巻を付けている。 「運動会で僕のクラスが優勝した時の記念写真だね」 「それはチェリオさんもこんな表情になりますわ」 「でもでも、やっぱり記念写真は増見と撮りたいっていう僕の愛なんだよ?」 まゆみの言葉に荘一郎はふわふわと返した。 「花名さんダブルピース似合いすぎてムカつく」 「理不尽」 琉惺の言葉には真顔で返した。 またしばらくアルバムを捲っていくと、ある写真を見て琉惺が吹き出した。頬に紅葉を貰った智恵理の横顔の写真だ。 「盗撮じゃないですか」 「この頃からか」 「僕もアレだったけど、増見も相当だったよ」 苦情を言う智恵理を無視して、琉惺と荘一郎がしみじみ言った。 またしばらくすると、中学校の卒業式で大泣きする花名と、彼の涙を拭ってやる智恵理の写真が出てきた。 「チェリオさんお母さん!」 「こんなこともあったねぇ」 「そして一か月後、高校生活に馴染んだ花名は、ケータイのデータを殆ど消して人間関係の整理を始めます」 「えげつねぇな……」 「要らないものは捨てないと。断捨離、断捨離」 何でもないことのように言う荘一郎に、琉惺はゲテモノを見る様な視線を向けた。 またしばらくページを捲っていくと、出てきた写真に荘一郎が「やばっ」と声を上げた。 その写真を見て他面々も固まる。 出てきたのはキラキラキュートにデコレートされた荘一郎と智恵理のキスプリだった。 「え、花名さんとチェリオさんってそういう……?」 怖々と声を出した美樹に、真理が首を横に振る。 「いや、これは罰ゲームで花名さんが悪乗りしたんだ」 「あはは、そうだよ~。なんだ増見、真理さんに言ってたんだ。焦っちゃった」 「言ってませんけど……」 ほっとして調子の戻った荘一郎の言葉を、智恵理は神妙な声音で否定した。 「あれ、じゃあ勘?」 荘一郎に尋ねられて、真理は首を傾げた。どうしてそう思ったのか、真理自身も分からなかった。 「見てたんだったりして」 明がそう言って笑うと、真理は一層深く首を傾げた。自分はつい最近造られたばかりだし、彼女たちにも智恵理とは三か月前に初めて会ったと言ってあるはずなのに、と。 そんな真理の首を、「彼女の言う事は深く考えなくて良いです」と智恵理が元に戻してやった。 アルバムを片づけてしまうと、みんな席を離れて、好きに動き出した。荘一郎と琉惺はカンターの方で、明と智恵理はテラスに出て何やら話しこんでいる。テーブルに残った真理は、まゆみと美樹に挟まれた。 「チェリオさんと真理さん、見てて飽きないなぁ」 「真理さんって、見た目怖いけど、優しいですよね。チェリオさんのこと良く見てるし。さっきの写真だって、智恵理さんが好きだからああいう発想になったんですよね!」 二人の言葉に真理は首を横に振る。 「俺、性格悪いぞ。智恵理さんが嫌がることをしたくなる」 「嫌がることって?」 「触りたくなる」 真理の言葉に二人は顔を見合わせた。 「真理さん変わってますね。三大欲求に忠実なのは生き物の性じゃないですか」 「三大欲求……?」 まゆみに言われて、ハッとした。 「これが性欲か!」 ****** 晴れている間に始まったパーティーは、しとしとと雨が降り始めた頃に、遅くならないうちにとお開きになった。 そうは言っても、家に帰ると時計の針は十時を指していた。もう夜もいい時間だ。早く風呂に入ってしまおうと、智恵理が考えていると、おもむろに真理が口を開いた。 「俺、性欲あるかもしれない」 「……いったい何を吹き込まれたんですか」 突然そんなことを言いだした彼に、智恵理は目を眇めた。 「まゆみと美樹に『性欲』って何かを訊いたんだ」 「訊いちゃったんですか!?」 淑女に!? と声を裏返す。あの二人、特にまゆみに対しては、常に馬鹿だ馬鹿だと思っていたが、まさか男相手に性欲を語るとは考えていなかった。 「え、で、な、何を言われたんですか?」 「何とも言えない衝動に突き動かされて、触りたい、抱きしめたい、どうにかしてしまいたいと心が打ち震え、気づいた時にはもう……! と、ここから先は言えないと言われた」 真理は動揺する智恵理に冷静に答えた。 「それが欲情すなわち性欲だと。つまり、俺はあんたに欲情するらしい」 その言葉に場の空気が一瞬凍る。 「……は?」 智恵理の間の抜けた声がぽんと空間に放たれた。 「だから、俺はあんたにっ」 ――バン! 真理が皆まで言う前に、智恵理は彼の口を塞いで黙らせる。 「きききき聞き直したわけではあああありませんんん!! そそそそんな!? よよよよく!? よく、じょ」 「欲情」 言い直されて、ぶわぁっと毛を逆立てた。 「いやぁぁああ!! 意味が分かりません! 意味が分かりません! 意味が分かりません! そんな単語を僕を対象にして使わないでください!!」 「でも、俺はあんたを好きってことだろ?」 「そんなわけないじゃないですか!」 「ああん!?」 感情を否定された真理はドスの効いた威嚇の声を上げた。 「ひぃっ!」 「ちっ」 智恵理に怯えられて舌打ちをする。 「好きな理由は、前に上げただろう。そして俺はちょくちょくあんたに触りたくなる」 「ならない!」 また否定しやがるのかと、真理はより鋭い目つきで彼をギンと睨みつけた。 「なる!」 「な、ならない!」 「好きだ!」 「止めろ!!」 智恵理のらしくない荒々しい口調と声に、真理の口が止まった。重い空気に言葉が出ない。 肩を上下させる二人の荒い吐息だけが、空気に溶けた。 「……貴方、ロボットなんですよ」 しばらくして、智恵理が吐き出した。 「俺が、年をとらないことを気にしてるのか? 見た目なら、好きなようにあんたが改造すれば良いじゃないか。一緒に死にたいなら、あんたが壊せば良いじゃないか」 「そんなことじゃありません」 智恵理は首を振って、真理の胸を指す。 「貴方のここに、心は無いんです」 「俺はイレギュラーばかりだって言ったじゃねぇか」 「イラギュラーはただのイレギュラーですよ。貴方の感情が作り物であることに変わりない。貴方は僕が僕のために造ったロボットだから、僕を好きになって当たり前。だから、その感情は恋じゃないんです」 「そんなの、分かるかよ」 「分かります」 智恵理の断定的な口調に、真理はきっと何を言っても無駄だと悟った。 彼の言う事は、理屈が通っているのだろう。ロボットの自分の感情は、所詮作り物かもしれない。でも、 「……もう良い」 真理はぐっと眉を寄せて、投げ出すように言い捨てて、外に飛び出した。 偽物と言われようが、自分には今ある感情が全てで、否定されたらどうして良いか分からなかった。自分は偽物だから、作り物だから、本当に自分と呼べるものは無いから、否定されたら存在が消えてしまうと思った。 「真理!」 彼の声が背中を追ってくる。でも彼の理想でできている自分はきっと彼より足が速い。体力はロボットだから無限だ。だから捕まりたくなくて、必死に走った。 強くなった雨が、偽物の体温を冷ましていった。
山百合の魔女
「気になるの?」 明は長い睫毛に縁どられた豪華な瞳を細めて、智恵理を窺った。 「何がですか?」 「気取っちゃって。さっきから、彼のことばっかり見てるじゃない」 宴も終盤、日はすっかり落ちて、庭の草花は全て灰色に塗りつぶされている。テラスの明かりは点けていないが、大きな硝子窓から漏れる室内の光で十分明るい。 「……別に、気になるわけではありませんけど……」 智恵理は、その室内から視線を外して、空を仰いだ。オーニングを閉まったテラスでは、何の障害もなく空を見上げることができるが、今は生憎雲が覆って星空を眺めることは叶わなかった。 別に、真理が何をしていようと、誰と何を話していようと特に気になるわけではない。ただ、彼がいないと…… (半身が……) 「半身が、無いような気がするの?」 (胸が……) 「胸がスカスカするの?」 声に出そうともしていない思考を隣の美女に言い当てられ、智恵理はぞっと肌を泡立たせ「気持ち悪!?」と叫んでいた。 「一緒に居ないと落ち着かない、むしろ……」 「まだ言います!?」 明は、首筋に立った鳥肌を摩る智恵理を後目に、ミント・ジュレップのグラスをくるんと回した。 「自分と彼は同じはず」 「何を言っているんですか?」 意味が分からないと訝しむ智恵理をふふっと笑う。 「二人は一心同体のラブラブなのかしら、という話よ」と。 ****** 好きだ好きだと言っても、真理は初めから彼に恋をしていた訳ではない。 三か月前にあいつの好きなところを連ねた時は、面白いやつだとか、見ていて飽きないとか、そういう気持ちが強かった。触りたいと思ったのも愛しさからではなく、ただ滑らかな肌を触るのが、気持ち良かっただけだ。でも今は違う。 大学でカミングアウトをした日、小さくなって帰って来たあいつを見て、もやっとした。切なくなって、胸が苦しくて、守ってやりたいと思った。イレギュラーが多すぎると言いながら、俺の頭を守ろうとしてくれるから、愛しいと思った。自分が触れた時に、戸惑いがちに頬を染めて、少し震える声で咎める仕草を見たら、胸がぎゅっと締めつけられて、無いはずの心が悲鳴を上げた。 だから、好きだと思った。恋をした。 家を飛び出した真理は、雨に打たれて途方に暮れた。 真理は普段、店か大学にしか行かない。智恵理に頼まれればスーパーにも寄ったが、それも店からの帰り道にあった。必要もないから周囲を探索したこともなく、近所でも道を知らなかった。 つまりどうしたかというと、智恵理に追いかけられて、彼を撒くために無作為に走りまわった結果、道に迷ってしまったのだ。 目の前には、高い塀に挟まれた、緩い坂が続いている。塀や柵の隙間から見える民家には明かりが灯って、人の気配がした。胸がしくしくする。多分これは寂しいという感覚だ。 坂を上りきると、突き当りに、赤い実を付けた木の植えられた建物があった。円柱の塔のようなものを持った煉瓦造りのそこは、民家らしくない。よく見ると、小さな表札に『世界の不思議研究会』と記されていた。カーテンを閉めた窓から明かりが漏れている。個人の家でないなら、雨宿りくらいさせてもらえはしないかと、門の前で逡巡した。 「明様、お店でチェリオさんと何話してたんですか?」 「彼が、真理と一緒に居ないと落ち着かないって話よ」 「何それ、気になる!」 美樹、明、まゆみの三人は、明の自宅兼研究所で、二次会に興じていた。住居部分を二階に置いたそこの一階は、今は即席でバーのような形状になっている。 明は、はしゃぐ二人にふふふと笑って、梅酒の氷をカランと鳴らし、入口の扉に視線をやった。 「酒の肴が来たわねぇ」 立ち上がり、扉を開ける。 「あんた……!」 ずぶ濡れで立ち尽くしていた肴は、明を見て鋭い瞳を見開いた。 「どうしたの? チェリオさんに家追い出されちゃったの?」 招かれた真理にまゆみと美樹が駆け寄ってきた。 「……いや、家、出てきた」 「家出だって! 思春期の犯行だ!!」 「とりあえずタオル! 体拭かなきゃ。故障しちゃうかもしれないし!」 「精密機械だし!」 二人の言葉に真理は「え」と声を漏らす。それに二人も「え?」と疑問符付きで返した。 「なんで!?」 彼女たちがどうして真理がロボットであることを知っているのか。智恵理からは言わないだろうし、当然真理も誰にも言っていない。 「この人は誰でしょうか?」 困惑する真理に、まゆみが明を指して訪ねた。 「愛場明だろう?」 「またの名を?」 「山百合の魔女」 「由来は?」 「天才科学者だから?」 「それ、外れ」 まゆみは腕をクロスさせてバッテンのポーズをとる。 「明様は不思議マニアなの。美樹ちゃん、今まで何したんだっけ?」 「猫になっちゃった男の子を助けたり、男女の双子を入れ替わらせたり、幼馴染に猫耳尻尾を生やしてみたり、従弟同士を『もう一人のお前だ』って引き会わせたり」 「最後のは何か違うんじゃないか?」 指折り数えて明の武勇伝を語る美樹に、真理がつっこんだ。冷静なつっこみだが、この場に他に人がいたならば、その不足を指摘するだろう。 「とにかく、不思議で奇抜なことをしているうちに、魔女と呼ばれるようになったんですよ」 「そんな明様は、一目で真理さんが人間じゃないと見抜きました」 「ちなみに私の旦那も見抜きました」 男気がなさそうな美樹の「旦那」発言に、真理が首を傾げると、明が説明を加えてくれる。 「神様と結婚すると書いて『神婚』って知ってるかしら? 神様じゃないけれど、美樹は天使様と結婚しているの」 「天使……」 「翡翠さんだよ。非現実的だと思ったかな? でも、真理さんも結構現実離れした存在ですよね、一緒です。それで、その翡翠さんが私に、真理さんはチェリオさんの作ったロボットだって教えてくれたんです」 「まあ、良いじゃない。知っているものは知っているのよ」 「そうそう! だからロボットならではの悩みとかも話してくれて良いんですよ! まあ、力になれるかは別なんですけどね」 彼女たちの話は、真理のデータにないことばかりで、どこまで本気にして良いのか分からない。しかし、とにかく彼女たちが、真理がロボットであることを知っていて、その上で親身になってくれようとしていることは分かった。 説明が一段落すると、すぐに美樹が外に出ていく。彼女はしばらくしてタオルとスウェットを持って帰ってきた。 「二階の貸部屋に住んでるお兄さんに借りてきました」 「ありがとう。いつ返しに来れば良い?」 「仕事帰りに寄ってくれれば、助手の子がいるわ」 「わかった」 ありがたくそれらを受け取り、トイレで着替える。戻って来ると、明がグラスを差し出してきた。 「飲みましょう。家出少年」 少年という見た目年齢ではないが、と思いながらも、真理は琥珀色のそれを受け取る。 「で、真理はどうしてずぶ濡れで彷徨っていたのかしら?」 答えにくい質問は、琥珀色のそれで、乾いた喉を潤してから答えた。口の滑りが良くなった気がした。 「……智恵理さんと喧嘩した」 「貴方たち喧嘩するのね」 「そりゃあしますよ。私と美樹ちゃんだって喧嘩しますもん」 「この前は特撮男優の誰が好きかでもめたよね」 まゆみと美樹が、フォローのような雑談のようなそれをいれる。彼女たちのおかげで、自分が答えるまでに間を置けるのはありがたかった。 「……告白したら、怒鳴られたんだ」 「あらまぁ」と美樹とまゆみが声を漏らす。 「どうして怒鳴られたのか、分かっているの?」 明に促されて真理は続けた。 「俺はつくりものだから、恋なんてしないって、気の所為だって。俺はあいつがあいつのために造ったロボットだから、あいつを好きになって当たり前なんだって。それなのに俺がしつこく好きだって言ったから」 明はグラスを握り締める真理の手に自分の手を重ねて、彼の耳元に囁いた。 「こういう事したい? 彼と」 「……したい」 真理は目頭に熱くこみ上げて来るものを堪えて、彼女を見返した。 「俺は、あいつが嫌がってるって分かっても、やっぱりあいつに触りたい」 「じゃあ、おかしいわね。貴方は守るべき筈のものを傷つけたいと思うんだもの。貴方はただのロボットじゃない、イレギュラーよ」 明は、「そんなこと分かってる」と唇を噛む真理の左胸をトンと叩いた。 「貴方のここには、本物の魂が入っているわ」 真理は「は?」と声を漏らす。 (本物……?) 「……翡翠さんが天界に確認をとってくれたんですけど……。真理さん、死人を蘇らせるのに、何がいけないことだか分かります?」 美樹の質問に答えることができずに、真理は首を傾げた。 「体を作り直すのは細胞を作り直すだけです。なんなら最初から作り物の体でも良い。本当に欲しくて足りないものは――魂」 美樹を引き継いで、明が続ける。 「魂は呼び戻したらいけないの。一度死んだら、戻らないのよ。でも、貴方生きていたのよね。チェリオの中にずっと居たのよ」 「話が見えねぇんだけど」 「チェリオに兄がいたことは知っている? そう、知ってるのね。その兄が貴方よ」 真理は、それこそ話が見なかった。あいつの兄は流れたはずだし、自分はあいつの作ったロボットだ。 「子は流れたけれど、魂は流れなかったのよ。貴方は、母体に残って漂っていたの。そこに、チェリオが生まれた。体のない魂、行き場を見失った魂に、彼は眩しく見えたでしょうね。貴方は彼に手を伸ばし、一つになったの。それから、貴方たちは一つの体に二つの魂を持って、二十余年を生きてきた」 真理は彼女の話が、毎晩繰り返し見ている夢と一致することに気が付き、瞠目した。 「そして、貴方たちの魂を分けたのは多分、雷。魂は電気信号に似た形をしていると言われているわ。貴方は電気の流れに乗って、彼から抜けてその体に入ったの」 「じゃあ、俺の気持ちは本物なんだな」 希望を見つけた真理の言葉に、しかし明は頭を振った。 「貴方の体は目的を持って造られたものだから、本当に本当は、自分の意思で動いているわけじゃないのかもしれない。それは、人間になった貴方にしか分からないわ」 上げて落とされた気分になった真理は、がくんと肩を落とした。 「これは――初めに貴方が空に帰らなかったこと、二つの魂が同居してしまったことは、天界の落ち度でもある。だから、貴方にチャンスを与えてくれたわ」 明はすっと天井を見上げた。 「ロボットのまま、チェリオに好きと言われれば人間になれる。でも、このことを彼に知られてはいけない。知られたら最後、貴方の魂は空に帰る。――貰ってばかりじゃ潰れるから、制約が無いといけないの」 真理は彼女の言葉に愕然とする。上げて落として上げて、また落とされた。 「でも、王子様の愛の言葉でお姫様が生まれ変わる魔法だと思うと、素敵じゃない? 難しいけどね」 難しいなんてものじゃない。反り立つ崖から奈落に突き落とされるようなマイナスGを感じた。 (だってあいつは、俺の気持ちを認めなければ、きっと俺を好きにならない) 「……認められたいから人間になりたかったのに、人間になるためには認められなければならない。もし、人間になれたとしても、あいつを好きという気持ちは間違いかもしれない――ということだな」 顔色を無くして、ぼやくように言葉を紡いだ真理に、明は「それでも」と続けた。 「あなたは頑張れる?」 彼女の言葉に絶望を後押しされる。無理だと思える要素が多すぎた。「頑張れる?」頑張れると思っているのか。正直できる気がしなかった。でも、他に方法がない。 真理は言葉を発することなく、ただ静かに頷いた。 ****** 土砂降りの雨の中家を飛び出した真理を、玄関で膝を抱えて待っていた智恵理は、明け方に近い時間になってやっと帰ってきた彼に掴みかかった。 「真理!! 貴方、こんな時間まで一体どこに行っていたんですか!?」 「女性陣の二次会に混ざってきた」 真理の返しに、智恵理が苦虫を噛み潰したような顔をした。その表情に真理はぐっと胸を鷲掴まれる感覚がした。 彼は、勝手に飛び出していった自分を寝ずに待っていてくれたのかと、人一倍美容と健康を気にする彼が、冷たく硬い床に何時間も座って自分を心配してくれていたのかと思うと、苦しくなった。 「これは?」 「ずぶ濡れだったから借りた」 「傘ぐらい挿していきなさいよ!! あれだけ降っていたんだから、少し考えればわかるでしょう!?」 借り物のスウェットを指す智恵理に真理が答えると、彼は真理の肩を掴んで怒鳴った。 「どうせ風邪なんてひかないだろ。ロボットなんだから。人間じゃないんだから」 真理は吐き捨てるようにそう返した。自分が人間になれる可能性は限りなく0に近いのに、心配してくる彼に苦しくなる自分が虚しかった。 しかし、感傷に浸る間もなく智恵理の手刀を腹にきめられて、真理は体をくの字に曲げて咳き込んだ。 「テメ、何すんだ…っ」 智恵理を見上げて息を呑む。彼は泣きそうに顔を歪めていた。 「もし、もし……何かあって、脳が壊れたら、どうするんですか。風邪を引かなくても、体温が低くなったことでおかしくなったら、どうするんですか!?」 智恵理は真理の胸ぐらを掴んで揺さぶった。 「人間じゃなくても、壊れたら終わりなんですよ! 貴方の頭は、直せないんです! 自己回復もしないんです!」 震える声で叫ばれる。長身の真理に詰め寄る彼は、襟首を掴んでいるというよりも胸に縋っているように見えて、真理は小刻みに震える彼の肩を抱こうとする衝動を堪えた。 興奮して肩で息をする智恵理の瞳が揺らぐ。彼は脱力して真理から手を離した。 「もう良い、寝ます」 背を向ける彼を、真理が何もできずに見送ろうとすると、足を止めた彼が振り返った。 「寝ると言っているでしょう!」 促されるままに彼のベッドに入ると、彼は真理の腕の中に落ち着いて、真理はどうしようもなく胸がムカつくのを感じた。
スパイス
智恵理がゲイだと公表してから、徐々に女性から言い寄られる回数は減っていき、最近では全くと言って良い程声をかけられなくなった。しかし、女性からだけでなく、男性からも距離を取られるようになった。また、聞こえよがしの中傷はなくなったが、じっとりとした気味の悪い視線は消えなかった。 「正直さ、男を好きってどうかと思うよ」 智恵理をカフェテリアに呼び出した琉惺が言った。 「何故です。貴方には関係ないでしょう」 智恵理は呼び出しに応じた代償に奢らせたアールグレイをゆっくり舌に馴染ませて味わう。夏休みに入り、カフェテリアの利用者は減った。そのためせっかく競争率の激しいボックス席に座ることができたのに、彼の選んだ話題にすっかり気分が害されてしまった。 「俺は良いけどさ、一般的な話。結構周りとぎくしゃくしてるんじゃねぇの?」 琉惺はそんな彼を気にせず続ける。 「いつか、自分が対象になるかもしれない、って思うんだよ」 「自意識過剰ですね」 「そうかもな」 琉惺は話に乗り気でない彼に、これみよがしに溜息を吐いた。 「でもお前、あの人に対しても本気じゃないんだろ?」 「は?」 「だから真理さん。お前ら全然恋人らしくないよ。そんなのさ、誰でも良いんじゃないかって思うじゃん」 「そんなこと……」 「ない」とは言い切れなかった。 真理と智恵理は本物の恋人同士ではないから、智恵理自身は恋人らしく振舞っているつもりでも、周囲から見れば違ったのかもしれない。だったら、恋人らしさとは何だ? 「空気が違うんだよ。全然甘くない。特に最近は、ピリピリしてる」 琉惺はそう言うと、智恵理の紅茶と一緒に購入したコーヒーを口に運んだ。砂糖もミクルも入れないそれの、苦味と酸味がじんわり体に染みていく。 「なあ、今普通に接してくれる男、どれだけいる? ……そいつら、きっとお前のこと狙ってるよ」 「班員と貴方は?」 「俺は、お前と便所で鉢合わせたら、不味ったなって思うよ。相合傘はできなくなったし、パーソナルスペースは広くなった。気付いてるだろ?」 それを言われて考えれば、班員にも、ふと手や肩が触れた瞬間に弾かれたように距離を取られることを思い出した。気まぐれに差し入れを渡せば、引き攣ったような笑みを浮かべ、その人だけでなく周囲にも声を掛ければ、その笑みが自然なものに変わったことを思い出した。その意味に気が付いた。 「居た!」 智恵理が途方にくれて琉惺の手元を見つめていると、女性特有の高く甘い声が掛かった。琉惺が彼女を手招く。 「あの子、他大学で知り合った杏奈ちゃん。お前と話してみたかったんだって」 「どうして」 「みんな、お前らがお似合いだなんて思ってないんだよ」 呆然と呟く智恵理に、琉惺は歪に笑ってそう答えた。 「クロちゃん、増見に意地悪したでしょ」 相変わらず朝から店に上がり込んだ琉惺に、荘一郎はぷぅっと頬を膨らませた。優男といえども立派な成人男性がその仕草をすること、またそれが似合ってしまうことに薄ら寒さを感じつつ、琉惺は彼の言葉をはぐらかした。 「花名さんは、なんで俺の名前を覚えないの?」 「覚えられないんだもん」 「畔戸。はい、リピートアフタミー、く・ろ・と」 「くろと」 「覚えマシタか?」 「多分」 「前もそう言いマシタネ」 「ごめんね、ドンマイ!」 呆れたような諦めたような薄笑いを浮かべる琉惺に、荘一郎はウインクと共に星を送る。そんな彼に琉惺はなんとも物悲しい気分にさせられた。 テラスから見上げる空は青い。爽やかな朝の光に醜い心を晒される。――琉惺の智恵理にした行動は、ただの八つ当たりだった。琉惺は彼が男に一目惚れをし、その恋を実らせたことを理解できないと思っていた。でも、本当は違かった。 (クソ野郎だな……リア充爆発しろってきっとこういう気分……) 心の中で吐き捨てる。 「俺、羨ましかったんだ」 琉惺は、智恵理が自分や周りと異なる価値観を持っていることを知っていた。周りに何を言われても態度や意見を変えない彼が、心配でもあり、羨ましくもあった。 「そっか。でも、あんまり虐めないでね」 花名がしょぼくれる彼に花を銜えさせる。琉惺はけして美味しくはないそれを、なされるがままに咀嚼した。 「……名前覚えてよ……」 彼の小さすぎる呟きは、庭いじりに戻った花名には届かなかった。 ****** すっかり日の落ちた休日、実験当番で一人シフト部屋に入っていた智恵理は、視線に気が付いてふと作業の手を止めた。入口を振り返ると、薄く開いたドアからもっさりした頭の男がこちらをじっと見つめている。 男は、顎がやけに細く、洗いざらしにしたような艶のないくせ毛で、落ち窪んだ目と青白い顔は不健康そうに見える。一見して怪しく見えるが、研究に没頭する生徒の中にあっては珍しくもない風貌だった。 「何か御用でしょうか」 「増見さんに」 「僕ですか?」 智恵理は何の危機感も覚えずに彼を招き入れた。 智恵理に邪な思いを抱いている輩がいるとは聞いたが、この男は違うだろうと思ったのだ。近頃、智恵理は気が付けば、肌に張り付くような監視する視線を感じていた。しかし、それはこの男のように自己主張の激しいものではなかったから、本当に用事があって来たのだろうと思ったのだ。 しかし、男は智恵理の手を取ると、ぐっと身を寄せて言った。 「貴方はとても綺麗だ」 その瞳の奥に、どろりと濁った光を見て、智恵理はやっと読み違えたことに気が付いた。 「やめろ!」 咄嗟に男を突き飛ばして距離を取るが、男はゆっくりと顔を上げて恍惚といった表情で距離を詰めてくる。 「ごめんなさい。でも許して欲しい。僕はどうしても貴方に触れたい」 男の言葉にぞっとした。声も出せない程の怖気が背筋を這い上ってくる。伸びてきた男の手を振り払って、部屋から飛び出した。その瞬間、人にぶつかった。 「うおっ!?」 弾丸のように突っ込んできた智恵理を、声を上げながらも受け止めたその人は、逃げようとする智恵理を捕まえて離さなかった。 「触るな! 離せ!」 「ちょ、おい! 増見!! どうした!?」 馴染みのある声に名前を呼ばれ、やっとその人を認識する。 「……畔戸」 「なんだよ、そんなに取り乱して」 智恵理は恐怖からその胸にすがった。彼の小さく震える肩に、琉惺は戸惑いがちに手を置く。 「どうして逃げるの?」 智恵理が飛び出してきた部屋から、男がのっそり顔を出した。 「俺は貴方に触れたいだけなんだ。貴方を手に入れたいだけなんだ」 琉惺は無言で彼にケータイを向けた。 「何してるの?」 「記念写真だよ。お前の告白記念写真。増見、告白されてるぞ。ほら、答えないと」 「畔戸、貴方何を言って……」 智恵理は常以上に軽い口調で促す琉惺に訝しげな視線を投げ、彼の目が鋭く、男に警戒心を持っていることに気が付いた。 「……僕には恋人がいるので諦めてください」 「どうして? どうして恋人がいると諦めなくちゃいけないんだ? そいつの方が諦めれば良い」 智恵理の背に再び怖気が走る。血の気の引く感覚がした。男の全てが気持ち悪かった。理屈の通じない、話の全く通じない男がひたすら怖かった。 琉惺は舌打ちをすると「無理だな」と呟いて青い顔をした智恵理の腕を掴んで男から逃げた。 「真理さん?」 琉惺は校内を歩く男に声を掛けた。彼は琉惺を認めると、不自然に視線を巡らせる。 「こんなところで何してんだ? 増見に用事?」 真理は縋るように琉惺をじっと見つめた。 「どうかしたか?」 「……最近あいつ、変なんだ。だから、ここに来れば理由が分かるんじゃないかと思って」 数拍置いてやっと口を開いた彼を、琉惺は「話くらい聞くよ」とカフェテリアに誘った。 「最近あいつの帰りが早くなって。喧嘩ってわけじゃないけど、俺とも少しぎくしゃくしてた筈だから、遅くなるのはありえても早くなるのはおかしいんだ。それに、やっぱり避けられてる気がするし」 真理はコーラのボトルを握って言葉を紡いだ。 「飲んだことがないから」と言ってそれを選んだ彼に、琉惺は「前から世間ずれしているとは思っていたけど相当だな」と彼への認識を強固にしていた。 「もしかして、真理さんと増見ってまだそういう関係じゃなかったりするの?」 琉惺の言葉に、真理はこてんと首を傾げてハテナを飛ばす。 「そういうって何だ?」 「セックスしてないの」 顔に似合わず可愛らしい仕草をする彼に琉惺が直球で返すと、彼は「な!?」と顔を染めて固まった。そんな彼に笑いそうになるのを抑えて、琉惺は目を伏せて続ける。 「……じゃあ、怖いのかもしれないな」 我ながら神妙な空気をつくれているのではないかと思った。 「なんかさ、襲われたらしいよ。男に」 ちらりと真理を伺うと、彼はぐっと息を詰まらせて拳を握っていた。 「なんで、そんなことお前が知ってて、俺が知らないんだよ」 「恋人だからこそ言いづらかったのかもよ」 琉惺は心にもないことを口にした。本当は恋人云々に関係なく、智恵理は誰にもあのことを話していないのだろうと思っている。 あの後、男から逃げた琉惺と智恵理は、すぐに学生課経由で警察に連絡をした。その数日後、男は薬物を乱用していることが分かり無事お縄についた。 すぐに解決してしまったから、余計に報告する必要性を感じなかったのだろう。何をされたという訳でもないから、彼の気持ちを抜きにして、事実だけを見れば些細なことだった。 黒い心と裏腹に、琉惺は眉を下げて困ったような笑みを真理に向ける。 罠を張ってやろうと思った。彼らの仲が上手くいかなくなるような罠を。自分にできないことを平気でしてしまう彼らに、これくらいの意地悪をしても良いじゃないかと思った。 (『あんまり虐めないで』って花名さん言ってたな。でも、そんなに虐めてないよ?) 「なんでそんな顔してんの? 俺の言ってる意味、分からない?」 琉惺は愕然とした表情で黙り込む真理を流石に不審に思って窺う。 「違うんだ。俺とあいつは……」 呟いた真理は、そこまで言ってハッと目を瞬くと、コーラを一気に流し飲む。続く言葉を一緒に喉の奥に押し戻すかのようだった。 コトコトと小さな音を立てる鍋を前に、智恵理はふう、と溜息を吐いた。 実験のシフトもなく、学校に行く用事もなかったこの日、時間を持て余した智恵理は料理に没頭していた。 智恵理の辞書に「暇」などいう言葉はないはずだった。時間があれば、勉強、実験、研究とやれることはいくらでもあるはずだった。しかし、やる気がおきない。実験や研究と名のつくものに手を付けようとすると、どうしても真理かあるいはあの男の顔がちらついた。 男に襲われてから、他人との接し方が分からなくなった。例えば、ふと手や肩が触れた瞬間に弾かれたように距離を取ってしまうような。今まで班員にされていたことを自分がしてしまう状況だった。 ――もしかしたら、自分を狙っているかもしれない―― そんなふうに思ってしまう自分が自意識過剰なようで恥ずかしく、今まで自分に対してこれと同じような反応をしていた人たちが、こんな気持ちでいたのかと思うと、それも無性に恥ずかしかった。 加えて厄介なことに、このことがきっかけで、自分が真理へ向けている感情に、気が付いてしまいそうになった。「しまいそう」というのは決して気が付いていないということだ。気が付くわけにはいかない。気が付くものか。 男に迫られた時、とにかく男を嫌悪した。触れられたくないと思ったし、自分をその視界に入れるなとさえ思った。そこでふと、真理に迫れたときは、戸惑いはしたがこんな風には思わなかったと気が付いた。 また、先に述べたように、他人との距離のとり方が分からなくなってしまってからも、真理との接触は嫌ではなかった。だから、余計に挙動不審になってしまった。 ――♪ チャイムの後に、玄関扉を開ける音が聞こえて、智恵理は思考を中断した。 「お帰りなさい、真理。今日は時間があったので、スパイスからカレーを作ってみたんですよ。食べるでしょう?」 キッチンと廊下を隔てる扉から顔を出して声を掛ける智恵理を、真理が無言で見つめた。 「真理?」 好物のカレーに食いつかない彼を訝しく思って伺う。彼は、智恵理の前で足を止めると、がっとその腕を掴んだ。智恵理は反射的にその手を振り払う。触れられたそこから血液が巡るようなときめきを感じて、居た堪れなかった。 しかし、そんな甘い気持ちは彼の言葉で風化する。 「……あんた、男に襲われたんだって?」 どうしてそれを知っているのかと、すぐに彼の前から逃げ出したくなった。 「なんで言わなかった?」 静かに見つめてくる彼の瞳に怒りの色を見つけて、智恵理はぐっと唇を噛んだ。 「……貴方には関係無いでしょう」 その言葉に、真理は思考の隅で頭の血管の切れる音を聞いた。 「俺が恋人(仮)だからか? 違うだろ?」 真理は、再び智恵理の手首を掴んだ。弾かれるように彼の肩が跳ねたがもう離さない。 「俺は、お前のために存在してる。俺は認めないが、俺がお前のことを好きなのは、お前のためで、お前のせいなんだろ? だったら、俺がお前のことが心配で、危険な目にあったことを知らないでいたことが許せないのはお前のせいなんだろ!?」 彼が逃げないように捕まえて一気に捲し立てた。 「畔戸に、あいつにその話を聞かされたとき、何でこいつの口から聞いてんだろうって思った。俺の知らないところであんたが怖い思いをしたのかと思ったら悲しくなった。畔戸に、恋人だからこそ言いづらかったんだろうって言われて、そんなわけあるかって、腹の底が煮えるような気持ちになった」 真理は智恵理の揺れる瞳を見つめて言い放つ。 「辛いんだよ! 責任取れよ!!」 魂ごとぶつけてくるような叫びに晒されて、智恵理は呆然と呟いた。 「僕は……」 ――なんてものを造ってしまったんだろう。 以前にも智恵理を優先する彼に思ったことだった。彼の言うとおり、自分は彼に責任を取らなければいけない。でも、責任なんて取れない。 (彼は僕を好きじゃない。だから僕は彼を――) 「……貴方にだけは知られたくなかった」 自分を好きだという彼に、自分が男に求愛される立場だと知られたくなかった。 自分を心配するようにできている彼に、隙を見せたくなかった。 自分が弱い立場にいると思われたくなかった。 ――それは、どうして? 離れた席に座って食べるカレーは、せっかく手間をかけたのに、何の味も分からなかった。
スクラップ
肌寒くなり長袖の上に薄い上着を羽織るような季節になっても、智恵理と真理はお互いに本音を口に出せない、塩水に浸かるような関係を続けていた。 智恵理に対する気持ちを自覚し、彼に拒まれながらも離れることのできない真理は、明の家に逃げることが多くなった。帰宅の早くなった智恵理は、必然的に夜、一人で居ることが多くなった。智恵理が寝てしまってから真理が帰るときには、同じベッドには入らないから、そうしているうちに常にばらばらに眠るようになった。 「あれ、チェリオさん。珍しいですね」 智恵理は、「お菓子の庭」を避けて入った喫茶店で、偶然まゆみと居合わせた。そういえばここは山百合大学の近くだったと気が付き、尋ねる。 「ここへはよく来るんですか?」 「『お菓子の庭』程頻繁じゃないですけど。ここ、コーヒーと定番メニューは何でも美味しいですよ。今日のまゆみはナポリタンです」 流れで同席した智恵理も、彼女と同じメニューを頼んだ。 レトロな雰囲気の喫茶店は、「菓子の庭」とは違う、落ち着いた印象で、学生やOLよりも定年を過ぎた老人や、自営業らしい中年層の利用が多いようだった。 智恵理の頼んだコーヒーが運ばれて来て、空間の芳ばしい香りが濃くなる。耳に馴染むクラシックメドレーを何となしに聞きながら、まずは何も入れずにブラックのままそれを口に運んだ。 「チェリオさんもなかなかイイ男になってきた」 まゆみがおもむろに口を開いた。 「『も』ってなんですか」 智恵理は照れることもなくそう返したが、彼女が智恵理にこういった言葉を掛けるのは初めてのことだった。彼女は琉惺や壮一郎、特に琉惺がお気に入りなようで、よく好きだなんだと言っていたが、今回はどんな気まぐれだろうか。単純にこの場に智恵理しかいないからかもしれない。愛を語らなければいられない人種というのもあるのだろう。 「本当のこと言いますと、初めて真理さんを紹介された時、女の人への牽制で恋人ごっこをしてるんだろうな、て思ったんですよ」 「似合わない、っておっしゃるんですか?」 「もー! そんなんじゃないですよ! だって、恋してる顔じゃなかったから」 彼女の言葉に、智恵理は「まただ」と思った。 「恋人らしくない」「空気が違う」琉惺にも言われた言葉だった。だったら、もう何もできない。恋人という形をとるだけではいけないなら、どうにもならない。智恵理と真理は愛し合っていないのだから。 「まゆみ、好きな人が居る男の人ばっかり好きになるんです。趣味悪いですよね」 しかしその台詞に、彼女の言わんとすることが、智恵理の考えていることとは違うようだと勘付いた。彼女の続く言葉を想像して身構える。 「最初はそんなことなかったのに、今はチェリオさんも真理さんも魅力的に見えちゃいます」 (違う……、違う……) 智恵理は縋るように心の中で繰り返した。自分は、彼のことを好きじゃない。 ――でも、帰りの遅い彼を待って、一人で家に居るとどうしても、そうなんじゃないかと考えてしまう。 最初からおかしかった。造った当初から、近くに置かないと落ち着かなかった。そのくせ不意に触れられると、戸惑った。初めて名前を呼ばれた時も、それだけのことに取り乱した。 「――どうして彼なんでしょうね」 諦めたような言葉がぽろっと零れた。 「大雑把で、趣味も合わなくて、理想から程遠い」 「チェリオさん世話焼きだから、丁度良いじゃないですか。それに、真理さんはチェリオさんを大切にしてくれますよ」 彼女の言葉に頭を振る。 真理が不器用ながらも智恵理のために色々行動してくれていることは分かっている。彼は智恵理が本当に嫌がることはしない。横暴そうに見えて、いつでも智恵理を優先する。 でも、そうじゃない。僕は、 「大切に、されたくないんですよ……」 ――対等でいたかった。 彼は、僕を好きなわけじゃない。造り手に縛り付けられているだけだ。 僕を避けている今、彼は自由に振舞うことができている。僕が彼を好きだと言ったら、彼の世界はまた僕を中心に回りだすだろう。それは、嫌だった。 一人で寝る夜は、決まって夢見が悪い。前を行く背中に手が届かなくなる。真理と出会ったばかりの頃に逆戻りだ。 手が届かないほどに、溢れる気持ちを持て余した。以前なら平気だった筈なのに、触れる喜びを知ってしまった今の気持ちは、吐き気を伴う程の喉の渇きに似ていた。 その日も恋しくて仕方なかった。どうしても触れたくて必死で追いかけて手を伸ばし、どうにかその手が届いた。恋しくて、恋しくて、しがみついて、涙を流す。止まらなかった。好きだ、好きなんだ。彼が振り向いた。抱きしめられる。口づけられる。 その彼の顔は―― 真理は魘される智恵理の髪をそっと撫でた。 彼に「好き」と言わせるために、何をしたら良いかが分からなくて、結局何も出来ないでいる。正直、彼と暮らすのも限界だった。好きな人とこんなにも近い距離にいるのに、意識して触れることができないのは辛かった。 薄く汗の浮いた額に手を置くと、眉間のしわが薄くなる。彼は真理の手に擦り寄って、両手を伸ばしてきた。どうしてそんなに無防備でいられるのかと不安になる。伸びてきた彼の手をとって、指を絡める。意識のない彼に酷いことをしている気分になった。 「……いかないで……」 智恵理が湿った声で呟いた。ただの寝言だ。自分が言われたわけじゃない。それでも、都合の良いように捉えたらいけないのか。 真理は彼の腕を引いて、脱力する体を抱きしめた。 「ごめん……」 懺悔して彼の唇に指先で触れる。 「ごめんなさい……」 もう一度呟いて、そっとそこに唇で触れた。 「――!?」 目を覚ました智恵理は、思わず目の前の男を突き飛ばした。 「な、なんです!?」 夢で見たのと同じ顔に、同じことをされていたことに混乱して、咄嗟に状況を理解できなかった。 (なんで、真理が夢に……なんで、今) 唇に手を押し付ける。ここに、彼の感触がした。 「なんで……」 「わるい……、魘されてたから」 「――っ、貴方は、魘されていたら、襲うんですか?」 「それは……」 バツ悪く目を伏せる真理に苛立つ。 「貴方は、いつもそうやって、僕を振り回す。……貴方なんか、……貴方なんか」 智恵理はぐっと奥歯を噛んだ。眉間とこめかみに力が入ると、色々なものが溢れそうになる。 「――造らなければ良かった!!」 智恵理が言い放つと、真理は無言で部屋を出て行った。 智恵理も黙ってそれを見送る。またどこかに逃げたのだろうと――今日は雨も降っていないから、気にすることじゃないと、そう思った。しかし、 ――ドゴンッ すぐに地下から爆音が響いてきて、慌ててラボに走った。 「真理!?」 厚い扉を開けると、煙の向こうに彼が横たわっていた。慌てて駆け寄り、その場に膝を付く。 「なんで……!?」 電気ショックのコードを繋いだ彼が、虚ろな瞳で智恵理を見上げた。 「……智恵理さん、……ごめん、……好きになって……」 プスプスと煙をあげる音に混じって、小さな声はとても聞こえづらい。煙が染みて視界が滲んで、姿さえ霧のように儚く消えてしまいそうに見えた。 (ああ、離れていってしまう。この手が永遠に届かなくなってしまう) 「嫌だ……嫌だ、嫌だ!」 待って―――! それは、夢であの背中を追いかけている時と同じ感覚だった。智恵理は、ゆっくり瞳を閉じる真理の手を、必死で握った。 「嘘だ……」 この光景を、嘘だと言って欲しかった。 「だって、どうすれば良かったんですか……。好きだなんて言ったって、どうしようもないじゃないですか……、意味なんて無いじゃないですか……」 涙を煙に後押しされる。ほろほろ零れるそれと一緒に、溜め込んでいた感情が言葉になって溢れだした。 「誰が、壊れろなんて言うんですか……。僕はずっと、造らなければ良かったって、言っていたじゃないですか……」 智恵理は、もうピクリとも動かない彼の顔に手を添える。湿った声が喉に絡まった。 「これ、死んだんですよ……?」 口にしてしまえば、本格的にそれを実感してしまって、駄目だった。 「……ひぅっ、く……、真理……っ」 額を彼の胸に押し付ける。 自分は彼と対等でいたいだけだった。男に襲われたことを言わなかったのも、弱い立場にいると思われたくなかったのも、彼に守ってもらうのが嫌だったから。好きだと言わなかったのも彼を縛り付けたくなかったから、だから本当は…… 「ずっと、好きだったのに……!」 彼の胸に頭を伏せて泣き叫ぶと、その胸が動いた気がした。 「……え」 背中に腕を回されて抱きしめられる。 ありえないことに驚いて顔を上げると、壊れた筈の真理が、目を開けてにやりと笑っていた。 「やっと、言ったな」 「なんですか、それ……っ」 智恵理は唇を噛んで、彼の腹部に手刀を入れた。
その後の彼ら
「なんだ。冷戦、終わったのか」 店の帰りに智恵理を迎えに研究室に来た真理を見て、琉惺は言った。 「はあ?」 「こっちの話」 威圧感のある瞳を向けてきた真理に適当に返す。 「何だよ、智恵理さんはやらねぇからな」 「要らねぇよ。そんなババァ」 しっしと手を振ると、智恵理が「ちょっと」と青筋を浮かべた。 (あーあ、独占欲発揮しちゃって) 智恵理を背に庇う真理に思って、琉惺は「ふはっ」と笑った。 真理は夜道を帰る智恵理を心配して迎えに来るようになり、智恵理は真理が来てくれるからと安心して研究に打ち込めるようになった。二人の関係は琉惺が苛める前より親密になったようで、今では空気がとても甘くなっている。琉惺が彼らにしたちょっかいは、結局ただの恋愛のスパイスになってしまったらしい。 「すっかり恋人になっちゃってさぁ」 「何が言いたいんですか」 「べっつに~?」 琉惺は、訝しげな智恵理に、胡散臭いと言われる笑顔を向けた。 「せいぜいお幸せに。俺にも夢、見せてね」 夢を現実にしたいと思いながら。 「まゆみは言ったんだよ?『今は』チェリオさんも真理さんも魅力的に見えちゃいますって。真理さんも最初は魅力的に見えなかったの。真理さんだって、最初からチェリオさんのことを好きだったわけじゃないんだよ」 世界の不思議研究会の一階で、まゆみは美樹を相手に得意げに話した。 「まゆみちゃんは真理さんの気持ちが本当だって分かってたんだね」 美樹はクッキーを摘みながら相槌を打つ。 「真理さんは生まれたての赤ん坊みたいなものだから、徐々に好きになる=本当の気持ち、とは分からなかったみたい。チェリオさんの為のロボットとしての特性だったら、最初からじゃないとおかしいのに。だからチェリオさんの方にそれとなく伝えたかったんだけどな」 「好きなわけがない、って思い込みだったのかもしれないね。でも、まゆみちゃんは色々考えて行動してすごいね」 「うん! まゆみすごい!」 まゆみはぐっと拳を握ると、高い天井に向けて突き上げた。 「だから、すごいまゆみの運命の王子様、早く来い!」 そんな彼女に、「好きな人の好みを変えなければ、難しいんじゃないかな」と美樹は思うが口には出さない。ただ「頑張れ」と言って、甘いクッキーをすすめた。 「クロちゃぁんっ!」 相変わらず早朝に店にやって来た琉惺に、荘一郎が跳びついた。 「外寒い! お花冷たい!」 「花名さん、いい加減俺の名前覚えてくれた?」 抱きついて指を絡めてぎゅっぎゅと握ってくる彼に、琉惺が尋ねると、彼はテヘッと舌を出して小首を傾げた。 「ごっめーん! やっぱり出てこない! ドンマイ、クロちゃん! それでも花名さん、クロちゃんのことは嫌いじゃないから、きっと許してくれるよね?」 琉惺は悪びれない彼に、特上の頭突きをお見舞いした。 「貴方の掌の上だったのかと思うと釈然としないのですが」 真理を避けている間、足が遠のいていた「お菓子の庭」で、久々に明と顔を合わせた智恵理は、勝手に同席してきた彼女に言った。 「大げさね。私はただの傍観者じゃない。何もしていないわよ」 明はチーズケーキを一口掬って、肩をすくめる。 「だって、真理を作ったのは貴方でしょ? 人間になりたいと思ったのは真理で、真理のことを人間にできないか掛け合ったのは美樹の旦那さん。最後まで頑張ったのは、壊れても未練タラタラで魂繋いで、貴方の言葉を聞いていた真理」 明は形の良い指をすっと伸ばして、智恵理の胸を指した。 「胸、すかすかするでしょ? 二つあった魂が片方抜けたんだもの」 見透かされたことに拗ねて唇を尖らせる彼に、にっこり笑う。 「そうしたら、真理に抱きしめてもらえば良いんじゃない?」と。 「ほら、真理! ちゃっちゃか起きなさい、ちゃっちゃか!!」 「うぅん……智恵理さん、うるさい……」 掛け布団を剥ぎ取って、甲高い声で叫ぶ彼に、真理は苦情を漏らした。 「うるさいとは何ですか!? なんなら放っておいても良いんですからね」 真理は窓から入る光に目を眇めて体を起こすと、綺麗な眉間に皺を寄せて睨んでくる彼の目を見つめ返した。 (そう言って、世話をするのをやめないくせに) 「智恵理さん、俺、あんたに優しくされるとムカッてしたんだ」 「はあ!?」 「でもあれ、ムカッじゃなくてムラッだったらしい」 声を荒げる智恵理にしれっと続けると、彼は一気に顔を赤く染め上げた。 「……っ、どうなっているんですか、貴方の頭の中は。故障してるんじゃないですか?」 眉を顰める、そんな反応にもムラっとする。 「智恵理さん、俺、人間」 「知ってます!!」 爽やかな朝に似合わない怒鳴り声が、一際大きく響いた。
科学者の恋人<完>
