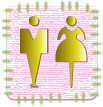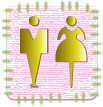
最高の二股男 カップル 編
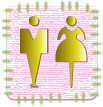
最高の二股男 カップル 編
![]() 街でキメラを見つけまして!
街でキメラを見つけまして! ![]()
本日は晴天なり。青く澄み渡った空に時々薄い雲が見え隠れする。 男の子みたいな女の子、愛場千晶は大好きな彼、白鳥昇と大好きなゲーセンでデート。行きずりの挑戦者相手に挌ゲーで連勝記録を更新し、とても気分よく、町を歩く。 そしてちらっと、背の高い彼を仰ぎ見た。たまにこういう気分になる。 千晶は昇の手を引いて路地に入った。 「なあ、昇…」 「なに?」 声をかければすぐに柔らかい声が返ってくる。 なんで彼はこんなに背が高いのだろう。なんで自分はこんなに背が低いのだろう。 千晶の瞳が熱を帯びる。 これじぁ、顔が近くで見たいと思っても、キスしたいと思っても―― 不意に昇が屈んだ。欲しかったそれが目の前にある。千晶はゆっくりと瞳を閉じた。 ――その時、喧騒にまぎれて千晶のケータイがなった。 すでに昇の意識もそちらに移ってしまっていて、仕方なく着信画面を確認すると、『明』の文字。これで今日のデートはお開きだ。 千晶は泣きたい気持ちでケータイを閉じた。すると、優しく撫でられた頬、掬われた顎先、重ねられた優しい唇。 あ―― それと気づいた時には彼は目の前で「いってらっしゃい」とほほ笑んでいた。 本日は晴天なり。折角の良い天気の中、科学室に籠って実験をしているのもなんなので、世界の不思議研究会会長・愛場明とその助手、木下まゆは、キメラを探しに街へ出た。 明は腰まで伸ばしたふわふわウェーブの髪の毛と、眉の高さで切り揃えられた前髪に囲まれた、卵型の美しい輪郭。筋の通った鼻、長いまつ毛に囲まれた大きく黒目がちな瞳、桃色の唇はどれも整っていて、前髪から覗く濃く細い眉が意志の強さを感じさせる。加えてボンキュッボンの誰もが認めるナイスバディとくれば自然と人々の注目を集めてしまう。 隣に並ぶまゆも可愛らしい顔立ちなのだが、如何せん今だ十二歳。発達途中の体には起伏が乏しかった。 高い位置で二つに結った癖のない長い髪を揺らしてまゆが言う。 「キメラ、たくさん見つかると良いですわね明様。」 「そうね、まゆちゃん。」 微笑みあう二人の姿はすぐに雑踏の中に紛れてしまった。 姉の明から連絡があったのが今から三十分前。今おれはこの扉を開けるべきかものすごく悩んでいる。自分の家のそれも自分の部屋の扉だ。正確には姉と共同の部屋だ。そこから聞こえる声は、明らかに明とまゆの二人ではない。 …キメラの声ですか?大体あれだ、なんで街にキメラが居るんだ。変だろ!絶対変だろ! 「千晶、居るなら早く入ってきなさい。」 「…はい。」 …終わった。 力無く部屋に入り、明の向かいに座ると、明より少し下がったところにまゆがちょこんと座っていて、その後ろでは 数人のおっさんが談笑。 あはは…なんでおれここに居んだろ。 「遅いわ、千晶。待ちくたびれたわよ。」 「しょうがないですわよ。千晶様だって用事がおありでしたのよ。」 好き勝手言ってんじゃねえ! 「それに、またそんな男の子みたいな格好して。伊達めがねなんかで可愛い顔を隠すなんて、勿体無い!」 「ああ!もう、いいだろ。昇がこれで良いって言ってんだから。つーか、誰だよこの人ら!どこがキメラだよ!どう見ても普通の人だろ!」 千晶、プチ切れ。だってどう見てもただのおっさん。 「ただのおっさんじゃないわよ。」 心読まれた! 「では、紹介します。右から猫と人間のキメラの田所さん。熊と人間のキメラの島村さん。鳥と人間のキメラの田所さん。猿と人間のキメラの小池さん。像と人間のキメラの田所さん。魚と人間のキメラのフィッシュ田所さん。彼は恥ずかしがりやだから、ペンネームなの。」 「…いやあ、あの…はは…、はい。」 で、どこから突っ込めと? 「田所様は猫舌。島村様は隈が酷い。田所様は夜目がきかない。小池さんは猿顔。田所さんは像足。フィッシュ田所さんは先ほど目から鱗が落ちた。とのデータがえられましたわ。」 「それは普通の人間だ!お前らはバカか!?バカだな!あんたらもよくこんな馬鹿げた事に付き合ってられるな!あと田所が多い!ややこしいんだよ!!」 千晶ブチ切れ。 「つっこみが長いわー。」 五月蝿い。 「明様の美貌に魅せられ、お供したしだいでございます。」 五月蝿い、五月蝿い! おれの休日を返せ――!!
届かない。物理的に
side千晶 この身長差が気にくわない。 キメラの時は結果、あいつからキスされたので、目的は果たしたように思えるが、そうではないのだ。 キス、したい。 受けるのではなく、自分から、だ。 あいつはいつも、俺を好きだと全身で語ってくれる。人の目があるところでは、にこにこ笑って、跳びついてきて。 二人の時は、優しく抱きしめて、愛しくて仕方がないと、髪を梳いてくれる。 甘すぎる空気に、いたたまれない気持ちになることもあるけれど、彼が居る空間は心地良い。 でも、自分はどうだろう。 言葉も、行動も、あいつから貰ってばかりだ。 自分は素直じゃないから、好きだなんて、告白の時以来言ってないし、言えない。だから、行動で示そうとしても、甘えるなんて、プライドが許さない。 あいつの前で男である意味は無い。いや、大体普段から男である必要は無いのだ。しかし、男であろうと女であろうと、誰よりも強くあろうとする気持ちは変わらない。 俺は甘えられない。だから、甘えさせたい。 今更だって?確かに、彼の普段の行動は、甘えていると言えなくもないかもしれない。しかし、それは、じゃれていると言った方が正しい。 そうではなくて、自分も、彼が好きだと伝えたいのだ。 だって、あいつのくれる思いはとても自分を幸せにしてくれる。だから、自分も同じに応えたいのだ。 頬を撫でたい。髪を梳きたい。――キスが、したい。 でも、届かないのだ。あいつの背が高すぎて、物理的に。(昇の背が高いだけではなく、千晶の身長も低いのだが、悔しいのでそれはあまり考えない。) あいつのが俺の手の届く位置にいるときは、あいつが俺を構うときだ。だから、必然的に俺は構われる側に回ってしまう。 どうにかならないものか、と千晶は真剣に考えていた。 side昇 小さい彼女が可愛くて仕方ない。 抱きつくと冷めた口調で「懐くな」とか言ってくるのに顔がほんのり赤くなってるのが可愛い。構いすぎると、すぐに手を上げるのが可愛い。 二人きりの時だと、恥ずかしがりながらも、大人しくしているのが嬉しい。 素直じゃなくて、プライドの高い彼女は、甘えてこないし、気持ちを口に出して言ってはくれない。 だから、その分、俺が甘えて、好きだと言う。彼女から行動してくれなくても、その反応を見れば、彼女がどれだけ自分を好きでいるか分かる。 しかも、最近その可愛さがより強力になった。じっと自分に熱い視線を送ってくるようになったのだ。身長差から自然と上目使いになる大きな瞳に、いつも我慢できなくて、「どうしたの?」って言いながら、小さな唇にキスを落とした。 すると、ちょっと悔しそうな表情をして、いつもより積極的に応えてくれるのだ。 ****** ある日の放課後、係の仕事を終えた千晶が緑館に顔を出すと、昇がソファで寝ていた。これはチャンスかもしれない。 寝ている昇に千晶がキスをしようとする。意識は無いから、彼は気づかないかもしれない。でも、それはそれで良い。自分がしたいのだ。 スッと顔を近づけると、昇が唸った。とっさに離れようした千晶を昇は引き止め、抱きしめる。 「キスしてくれたら離してあげる。」 耳元で囁かれて、動けなくなった。 一向に動かない千晶。やっぱり、自分からキスはしてくれないか…、と諦めた昇が千晶を離そうとするが、今度は千晶がしがみついてくる。 「キスしなかったら、離さないんじゃないのかよ。」 切なそうに見つめてくる千晶に、昇は自分の失言を知った。 「キスしても離さないから、キスして!」 慌てて上ずった声でそう言うと、千晶がにっこりと笑って、キスをくれた。 角度を変えなから、唇を合わされて、同時に頬を撫でられて、髪を梳かれる。合わせるだけのキスだけど、いつもなら俺が彼女にやっていることだけど、全部が優しくて、すごく幸せな気持ちになった。 最後にチュッと軽い音を立てて、千晶は昇の肩に顔を埋めた。そのぎゅうっと抱きついてくる体が熱い。 それから、「好きだ。」なんてくぐもった声で言われて、 どうしよう。幸せすぎて、死にそうです。
泳げ千晶ちゃん!
鳥の鳴き声と、虫の声に意識が浮上した。目覚ましはまだ鳴っていない。ふわふわと漂う思考の中で、天井を見つめる。骨組みの見える木の天井。合宿七日目の朝、この天井にももう慣れた。 「う、…ん。」 すぐ横で声がして、ついで腕が腹に乗っかってきた。 「明、重い…」 その腕をどかそうとして気が付く。この腕、誰だ。 「んー、兄様ぁ…。」 あれ、どうしてこんなに近くで声がするんだ?とゆうかこいつは… くるっと横を向いてありえない事態に目を剥いた。目を覚ました相手も目を見開いている。 「うわぁぁぁぁあああ」 「きゃぁぁぁぁあああ」 千晶と昇が同時に叫ぶ。 「うるさいわよ!」 隣のベッドから枕が飛んできた。 山百合高校の一年の夏休みには、親睦・学習合宿がある。一日10時間缶詰で勉強させられる鬼のような企画だ。 場所は白鳥家所有のペンションで、体育館ほどある大きなものが一つと、十畳の小さなものがいくつも並んでいる。 昼間は主に大きなペンションに缶詰で勉強。夜は小さなペンションで就寝。二人部屋だ。通常、同じクラスの生徒同士で組むのだが、女のくせに男の振りをしている愛場千晶は姉の明と同室だ。 「朝の悲鳴何?」 屋外にある洗面台で歯を磨いていると、隣から出てきた藤本光が話しかけてきた。クラスの違う光は隣ではなかったはずだが、照を引きずっているところから、低血圧の兄を起こしに来たのだろう。ちなみにペンションの壁に備え付けの洗面台はペンションと同じナチュラルブラウンの木でできている。こだわりを感じた。 「…寝ぼけた昇が間違って千晶の部屋に行っちゃったんだよ…」 歯磨き中ですぐに返事ができない千晶に変わって、目が覚めなくてゆるゆるな照が答えた。 彼の言うとおり、昨夜、トイレに行った昇は、間違えて隣の千晶たちの部屋に入り、千晶の布団に入ってしまったらしい。 「知ってたなら、止めてよー。」 「いやですよ。面倒くさい。」 千晶の隣で昇が言うと、照は座った目を向けた。これは目が覚めていないからだと思いたい。 ****** ペンションを出て、林を抜けると、すぐに海が見えた。木陰に慣れた目に、白い砂浜とキラキラと光る海が眩しく映る。 勉強合宿最終日には海での自由時間が設けられている。きつい合宿に耐えたご褒美だ。 点呼をとったら自由行動。着替えに行くまえにどこかで男装をとかないといけないな、なんて思っていると、ここに居ないはずの人影が手を振っていた。 「兄様!」 「陽!」 「陽君!」 そこにいたのは白鳥昇と藤本陽と、ひとり名前を呼ばれず、苦笑いをする影木幻十郎だった。 「兄様、どうしてここに?」 「ここはうちのプライベートビーチだぞ。俺がいて何がおかしい。」 「確かに。」 確かにじゃねえよ。 結局、三人も一緒に遊ぶことになった。 「光、すごい良い体してる!」 「えっへん!僕ってば超着やせするタイプなんだ。」 男組の着替えは早い。藤本三兄弟はその肉体美を惜しげもなく太陽の下に晒していた。 本当、三人とも細いのに筋肉ついてて羨ましいな…。影木さんは影木さんで小さくて細いけど、顔が可愛いから釣り合い撮れてるし。僕なんてただひょろいだけなのに。あ、でも兄様は僕の仲間だ。知ってたけど。 千晶たちが来るまで浅瀬で時間をつぶすことにする。水面が複雑に光を反射して、その向こうで歪んだ足がゆらゆら揺れた。 「ぬるいー。でもきもちいー。」 パシャッと軽く水を蹴れば、しぶきが白く弾けた。 「おーい。待たせたな。」 大好きな声に振りむくと、水着姿の千晶が居た。 ボックスタイプのスイムショーツのへそ出しツーピースはスポーティーだけど、可愛らしい。赤地に白の小さな雫が散りばめられて、肩ひものところに緑のリボンが付いている。その上、今日は前髪を苺の飾りのついたゴムでポンパにしていて、頭上でふよふよ揺れていた。 「可愛い!すごくかわいい!苺の妖精さんみたい!!」 「――っ!可愛くない!」 「可愛いでしょ。私と千晶で一緒に選んだの。」 駈け寄った昇に、真っ赤な顔で否定する千晶。その隣で、明はすごく楽しそうだ。彼女の水着はホルターネックのモノクロ幾何学柄ビキニ。シンプルながら、彼女のグラマラスなラインを綺麗に強調している。 「可愛くない!」 頑固に否定する千晶は文句なしに可愛い。千晶と明が妥協点を捜すうちにこの水着になったのだろう。千晶はもっとさっぱりした水着が良かったのだろうし、明はもっとひらひらふわふわした水着が良かったのだろうが、昇的には胸のぺたんこ具合が分かる上にロリロリしいこの水着はグッジョブだ。 「千晶可愛いよ、千晶――ヒデブッ」 抱きつこうとしたら殴られた。なんでだ。 「千晶って呼ぶな。ばれるだろう!」 「じゃあなんて呼べばいいのさっ」 殴られた腹をさすりながら昇が言う。身長が違いすぎて千晶が普通に殴ると腹に当たるのだ。 「千で良いんじゃない?千ちゃん!」 「ああ、じゃあそれで良いや。」 光が言うと千晶が簡単に了承した。 「千晶というのかい?贅沢な名だねぇ。今からおまえの名前は千だ。いいかい、千だよ。」 「うるせえよ!」 もしかしなくても光はこのセリフが言いたくて千にしようと言ったんだと思う。じゃれ合う二人は相変わらず仲が良い。 「千ちゃん、俺も構ってよ。」 それに突撃できるくらいには俺も図太くなったんだけど。腕の中で千晶が暴れた。 浮き輪は三つ。苺柄の浮き輪は金槌の千晶専用で、他二つは皆で交代制。今は幻十郎と照の番で、三人は浮き輪の上に寝てぷかぷか浮いている。 そろそろ交代の時間かな、なんて思っていたら、明が千晶の浮き輪をひっくり返した。 「うわっ!!」 投げ出された千晶は狙い澄ましたように昇の腕に収まった。あわあわと離れようとした千晶は、水中であることを思い出してすぐに大人しくなった。それどころか昇の背に腕を回してきた。 細くて小さい、柔らかい体が抱きついてきて。ペタンコの胸を薄い布越しに押し付けられて、なんかもう、鼻血でそう。 「何すんだよ!明!浮き輪よこせ!というか昇が浮き輪まで連れていけ!」 うーん。放さないと俺の理性飛びそうだし、でも放したくないし。理性飛んだら誰かが止めてくれるよね!と言い訳して、昇は千晶を放さないどころかぎゅうっと抱きしめて、ほっぺたをすりすりしたら、彼女は抱きついたまま、嫌だ、止めろ、と言ってきた。 「えー。でも放したくない。」 「……放せ。」 真っ赤な顔で睨まれたけど怖くない。怖くないけどこれ以上怒らせると大変だから、しぶしぶ浮き輪までつれていった。 そんな一部始終を見ていた美千代と陽が仲良く 「デジャブ…」とつぶやいた。 「ここまで金槌だと、命に係わると思うのよね。というわけで、泳ぐ練習をするわよ。」 明の言うことは絶対である。と言うか逆らっても押し切られるから意味が無い。千晶は早々に反抗することを諦めた。 「なあ、お前ら全員で教えるのかよ。」 「あら、そうね。こんなにいても千晶が恥ずかしいだけよね。」 その言い方もなんか腹立つ。言わないけど。 「じゃあ、昇に一任するわ。」 「え、俺!?」 いきなりの指名に驚く昇。 「他の人に千晶を触られていいの?」 「明様なら良いですけど?」 「嫌よ。面倒くさい。」 面倒臭いならやるなよ、と思うが、言っても俺の為とか理由を付けて練習させるのだろう。 「じゃあ、平泳ぎ教えといてちょうだい。」 「何で平泳ぎ?」 昇が聞くと明はやけに綺麗な顔で笑った。 「一番実用的でしょ。」 でもその顔がすごく怖かった。 この構図。やばい。 昇は目の前の光景に眩暈を覚えた。 「蛙泳って言うけど、本当に蛙みたいな動きするよな。」 昇は、両手を岩に着けて、呑気にそんなことを言っている千晶の足首を持って、平泳ぎの足の動きのレクチャーをしていた。 広げた股に水着が食い込む。ボックス型のそれだけど。柔らかく動く肉の形は隠してくれない。足首も細いし、柔らかいし、千晶可愛いし千晶可愛いし千晶可愛い千晶可愛い千晶可愛い千晶可愛い。 「昇?」 やけに静かな彼を不審に思って千晶が振り向くと、鼻血をしたらせた昇がそこにいた。 「暑いからのぼせちゃったのかしらねぇ?」 綺麗に笑ってそう言う明は絶対に確信犯である。 「で、千晶は泳げるようになったの?」 そして綺麗に笑ってそう聞いてくる照もまた確信犯に違いない。 「人間は浮くようにできない!」 イライラとそう返したら、総ツッコミを入れられたけど。 合宿帰りのバスでカラオケ大会が始まった。マイクが回ってきた千晶が歌う。 「わー、千晶上手!」 「俺は何でも完璧なんだよ。」 「だからこそ金槌が目立つんですよね。」 光が誉めれば、千晶の照れ隠しが発動して照がすかさずつっかかる。 「お前の欠点はその性格だよな。」 「何のことだか。」 「にゃろう。」 「まあまあ。」 昇はじゃれ合う二人をなだめようとするが、睨みあいは続いたままだ。 「もー、二人とも喧嘩しないの。ここはピカリンがいっちょ和ませますか。」 そう言ってマイクをもらった光は、絶妙に外した音程で学園天国を歌い上げた。
うざい子現る!
夏休み中のある日の出来ごと。昇とデート中、ドーナツ屋前の道で光を見つけた。 「君、可愛いね!すごくかわいい!!」 「ああ、そうありがとう。」 「ねぇ僕と契約して友達になってよ!」 「間に合ってます。」 「今時間ある?」 「無い。」 「俺、昨日こっちに引っ越してきたばっかりでさ、でも良いところだね。だってこんなにかわいい子が居るんだもん!そうだ、ここらへん案内してよ!」 「…。」 変なのに絡まれてた。 フード付きパーカーの小柄な男が、お構いなしに歩く光にスキップしそうなテンションで話しかけ続けている。 「おい、光。」 「あ、千晶!昇!」 千晶が声をかけると気付いた光がさも待ち合わせてたという態度で飛びついてきた。 「あ!友達?今からみんなで遊ぶの?僕も混ぜてよ、良いじゃん、ねーえ!」 それでもめげずに仲間に入ろうとするパーカー男子。何だこいつ…うざい。 「あ、待ってよ!」 無視して歩き出す三人にそいつはやっぱりついてきた。 当初の目的地はデパート内のゲームセンターだったのだが、新しくできた雑貨屋を見に来たという光に付き合うことにした。毎回ゲーセンデートもなんだしな。 光に連れられてやって来た店には、カラフルで可愛い小物がたくさんあった。キャラクターものは少なく、レースやリボンで飾った手作り系の小物が多い。明が好きそうな店だ。好きそうといっても、明自身のためではなく、千晶に身に着けさせるための物を選ぶのに好きそうだという意味だ。だから絶対教えない。 男三人で入るには少しきつい店だ。俺は女だけど。でも、きゃっきゃとはしゃいでいる光が美少女にしか見えないから問題は無いだろう。 それより…。 三人の後ろでうさぎのポーチを手に取るパーカー男子をちらっと見た。童顔だからこの場所でも浮いていない。 「なあ、あいつ、まだついて来てんぞ。」 「無視しよう。無視。」 千晶がそう言うも、光は一瞥もせずに、中心が布でできている指輪を中指に嵌めて眺めていた。 なんで女物の指輪を自然に嵌められるんだよ。 「でも、変な子じゃなさそうじゃない?引っ越してきたばっかりだって言うから友達が欲しいとか。」 「そういやさっきそんなこと言ってたな。」 昇の方を見れば、花のモチーフの指輪とリボンのモチーフの指輪を両手に持って見比べている。 まさかお前は嵌めないよな。お前には無理だよ。 「そーだっけ?」 真顔ですっとぼける光。 「…光おまえなんかおかしくないか?いつもそんなキャラじゃないだろう。」 「そうだよね。いつもの光なら喜んで一緒に遊びそうなのに。」 二人にそう言われてやっと光は視線だけちらっと後にやった。 「えー、だってあの子――」 途端に上がる黄色い声(パーカー男子) 「――うざい。」 「禿同。」 「やめたげてよぉっ」 昇、お前は優しいな。 「でもなぁ、このまま引き連れてるのもあれだし、二人のデートをこれ以上邪魔するのもな…。」 「デート云々はともかく、あいつお前についてきてるんだろ?俺らと別れて撒いたらよくないか。」 ここで光はハッと驚きの表情。 「その手があったか!さらばだ!!」 「行動早すぎ。」 風のように去っていく光に千晶は笑いが止まらなくなった。 ****** 「ビッグニュース、ビッグニュース!」 朝の教室に、レースカチューシャの、ゆるふわロングの少女が飛び込んできた。 「どうしたバカ林!」 一番に反応したのは、横髪が少し外に跳ねてた、全体的にはストレートの髪のポニーテールの少女。 「若林であります!」 「それでどうしたバカ林!」 敬礼して訂正するカチューシャに、それでもポニテは呼び方を変えない。 「転入生が来るらしいであります!」 「何!?それはかわい子ちゃんか!?」 「分からないであります!」 「女か男か!」 「分からないであります!」 「それだからお前はバカ林だというんだ!」 「若林であります!」 九月二日。始業式を前日に終えた二学期二日目。若林春香&山瀬千春の春春コンビが漫才を繰り広げるのは日常風景だ。藤本光もそれを見てくすくす笑っていた。 そう、その転校生が来るまでは…… 「お早ございます。もう知っている人もいるかもしれませんが、今日は転入生を紹介します。入ってらっしゃい。」 担任がそう言うと、扉を勢いよく開けて小柄な塊が飛び込んできた。 「呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン!三反田巧太郎です!」 そこに居たのはまさかの先日のうざい子で、光を見つけて駆け寄ってくる。 「あぁ!そこにいるのはこの前の!これって運命?ねぇ運命!?」 「僕、そういうの偏見ないけど、自分はノーマルなんだ。」 零れんばかりの笑顔の巧太郎に光も笑顔で返す。 えぇ!?男だったの!?と、驚愕している巧太郎に、 ――ああ、くしゃみするから消えてくれないかな…。 光は心の中で悪態をついた。 「もうね、ほんとにうざいの!席は遠いんだけどね、休み時間ごとに来るし、事あるごとに巧ちゃん呼びを強要してくるの!」 「ご愁傷様です。」 巧太郎の攻撃から逃れるため、そして愚痴を言うために千晶のクラスを訪れた光。しかし、話し相手の千晶は笑いを隠そうともしていない。 「もー、真面目に聞いてよ!」 しゃがみ込んで手のひらで机をバンバン叩いて講義する光の後ろで上がった声。 「あ!こんなところに居た!」 噂をすれば何とやら。 「うわ、うざい子が来た。」 盛大に顔を顰める光にしかし、まったく堪えた様子の無い巧太郎は、 「うざい子じゃないってば、巧ちゃんだってば!」 見事千晶の腹筋を崩壊に導いた。 「もう…っ、巧ちゃんって…く、くふっ…呼んで、やれよ…っぶは…っ」 「他人事だと思ってぇ!」 机に突っ伏し、震える千晶に光はほんの少しの殺意を覚えた。 ****** 「あ、光!肩のところ破けてるよ!」 朝いちばん、例のごとくハイテンションな巧太郎に指摘されて、確信すると、制服の肩の部分が盛大に解れていた。 そういえば昨日、洗濯機変な音してたな。引っかかったのかな。 「俺が直してやんよ!」 そう言ってポーチから携帯ソーイングセットを取り出す巧太郎。 「男子ってそういうの持ち歩くものかな。」 「チッ、チッ、チッ、今は女子力の高い男子がモテる時代ですよ。」 指を振りながら舌を鳴らしてドヤ顔の巧太郎。 「うざい。」 「ふんふーん♪折角だからアップリケとか付けちゃう?動物のとか、乗り物のとか、植物のとかありまっせ。」 鼻歌を歌いながら、かわいらしいアップリケを光の机に並べていく巧太郎。 彼が転入してきて数週間。このうざさにも慣れて……来ない。 それなのに、巧太郎の方は光の毒舌に慣れてしまったのか、平気な顔でアップリケを並べている。 そんな中、光の目を奪うものがあった。それは、薄い水色のうさぎさん。 「これが良い。」 指さした光に巧太郎はキョトン顔だ。 「え、本当に付けるの?」 「付けるけど。」 「うさぎさん付けるの?」 「付けるけど。」 すると巧太郎が変な顔をした。歯をいぃっと食いしばって鼻の付け根に皺がよっている。それでもって頬がほんのりと赤い。 「か、か、かーわーいーいーっ!!」 「うーざーいーっ!」 次の瞬間、飛び掛かってきたうざい子に、光はチョップをかました。 「なんだかんだ楽しそうじゃないか。この前も調理実習のカップケーキ貰って、おいしいって言って食べてたろ、おまえ。」 肩に可愛らしいうさぎを張り付けてやって来た光に話を聞いて、千晶は言った。 「まあ、便利ではあるよね。」 「美術も手伝ってもらってたろ。」 「まあ、便利ではあるよね。」 「ほんと、三反田にだけ素直じゃないよな。」 ひねくれた答えを返す光に千晶はにやにや笑いで返した。 放課後、昇が二組の前を通りかかると、光が巧太郎に勉強を教えていた。 手先が器用なうざい子は、勉強は苦手らしい。 なんだ、やっぱり光もまんざらでもないんじゃない。 昇はくすくす笑ってその場を後にした。 そんなある日、巧太郎体育館裏に呼び出しをくらっていた。 「お前が三反田巧太郎か。」 「え、あの…そうですけど、これは……いったい?」 上級生の男子に連れられてやって来た敷地の隅に建った、何やら古びた建物の影では、十数名の男子生徒が待ち構えていたのだ。 「そうかお前が我らが光さんに迷惑をかけ続けている三反田なんだな。」 中央に立つのがリーダーなのか、一際体格の良い男がそう言って睨みつけてきた。 「迷惑だなんてそんな…、あんなのただじゃれているだけで――」 「黙れ!」 「ひっ」 言い訳の途中で恫喝されて、巧太郎はその小柄な体をいっそう縮こませた。 「我らは藤本光親衛隊(非公認)だ。親衛隊(非公認)として、貴様の行動を黙って見ているわけにはいかない!」 男が指を鳴らすと、他の男たちが巧太郎を囲むように移動した。 「今ならばまだ許そう。今後光さんに近づかないとこの場で誓え!」 身長160センチ弱の巧太郎を取り囲む屈強な男たち。最早巧太郎は涙目だ。 ここで反抗したら確実にボコられる。そして絶対に俺に勝ち目はない。 巧太郎は震える唇をこじ開けて、歯をカタカタ慣らしつつ、か細い声を絞り出した。 「………いや、です…」 追い詰められて、追い詰められて、思考が焦って正直な答えをしてしまった。 あ…、あ…、と今更ながらに口を塞いで首を振る巧太郎に、リーダーの男は大きく腕を振りかぶる。 その瞬間、二人の間に空から降ってきた影。 「……何しているの?」 尻もちをついた巧太郎が見たのは、男の拳を手のひらで受けた光だった。 「光、どうして。」 困惑する巧太郎を振り向かず、光は男を睨み続ける。 「本気でうざかったら自力でどうにかできる。大きなお世話だ。君たちの方がよっぽどうざいよ。」 光に拳を振り払われて、男はやっと我に返った。 「で、でも!俺たちは光さんのことを思って!」 「じゃあ、勘違いしちゃったんだね。」 縋る男に光が向けるのは冷たい視線。 「――こいつはもう僕の守るべきエリアに入ってる。手出しは許さない。」 「…そんな……っ」 後半に向かって怒りの熱を帯びる彼の言葉に、男は顔に絶望を浮かべた。 それでも光の視線は揺るがない。 「分かった?」 確認をとる光に、男は項垂れて、 「………分かり、ました……」 本当に渋々、低い声で応えた。 「うん。ものわかりの良い子は嫌いじゃないよ。」 すると反って来たのはそんな優しい言葉で、それを聞いて男はっと顔を上げた。しかし、その先に会ったのは相変わらずの鋭い視線。 「でも、――次は無いから。」 「――っ、はい!」 「解散!」 光の言葉に従って、男どもは散り散りに走り去った。 「――光?」 男どもの影も形もなくなって、残ったのは、所々緑ペンキの残ったはげた壁と、杉の林に囲まれたこの空間と光と自分。 「なに?」 「――俺、こんなときどんな顔していいか分からない。」 やっとこっちを見た光は声を出して笑った。 「すでに相当情けない顔だけど?」 「ひでぇっ!」 酷いけど、光は俺を守ってくれた。 「…おまえさぁ、俺のこと大好きジャン。」 そう言えば光はそっぽを向いて、 「まぁまぁだよ。」 「うぇ~、うっそだぁ。」 「うざい。」 そう言いながらも手を差し出してくれた。 「…帰るよ、巧ちゃん。」 「!」 その手を取ろうとして固まる。 「もう一回!もう一回言って!」 「うざい。巧太郎。」 腕を掴まれて無理やり立たされた。 「違う!巧ちゃん!」 「あーはいはい。巧ちゃん。」 「~っ!光、大好きっ!」 「うざい。」 抱きつけば引きはがされて、いつも通りのセリフを言われる。でも、 「もっと言って!」 「…キモイ。」 「ありがとう!」 全部嬉しい! 「……」 ゲテモノでも見るみたいな目で見られても、巧太郎の頬は緩みっぱなしだ。 光かっこいい、大好き!もう何を言われてもご褒美です!! ****** 「あ――もう、巧ちゃんがうざい。」 「はいはい、大変だな。ぷーくすくす。」 「なに、笑ってるの?」 「いやぁ、ずいぶん仲が良くなったもんだと思って。」 「…まあまあだよ。」 「はいはい。ぷーくすくす。」 「千晶~?」
緑館で午後ティタイム
その日は三年生の模試の関係で一・二年は午前放課。これはそんなまったりとした午後の一場面である。 猛暑を越えて、秋の色の濃くなってきた今日この頃。風も軽く、涼やかなものに代わった。高い空から降り注ぐ光に眉を顰めることも無くなり、強い日差しを遮るためのレースのカーテンも、今は開け放たれている。 頬を撫でる自然の風に、穏やかな時間の流れを感じながら、藤本光は膝の上に横たわる小さな頭を撫でた。 「光って、実は巧ちゃん大好きだよね。」 テーブルを隔てて正面に座る白鳥昇がそう言うと、膝の上の彼が小さく身じろいだ。 光は、そんな彼の目元を手で覆い、なだめる。 「のぼるー。寝てる子の名前を不用意に呼んだらダメなんだよー。」 「なんで?」 「起きるでしょぉ?折角、うるさくないのに。」 再び規則正しい寝息を立て始めた巧太郎に光は目を細める。 「そうだな。そいつが寝てるだけでずいぶん静かになるもんな。」 昇の膝の上でぬいぐるみ宜しく抱きかかえられた千晶が言った。もちろん千晶から膝に乗った訳ではない。初めは二人掛けソファに隣同士で座っていたのだが、昇が「千晶ちゃんむぎゅー」などと言って隣の千晶を抱きしめだし、いつの間にかこの体勢になっていた。しかも、今は二人の隣に影木幻十郎が座っているため今更元の位置には戻れない。戻る必要もないが。 「いつも騒がしいからね。でも、突然電池が切れたみたいに大人しくなるよね。」 「光が電池?」 幻十郎が言えば、ポットの様子を見つつ藤本陽が続けた。 「え、じゃあ誰か変わってよ。これじゃ元気になっちゃうじゃない。」 「だが断る。」 嫌そうな顔の光に応える声は七重奏。 それからまた誰も口を開かなくなり、カーテンレールの端にかけた、エッフェル塔の白い風鈴がりんと鳴った。 普段部屋の中央に置いてあるのは、木の机と丸太の椅子三つだけ。今は、壁際のソファセットを移動させたので、それに加えてガラスのローテーブルと皮の二人掛けソファが二つ。ソファには、光に巧太郎、千晶と昇と幻十郎が陣取り、藤本照は丸太の椅子の一つに、愛場明は自分が気に入って持ち込んだ、花柄のクッションの丸椅子に腰かけている。残り二つの丸太の椅子と、巧太郎が持ち込んだカエルの椅子は空席。少し離れた窓際で、白鳥美千代がロッキングチェアを揺らしていた。 「お湯わいたけど、皆何か飲む?」 「ぺこー」 陽の問いに光が答えれば、他メンバーもそれに従った。 手伝うと、美千代が席を立って、すぐに紅茶とオレンジの香りが室内に漂う。 「ぅんー」 巧太郎が声を上げて、目元を擦った。 「うー、おちゃぁ?」 むくりと起き上がった巧太郎は、寝ぼけ眼で何かを求めて手を彷徨わせる。 「何?」 「おれのかばんー」 「はい。」 まだ目が覚めないのか、ひらがなの発音で話す彼に光が鞄を差し出した。 それを受け取り、ごそごそと鞄を探って、巧太郎はクローバー柄の半透明の袋を取り出した。 「くっきー」 「また焼いたの?」 「また焼いたの。」 光に言われて、輝く笑顔で差し出すそれからは、甘く香ばしい香りが。 「巧太郎のクッキーだやった!」 「千晶は結構食い意地はってますよね。」 嬉々として立ち上がった千晶が棚からバスケットとレース柄の紙ナプキンを取り出して、南国の色鮮やかな花のカップと持ち手が立体のオレンジになっているティースプーンのティセットに陽と美千代の淹れたオレンジペコを注いだ。 「クッキー投下―。ざざざざざー」 「結構量あるね。」 言いつつ幻十郎が口に運び、 「小麦粉特売だったから。」 「おやつのことを考えると巧太郎が仲間になって良かったかも。」 光が言えば弘太郎はぷくっと頬を膨らませる。 「おやつだけじゃなくてぇ。」 「あはは。」 午後ティタイムはまったりのんびり過ぎていく。
緑館の一角がうさぎで埋まってる
緑館二階奥の秘密の部屋は、白鳥美千代の厳選した家具雑貨でコーディネートされている。壁紙までこだわったそこは、シックで落ち着いていて、それでいてどこか遊び心のある正に美千代の性格を具現化したような空間だった。 しかし、彼が二年に上がり、この部屋の利用者が増えると、部屋の様子も変わった。 愛場明の持ってきた花柄のクッションの丸椅子は、キャスキッドストンのパチモンらしく、ビビットで華やか。三反田巧太郎の持ってきたカエルの椅子は、どうぶつの森から持ってきたかのようなファンシーさ。そして、もう一つ。いや、一つとは言わないだろう。この部屋のいたるところで可愛さアピールをしてくる存在。愛場千晶がクレーンゲームでとってきた大量の兎のヌイグルミがこの空間の雰囲気をキャッチーなものにしていた。 あまりに、部屋の感じが変わったものだから、昨年からこの部屋を利用する影木幻十郎は、美千代に尋ねた。 「ねぇ、白鳥。白鳥は、この部屋のコーディネートに思い入れとかは無いの?大丈夫?」 「いや、別に?好きなもの揃えたらああなっただけだし。俺は俺の選んだものがあれば他に何が増えようと構わないし、楽しければ良いけど。」 一際大きな兎をクッション代わりに背中とソファの背の間に入れて寛ぐ彼は本当にどうでも良いようだ。金持ちだから、安物を使うのは嫌だとか、庶民とは話が合わないだとか、そういう所が無い、彼のこういう性格は好感が持てる。 そう思ったら、彼の隣で、藤本陽が嬉しそうに微笑んだ。 「美千代。」 「ん?」 「好き。」 「…唐突だな。」 「言いたくなった。」 「そうか。」 淡く頬を染める美千代に、僕も言いたかった(笑)とか思いつつ、幻十郎はメモ帳を取り出し、今の出来事をメモするのだった。 ****** 白鳥昇は千晶が好きだ。彼女と一緒に居られればそこが学校でも天国になるし、彼女と一緒に食べればファストフードはご馳走になるし、彼女とのデートならばゲームセンターでも最高のテーマパークになる。 デートでゲーセン?と思うだろうか。でも、俺じゃなくても千晶とゲーセンに来るのは楽しいと思う。 千晶は格闘ゲームが強いから、見ていて楽しい。でも、俺が飽きるだろうと思うのか、長くはやらない。それより音ゲーをやる方が多い。それで、こっちは俺も一緒にやる。でも、こっちも神がかってうまいから、人が集まっちゃって、そうすると止める。 千晶と撮るプリクラも楽しい。でもこれは千晶が率先して入ったんじゃない。俺がどうしても撮りたいと言ったから、わざわざヘアバンドをとって、女性かカップルしか入れないスペースに連れて行ってくれたのだ。それで、ダブルピースとか、宇宙人のポーズとか、鬼瓦とか、いろんなポーズを教えてくれて、落書きの仕方も教えてくれた。 「良く来るの?」 と問えば、 「明に無理やり連れ込まれるんだ。」 と言う。 「仲良しだよね。」 ちょっとさみしいと思ってしまうのはどうしてか。実の姉相手に嫉妬してどうする。俺って実はめんどくさい性格だったのかな、と思っていたら、 「今日連れ込んだのはお前だな。」 て、 「…千晶ちゃん。」 「…なんだよ。」 「なんか今すごいきゅんときた。」 「あ、そう。」 千晶はクレーンゲームも得意だ。今は最近人気のちょっと間抜けな顔の、のぐでっとしたカラフルなドットのうさぎを狙っている。ちょっと某ギャグ漫画のポクテに似ていると思う。 「千晶はどうしてうさぎをとるの?」 「そこにうさぎがあるからさ。」 集中しているからか、答えが適当だ。 千晶はクレーンゲームをするときいつもうさぎ関連の物を狙う。それはぬいぐるみだったり、マグカップだったり、目覚まし時計だったりする。しかし、それは別に千晶が無類のうさぎ好きだからというわけではない。現にとったものは、光にあげるか、緑館におくかで、家では使っていないのだ。 「取れた。」 「おめでとう。」 昇は、得意げに笑う千晶に拍手した。 「で、何だって?」 「ん?」 「なんか聞かなかったか、これやってる時。」 「ああ。なんでうさぎをとるのかなって。」 「光が好きだから。」 昇の笑顔が固まる。一瞬時間が止まったかと思った。 「光がうさぎ好きだから。俺、クレーンゲームは好きだけど、商品に興味は無いし、誰か貰ってくれる物の方が良いだろう。」 「あ、そっか…」 心臓がバクバクする。ほっとして良いのかな?でも、千晶はいつも光のためにうさぎをとってたっていうのは変わらない?デートしてるのは俺なのに、いつも光のこと考えてるの? 「昇」 「あ、え、なに?」 嫌だな。千晶と光は幼馴染で、普通に仲が良いだけなのに、こんな風に考えるなんて。 「お前が好きなのはなんだ?」 「千晶。」 昇がそう答えると、千晶は一瞬キョトンとして、笑い出した。 あ、もしかしてクレーンゲームの話だった? 「昇、俺さ、新しい技覚えたんだ。」 言い直そうと思ったら遮られた。 「え、なに?」 「おう、見せてやるからこっち来いよ。」 手を引かれて、店の外に出る。 「クレーンゲームじゃないの?」 そのまま路地に連れ込まれた。 「よし、動くなよ。」 千晶はそう言って昇の上腕を軽く持つとジャンプした。同時に、唇にふわっとした感触。 ぽかんとする昇に、着地した千晶は親指を立てて一言。 「ジャンピングキッスだぜ!」 良く分からないけどカッコいいと思った。 ****** 扉を開けると小っちゃい子が床に転がっていた。 緑館の床にはインディアンチックな絨毯が敷かれている。だから、寝っ転がっても悪くは無い。しかし、そばにはソファもあるのになぜ? 藤本光はとりあえず小っちゃい子、つまりは巧太郎の隣に寝転がってみる。いつもより天井が高い。腕も伸ばせる。 「ちょっと気持ちいいかも…」 扉を開けると光と巧太郎が床に転がっていた。二人は並んで仲良く、すぴぃすぴぃ、と寝息を立てている。 巧太郎はともかく光は可愛い。でも、絨毯を敷いてあるとはいえ下は硬い。 寝ずらそうだな。 藤本照は二人の頭と腰の下うさぎのぬいぐるみを敷いた。ついでにうさぎを抱かせて、周りもうさぎで飾った。 扉を開けると光と巧太郎がうさぎに埋もれていた。その隣でカエルの椅子に座った照が満足そうに頷いている。 「何これ。」 「千晶も混ざりますか?」 「はあ。」 「まあまあまあまあ。」 無理やり隣に寝転がされた。 照からメールが来た。開くとそこには、うさぎに埋もれた千晶の写真が。昇は走り出した。 扉を開けるとうさぎに埋もれた三人を、陽が連写していた。 「可愛いっ、天使っ!」 表情が少し危ない。しかし、それには構っていられない。昇も、自分の天使を連写し始めた。 撮影会のすぐそばで、照はにこにこと笑っている。陽に連れられてきた美千代はうさぎの一つを抱えて、ロッキングチェアに揺られていた。そのうちに陽はそちらも撮りだすのだろう。幻十郎は、巧太郎が寝転がったあたりから、その様子を観察していた。
腐海森の会
薄暗い教室で、円卓状に並べられた机。その一つの前の椅子に腰かけて、小柄な青年は一同を見渡した。 「やあ、みんな揃ったようだね。」 「はい!この日のために生きてます!」 「萌え補給プリーズ!」 「誰か私に餌をくれ!」 「うんうん。腐女子、腐男子の皆さん今日も元気だね。じゃあ、早速、誰かネタのある人。」 「はいはーい!腐海森の会会員番号十三番!今朝の電車内の藤本先輩と白鳥先輩!」 「安定のにゃんにゃんコンビか。みんな、メモの用意は?」 彼に言われずとも、皆すでにメモ帳やら、ノートやらを開いている。強者になると原稿用紙を広げているものまでいた。 「万全です!」 「では、話します。 光君が入学してから、藤本先輩が朝、去年より一本早い電車に乗っているのは知っていますよね。で、私はそのおかげで、陽さんたちと同じ電車に乗れていたんです。 それで、今朝はラッキーなことに、藤本・愛場・白鳥兄弟が扉の前で固まっているすぐ近くの端の席に座っていたんです。手すりを隔てた私のすぐ横には、白鳥先輩の背中がありました。 で、私も藤本先輩ほどではないですが、朝に弱くて、掴んでいた手すりから手がすっぽ抜けて、白鳥先輩の背中を私の指がすぅってなぞったんです。一旦切ります。」 「何故切る!?」 「これが焦らしプレイか、しかし私はMじゃない!だけど悔しいっ、かんじちゃうっ!」 「すぅってなぞった時の反応妄想タイム!」 「………………しゅーりょーっ!会員番号十三番、続き!」 「皆さん、良い感じにペンが進んだようですね。では正解もとい、続きです。 白鳥先輩は、背を弓なりに逸らして、『ひゃっ』と声を上げて、向かいで光君に支えられてうとうとしていた藤本先輩にしがみ付きました。 『え、なに?』覚醒前の藤本先輩は、状況を把握できないまま、きょとんとしています。すごく、可愛らしいです。しかし、その腕はギュッと白鳥先輩の腰を抱いています。すごく、彼氏です。 この話は私が『寝ぼけましたすみません』って謝って終わりです。」 「ブラボー。良質の萌えをありがとう。」 「最高だったわ!」 「やっぱり、ほのぼのエピソードは落ち着くわね。」 「毎朝、光君が双子を両脇に抱えて登校するってだけでも萌えなのにこれは、良い仕事したね!」 「あの!電車ネタでもう一エピソードあるんですけど!」 「どうぞ。」 「はい。会員番号二番!昨日の帰りの電車内の藤本君と白鳥君! 昨日は幸運なことに、白鳥君、藤本君、私、の並びで座れたんです。藤本君は、夕方なのに珍しくうとうとしていて、白鳥君は文庫本を読んでいました。 うとうとしてる藤本君可愛いな、なんて思ってたら、なんと、その頭が私の肩に乗っかって来たんです!あの超絶美形が!ゼロ距離です!私、顔面蒼白!」 「自慢ですかwww」 「いえいえ、ちゃんと続きがあります。私が固まっていると、白鳥君がすぐに気が付いて、『悪いな』って言いって、もりもり山のくだもの飴いちご味を私にくれて、藤本君を引き寄せたんです。こう、腕を引いて自分に寄りかからせて、反動で藤本君の頭が白鳥君の肩に乗って、で、白鳥君は藤本君の背中に腕回して、頭撫でてました。降りるまでずっと、文庫本放っておいて、髪の感触楽しんでました!庶民的お菓子を彼が持っていたとに悶えればいいのか、飴をくれた優しさに悶えればいいのか、二人の仲の良さに悶えればいいのか!もう、僕は私は俺は…」 「さらさらは正義だ!」 「頭撫でながら、微笑んでるんですね、分かります!」 「なぜ分かった。」 「庶民派御曹司イェア!」 「落ち着け!」 「落ち着いた!」 「次!会員番号十一番、今週の三反田君と光君!」 「出たな、不憫クラスタ!」 「今日も私の時代がやって来たポウッ! 今週も三反田君はひな鳥のごとく光君の後ろを付いて回っていました。 『光―。』 『はいはい、うざいうざい。』 まあ、これがデフォです。最近はあんまり相手にされなので、背中に飛びつくようになりました。 『光―。』 『はいはい、うざいうざい』 飛びついても光君は平然と歩き続けました。かわいいです。」 「私が見たときはだいしゅきホールドしてたよ。」 「何それ、うらやま!」 「それでも光君は平然としていました。」 「良いぞ、不憫!もっとやれ!」 「真っ黒ピカリンが見られるのは不憫だけ!」 「次話して良いですか?」 「どうぞどうぞどうぞどうぞ。」 「では、会員番号十五番!先週火曜日の体育の千晶君と昇君。 ご存知の通り、人並み外れて運動神経の良い千晶君ですが、その日は、不幸に不幸が重なって、怪我をしてしまいました。」 跳び箱を飛ぼうとしたら、崩れて、それでもうまく着地しようと思ったのに、そこに運悪く生徒が通りかかって、そっちも回避したら足を捻ってしまったんです。そこに駆け寄る昇君。 『千晶!千晶――っ!嫌だ、どうして…こんな……』 『…昇、俺はもうだめだ…』 『嘘だ、あの時の約束を、まだ果たしてないじゃないか!』 『昇……後のことは頼んだ…ぞ……がくっ』 『…千晶?千晶―――っっ!!!』 と、茶番を繰り広げたのち、昇君は千晶君を保健室に連れて行くと言って抱っこしました。軽々持ち上がる驚異の身長差hshshshs。 『いやいやいやいや、おかしいだろう。』 死んだはずの千晶君がツッコミました。 『何が?』 『抱っこは無いだろ。おんぶとかだろJK。』 『常識的に考えても、女子高生的に考えても、情熱的に考えても、これが正しい!』 無駄にきりっと決め顔で答える昇君。 『嫌だよ、おろせよ。お前の常識どうかしてるよ。』 『えぇ?…………ダメ?』 渾身の可愛い顔&可愛い声&首を傾げる可愛い仕草でおねだり。私には垂れた犬耳と尻尾が見えました。きっと幻覚じゃない!もちろん千晶君はノックダウン!真っ赤な顔を彼の肩に埋めて隠して運ばれていきました。 千晶君の怪我は全治一週間と言われましたが、驚異の回復力で三日で完治しました。終わりです。」 「身長差コンビイェア!」 「身長差驚異の40センチヒーハー!」 「古い!」 「古い言うな!失礼だろう!」 「ごめんね!」 「会員番号五番!金曜日の電車内での照君と謎のイケメン!」 「いきなり始めやがった。でも良いぞもっとやれ!」 「兄弟にだけ甘いクールなメガネキャラ、照君が周一、二の周期で痴漢に遭っていることを私は知っている。」 「助けてやれよ。」 「いや、なんか彼もまんざらじゃなさげだったんで。」 「まあ、そうだけど。」 「マジですか会長!」 「まあ、良いじゃない。続けて。」 「金曜日も彼は痴漢に遭っていました。しかし、それはいつものタレ目長髪黒髪イケメンではなかったのです!」 「タレ目長髪黒髪イケメンとな!?」 「タレ目長髪黒髪前髪で片目隠れた長身イケメンとな!?」 「会長wwwやっぱり知り合いじゃないですかwww」 「まあまあ、続けて。」 「金曜日に我らが照君の尻を弄っていたのは、油髪のおっさんだったんです。照君可哀そう。涙目で震えてました。私は助けようと思ったんですが、満員電車で、近づけません。でも、照君はすぐ近くにタレ目長髪黒髪前髪で片目隠れた長身イケメンを見つけてその手を掴んだんです。そうしたら、タレ目長髪黒髪前髪で片目隠れた長身イケメンはすぐに事態を把握して、照君を抱き寄せ、痴漢の腕を掴んで凄みました。会話は聞こえませんでした。」 「痴漢は、照君がイケメンにいつも好きなようにされてるから、自分もって思ったらしいね。会話は、 『なに、俺の照に手を出してるの?』 『何のことだ。と言うか、おまえ、何なんだよ!』 『俺は、この人の恋人だけど何か。ていうか何?現行犯の癖にしらばっくれるわけ?』 『診、もう良い。触られただけだ。』 『だけじゃないよ。』 ここでイケメンは照のお尻の割れ目をなぞって、声を殺してしがみ付いた照の耳元で、 『今日、我慢できる気がしないから、続きは後でね。』 って囁いたんだって。痴漢は交番につきだしました。ソースはイケメン。」 「イケメンと照君が付き合ってた――っ!!」 「痴漢プレイは当たり前、アブノーマルカップル!」 「会長とイケメンの関係詳しく!」 「従兄弟でーす。」 「うきゃーうっ!!なんで…そんな…隠しだ、ま……がくっ」 「いやぁ、わざわざ他人の性癖暴露するのもどうかと思って。でも、この場合は僕がばらしたわけじゃないからね。と言うか、二人が悪いよね。アブノーマルイェア!」 「他にネタのある奴はいねがぁ!」 「返事が無いただの屍の様だ。」 「ではここで僕が立ち上がろう。」 「会長!」 「緑館組、ケツタッチ騒動だ!」 「会長の口からケツタッチとな!」 「タレ目おかっぱ童顔美少年の口からケツタッチktkr!!」 「そこで躓いたら先に進まない!」 「すみません会長!」 「自重します、会長!」 「宜しい続ける。 僕はふと、みんなのケツをタッチしたら、どんな反応をするのか知りたくなった。それで、千晶君と明様に撮影と録音を頼んで、まずは光君に試してみた。 『きゃっ』 と、短い悲鳴を上げて、素早く腕を掴まれた。そしてそのまま投げられそうになって、途中で気付いて手を離された。僕は空を飛んだ。で、地面に叩きつけられるのを覚悟したんだけど、ちゃんと光君に受け止めてもらえました。 次に、千晶君に協力してもらって、昇君に仕掛けてもらった。僕がやらなかったのは、ただ単に二人を見たかったから。千晶君は、お尻の割れ目をそっとなぞった。 『ぃやぁっ』 って、昇君は耳が溶けるくらいの可愛い声あげて振り返った。顔真っ赤で涙目だった。 『ち、ちあ、千晶…っ?』 『…なんかごめん。』 謝る千晶君の手を取って、昇はその手を自分の胸に当てた。 『心臓の音、すごいんだけど…責任、取ってよね!』 何その可愛らしいおねだり。身長190ニアの癖に。可愛いって何。千晶君はそのまま連れて行かれちゃった。そこから先は明様が追跡してくれましたが、企業秘密だと言われました。 次に、光君に協力してもらって、三反田君に仕掛けてもらった。僕がやらなかったのは、ただ単に二人を見たかったから。で、光は、気づかれないように弘太郎の背後に回ると、思いっきりお尻を下から掬いあげるようにして掴んだ。そりゃもう潔いぐらいに、ぐわしっと。 『わきゃ――っっ!!』 飛び跳ねて振り返ったよ、涙目だった。 次に、また光君に協力してもらって照君に仕掛けてもらった。なんで僕がやらないかって言ったら、反撃が怖かったから。溺愛されてる弟の光だったら大目に見てもらえると思って。 で、光は、気づかれないように照の背後に回ると、思いっきりお尻を(以下略)。照は、 『ひっ』 って息を詰めてから回し蹴りをさく裂させた。もちろん光は避けられたけど。 『光!?』 『ごめんね、悪戯しちゃった☆』 『もう、びっくりするじゃない、お返しに光るのも触っちゃうんだから』 『いやんっ』 とか百合百合な展開が始まった。ごちそうさまです。 で、光と別れた僕は次に、自ら藤本に仕掛けた。千晶方式で、割れ目をなぞったんだけど、 『きゃっ』 と、短い悲鳴を上げて、素早く腕を掴まれた。光君のパターン再びだと思って身構えたら、後は振り返るだけだった。普通の反応だった。 そして、おおとり!藤本に協力してもらって白鳥に仕掛けてもらった。 『ぃやぁっ』 って、すごい可愛い声を上げて腰抜かした。 『よ、よよ、陽…っ?』 って涙目で振り返って、兄弟だなって思った。兄の方がより感度良いみたいだけど。 終わりです!」 わぁああああ! 感動の声とともに皆がスタンディングオベーション。 「ありがとう、感動をありがとう!」 「悲鳴だけ集めたCDも作りました。」 「神様!あんたは神様だよ!」 腐海森の会は、毎週水曜日の放課後、山百合高校のどこかの空き教室で集会を開き、栄養を補給しています。
だってお前、ショタコンだろ?
「雨が降るとか聞いてないんだが。」 下校途中、突然の雨にみまわれた愛場千晶と白鳥昇は、公園のテーブルセットの屋根の下に避難していた。 「ちょっとの間にびしょ濡れになっちゃったね。」 「絞れるな。」 そう言って、昇がベンチに座るので、千晶もその隣に座り、シャツの裾を持って絞った。捲れた裾から、千晶の滑らかな肌が覗く。昇の手は、無意識にそのくびれに引き寄せられた。 「――うわっ、な、何?」 敏感な脇腹に突然触れられて、千晶の体が跳ねる。濡れた手のひらで、濡れた肌を触られて、吸い付くような生々しい感触に、羞恥心が湧き上がった。 「あ、いや…寒くないかなって。」 しどろもどろに言いつくろう昇。しかし、その手は千晶の腹部をまさぐっている。触れた手から直に体温が伝わってくる。心なしか彼の手も、自分の体も熱を持ったようだ。千晶はくすぐったさの中に混じる甘い感覚に戸惑いを感じ、目を泳がせた。 「…撫でてるけど。」 「い、やあ。なんか千晶の方が体温高いね。」 言いつつ昇は、もう片方の手で小さな体を抱き寄せる。華奢な体に張り付いた濡れたシャツは、常より薄く頼りなく見え、地肌との境界が曖昧になる。肩にはタンクトップの輪郭、またその中央にはブラのストラップがくっきり浮き出ている。昇は指先でそっと紐状のそれをなぞった。千晶の体がびくっと跳ねる。 「――っ、やめろ!」 「…だめ?」 距離をとろうと、昇の胸に手を当てて腕を突っ張るのに、腰を抱えられて離れられない。やめろ、そんな真剣な目で見つめるなよ、柄じゃないだろ。 「ダメだ。」 「もうちょっとだけ。」 「ダメだ!」 構わずシャツに潜りこんだ手が、背中を這い上がってきて、体が震えた。 腕の力が抜けて抱き寄せられる。 「誰もいないよ?」 「そう言う事じゃない。」 「なんで?」 耳に吐息を吹き込まれて、声が震える。 泣きたい。 「……だって俺、女だもん。」 「は?」 頭上の間抜けな声に、千晶は彼を見上げる。必然的に上目使いになった。 「おまえ、男が好きなんだろ?」 「何それ!?」 可愛い顔で、可愛い仕草でそんなことを言われて、昇はとんでもないと声を張り上げた。そうすれば、今度は首を傾げて、 「だってお前、ショタコンだろ?」 なんていうものだから、 「ロリコンでもある!」 叫んだ。 「うわぁ……」 「ひかないで!」 ****** 今年は体育祭の年である。学際と違って買いしは少ないが、応援合戦の衣装の材料やボンボン用のテープなど、必要なものもある。そんなわけで、白鳥昇は一人、最寄りの文房具屋に来ていた。 「テープの色はピンクと青と黄色と…」 「あ!昇じゃん!」 しゃがみ込んで棚を見ていると、声をかけられる。振り向けば見慣れた真ん中わけの少年が歩み寄ってきたところだった。 「二組も買い出し?」 昇が聞くと三反田巧太郎は口を尖らせて、体全体で不機嫌であると主張する。 「そうそう、ジャンケン負けっぱなしでさぁ。最後は春香ちゃんと俺の一騎討ちで、俺が負けたからこっち。春香ちゃんは手芸屋。」 身振り手振りでジャンケン大会の様子を伝えてくる彼の前に立つ。千晶よりは大きいが、やはり小さい。二人の身長差は20センチ弱だ。 「昇はそれで全部なん?」 「あとは赤の油性マジックだね。」 「それならあっちにあったぜ。それかって一緒に帰ろ。」 「うん。」 「なぁ、昇ってショタコンなのか?」 巧太郎が無邪気に尋ねれば、昇は不思議そうに首を傾げる。 「え?なんで?」 「いつも千晶が言ってんじゃん。このショタコン野郎が!って。」 「あー。」 その言葉に昇は納得した。まあ、あながち間違いではない。 と、その時風が吹いて、砂埃を巻き上げた。 「――っ、目にごみが…。」 痛みに弘太郎が、思わず手で擦ろうとすると、その腕を掴まれる。 「擦らないで、じっとして。」 痛いのを我慢して、目を開ける。昇の優しげな眼がすぐ近くにあってビックリして、目を見開いた。そうしたら涙と一緒にごみが流れたのか、目が痛いのが直っていた。 「あ、痛くない。」 「良かった。」 にこっと笑って昇は巧太郎から離れる。その直後、 ゴッ ぐしゃっ 昇の頭と彼の足下で大きな音がした。 「どわぁっ!」 ずっこけた昇の足下には手芸屋の大きな袋が転がっている。つづいてドサッと荷物が落ちたような音が聞こえて、そちらを見ると、そこには弘太郎と同クラスの若林春香と、千晶が居て、その千晶が昇を睨みつけていた。 千晶は巧太郎と目が合うと回れ右をして駆けだす。 「千晶!!」 昇も少年の後を追って駆けだした。弘太郎と春香もそれを追う。しかし、千晶の足の速いのなんのって、三人して全然追いつかない。背が低いから必然的に足も短いのに、何ていう回転の速さだ。 どうしようか、と昇が思ったとき、春香が何かを投げた。 べしゃぁ 千晶がそれを踏んでこけた。反動で彼女の足元からころころと転がってきたのはミシン用の糸だ。 「千晶!」 慌てて昇が彼女を抱き起す。 手の平に砂利が食い込んでいるが、怪我はなさそうだ。 「は、放せ!」 放せと言われて、逆にがっちりホールドする。 「千晶、どうしたの?」 逃げだそうともがく千晶に昇が尋ねた。 「――っ」 逃げられないと察したのか、千晶は抵抗を止めた。すると、にわかにその肩が震えだす。 「千晶っ!?」 千晶は釣り目の大きな瞳からぽろぽろ涙を流していた。 「…っ、だって…おまえ、が…、浮気…」 震える唇で紡がれた言葉に唖然とする。 「俺、浮気なんかしてないよ!?」 「嘘だ!さっき三反田とキスしてただろ!!やっぱりショタコンだったんだ――っ!!」 千晶はそう叫んで弘太郎を指さした。 ――俺!?俺と昇がキッス!? 弘太郎からしたらなんだそれ、である。 「いやいやいやいやいや無いから!あれは俺の目にゴミが入って見てもらっただけ!」 「まだそんなこと言ってるの!?違うよあれは、目にごみが入ったって言って、擦ろうとしたのをとめてただけだよ!」 んなベタな!?と、二人で同時に捲し立てた。 「…ほんとだな?…」 「あたりまえでしょ、浮気なんかしないよ。」 千晶の濡れた目尻を親指でそっと拭い、昇は甘い言葉を囁く。 「――だって、こんなに千晶が好きなんだから。」 「…昇。」 その空気に弘太郎は目を泳がせた。甘い、甘すぎる展開だ!目のやり場に困るぞ、居たたまれないぞ! 昇は千晶の柔らかな頬を壊れ物でも扱うかのように、両手で優しく包み込み、千晶は昇の頭に手を添えた。そうして二人は見つめ合い、お互いの距離を縮めていき、唇を 「うわーっ!」 ――合わせなかった。 突如気を取り戻した千晶が声を上げて彼を押しのけたのだ。 「若林さん!違うんだこれは、違くて!」 千晶の言葉に春香の存在を思い出す。見れば彼女は見開いて硬直していた。 「春香ちゃーん?」 弘太郎がその目の前で手を振る。 「はっ、あの!男同士でも構わないと思います!」 なぜ敬語? 目を輝かせてそう言うと、彼女は「山瀬せんぱーい」と春春コンビの片割れの名前を叫びながら走り去ってしまった。
千晶ガール
おはようございます。こんにちは。こんばんは。春春コンビの片割れとしてお馴染み、深い森の海会員番号2番、影木幻十郎君の腐友の山瀬千春です!え?お馴染みじゃない?そんなぁ、結構登場回数重ねてると思ってたのに…ショックだ… そんなことより、なぜ私がこんなところで語っているかって?よくぞ聞いてくれました!え?聞いてない?聞いて無くとも語りますともそうしますとも。 皆さんは前回の話を覚えていらっしゃるでしょうか。そう、ホモォな話ですよ。一年一組の愛場千晶君と白鳥昇君の話でございますよ。それは暴力のような暑さが和らぎ、呼吸のしやすくなった10月の終わり、つまり昨日のことですが。春春コンビの片割れであるわが後輩バカ林春香改め若林春香が、採れ立て新鮮のネタを提供してくだすったわけであります。詳しくは『だってお前、ショタコンだろ?』をご覧あれ。そんな話を聞いたら、事実確認のために、二人に密着すしかないではありませんか!あ、今暇なの?とか思ったでしょう!?皆さん知ってます?高校二年生って中弛みって呼ばれているんですよ?ええ。中弛みますとも尾行しますともしましたとも。で、ですね。ご期待にお答えしまして、報告したいと思います。 千晶君と昇君の身長は約四十センチ違います。千晶君は最近肩こりが酷くなり、昇君は腰が痛くなったそうです。あ、影木君談です。 まあ、あれです。そんな情報を聞いたら妄想が爆発するわけですよ。千晶君は昇君の顔が見たいがためにいつも顔を上げているから首が痛くなるんだろうな、とか。昇君は、千晶君と近づきたいから腰を屈めるんだろうな、とか。 例えば千晶君がキスしたいとか思ったときはどうするんだろうって。めいっぱい背伸びをしても届きませんよね。袖を引っ張って、ねだるんでしょうか。でも、彼ってきっとツンデレですよね。素直にそんなことを言えるのか、きっと頬を染めて目を逸らして、ぼそっと「分かれよ…」とか呟くんですね。はぁ…。 昇君は千晶君が近くにいればいるほど身長差で死角に入られてしまいます。これは観察している中で気が付きました。二人は一緒に居ると、数秒ごとに昇君が彼の存在を確認するためきょろきょろするんですね。ふふふ、ここがまた萌え剥げるんですが、千晶君がそれに気が付くと、体の一部をタッチするんですよ。ここに居るぞって。大体は腕ですね。パンって叩きます。それからですね、レアな時だと、手を繋いでたりするんですよ。見えなくても存在が分かるように、てことですかね。 立ち話する時は、昇君がいっそしゃがみこみます。すると千晶君は昇君を見下ろすことになるんですね。いつも届かない頭がそこにあるという事で、なんとなく千晶君は昇君のふわふわ頭を撫でます。身長の高い人ほど、頭を撫でられるのに弱いという話がありますが、昇君のその時のときめきようったらないです。天にも昇る勢いです。それを見ている私も天に召されそうですけどね。興奮しすぎで倒れそうになったところを何度影木君に支えて貰ったことか…え、なんで影木君がここに居るんですか?え?私と同じ理由?愚問でした。 ところで、ぜんぜん関係ありませんが、千晶君って結構可愛い顔してると思うんですよね。大きな眼鏡で隠れてますが、もったいない事です。千晶君は特別女の子にモテるわけではありません。でも、眼鏡を外したら、男子からはモテると思うのですよ。小さくて、目が大きくて、強気で。最高の受けキャラです。ありがとうございます。 ん?何、若林。え、体育祭のチアの人数が足りない?ほほう、それはそれは… ****** 「ちーあき。」 体育祭の準備が着々と進む中、二組からやってきた愛場明が入口から千晶を呼んだ。その手には、赤ラインの入ったタンクトップと、赤いプリーツスカート、つまりチアガールの衣装を持っており、それを視認した千晶は――窓から逃げだした。 「光GO!」 「OK明ちゃん!」 しかし、それを予測していたかの如く窓の外に待ち伏せていた光によってあっけなく捕まってしまった。 「なんだよ、何する気だよ!?」 「見て分からないの?千晶をチアガールに、いいえ、千晶ガールにしようとしてるんじゃない。」 それでも往生際悪く抵抗する千晶に明は何故か頬を膨らませて言った。 「何それ!?」 「忘れちゃったの?今年の応援合戦は一組二組合同でチアをやるって決まったじゃない。」 「それは有志だろ!?」 「昨日練習中にセンター二人が怪我して人数足りなくなっちゃったのよ。」 「俺に来る前にもっと可愛い女子が居るだろうが!」 「千晶以上に可愛くて運動神経の良い女子なんていないわよ。というか今から練習して間に合うのなんて千晶と光くらいよ。」 美人の姉に褒められれば嫌な気はしない。少し千晶の頬が赤く染まった。 「センターやって欲しいんだよ。」 しかし、羽交い絞めにする光の声でまた抵抗を始める。 「よりによってセンターかよ!嫌だよ!!」 「二組から出すセンターは光なのよ。そうしたら一組は千晶でしょう?」 「何を当然のように言っているんだ?全然当然じゃないからな!?」 「ああ、もう。往生際が悪いわね。ここで着替えさせてもいいのよ?」 意地でも首を縦に振らない千晶に焦れた明が、そのベルトに手を掛ける。 「え、ちょっとまっ――ぎゃぁぁぁぁあああ!!!!」 暴れる千晶の制服の上と下をいっぺんに枌はぎ取ろうとした瞬間―― 「千晶!!」 ひょろっと長い影が二人を引きはがし、千晶を奪い取った。 「だめだめだめだめだめぇ!!」 千晶の小さな体を抱きつぶして、狂ったように「だめ」を連呼のは、実は今の今までおろおろと三人のやり取りを見ていた昇である。 「ちょっと二人とも何してるの!?何千晶にストリップやらせようとしてるの!?」 「…怖かった、まじで怖かった…」 彼の腕の中で、千晶はその胸にすがって震えている。 「ほら見なさいよ!この子震えてるじゃない!!」 「「なぜカマ口調?」」 そうツッコみを入れつつ、加害者二人の視線は彼の手の動きに注目していた。 片手で捲れた裾を直して、そのまま腰を抱き、もう片手で、ベルトを上げて、そのまま小さな尻を…撫でている。 「…ゃ、ちょ…お、まえは!どさくさに紛れて尻を撫でんな!」 当然千晶が腹に一発食らわせた。 「はうあっ!い、今ならいけると思ったのに…」 「何がだ馬鹿やろう。」 まあ、いつものじゃれ合いである。 「そんなことより千晶。」 「そんなこと!?」 じゃれ合う二人に付きあってられないとばかりに、明がそう切り捨てると、千晶は心外だとばかりに振り向いた。しかし、すぐに彼女は振り向いたことを後悔する。その視線の先では、加害者二人が、指をわきわきと蠢かせて、危険な笑みを浮かべていたのだ。 「千晶がやると言うまで私たちは特攻を止めない。」 「……」 「ちーあーきー?」 「……分かりました。」 自分には味方なんて居なかった。千晶は真っ黒な顔で項垂れた。 着替えるから絶対入って来るなよ!絶対だからな!と、更衣室にこもって数分後。出てきた千晶は完全な女子になっていました。 「すごい!千晶君それ一人でやったの?」 「一人でって、着替えて眼鏡とバンド外しただけだぞ?」 「千晶君、本当に可愛い顔してるね!肌綺麗だね!もち肌だね!」 「それだけでこんなになるなら髪の毛とかいじったらすごいことになるね!!」 そうして女子に連れ去られてまた10分後。 「ありがとう、そしてありがとう!明ちゃん!光君!」 髪を弄られ、ふわっとしたボブになった千晶は、化粧無しでも美少女だった。 もともと千晶は、大きな眼鏡で隠れているが、丸顔で、目が大きくて、それ以外のパーツが皆小作りで、とても可愛らしい作りをしている。男としての魅力には掛けるが、女としてみればややマニアックな感はあるが、とても魅力的なのだ。 それを何故か居る二年の影木幻十郎と山瀬千春が連写した。 「千晶君マジカワ!!」 「リアル男の娘キターーー!!!」 二人してキャラが崩壊している。 その後ろで若林春香が昇の目隠しを外している。 「で、昇君はもう目隠し取って良いよ。」 いや、何してんの? Qbitsグッズのリンピッツのキラキラの目を外された昇は、千晶を見るなり飛び掛かってきた。 「か、か、か、かわいいぃぃぃぃぃいい!!」 ああ、こうなるから目隠しされてたのか。 「持ち帰り、お持ち帰りしても良いですか!?」 「だめですよ。」 千晶の前にひざまづいて抱きつき、そう乞う昇に春香は冷静に返した。 「いや、ムリ!ミニスカ!ミニスカ!!下何穿いてるの!?」 しかし、昇の暴走は止まらずそれどころか、千晶のミニスカを捲りにかかった。 「ぎゃぁぁあ!?」 「痛い、痛い!」 「痛いじゃねぇよ!何をいきなり捲ってるんだよ!?」 「つい出来心で。あ、ちなみにスパッツ履いてました。」 「報告してんな!」 その後千晶はどうせやるならと吹っ切れて、光と共にその運動神経を発揮し、中心になってチームを引っ張っていった。 ****** 体育祭本番。天候にも恵まれ、青空の元、一組二組合同のチアダンスは大成功を収めた。綺麗にそろったラインダンスはもちろん、千晶と光のサーカスレベルの空中芸(笑)が見事に観客の心を掴み、歓声が上がった。 「チアの出来はどうだったよ?」 待機席に戻った千晶が、クラスメイトに尋ねると、皆興奮気味に答えてくれる。 「すっごかった!!ホントにすっごかったよぉ!!」 「千晶君と光君のアクロバットすごかった!」 「人間!?って感じ!!」 「他の子もすごい動き良かったね!!」 「千晶君と光君が手本になって教えてくれたんだよぉ!」 「あーヤバいヤバい、私すごいとヤバいしか言ってない。やばい。」 「先輩が、センターの小さい子誰だって!すごくかわいいって言ってたよ!!」 しかし、その答えは喜んでいいものか。 「コメントに困るんだけど…。」 「笑えば良いと思うよ!」 「あはははは」 光がそう言うので笑っておいた。アドレナリン出過ぎておかしくなっているようだ。 「ところで二人は次すぐに選抜リレーだからそのまま出るんだよ。」 「う、わマジか。」 「きゃぁぁああ、楽しみ!!」 引き攣る千晶の隣で光が黄色い悲鳴を上げる。 「光、おまえ話し方まで女っぽくなってるぞ。」 「千晶、早く行こう早く!」 「俺とお前敵なんだけど!?」 いつも以上にテンションの高い光は、嬉しそうに千晶の腕を引いて行った。 『一年の選抜リレー、一組二組が、アンカーにバトンが渡りました!おおっと、これは先ほどチアでセンターに居た二人ですね。早い早い早い!』 直線で早いのは光、カーブで早いのは千晶。接戦を繰り広げたが、結果二人は同着で一位になった。 ゴールテープを同時に切った二人は、息を切らして笑いあう。このシーンだけはまるで爽やかスポーツ青春少年漫画の様だ。周囲からはすぐに二人をほめたたえる言葉が掛けられた。 「おめでとう!!」 「おめでとう!」 それに対して二人は人差し指と小指を立てた両手を前に突き出し、「うぃー」と答える。 「何それ!」 と笑いがおこる中で数人の男子がバケツを持って走ってきた。 「せーの!」 ばっしゃーん! まさかと思えば案の条、主役二人は盛大に水を掛けられる。 「きゃあー」 「つめてー、バカだろお前らバカだろ――って、なんだよ?」 可愛い悲鳴をあげる光と、怒鳴る千晶。しかし、その怒鳴り声はすぐにしゅんと勢いをそがれてしまった。何やら周囲の空気がおかしい。 みんなが、え、と一瞬動きを止めてしまったのだ。 「え、あ、いや…?」 混乱しているのか、誰もまともな言葉を発しない。そんな中、 「千晶――っ!!」 「ぎゃっ」 昇が飛んできて正面から千晶を羽交い絞めにした。 「見ちゃダメ見ちゃダメ見ちゃダメぇ!!」 「あ、おい、ちょっと?なんなんだよ!?」 その手は、ブラの線と尻というとても際どい位置に触れている。慌てて千晶がどけようとするが、何処からそんな力が出るのかという頑なさで、手はそこから動かなかった。 「何って、透けてるんだよ!」 「な…っ!」 やっぱり、手はどかさなくて良い! 千晶は抵抗を止めて逆に昇に抱きついた。 「ばかばかばかみんなばか!千晶もばかぁ!うわぁぁああん!」 昇は、そんな千晶をよいしょと抱えて泣きながら走り去った。 「…あれって女装?」 「違うよ。」 残った生徒が言うのに、光が答える。 「え、どういうことだよ?」 「千晶は女の子なんだよ。」 「えぇぇえええ!?」 さあ、みんなはどう思ったでしょうか? ①今まで騙していたのかと憤慨した。 ②なんで男の格好をしていたのか不思議に思った。 ③昇との怪しい関係が怪しくなかったと知って安心した。 ④こんな可愛い娘が女の子なわけ…あった。 正解は――全部です。 この後千晶は思う存分質問攻めにされつつ昇との関係を茶化され祝われるのでしょう。 そんな中、腐女子山瀬千春は、腐友影木幻十郎との会話やチャットでの出来事を思い出し、一人色々解決してすっきりしたのでした。
こんなときどうする?
この秋、愛場千晶は生徒会実行委員に襲名した。そして近々行われる、生徒会役員引き継ぎのイベントの準備のための集まりに参加していた。 特にその後教室に戻る用事は無かったので、荷物は持ってきていたのだが、課題のために必要な辞書を教室置きっぱなしであることに気が付き、とりに行くことにした。 放課後の掃除のあと、すべての窓の施錠は完了していて、風は吹かない。窓から見える景色だけが秋の色をしていた。少し前までのちりちりと焦げ付くような暑さは無くなり、高くなった空から、茜色の光が落ちて、廊下に四角い模様をつくった。窓枠の影が、長く落ちて、その中に千晶の影が実際の身長よりも長く伸びて混じる。 開けっ放しの教室の扉の向こうに見慣れた姿が見えた。 廊下側の一番前は千晶の席だ。そこで、白鳥昇が両腕を枕にして寝息を立てていた。彼は確か千晶の仕事が終わるのを緑館で待っていると言っていたはずだが、どうしてここに居るのだろうか。少し疑問に思ったが、彼の座っている場所が、千晶の席であることに自然と頬が緩んだ。長身を丸めて、彼には小さすぎる席に無理やり収まっている彼が可愛いと思った。 「う~」 やはり姿勢がきついのか、片手が前に投げ出される。緩く握った手の中にある携帯電話が床に落ちそうだった。おっと、とそれを回収すると、ちらっと開かれたままの画面が見えてしまった。 ――そこに映っていたのは、スクール水着姿の幼女のイラスト。 こんなときどうする? 千晶の体がびくっと跳ねた。そして、画面をスクロールした。 きっと見ない方が良いのだろう。しかし、見てはいけないと思うものほど見たくなる。 ビート板を胸の下に敷き、バタ足の練習をする幼女が、胸が擦れる感触に戸惑っているという描写のイラストに続き、戸惑っている幼女の足をコーチが持って動かし、さらに戸惑わせ、幼女が小さく喘いでいるイラスト。続いて勃った乳首に張り付く水着を引っ張る幼女に、コーチがわざとらしく声を掛けているイラスト。 …これは、何と言うか…… 「う~ん…っ」 昇の声にハッとした千晶は、慌ててケータイの画面を閉じて机に置いた。 「あ、千晶!」 「お、おう。」 「もう帰る?」 「お、おう。」 こんなときどうする? 見なかったことにする。 いつも通りを装うのはおおよそできていなかったが、昇も寝起きでぼうっとしているから大丈夫だろう。 二人で、学校を出る。隣で昇が何か話しているが、千晶はさっきのイラストのことを考えてしまい、それどころではない。 「最近涼しくなって来たよね。」だとか、「落ち葉が積もったらみんなで焼き芋作ろう。」とか、それどころじゃない。 どうして、彼は緑館ではなく、教室に居たのか、なぜわざわざ千晶の席にいたのか。千晶の見た目が幼女だからか。普段は学ラン着ているが、実際は幼女だからなのか。幼女だからわざわざ千晶の席であの画像を見ていたのか。彼の妄想では彼はどの位置に居るのか。まさか幼女の視点に立っているわけではないだろう、コーチの立場であのイラストを見ているに違いない。まさか幼女を千晶に置き換えてあの… 「千晶?」 「はひぃっ!」 名前を呼ばれると同時に肩を叩かれて、思わず返事をする声が裏返った。 「どうかした?」 「い、いや。何も。何の話だっけ?」 「臨海学校楽しかったねって。」 「リンカイガッコウ」 千晶の脳裏に、彼に平泳ぎを教えてもらった時の記憶が走馬灯のようによみがえってきた。彼は千晶の足を持って開かせて、そして――鼻血を出したのだ。 千晶はじりじりと彼から距離をとった。 「千晶なんか遠くない?」 「ちょっと待って、今頑張ってる。」 「何を!?」 そうだ、ポジティブに考えよう。昇はショタコンだけど、ロリコンだった。これだ。 「…おまえ、女が好きだったんだな。」 「いきなり!?というか千晶とつき合ってるんだから当然でしょう。」 「うん。そうだよな、うん。」 あとはあれだ。こいつはロリコンだから俺を選んだよな。ロリコンじゃなかったら、もっと他に居るもんな。明とか、若林とか。 「おまえ、ロリ好き?」 「え」 「俺ってロリ?」 「え」 あと問題はスク水だ。ちょうマニアックだ。もしこいつが俺にスク水を着てくれと言って来たらどうする?抵抗はあるか?もちろんあるさ。しかし、こいつが喜ぶなら恥を忍んでやっても良いんじゃないか。寧ろプレイ的な意味で言ったら、恥ずかしがっている姿ですら萌えポイントに!? さっきのイラストの幼女を自分に、コーチを昇に変換してみる。ぶわっと顔に熱が上ってきて、「うわっ」と思わず声が漏れた。自分の声にびっくりして手の甲で口を押える。 「え、千晶!?」 「う、う、ぁ…っ」 顔を隠して俯くのに、昇が覗き込んでくる。 「え、なんで?どうしてそんな、いきなり可愛くなってるの!?」 まともに顔が見れなくて、押しのける。 「うるさい!」 「酷い!」 「酷いのはお前だ!お前のせいで変な扉開いたじゃないか!!変態!!」 「何で!?」 「ばか!変態!!ばか!!!」 叫びながら彼をおいて駆け出した。 「千晶――!?」 彼が追ってきたが追いつかれるつもりはない。ちょっと頭を冷やさせてくれ。明日になったら…、ああ、明日になったら、まともな顔して会えるかな…… こんなときどうする? 見なかったことにする。 でもできなかった。
巧太郎は馬鹿だ
馬鹿だから勉強ができない。 「ひかる~っ!」 「巧太郎うざい。」 数学の小テストの返却後、泣きついてきた巧太郎に、光はすげなく返した。 「巧ちゃん!」 「はいはい、巧ちゃんは相変わらずうざいねぇ。何、また再試?僕が教えてあげたのにその頭はいったいどうなってるのかな?ババロアでも詰まってるのかな?」 「ごめんなさい~!でもまた教えて欲しい…」 光が、真ん中分けの前髪の、分け目から見えるでこをゴスゴス突くと、巧太郎はあうあう言いながら涙目で訴える。 「同級生の男に甘えた声出されてもキモいだけなんだけど。」 光の暴言に慣れてしまった巧太郎は眉を下げながらプリントを広げてその場で問題を解き直し始めた。 「ちょっと勝手に広げないでよ。て、はあ!?ここ間違えたの!?ありえない!直前にやったところじゃん!」 「だって、どこでどの公式使うのかいまいちよく分かんなくて…」 「ちょっと千晶!ヘルプ!」 明の呼び出しに応じて、隣のクラスから来ていた千晶に声を掛けるが「無理!」と即答されてしまった。 「悪いな。俺は明という珍種の相手で手いっぱいだ。」 明は所謂天才で、答えは分かるがその過程が分からず、途中式が書けない。文章問題に至っては式すら書けないから、当然彼女も再試である。 「答えが合ってるんだから良いじゃない。」 「答えだけ書かれても困るっつーの!寧ろ何で答えだけ浮かぶんだよ!」 「こう、ばばー!と来てふわふわっと何か考えてはいるんだけれど、その思考回路を言葉に表すことが難しいのよ。」 「意味分かんねぇ。」 「例えば現代文が苦手な人に、現代文が得意な人が教えようとするじゃない。でもどうやって教えたら良いのか分からない。だって普通に考えたらこうなるだろう、分かるだろう、と。そういう事よ。」 天才明と秀才千晶の会話をうずうず落ち着かなく聞いていた巧太郎が、がばっと両手を上げる。声だけでなく行動もうるさい。 「俺もばばー!と来てふわふわっとしたい!」 そして馬鹿だ。 「巧ちゃん、それ確かにすごいけど結局再試だから、状況の解決にはならないから。」 「あ、そっか。」 「巧ちゃん本当は脳みそ無いんじゃないの?大丈夫?ちゃんと検査してもらった方が良いよ?」 「うう…」 「はぁー…、問題やり直す前に公式の使い方の覚え直しから始めるよ。」 光は悪態をつきながら教科書を開いた。 馬鹿だから鈍い。 「光!次体育館だって!」 「光!購買で新商品買えた!」 「光!今日の弁当も力作だから!」 休み時間には光の所に来るし、移動教室も一緒だし、昼休みには巧太郎の用意した弁当を一緒に食べるのが当たり前。ちょっと離れても光を視界にとらえればすぐに寄って行き、邪険にされても引っ付いて、無視されてもコアラの如く背中に登る。 そんな彼を、腰巾着だとか、金魚の糞だとか言う生徒がいるのに、馬鹿だから気が付かない。 言われていることは本当のことだし、光は「自分には関係ないからどうでも良い」と思う。でも、「相手にされてないのに可哀そう」とか、「ただのシンパのパシリじゃん」とか揶揄されるのはムカつくから、そういう言葉が聞こえたときには構ってやった。 「巧ちゃんは馬鹿なくせに美術と技術家庭は無駄にできるよね。」 「光がデレた!!」 「うざい。」 「それでも俺は光が好きです!」 「…意味わかんない。」 (これ、いつもと変わらなくないか…?) そう思って、バカ丸出しに見上げてくる頭に手を置いて髪の毛をかき混ぜた。 「ひ、ひか、ひか…っ!?」 「うるさい、早く行くよ。」 (巧太郎の弁当早く食べたいんだから。) 光は顔を赤く染めて立ち止まってしまった彼の腕を引いて緑館に急いだ。 馬鹿だから利用される。 「あ、あの!三反田君、ちょっと良いかな!」 女子に呼び止められた巧太郎は、そのまま人気の無い場所に連れて行かれた。 「なに?」 「あ、あの…これ…」 頬を染めて緊張する彼女に手紙を渡される。 「これ、光君に渡して欲しいんだけど…」 「俺へだって思ったのに!畜生、また純情を踏みにじられた!!」 「巧ちゃんは勉強だけじゃなくて、こっちも学習しないよね。どうして毎回期待できるの。」 光は巧太郎経由で渡された手紙を開いた。 本当は読まずに捨ててしまいたいところなのだが、呼び出しや返事を期待するような内容だったとき、無視をしたらまた巧太郎が捕まるから。 「だって、今度こそは、て思うじゃん…」 肩を落とす彼の頭を鷲塚む。 光は毎回交際を断る際に、巧太郎を巻き込むなと言っているのにどうして浸透しないのか。 (巧太郎は馬鹿だけど、女子も馬鹿だ。巧太郎を使えば僕への心象が悪くなることに気が付かないんだから。) 巧太郎経由の手紙なら確実に返事をしてくれるからだと、光は気が付かない。 馬鹿だから信じる 「うち、ハムスター飼い始めたんだ。」 嬉しそうに話すクラスメイトに、巧太郎はうおお!と歓声を上げた。 「ハムスターって小さくて可愛いよな!」 「そうそう、成長しても両掌いっぱいに乗るくらいの大きさにしかならないからな。」 「え!?ハムスターってそんなに大きくなるのか!?」 「え、お前しらねぇの?」 「ねえ、光!ハムスターってこんなにデカくなるんだって!」 巧太郎は馬鹿だから、何でも信じる。何度騙されてもまた信じる。 「馬鹿か。」 光は両手をお椀のようにして、すげーすげーと目を輝かせて報告してくる彼に冷たい視線で答えた。 「うおー!騙された!!なんだよ酷いぞ!」 うそだと気が付いた彼はすぐにクラスメイトに詰め寄って抗議した。 騙されて、笑われて、悔しがって、また笑い出したけど、光は知っている。何でもないような顔をしている彼が、騙されるたびに、少し悲しく感じていることを知っている。 騙されても学習しない、形状記憶合金みたいな脳みそは、いらいらするけど、だから弄られて友達が多い。でも、心は形状記憶じゃないでしょう。 「今日はハムが特売なんだ!だから明日はハムチーズ作ってくるからな!」 嬉々として光に報告する巧太郎に、クラスメイトがにやにや笑いながら近づいてきた。 「おい、三反田知ってるか?ハムって兎の肉でできてるんだぞ。」 「え。」 「あとこの前お前が食べたって言ってた駅前の店のミートパイ、あれも兎の肉でできてるんだぞ。」 「え。」 彼の言葉に巧太郎は血の気の引いた顔で固まる。 「うさ、ぎ…」 「お前、この前絵かなんかで表彰されて図書カード貰ってたろ?そんでイラストの兎が可愛いって言ってたけど、あの兎の父親って磨り潰されてミートパイにされたんだぜ。お前が食べたのあいつの父親かもな。」 またうそだ。 「馬鹿か。」 巧太郎が固まってしまったから、光は彼に報告される前にばらした。 「う、うさ…」 ばらしたつもりだったのだが、巧太郎の報告に答える形でなければ、うそを信じたから馬鹿なのか、兎だと知らなかったから馬鹿なのか分からない。 当然馬鹿正直な彼は後者だと思うわけで。 「うさぎ、うさぎ…っ、光の好きなうさぎ…っ」 声を低く震わせた。 「うわ、ちょ巧太郎!?」 「は、まじ?泣くほど信じた!?」 じわっと瞳を濡らした彼に、光とクラスメイトが慌てる。 「馬鹿なの?本気にしないでよ!ハムが兎でできてるわけないじゃない。豚だよ、豚!」 「涙がこぼれないように上を向かせなければ!」などと混乱して意味の分からないことを考えた光は、彼の顔を上げさせて上から覗きながら「豚!豚!」と捲し立てた。 「は、う…、うそ…?」 「「父親のくだり以外は」」 クラスメイトとハモレば、巧太郎は膝から崩れ落ちて叫んだ。 「お父さーーーん!!!」 馬鹿だから感受性も豊かだ。 「巧太郎は馬鹿だね、何度も騙されて。」 「巧ちゃん~!」 「巧太郎。」 「巧ちゃん~!」 「巧太郎。」 あんまり可哀そうだから頭を撫でてやったら抱きつかれた。可哀そうだから特別に抱き返してやった。でも行動と言葉の両方で優しくしてやる価値は無いから巧ちゃん呼びはしてやらなかった。 馬鹿だからからかわれる。 「三反田!」 放課後、いつものように緑館に行こうとしていた巧太郎を、クラスメイトの男子三人が呼びとめた。 「お前はどの子が好みだ?」 アイドルグループのプロフィールの載った雑誌を見せられた巧太郎は、ぱらぱらページを捲って首を捻る。 「えー…、なんか、どれもしっくりこない。光の方が可愛い。」 その微妙な反応にクラスメイトはつまらなそうに巧太郎を小突いた。 「三反田さ、お前光のこと好きだろ。」 「好きだよ!」 「いや、そうじゃなくて。LOVEの方で。」 「え、違うよ。俺ホモじゃないもん。」 「女の子と光どっちが好き?」 「光。」 「即答じゃねぇか。」 「だ、だって!彼女でも家族でもない女子と親友比べたら親友になるだろ!」 「それでも普通はアイドルと男の親友比べないんだよ。」 クラスメイトは徐々に焦りだす彼の反応を面白がった。 「お前ぬくときも光オカズにしてんじゃねぇの?」 だからこれも冗談だ。 「え、は、な…っ!」 それなのに、にやにや笑いながらの台詞に、巧太郎はぶわわっと全身を真っ赤に染めて、言葉を詰まらせる。 「え、マジそうなの?それはガチだろ。」 「え、うそ違う、してない!」 「慌てすぎ。隠さなくても良いって。みんな薄々そうだと思ってるから。」 「なんで!?」 血圧上がりすぎて倒れるんじゃないかと心配になるほど取り乱す彼にクラスメイトは追い打ちをかけた。 「だってすごくべたべたくっ付いてるし。」 「おかしいんじゃないかってくらい尽くしてるし。」 「だから少しは下心もあるだろうって。」 身に覚えのありすぎる言葉たちに巧太郎は目をまわして背後の机に手を付いた。 「違う!下心無い!オカズにもしてない!ただ…」 「ただ?」 顔も熱いし、心なしか頭痛がする気がして、額に手を当てる。手も熱いから意味が無かった。 「ただ、ちょっといけるかもって…」 「やっぱLOVEじゃん。」 「LOVEだな。」 「え、え…!?」 うそ、うそ、と助けを求めるように泳ぐ瞳をすらっとした手が塞いだ。冷たくて気持ちが良い人肌に、沸騰した脳みそが少し落ち着く。 「…あのさ、よく本人が居る所でそういう話出来るね。デリカシー無さすぎ。」 とんでもない方向に転がった話の展開について行けずに、傍観していた光は、やっとそう口を挟むと額を押さえてため息を吐いた。 「光!ご、ごめん、俺…」 光は、慌てて顔を見ようとしてくる彼の頭を押さえつけて目を塞ぐ手を強く押し付ける。今どんな顔をするのが正解か分からなかった。 「巧太郎はエロ本の女の人に恋してるの?」 「え、してない。」 「AV女優に恋してるの?」 「してない。」 「雑誌見せて。」 光はクラスメイトに差し出された雑誌の表紙のアイドルを見て鼻を鳴らす。 「僕の方が可愛いじゃん。」 誰も反論はしなかった。 「今日も若林さんと山瀬さんは手を繋いで歩いてたね。廊下で抱きあってたね。」 「うん。」 「あの二人は恋人?」 「違う。仲のいい先輩と後輩。」 「巧ちゃんが差し入れ持ってくるのは僕にだけじゃないよね。」 「うん。皆に持ってくる。弁当は光にだけだけど。」 「僕、巧ちゃんに勉強教えてるよね。ジュース奢ってあげるよね。貰うばっかりじゃないよね。」 「うん。」 「LIKEでしょ。」 「うん。」 答えるとやっと手を離された。窓から入る西日が少し眩しくて目がしばしばする。 「巧太郎行くよ。」 「巧ちゃん!」 「巧ちゃん行くよ。」 「おう!」 光は自分の鞄のついでに巧太郎の鞄を掴んで、ついでに巧太郎の手も掴んで緑館に向かった。 (馬鹿が馬鹿すぎて放っておけない。)
To be continued