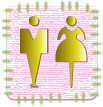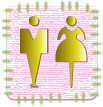
最高の二股男 恋愛成就 編
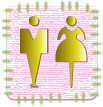
最高の二股男 恋愛成就 編
![]() 出会い頭に
出会い頭に ![]()
問題です。俺は今ドコにいるでしょう? 答え。見ず知らずの男の腕の中です。 桜咲く新学期。受験戦争を勝ち抜いた新入生達は期待と不安を抱えてこの門をくぐる。 中学と比べるととてつもなく広く思われた体育館も、新入生240人と保護者が椅子に座れば、いっぱいになってしまう。 初めて歌う校歌に国歌。入学前に配られたCDには校歌しか入ってなかったから、国歌が歌えない。国歌くらいみんな知ってると思ってるのかな?甘いな。まあ、校歌だって練習してきた奴は少数で、ほとんど校歌を歌うために後から入ってきた上級生の声しかしない訳だが。 「新入生代表挨拶、愛場千晶。」 「はい。」 歌が終われば俺の出番。俺の名前は愛場千晶。成績優秀、スポーツ万能。そんな完璧人間の唯一のコンプレックスは―― 「ちっちゃ!?」 「小学生?」 「え、飛び級とかあるの!?」 145センチしかないこの身長だ。 中学校よりも広い敷地。広い校舎。広い体育館に広い檀上。その上に立つ俺は小さいけど、男らしく胸を張る。少しでも自分が大きく見えるように。 ガラッ 一年一組の教室の扉を開ける。公立校だから、私立のようにきれいなわけじゃないが、ぼろい割に立て付けは悪くない。愛場千晶は出席番号一番だ。とりあえず鞄を掛けて、教室をぐるりと見渡す。見事に同じ中学出身同士で固まっていた。しかし、この中に俺の知り合いはいないようだ。少し考え、適当なグループに入り込もうと腰を上げると、開けたままだった扉からずば抜けて背の高い男が入ってきた。 特別がたいが良いと言うわけではない。けれども、小柄な俺の目線はこいつの胸どころか胃の辺りで、何でそんなこと分かるのかって言うとそれは――こいつが出会い頭に抱きついてきたから。 「可愛い!!」 俺を見たとたん、こいつはワンコのように顔を輝かせ、ガッシと俺を長い腕の中に閉じこめた。 クラスが騒然とする。 学制服同士で抱き合ってたらそうだよな。千晶は拳をワナワナと振るわせた。 「気色悪いわ――っ!!」 無礼な大男に強烈なアッパーを繰り出した。 ****** 赤メガネにヘアバンドのチビへの頭の緩そうなデカの突然の抱擁とチビの逆襲に騒然とする教室。 静まり返った教室では外の音が良く聞こえる。いや、廊下が騒がし過ぎはしないだろうか…。 ガラッ 「昇!」 現れたのは大男によく似たふわふわの髪の毛のネコ目の男、だけど身長は平均的。そいつが目の前の大男を呼んだ。 「兄さま!」 「兄さま!?」 答えた大男に思わず突っ込みを入れてしまった。おまえ、どこの坊ちゃんだよ! 「こんにちは昇君、はじめまして。僕、影木幻十郎、よろしく。」 その兄さまの後ろからちっこいのが顔を出した。首にカメラを掛けている。サラサラヘアーの可愛らしい顔に古風で男らしい名前がミスマッチだ。 「よ、千晶。」 二人の隙間から顔を出して千晶に話しかけてきたのは藤本陽。学年は一個上で千晶の幼なじみだ。 「あ、千晶同じクラスなんだ?」 声だけ聞こえるのは陽の双子の弟、照。年度終わりと年度始めに生まれたとかで、陽より一学年下のため千晶と同い年だ。しかも同じクラスらしい。 「僕、言ったじゃん!照聞いてなかったの?」 男にしては高いこの声は藤本家の末っ子光。こちらも同学年。 「千晶、来ちゃった。ミィ君早く入ってよ、後ろが詰まるじゃない。」 千晶によく似たこの声は愛場明。千晶の二卵生の双子の姉。ちなみに後半の台詞は兄さまに言ったらしい。彼はわるいと言って教室内に入ってきた。それにしてもタメ口の上あだ名呼びとは、相手は先輩だろうに。 にわかに教室内がざわめき始めた。廊下が騒がしかったのはこいつらのせいらしい。だって、こいつら無駄に目立ってるし。 顔は一般陣の域を出ていないのに何か大物オーラを放っている美千代。(陽が兄さまをこう呼んでいる) 超絶美形、黒髪サラサラの陽、そして照。 そして照に肩を抱かれているどう見ても美少女にしか見えない金髪蒼目の光。兄弟仲の良すぎるこいつらは兄弟に見えないところがなお悪い。変な勘違いをした奴も多いだろう。 「白鳥君、登君と並んで。――はい、笑って。」 なぜここで写真を撮る、幻十郎。 「次は千晶と私。」 「なんで俺が。」 「あら、お姉さまと写真撮りたくないの?」 千晶をカメラの前に連れていく明。高校一年にあるまじきダイナマイトボディにはっきりした顔立ちの美人。千晶は彼女に逆らえた例がない。 変人どもに囲まれて、入学早々目立ちまくった千晶は、これからの高校生活に波乱の予感を禁じ得なかった。 ****** シャー… 狭いバスルームでシャワーを浴びるのは細身で小柄な少女。控えめな胸はAAカップ。 少女は脱衣所に上がり体を拭く。パジャマをきようと手を伸ばしたところでその動きを止めた。 「おい、明!?なんだよ、このひらひらした服!」 脱衣所の扉を開け、そう吠えるのは短いふわふわの赤毛に、大きな釣り目にくるくる睫毛の女の子。 「あら、似合うじゃない。」 「俺がこういう服が嫌いだって知ってるだろう!?」 「良いじゃない。可愛い妹には可愛い服を着せたいのよ。――千晶。」
ここが我らの城
高校生活二日目。ぽかぽかと暖かい日差しが降り注ぎ、街路樹やアスファストを柔らかに照らし出す。上級生ともなれば、裏道をガンガン使って、最短距離で登校するようだが、まだ入学したての俺としては、道に慣れるまでは大通りを使うつもりだ。 朝は時間ぎりぎりに出て、慌ただしく登校するのが一般的だと思っていたのだが、進学校の生徒はそういうところの意識まで違うのか。自分としてはずいぶん早い時間に家を出たつもりだったのに、信号で同じ制服が列を為すほどに通学路は賑わっていた。 通常ならば、集団の中に埋もれてしまうチビで地味な千晶。しかし、今回は埋もれることなく、周囲の注意をひいていた。ちらちらと投げられる視線は彼女の右手に。 彼女の右手は隣の美女の左手としっかり繋がれている。シスコンの姉はいつまでたってもシスコン。しかし、保育園のころから変わらない彼女の要求に、答えてしまう千晶もまたシスコンと呼ばれても仕方ないのかも知れない。 春うらら、窓から差し込む日差しは柔らか。眠りへ誘う、魔法の薬。 春の日差しの魔力に午前も午後も関係なし。いや、確かに午後の方が勢力は増すが、午前だって眠くなるという話。 それでもさすがに入学したてで堂々と眠りこける奴などいない。話を聞いているかはともかく、視線だけは黒板に向いている。そんな中、 「白鳥、よそ見するな。」 注意を受ける彼はいったい何を考えているのだろうか。 「あ、はい。」 すぐに教壇を向く彼は本当は真面目な筈。しかし、 「白鳥。」 「すみません。」 二度目の注意に、言葉では反省しつつも、やはり視線は斜め前に向いてしまう。その視線の先には愛場千晶。彼、白鳥昇は視線の先のその子が可愛くて、可愛くて仕方ない。 しかし、そんなことは授業を聞かない理由にはならない。 「そこ、仕切り作ろうか?」 「ええ!?そんなぁ!」 「冗談だ、馬鹿者。」 素っ頓狂な声を上げた彼は、頭を教科書で叩かれクラス中に笑われた。 ****** 「おまえさぁ、それどうにかなんないのかよ。」 千晶は休み時間ごとに席に来る大男に呆れた顔を向ける。 「だってぇ…。千晶が可愛すぎるのがいけないんだもん。」 情けない顔でそう漏らす彼は、怒られた大型犬のように見えた。垂れた耳と尻尾がお似合いだ。 「可愛いって言うな。」 眉間に皺を寄せる彼女は、誰よりも男らしさを求めている。制服も男のものを着るし、男として学校生活を送っている。 そんな彼女に可愛いは、全くほめ言葉にならなかった。 「なんで席こんなに離れてるんだろう…。」 彼女がどんな顔をしていても気にしないのがこの男。昇は席順に文句をつけてうな垂れる。 「お前がでかすぎるのが悪い。」 「席が背の順ってのがおかしいんでしょ!?」 そう、この学校の席は、名前でなく背の高さで決められていたのだ。廊下側の一番前が一番背の低い奴で、窓側に向かって二番、三番と徐々に背が高くなっていく。一番端まで行ったら廊下側に戻る。 愛場だから一番ではなく、一番チビだから一番… 入学早々プライドをズタズタにされた気分だった。 お前より俺の方が席順には不満があるんだよ。そう思って、千晶は彼を冷たく突き放す。 「名前順だって近くないと思うけど。」 「…ちっちゃい男の子可愛い。可愛いは正義…」 バチンッ 「無言で叩かないでよ~…」 「うるさい。」 人の話を聞かないうえに本当にまったく失礼なショタコン野郎を思い切りぶん殴ってやった。 「お前、千晶?」 「そうだけど?」 昇と騒いでいると、入口から三人組の男子が声を掛けてきた。 彼らはお互いを小突きあうと、にやにや笑ってこっちを見てくる。 「なに、なに。こいつシスコンな上にホモなわけ?」 「はぁ?」 喧嘩売ってんのか?なら、買ってやろうじゃねえか。 千晶が立ち上がろうとすると、それよりも前に教室の中央でガタンと大きな音がした。 「ちょっと、聞き捨てなりませんね。」 勢いよく立ち上がった照が、凄味をきかせて近づいてくる。 「兄弟愛最高!光は正義!」 「照!」 照が宣言すると、光が窓をあけて入ってきた。どっから入ってきてんだよ、おまえ。 「そうだ!兄弟愛は正義!」 千晶の突っ込みを待たずに今度は三人組のいるドアの横の窓が勢いよく開け放たれ、美千代と陽が顔を出す。 「兄様!?」 「昇!」 「お昼誘いに来たよ。」 「陽!」 「陽君!」 「どうどう。」 陽は窓を隔ててぎゅうぎゅうと抱きつく弟たちをなだめた。しかし、どうどうは牛に対するものではなかったか。 「じゃあ、兄弟愛を確かめつつご飯食べに行こうね。明は隣の教室かな?」 「あら、私も呼んでくれるの?」 「明!?」 「やっほー、千晶。可愛いは正義。」 陽の後ろから現れた明は昇のセリフを真似して千晶に手を振った。 「可愛いって言うな。」 千晶は顔を真っ赤にして吠える。まったくいつから聞いてたんだ。 「可愛い、可愛い。」 「うるさい。」 カシャカシャッ シャッター音に場が静まる。 「いやー、まったくカメラの回しがいがあるメンツだよねー。目の保養、目の保養。」 人の影に隠れた幻十郎がカメラを構えていた。 ****** 「おおー。スゲー…」 「やるじゃない。」 「すごーい!」 「わー」 「ふぇー」 案内されたのは、本校舎とは少し離れた所にある別館。緑でないのに何故か緑館と呼ばれるそこの二階最奥。一年五人はそれぞれ感嘆の声を上げた。 床にはインディアンチックな絨毯が敷かれていたので、上靴を脱いで上がる。 中心に置かれた木の机とクッションの置かれた樽の椅子。机の上に瓶の蓋で飾られた金物のバスケットに花が飾られ、窓辺にはロッキングチェアが、壁際には皮製のソファが置かれている。アンティークの戸棚には、ティーセット。お菓子も充実しているようで、見えないところには電気ケトルまであった。 「去年一年で使いやすいように改良させてもらったからね。」 陽の言葉に千晶は首をかしげる。改良…改造? 「このカーテンの生地ずいぶん良くないか。」 「暑い生地じゃないと冬場寒いからね。」 余り布を縫い合わせたようなカーテンは、見た目によらず上質だ。生地を見る千晶に陽は当然のことのように答えるが、厚手のカーテンはそれなりに値が張るものではないのか。 「このソファいい感じ。」 「イタリア製だ。」 昇に応える美千代は、別に得意げでもなんでもなく、事実を述べただけという淡白さだ。 なんだ、金銭感覚が違うのか。 もう一度部屋を見渡すとあることに気が付く。面積が広すぎて意識していなかったのだ。 「壁紙まで変えてんのかよ…。」 黄ばんで傷や汚れだらけの筈の壁が白くきれいで、おまけに家や木などの街並みのイラストが並んでいる。改良の域を超えていた。いざ、元に戻せと言われた時どうするつもりなのか。しかし、千晶の心配は次の美千代の言葉で杞憂と分かる。 「理事の許可は取ってある。」 「何それすごい。」 「親父だけど。」 「…。」 「相変わらずお前の弁当うまそうな。」 「照の愛がこもってるからね。」 覗き込んできた美千代に陽は得意顔だ。 部屋について、色々思うところはあったが、要は居やすければそれでいいのだ。一行は当初の目的であるランチタイムに突入していた。 そして、当の照は例のごとく光といちゃつく。 「光、これ光の好きな肉じゃがコロッケだよ。あーん。」 「あーん。おいひー!照もあーん。」 「…おまえら相変わらずだな……。」 呆れる千晶に見向きもしない。 「昇も、あーん。」 「兄様もあーん。」 「こっちもか!」 「あははっ!」 吠える千晶に幻十郎だけが楽しげだ。いや、この場合千晶だけが楽しげでないと言った方が正しいか。 本日何度目か分からないため息をつく千晶に、今度は明が箸を向けてきた。 「千晶、千晶、あーん。」 「!?」 一瞬きょとんとして、首を振る千晶。 「いやいやいやいや。」 これをやったら、俺もバカップルの一員か? 「!千晶、あーん!」 便乗した光が嬉々として、スプーンを向けてくる。 「千晶。」 陽、何故お前まで。 「千晶あーん。」 そして、また食べ物を差し出す照はいつになく楽しげで、こんなに沢山の種類のものをいっぺんに口に入れたらどうなるか分かるだろうに。ドS心が透けて見える。 「あ、みんなずるいよ!千晶、あーん!」 昇まで、まあやると思ったけどな。 「さあ、千晶くんは誰を選ぶのか!?」 「え、何。そういう企画?」 外野二人も助けちゃくれない。 「お前ら、面白がってるだろう!?」 「楽しいは正義!」 結局、全部を一気に口に入れられて、千晶の口の中はワンダーランド状態になりましたとさ。
二人はキュアキュア!
高校生は、ノリで行動することが多々ある。 この日の発端は、光と照の些細な諍いだった。 「照が僕を好きなのより僕の方がもっと照のこと好きだもん!」 「光が俺を好きなのより俺の方がもっともっと光のことが好きだよ!」 「僕の方が好きだよ!」 「俺の方が好きだよ!」 「照の分からず屋!」 「光の方こそ!」 「照なんか知らない!」 「ちょ、どこ行くの光!」 そうして始まった鬼ごっこ。いつの間にか巻き込まれた千晶と昇。そしてそれはかくれんぼへと移行して… ****** 緑館を出て、本館に入り、渡り廊下を渡る。屋根があって、簀子が敷いてあるだけのほぼ室外。 梅雨入り前の乾いた風に、緑の若葉が舞い落ちて、行列を為す蟻の間に割り込んだ。列は葉を避けて二つに分かれてまた合流する。 渡り廊下を渡ってすぐの体育館では、屋内スポーツの運動部が昼の練習中でにぎわっている。バトミントン部の邪魔にならないように、端に敷かれた緑のマットを踏んで倉庫にたどり着く。 かくれんぼは昔から得意だった。千晶の小さな体は、鬼の気が付かない隙間に潜り込むことができたから。暗く、鉄臭い、ものに溢れた倉庫は、千晶が隠れるのにうってつけだ。どこに入り込もうかと、跳び箱の上を外す。 がらっ 「千晶!」 「うわっ!」 閉めた扉が勢い良く開け放たれ、そこから光が流れ込む。 音と声に驚いて、千晶は声を上げた。 節電目的で電気を付けていない体育館からの、人工的でない光はやはり春の香りがする。しかし、柔らかな光は、暗さに慣れ始めた千晶には少し強い。 眩しさに目をしかめると、少し慌てた様子で入ってきた昇がすぐにその扉を閉めて、光は消えた。 「照が来る!」 「まじでか。」 急いで跳び箱の中に入ると、昇も一緒に入ろうとしてきた。 「ちょ、おま、…それは無理だろ!」 「いやー、入れてー!」 「いやいやいや、お前、自分の図体考えて!?」 しかし、ちっこい千晶と、背は高くてもひょろい昇は、わあわあ言ううちに二人とも跳び箱に入ることができた。密着度は押して知るべし。 「…おまえ、バカだろう。」 「だってー…」 昇が足を上に投げ出したような歪な体育座りをして、千晶がそれに向かい合わせにまたがる格好だ。千晶の頬にあたる彼の髪は柔らかく、暖かい。密閉された空間に、彼の匂いだけがした。 ――あれ、これやばくないか?だって、ほら、俺、女ってばれるんじゃないか?この密着度。 千晶が居づらそうにしていると、何を思ったか、昇が動いて、足と手の両方で彼女を引き寄せ、抱きしめる。 「!?なにっ」 「あ、ごめん。膝が辛くて。」 千晶は、感触で女だとばれないように、力を入れて体を硬くする。胸が当たらないように手で相手の胸の間に壁をつくると、そこから鼓動が伝わってきた。 どくどく、どくどく 明らかに通常よりも高い心拍数に、つられて千晶まで緊張してくる。ついでに、頬まで熱くなってきて、良く分からない気持ちになる。 「――っ、おまえ、ホント…。この、ショタコン…。」 「ひどい!千晶が可愛すぎるのがいけないんでしょ!?」 「な!?ばか、耳元でしゃべるな…っ」 鬼に見つからないように、絞った声は吐息の量が多くて、熱が直に千晶の耳を刺激する。ぞくっと背筋を得体のしれない感覚が這い上がってきて、小さく体が震えると、昇がごくりと唾を飲みこんだのが分かった。すぐにシャツの間に彼の手が入り込んできて、脇腹を滑る。 「なに…っ!?」 「ごめん、千晶…っ」 またも耳元で囁かれ、そのまま耳を食まれる段階になると、千晶は、情報を処理できなくなるほどに混乱していた。抵抗しようにも、狭くて体の自由がきかない。 ――やばい、これはやばい。何がやばいのか分からないけど、とにかくやばい。 背中から侵入した手は、前に回って、徐々に上に上がってくる。AAカップの胸はブラを必要としていなくとも、わずかな膨らみはあるわけで、だから―― 「止めんかっ!!」 その手がそこに触れる前に、頭突きを食らわせ気絶させた。 ****** 「あ、千晶。」 ジャージ姿の小柄な子を発見して、声をかける。何をしていたって、昇の千晶センサーは素早く反応するのだ。 しかし、振り返ったその子は髪の色は彼と同じだが、花柄のパッチン留とクロスピンで前髪を留めた、ぱっちり目の女の子だった。 この気持ちは何だろー♪ この気持ちは何だろー♪ 春です。 季節は夏が来ようという所ですが、今、俺には春が来ました。 浮かれた昇は放課後、弁当箱が無いことに気が付いた。緑館かな、思って、そこに行くと、壁際のソファで千晶が寝ている。 「うーん…」 横を向いて丸くなる千晶は、首が傾いて寝づらそうだ。 膝枕をしてあげると、気持ちよさそうに頬を摺り寄せる。 ――うわあ、かっわいい! そのまま千晶が起きるまで寝顔を眺めていることにした。 「ぅん…」 頬を撫でられる感触に目を覚ますと、昇が真上から覗いていた。 「おはよう、千晶。」 「…何してんの?」 「膝枕。」 髪や頬を撫でていた彼の手が離れていく。 「あ。」 「あ?」 「…いや、なんでもない。」 何となく淋しくて声を上げてしまった。 ほら、あれだ。そういうんじゃなくて、さ。温かかったから名残惜しかったってゆうか。 起き上がった千晶は自分の頬が赤らんでいることに気が付かない。 「あ。」 「あ?」 「いや、なんでもない。」 今度は昇までもが声をあげた。 腿のあたりを擦る彼が、何を思ったか理解して、千晶はぼっと顔を赤くする。 「…あのさ、千晶。」 「…なんだよ。」 「…触って良い?」 「はあ!?」 昇は返事を待たずに千晶を腕の中に収めた。 彼の手が、頬を撫ぜ、指が耳を引っかける。 ――なんだよこれ…っ 「…千晶。」 襟元に顔を埋めて、彼がささやかくと、千晶の口から、ふぁっと熱い吐息が漏れた。 「なんなんだよ、おまえ。用があって、起きるの待ってたんじゃないのかよ。」 千晶が言うと、昇がバッと顔を上げる。その距離が予想外に近くて、うわぁ、となった。 「あるある!千晶に報告!」 「なに。」 「俺、好きな人できたみたい。」 「はぁ。」 「小柄な女の子でね。俺、初めて女の子のこと好きだなって思ったんだよ!」 わんこのように瞳を輝かせる昇に、なんだろう。むしゃくしゃする。 だって、そうだろ?今の体勢。だれがどう見てもこいつが俺を襲っているようにしか見えないわけだ。 「この状況でそんな話をするか。」 というかだ、いつも俺のこと好きだとか可愛いとか言ってのは何だよ、いや、別にその気になってたとかではなくて、 「ねぇ、どうしよう千晶。どうしよう。」 「だまらっしゃい!」 千晶ははしゃぐ昇にアッパーを繰り出した。
ショタコンでロリコンで二股をかける
土曜の13時。梅雨に入るか入らないかの不安定なこの時期だが、今日は快晴。 開けた窓から、そよぐ風が、ぽかぽか穏やかな太陽の香りを運んでくる中、愛場千晶は居間の机に向かっていた。 フローリングに敷かれた薄いマットは糸が所々解れている。アメリカンなタッチで描かれた自動車や、道路標識のイラストは明も千晶も気に入っていたが、そのプリントも色あせてきた。いかんせん安物だ。 今日は朝からクッションも敷かずにそのマットに座って課題に向かっていたから、腰が痛い。千晶はクッションを取ろうと手を伸ばしたついでに伸びをした。 しかし、その手はクッションにたどり着く前にぱたんと落ちる。 ああ、何もしたくない。 いつもなら、こんなに天気のいい休日は、喜び勇んで外出している。本来アクティブな彼女だ。宿題だって、そんなにあるわけじゃない。普段なら三十分で終わらせて、出かけている。だからそれは理由にならない。 千晶は横になったまま動くことを止めた。 「千晶、まだ宿題やってるの?」 「ああ。」 明が部屋から出てきた。姉妹の共同の部屋は居間に直接つながっている。 千晶は意識せずに返事して、のったりと身を起こした。 「朝から進んでいないように見えるけど。」 「ああ。」 あからさまに空返事をする千晶に明は眉を顰める。 「…千晶、新しい薬ができたんだけど。」 「ああ。」 これは重傷だ。 中学時代に自らで立ち上げた「世界の不思議研究会」の会長である明は、時折、魔術や薬の実験に千晶を使う。今までに冗談でなく多大な被害を受けてきた千晶が先のセリフを聞いてとる行動は窓から飛び出しアパートの庭木を伝って逃げる、だ。こんな気の抜けた返事をすることじゃない。 千晶が昨日からおかしい。生気が無いというか、ずっとぼーっとしているのだ。まあ、原因は見当がつく。 「愛しの彼と何かあったのかしら?」 「誰がっ!」 かまをかけたら、バッと千晶がこちらを向いた。 素直すぎる反応に、明は楽しげに目を細める。 「あら、やっとまともに反応したわね。それじゃ、出かけましょうか。」 「はあ?」 「あら、やだ。昨日言ったでしょ?」 にっこりとほほ笑む明に薄ら寒さを感じながら、千晶は昨日の会話を思い出そうとした。 昨日…。昨日の夜、昇に好きな子ができたと聞かされた夜だ。自分は何をしていたか…。 ヤバい、覚えてない。 「私とまゆちゃんと、新しいマットを買い行く約束したでしょ?」 まゆちゃんとは、二人の共通の年下の幼馴染で、世界の不思議研究会の一員でもある、ツインテールの可愛い女の子だ。 「…マジでか。」 「あら、約束を破るのは男らしくないわよ?」 「行かないなんて言ってないだろ!」 誰よりも男らしさを求める女、千晶は「着替えてくる!」と自室に入った。 着替えて自室を出ると、明が千晶の頭からつま先までをスッと目で確認して不満げに顔を顰めた。 「どうして私の用意した服を着てこないのよ。」 「…誰があんなビラビラ着るもんか。」 千晶の選んだ服は襟を広く丸くカットしたベージュのシャツに、パンツ部分がサルエルになったカーキのオーバーオール。色を落としたトリコロールのヘアバンドと赤の伊達メガネだ。 一方、明が用意した服はシフォンの白い丸襟ブラウスに、アンティークな雰囲気のバラ柄のキャミソールチュニックと裾にレースのついたレギンス、リボンのついた赤い水玉カチューシャに、コルク加工の厚底の赤い網紐サンダル。 事あるごとに千晶に女の子らしい恰好をさせようとするのはこの姉の悪い癖だ。どこから金が出てくるのか知らないが、まあ大方貢がせてるんだろうけど、金はもっと有意義に使えばいいのに。 「折角のお出かけなのにー。」 未練たらたらな彼女のことは無視させていただく。「さっさと行くぞ」と千晶は踵を返した。 ****** 月曜日。 白鳥昇は朝から何やら心痛な様子だ。その顔にいつものゆるゆるの笑顔は無く、時折ため息をついたりする。授業中、千晶を見てしまうのは相変わらずだったが、今日は、無意識に視界に入れていしまうと、慌てて目を逸らす、ということを繰り返していた。 机に突っ伏した昇は、悩ましい唸り声を上げた。 彼は見てしまったのだ。一昨日、某デパートの長椅子に女の子とで仲良く腰かけている千晶を!大好きな千晶が女の子とデートしているところを! 「デート!?やっぱりデートなのぉ!?」 ツンテールの女の子は千晶と同じくらい小柄で、可愛くて、遠目で見てお似合いだと思った。 うわーん、と頭を抱えて身悶える昇。それを直視してしまった藤本照。 昼休みが始まったばかりの教室は、がやがやとにぎやかだ。自分が彼の奇行に気づかなくってもおかしくは無い。照は面倒事はごめんだと無視することにした。が、照の視線に気づいた昇が、「どうしたのって聞いて~っ!」と、縋りついてきたから無理だった。 「――て、訳なんだよ。」 謎の少女と一昨日の千晶の話を聞かされた照は、はあ、とため息を漏らした。 「その子は千晶の彼女じゃありませんよ。」 「え!?ホント!?」 「その子のことは俺も良く知っています。木下まゆ、明と千晶、俺と陽、光の共通の幼馴染です。特に明と仲が良くて、千晶はその二人にいつも振り回されているみたいですよ。一昨日も明もいたんじゃないですか?ベンチに座っていたんでしょ、明が手洗いに行ったのでも待ってたんじゃないですか。」 「そっか。」 よかったー、といつものだらしない顔に戻った昇に、照がボソッと漏らした。 「まったく、ロリコンでショタコンって…。」 「え?ショタコン……て、ええっ!?」 その言葉に驚く昇にこっちの方が驚く。これはもう、呆れるを通り越して尊敬に値するのではないだろうか。 「まさか、無自覚だったんですか?」 「え、だって、だって、え!?」 千晶のことは好きだし、いつも好きだって言ってるけど、けど、一昨日のだって、友達だったら彼女がいたって羨ましいくらいにしか思わないんだろうけど、けど! 「……それって二股じゃん…」 「そうですね。」 「しかも、片方男じゃん…」 「そうですね。」 ショタコンを自覚していても、それは愛玩するという意味であって、真剣に一人を(この場合は二人か)好きになったのは、実は初めてである。昇は長身を丸めて、うぅー、と唸り声をあげた。 ****** 放課後、一番の電車は学生の帰宅ラッシュだ。 普段なら、ここまで混んではいないのだが、テスト一週間前になって、部活動が休みになったために、いつもの三倍近くの混みぐあいだ。ここが都会なら、人混みを避けて一、二本電車を見送くったりするのだろうが、あいにくここは田舎だ。この電車を逃せば次は40分後。照は身動きが難しいほどの圧に辟易とした。 ところで、痴漢に遭いやすい場所というのがある。それは車両の隅であり、角であり、一番壁に囲まれるところで、人に気づかれにくいポイントである。 自分の容姿を分かっている照は意図的にそこを避けていた。しかし、何故か今自分はそこにいる。しかも、誰かが背に張り付くように立っている。 くそっ、誘導されたか。 「…久しぶり。」 耳に吹き込まれた声に悪寒が背筋を駆け上がる。 「っ、おまえ――」 そこからが早かった。背中のそいつは後ろから照の手を取ると、あっという間にネクタイで縛り上げたのだ。 「声、我慢してね。」 言葉とともに耳朶を食まれて、息を詰めて肩を竦める。そいつは硬くなった体を慰めるように首筋に口づけた。 「ああ、滑らかな肌…」 肩に頬を擦りつけて恍惚するそいつ。普段触られる場所ではないから、無性にくすぐったい。照は口を一文字に結んでその感触に耐えた。 「――っ」 指で、背をつつつ、となぞられて、背筋が反り返る。 「っ、可愛いっ!」 すると、感極まった様に抱きしめられた。間近に感じる息が荒い。まったくこいつは… 「本当は色々したいんだけど、声出すとばれちゃうから、胸だけで我慢しておくよ。」 気遣っているのかなんなのか、まったく嬉しくない申し出だ。ばれたくないなら止めれば良い。 すぐに、つんっと両乳首を突かれて照は体を縮こませた。 そいつの愛撫は、認めたくは無いが、気持ちが良い。ゆっくりと乳輪をなぞったり、しこりを確かめるように転がしたり、尖った先端を押しつぶしたり。強すぎない刺激が快感だけを与えてきて、体の熱が一か所に集まるのを感じた。いっそ痛いくらいだったら、我慢できたのに…。 「気持ちいい?」 「…っふ、ぅ…っ」 時折漏れる吐息にそいつはごくりと唾をのんだ。次の瞬間、股間にダイレクトに刺激を与えられ、照は酷く狼狽した。こともあろうに、そいつは縛った俺の手をそこに押し付けたのだ。 「おまっ、バカ…っ」 悪態をつこうと開いた口を片手で塞がれる。少しでも快感を逃がそうと、こぶしを硬く握ると指の関節がゴリゴリとそこを刺激して、逆効果だった。 やばい、やばい、やばい――っ もう、イクっ と思ったその時そいつの体温が離れた。助かった思う反面、一番つらい状態で突き放されてどうしようかとも思う。 どうしたのかと振り返ると、そいつの俺の手を押さえつけていた方の手を、昇が掴んでいて。第三者の介入に照は顔面を蒼白にした。 満員電車で照を見つけた。しかし、様子がおかしい。 何とか近づいてみると、なんと痴漢に遭っていた。しかも、相手も高校生だ。一まとめにした長髪がいかにも変態っぽい。あの制服は確か、5つ6つ向こうの駅の学校だったように思う。自分ほどではないが、背が高くて、照がすっぽりと見えなくなってしまっている。これでは注意してみなければ痴漢だとは分からない。 昇は男の手を掴んで照から引きはがした。 こちらを振り返った照の目が見開かれ、元から白い顔がより一層白くなる。ああ、怖かったんだね。もう大丈夫だからね。 「何をしてんの――っ、て、照!?」 早速男を問い詰めようとした昇の手を照が掴んだ。丁度よく駅に着いた電車の扉がプシューと音を立てて開くと、照は二人の手を掴んで飛び出した。 「白鳥。」 「な、なに。」 「実はですね。」 電車が三人を残して走り去っていった。いつになく真剣な様子に固唾を飲む。 「この男、俺の彼氏なんです!」 「ええ――っ!?」 こ、こここここの痴漢が!? よく見れば、照には劣るがすごく整った顔をしている。黙っていればお似合いの二人に見えなくもない。しかし、痴漢だ。 「照!彼氏なんて言ってくれたの初めて!」 抱きつこうとした男を照が蹴り飛ばした。 「うるせぇっ!どこでも盛ってんじゃねぇって言ってんだろ!!」 「ああん、辛辣。だけど、そこが痺れる、憧れる~っ」 「死ね!」 「殺して!」 何これ!?俺、こんな照知らない! 目の前の光景に昇が驚愕していると、目をひくつかせた照がホームのベンチに膝を抱えて座った。 何これ可愛い。 「つまりさぁ。」 ああ、彼のことは放置するわけね。 「ホモなんてざらいるってことですよ。」 いないよ。 「だから、男だからって千晶を切り捨てるのはおかしいですよ。」 その言葉に昇は瞳を瞬かせた。 おまけ。 次の電車が来るのは40分後。3人で待つなか、照は落ち着かない。身体の熱が収まらないのだ。その肩に、隣に座った恋人、影木診が手を添える。それだけでぞくっと小さく震えた。 「照、何恥ずかしいフリしてるの?」 それは膝を抱えたこの体制をいっているのか。 「ああ、恥ずかしいのか。――ここが。」 「ぁ…っ」 膝の隙間から手を差し入れられて、張りつめたままのそこをなぞり上げられる。思わず漏れた声に前に立っていた昇が振り返った。 「どうしたの?」 「別にどうもしない。ちょっとトイレ行ってくる。」 診は涼しい顔で俺の手を引いて行った。
僕のヒーロー
真夏の空を映したスカイブルーの瞳が輝く。みずみずしい肌が汗をまとって輝いた。 金糸の髪と水色のランドセルが背中で揺れる。 その夏、少女は少年になった。 藤本光はその美貌を持って、入学当初から異彩を放っていた。 オーストラリア人の母を持つ光の目は、吸い込まれるような蒼色。雪のように白い顔の中で、頬が薄桃色に色づいて、唇はぷるんと潤いを持っていた。長い金髪にかかる光の輪は正に天使の物。レースやリボンをふんだんに使ったワンピースも、光を引き立てる側にまわっていた。 可愛い、お人形さんみたい。子供たちは、すぐに光と仲良くなろうとした。 誰にでもすぐに懐き、表情豊かな光は、多くの子供たちに好かれた。しかし、中にはそれを疎ましく思う者もいる。幼い心でそれを十分に理解できなくても、何かもやもやとしたものを感じる者が。 それでも誰も行動を起こさなかったのは、光の他にも、照や明といった目立つ存在が居たおかげで嫉妬が分散されたから、子供たちの中心にいる器をもつ子に光が可愛がられていたからだ。子供は時に打算的な考えもする。 しかし、その夏、その均衡が破られた。 藤本光が七歳になる年の7月。小学校はプール開きを間近に控えていた。 立派な寝殿造りの屋敷の一室で、光は、父・陽一、母・オリビア、兄・陽、照と向かい合っていた。 「光、実は貴方に隠していたことがありマス。」 「なぁに?」 拙い日本語を話すオリビアに、ほわほわと返事をする光。 「実は、貴方は男の子なんデス。」 「だから水着は海パンなんだ。」 「海パン?」 陽一は、きょとんと首を傾げる我が子に、唇を噛みしめた。 「最初は、光が本当に可愛かったから、女の子の恰好をさせてみたくなりマシタ。そうしたら、やっぱり男の子と女の子じゃ着せられる服も違うし、楽しみも違う。私は止めるタイミングが分からなくなってしまいマシタ。」 オリビアがガバッと頭を下げる。他三人もそれに続いた。 「今まで騙していてゴメンナサイ。」 「騙していて悪かった。」 「僕も黙っててごめんね。」 「ごめんね。」 四人に頭を下げられて、光は傾げた首を元に戻した。 「ピカリン、男の子なの?」 神妙に頷く四人。 「分かった。」 ほわほわと答える光は本当に分かっているのか、四人は不安を捨てられなかった。 実際、この時光は、事の大きさをまったく理解していなかった。そのことに気付いたのは、翌日、このことをクラスで告白した時だった。 長い髪をバッサリ切って、いつものフワフワフリフリのスカートでなく、ズボンを履いて登校してきた光に、子供たちがざわめいた。 小学校では、兄弟はクラスを別々にされる。だから、光は一人で、告白した。 「ピカリン、本当は男の子だったから、今日からおズボンを履いてきます。」 その時、クラスの空気が変わった。 男だってさ、気持ち悪いね、 いままで気づかないもん? わけわかんない、 ひそひそと交わされる言葉に、光はどうして良いか分からない。光は、今まで皆に愛されて、守られて育ってきた。黒い感情に免疫が無いのだ。 「女男じゃん。」 一人の言葉に周囲が同調する。 女男じゃん。 女男、女男。 天使の顔が歪んで、大きな瞳から涙がこぼれた。 誰かが音を立てて立ち上がった。 「泣くな、男だろ。」 立ち上がった愛馬千晶が強い視線を向けていた。 次の日、男の子のような恰好で登校した千晶は、 「今日から俺も男になる。男は強くなくちゃいけないから、今度、合気道を始めるんだ。光、お前も強くなれ!」 と、小さな歯を見せてにぃっと笑った。 その時、千晶は僕のヒーローになった。 ****** 外は生憎の天気だが、室内は蝋燭を模したシャンデリアのおかげで、優雅な光に満ちている。 部屋の隅の上質なソファーには、二人の男子生徒が腰かけていた。 ソファーの前のガラスの机に置かれた、ダークブラウンの液体を注がれたグラスは、露を纏って輝く。秘密の部屋は、コーヒーの香ばしい香りに包まれていた。 生徒の一人、藤本陽が、そのグラスにミルクを注ぐと、白い波紋が広がる。 「学校のセキュリティーが強化されたらしいな。」 話しかけられたもう一人の生徒、白鳥美千代は、ブラックのままのそれをすでに口にしていた。 「ん?ああ、昇が入ったからな。」 「あの噂、本当だったんだ。」 「噂?」 「セキュリティー強化に白鳥財閥が関わってるって噂。」 「ああ。」 「長男は美千代なのに、どうして美千代が入学したときにやらなかったんだ?」 「だって、俺だったら、最悪の事態になる前に猫になるだろ。」 そう、美千代は平気な顔をして答えた。 美千代という少年は、少し特殊である。 守護霊が猫なのだ。人間と相性の悪い守護霊は、守護する力にかけた。そのために、美千代は、霊媒体質であり、その上、人間の負の感情までもを背負ってしまう。 そして、その穢れが彼の許容量を超えた時、彼は、最終手段で猫になる。 穢れは、彼や他人の嫉妬であり、悲しみであり、苦しみだ。猫になれば、大抵の場面から逃れることができるだろう。しかし、それは彼の心が限界に達するのと同義だ。 陽は美千代をぎゅうぎゅうに抱きしめた。 「陽?」 「……」 無言で抱きしめてくる腕に、心が温かくなる。 「…ありがとな。」 顔を上げた陽。絡まる視線。 二人はどちらからともなく口づけを交わした。 昼休み。 外は嵐だ。ニュースでは竜巻が来ると言っていた。 本校舎から、緑館までの道に屋根は無い。傘をさしても、この暴風雨の前では意味をなさないだろう。 光も、照も、千晶も、今日は教室で過ごすようだ。しかし、昇はだからこそ緑館に行こうと思った。 千晶のことを意識した今、彼に今までと同じに関わることはできない。あんなにもスキンシップを平気で出来たのは、同性であり、そういう対象ではないと思っていたからだ。 しかし、己の気持ちに気づいてしまえば、それはできない。昇は彼との距離を測りかねていた。 男に好かれているなんて、普通は気持ち悪いだろう。しかも、二股なんて、――最低だ。 小さく息をつくと、昇は雨の中へと駆け出した。少しの距離でも、ずぶ濡れになる。 薄暗い廊下を歩いていくと、秘密の部屋から声が聞こえた。メンバーの誰かが居るのだろう。だとしたら、この扉を開けるのに問題は無い。しかし、中から聞こえる甘い声に昇はそれを躊躇った。 少し考えて、引き戸を僅かに開けて覗き見る。暗い廊下に慣れた目に、部屋の明かりは眩しくて、その光景は幻のように見えた。 ――兄様と陽さんがキス、してる。 昇の足はそこに縫いとめられたように動かない。 ――二人は、付き合っているのか、だとしたら… 昇はたどり着いた答えに愕然とした。 「昇君?」 声に振り向くと、合羽を着た幻十郎が廊下を歩いてきていた。我に返った昇は、とっさにその場から逃げ出す。 「昇君!?」 「昇!?」 背後で名前を呼ばれても、それに応える余裕は無かった。 だって、気づいてしまったから。二人が付き合っているのだとしたら、愛し合っているのだとしたら、 ――跡取りのために、自分は千晶を選べない。 ****** 昇の様子がおかしい。 この前から、明らかに距離を取られている。最初は、テスト前だからかな、とも思った。でも、テストが終わっても、その態度は変わらない。それどころか、最近では、避けられている。 「昇、なんで俺を避けるんだ。」 「え、そ、そんなことしてないよ!」 どもるし。 「俺、お前に何かしたか?」 「な、なにも!」 そう言う彼は目を泳がせているし、そわそわと、逃げる機会をうかがっている。 そんな態度にイライラして、目頭が熱くなるのを感じた。ぎっと力を入れてそれを堪える。そのまま彼を睨みつけた。 「――っ、ごめん!」 「昇!」 逃げられた! 「くそっ」 千晶は何とも言えない気持ちを教室の床に吐き捨てた。 「光。」 「なぁに?」 怒った顔で隣の教室からやってきた千晶に、光は笑顔で答える。彼女が何を言いに来たかは想像がつく。 「昇がムカつく。」 「どうしたの?」 「あんなにべたべた引っ付いてきたのに、今更…」 ぎりぎりと歯を噛みしめる千晶に、光は微笑んだ。 「良いよ、仲直りの協力する。」 「――なんで楽しげなんだよ。」 睨んでくる千晶には悪いけど、口元が緩んでしまうのはしょうがない。だって、気の強い千晶が僕に相談に来ることなんて今までなかったのだから。これは彼女の役に立つチャンスだ。 幸せになってもらわなくちゃ。だって、僕のヒーローなんだから。
ふわふわマシュマロ
山百合高校の試験は月曜日から土曜日にかけて行われる。そして、土曜日の分の振替休日が今日。 AM8:30、巨大テーマパークの最寄駅は、休日明けで気だるげなサラリーマンやOLで相応の混雑具合。千晶は人を避けながら、待ち合わせの場所に向かった。すると、そこに他人より頭一つ分とびぬけた男を見つけた。 いい目印だな。 しかし、あちらはまだ、千晶に気づいていないようだ。 「昇。――うおっ!」 声をかけて近づいたら、後ろから人にぶつかられて、つんのめった。思わず目の前の体にしがみ付く。 「ち、千晶!?」 頭上から聞こえる慌てた声。 「…大丈夫?」 見上げれば、昇が目を泳がせていて、 ――悪かったな。俺だって好きでくっ付いたわけじゃねぇよ。 「千晶?」 眉を寄せる千晶に戸惑う昇。千晶はそんな彼からぷいっと顔を背けた。 気まずい。けど可愛い。ぷいって、あからさまにへそ曲げてる目の前の子が可愛すぎる! 千晶の機嫌が悪いのは分かる。俺がいつまでもうじうじしてるからいけないんだって。でも、こんなに可愛いんだよ?俺だって、好きじゃなくなろうと努力してるんだよ?でも、こんなに可愛いんだよ!? 「千晶~、昇~!」 悶々とする昇に救いの声が。しかし、縋るように声の主を捜して目を疑った。視線の先では、水玉ピンクのブラウスにブリーチのショートデニムを合わせた、本日どう見ても美少女にしか見えない光が、兄・照を背負っていた。 知ってたけどね、照が低血圧で朝が弱いて知ってたけどね! 毎朝光に引きずられて登校する彼である。 しかし、これを救いの女神だとは思いたくない。美少女が美男子を背負う構図はすごく目立つ。周囲の目は釘づけだ。 昇の笑顔が引き攣り、隣で千晶があからさまに呆れた声を出した。 ****** 「最高の天気だね!」 張り切る光に、千晶は空を見上げる。 「曇ってるけど?」 「だから良いんじゃない。平日の雨降る直前。すごく空いてる。ビッツランドの乗り物乗り放題!」 笑顔で答える光になるほどと思う。 ビッツランドは、喜び、怒り、愛、癒し、哀しみ、恐怖の6つの感情をキャラクタービジュアル化したキュービッツ達がおりなすテーマパークである。 ちなみにこのキュービッツは、羽の付いた粒な瞳のキューブ型のキャラクターなのだが、キューブから直に手足が生えていて、しかもそれがやけにリアルなのが実にシュールだ。 ビッツランドに繋がるゲートを潜れば、そこは夢の世界。シルバニアを大きくしたような建物が建ち並び、建物の屋根から屋根へ、カラフルな旗が連なっている。コミカルな音楽に交じって、聞こえるポンッポンッという、火薬の音。 「なあ、光。やっぱ、おれチケット代払うよ。」 「なーに言ってるの。チケットは、たまたま貰ったんだって言ったでしょ?」 とか言いつつ、本当は千晶のために用意した光である。 「でも…。高いだろ?俺だって自分の分くらい出せるんだからな。お前らからすれば金無いように思えるかもしれないけど。」 昇もそうだが、光と照の家の相当な金持ちである。庶民は千晶だけだ。しかし、だからと言って、たかってしまうのは千晶の心情に反する。 「千晶のそういうところ好きだけどね。そんなに言うなら、チケット代浮いた分、普段だったら買わないもの買って楽しんで欲しいかなー。」 そう言って光は千晶の手を引いた。 ――あ、 昇の口が不自然に開く。それを、未だ目の覚めきらない照が、座った目で眺めた。 光が千晶を引っ張っていったのは、ゲート付近のお土産屋さんである。 ダークブラウンの木の床に、ベージュの壁、木の骨組みの見える天井。落ち着いた色合いの店内に、カラフルなキュービッツグッズが所狭しと並んでいた。 「やっぱり、ここに来たらまず被り物を選ばないとね。」 そう言って、帽子を選びだす光。 確かに普段の千晶だったら、こんな、この場所以外で使えないアイテムは買わない。でも、今日はチケット代だと思って奮発するか。 「キャラ的には、元気いっぱいなレンビッツが好きだけど。」 千晶は右目の周りがオレンジの星形になっているキューブを手に取った。 「えー、千晶ちゃんはピンビッツでしょ?」 しかし、光にそれを取られて、代わりにピンクのハートの目をしたキューブを被せられた。 そして、そのまま千晶の耳元に口を寄せて囁く。 「恋する乙女の千晶ちゃん?」 「な…っ」 耳に吹き込まれた吐息の感触と、呟かれた言葉に、真っ赤になった千晶は、ブルーの水滴の目をしたキューブを投げつけた。 「ちょ、商品投げないでよ。」 「うっせ、お前にはそいつがお似合いだよ!」 何とかキューブを受け止めて文句を言う光に千晶が吐き捨てる。お似合いと言われたキューブは、 「…ルービッツ?」 「泣き虫ピカリン?」 「むー」 わざと馬鹿にする口調でからかう千晶に、光は可愛い唸り声で応えた。 それを見て複雑な気持ちになるのはやっぱり昇で、 「仲良いなー…。」 と寂しそうな声を出した。しかし、その隣で舌打ちが。 「面白くないですね。」 憎々しげに呟く照。どうやら、昇以上にこの光景を気に入らない人がいたらしい。 自分は彼氏いるくせにー。と振り向けば、彼の頭の上に紫のうるうる目のキューブが座っていた。 「照……が、怖がりプルビッツ?」 「色は似合うでしょう?」 綺麗に微笑む彼は、さっきまで鋭い目で千晶を見ていたわけで。寧ろ怖いのは貴方ですっ、と昇は身が縮む思いがした。 「のーぼーるー。」 振り返れば、背中に何かを隠した千晶が呼んでいる。結局ピンビッツを被ったままの千晶、超かわいい。隣の怖い美人と違って正真正銘の癒しだ。 パールビーズとフロアスキービーズでできたピンビッツの目はキラキラきれいだけど、千晶の大きな瞳はもっときゅるるんって輝いている。でも、ここで可愛いと思ってしまうのも、昇にとって良いことではなくて、応えはぎくしゃくしたものになってしまった。 「な、なに?」 「かがめ。」 言われた通りにすれば、彼はその目を細めてにぃっと笑った。同じ目線で直視してしまった、小さな歯列が覗くいたずらっ子のような笑顔。 眩しい!眩しすぎる! 「おまえはこれな。」 ボスッと隠していたそれを被せられて、鏡で確認すると、情けなくも赤面した自分の顔の上に、緑のキューブ・癒し系のリンビッツが澄ました顔で座っていた。 ****** ゲートからセンターエリアまでの一本道では、キャラクターたちがうろうろしている。また、夜のパレードもここで行われる。 千晶は、オレンジ、赤、ピンク、緑、青、紫のキュービッツカラーとオフホワイトのタイルでデザインされた道を歩きながら、うーんと唸った。 勢いで昇に帽子を被せたけど、嫌そうじゃなかったな、と。 しかし、ちらっと昇を見れば目を逸らされて、ムッとする。 逸らすということは彼が千晶を見ていたということなのだが、ムッとした千晶はそこまで考えが及ばなかった。 「俺は子供じゃねぇ!」 千晶は、センターエリアの中心にある、城の前の噴水を囲むベンチの一つに腰かけてふてくされていた。 センターエリアにテーマカラーは無い。強いて言えばキュービッツカラー。ゲートから引き続いての、オフホワイトにキュービッツカラーが散りばめられた、ポップでキッチュな空間には、それに見合った楽しく可愛らしい音楽が流れている。 シアターでキュービッツの3Dを観たまでは良かったのだ。人の心の中で葛藤するキュービッツは可愛かったし、座席も動いたりして面白かった。問題はその後だ。 エリアの中心にある、キュービッツカラーの六つの三角屋根を持った白い大きなお城。これもアトラクションの一つであり、攻略しようと一行は乗り込んだのだが、そこで千晶が機嫌を損ねる事態が起こった。 千晶が勇者に選ばれてしまったのだ。 『キュービッツと一緒に悪の心を退治してくれる勇者はおられませんか?』 キャストに応える声は無い。立候補が無ければ選ぶのみ。 そうして選ばれたのが千晶だ。周りにはもっと幼い子供が居たにも関わらず(しかし身長は千晶が一番小さかった)。 と、言う訳で口を尖らせた千晶は、勇者が貰える、キュービッツカラーのルービックキューブに敵のように挑んでいた。 「体は子供、頭脳は大人?」 言って、光は千晶の頬にシールを貼りつけた。勇者以外が貰えるキュービッツ・タトゥーシールだ。 「体も大人だ。」 「なんか、その響きえっちぃね。」 可愛い顔して何を言うか。ふざけたその額をぺチンと叩いてやった。どうせ効きやしないけど。 光とじゃれていると、その腕をとられた。大きな手は昇のものだ。 実は、仲睦まじい二人に業を煮やして、咄嗟に手を出してしまった昇である。そして彼はそのまま固まった。 (うわ、柔らか…っ) 「なんだよ?」 「い、いや、そのっ…」 無意識にやってしまった行動であることと、掴んだ腕が予想以上に柔らかったことに慌てる昇。 「?」 不思議そうに見てくる千晶に、咄嗟にシールを一枚とって突き出した。 「俺のシールもあげる!」 ふにっ 指先に、とってもとっても柔らかな感触。確認すれば、千晶の頬に昇の指がめり込んでいて、 ――ま、ましゅまろほっぺだぁ 昇はしゅぅぅ、とその場に蹲ってしまった。
ほろ苦タピオカコーヒー
「あ!」 光の大きな声に千晶と照が振り返る。そこには照の頭の帽子と同じ顔の着ぐるみが立っていた。 三人の視線に晒されたそれは、低い声で「プルビッツビー」と叫びながら駆け出した。 「あ、待って!」 それを光がしがみ付いて止める。 「やー、すごい!プルビッツだ!写真、写真撮ろう!」 興奮する光に、千晶は呆れた声を出した。 「ビッツはゲート前に沢山いただろ?」 「何言ってるの!?プルビッツは人見知りでなかなか会えないんだよ!ゲート前にもいなかったし!」 早く早く、と急かされて、千晶は未だに蹲っている昇を促した。 「ほら、昇行くぞ。」 立ち上がった彼の手を引くと、彼があからさまに動揺したのが握った手を通して伝わった。 照がキャストを捕まえてきて、写真を撮ってもらう。昇と千晶を、照と光で挟んで、ぎゅうぎゅうと密着させた。そうすることで強張る昇に、千晶はそっとため息を漏らした。 センターエリアを囲むようにビッツ達の家が建っていて、ここはプルビッツの家の前。そしてそこから先はプルビッツエリアだ。 恐怖の感情を司るプルビッツのメインはお化け屋敷。 廃病院を意識して作られた建物は、ビッツランド特有のコミカルさを持っているが、それなりにおどろおどろしい。 しかし、麗しい兄弟はその空間に居ながら、まったく恐怖を感じていなかった。 「みんな怖がらなくて、面白くないですね。」 「あはは、こういうのは陽とミー君が良いリアクションするよね。」 緊張感の無い雑談に、表情を曇らせるのは昇。美千代と陽の、あのシーンを思い出してしまったのだ。 千晶を諦めなければならない、その理由。昇は、楽しいそうな隣のその子を窺い見て、どうしようもない気持ちになった。 「お、水道の中に手があるぜ。」 「見ろよ、トイレに人形が座ってる。」 そう言って、屋敷の隅々まで見ていく千晶に光が近づいていった。 「ちょっと、千晶。もっと怖がって昇と接触しないとだめでしょ。」 「…おまえさ、さっきから思ってたんだけど、目的が変わってないか?」 光の言葉に、やや顔を赤くした千晶が、恐る恐る尋ねると、 「昇と仲直りさせるんでしょ?」 と、きゅるんと目を瞬いて光が答えた。 間違ってないんだが、どうも釈然としない。 そんな会話をしつつ、続く扉を開けると、そこは病室。個室の様で、ベッドは一つきりだ。次に進むには、この部屋を横切った先にある扉から出ていかなくてはならないらしい。 「とにかく、怖がって。」 「いや、だって…怖くねぇもん。」 そう言った矢先、ベッドの下から化け猫が奇声を上げて飛び出してきた。 「ギニャーッ!」 突然のことに、怖がるというよりは、びっくりして千晶と光は思わず抱き合った。昇は照に跳びついた。 照がふうっ、とため息をつく。くっ付く相手が違うでしょう、と。 お化け屋敷を出て、次のアトラクションはパープルフォール。地上100mの高さから垂直落下する絶叫系アトラクションだ。 待ち時間にプルビッツエリア名物のタピオカジュースを飲む。 目の前で、光が照と回し飲みしているのを見て、千晶も昇に自分のを薦めてみる。昇のジュースはオレンジで、自分のはコーヒーだ。 「昇、こっちも飲んでみるか?」 「い、いらない!」 思いっきり拒否された。 「…そうか。」 そんなに強い口調で言わなくたって、とさすがの千晶もしょんぼりした。 それを見て、昇が慌てる。 当然だ。だって、昇は千晶が好きなのだから、認めてはいけないが。 悪いのは全て自分。それなのに、千晶に辛い思いをさせて良いはずがない。 「やっぱり貰う!」 言って千晶の手からコーヒーをひったくった。 口にしたそれは、砂糖もミルクも入っていたけど、昇にはまだ苦くて、何故だか泣きそうになった。 待ち時間に暑い場所にずっといた一行は、涼しい場所目指して、氷山のアトラクションに入った。 アトラクションと言っても、寒さを体感する目的のそこは、頂上が展望台になっているというだけでしかない。 「さむいー」と言って光が照にくっ付いた。それを見て、千晶が昇の手をそっと握る。そうしたら、すぐに戸惑った顔をされた。悲しいけど、でも、放したくはない。 少しの間に、距離をとられてはいるが、嫌われていないことは分かった。さっきだって、コーヒー飲んだしな。いや、これは希望的観測かもしれないが…。 でも、手を繋ぐぐらい、良いだろ?胸の中で言い訳をして、千晶はその手に力を入れた。 ****** 「晴れた!」 青い空を蒼い瞳に移して、光が叫んだ。 そう、氷山から出た一行を迎えたのは、晴れ渡った空だった。 「今のうちにルービッツエリアに行かなくちゃ!」 キラキラ輝く笑顔の光は大張り切りだ。さっきまでの曇り空を、最高の天気だなどと言っても、やっぱり、太陽の下は気持ちが良いのだろう。 一行は光に続いて、ルービッツエリアに向かった。 憂いのビッツ、ルービッツのエリアは、水に関連したアトラクションが多くある。 その一つが涙の滝だ。このアトラクションは、乗り物に乗って、水の上をゆらゆらと進み、最終的に、滝を落下し、まあ、ずぶ濡れになる。今の時期にぴったりだ。 そして、涙の滝を攻略した千晶たちも、例にもれず、ずぶ濡れになった。きらきら光る水面は綺麗だったし、飛び散るしぶきも太陽をさわやかに反射した。良い天気に感謝。大満足だ。しかし、ここに問題が。 千晶のタンクトップが透けている。 千晶本人は、(まあ、ブラまでは透けてないから良いか。)などと思っているのだが、昇からしたらたまったものではない。濡れた服が体に張り付いて、華奢な躰の線をはっきりと浮き出している千晶を、直視できないでいた。 消えろ煩悩。消えろ煩悩。消えろ煩悩。 そう心の中で唱えて、格闘していた昇は流されるまま、いつの間にか次のアトラクションの列に並んでいた。 「スカイツアーはね、二人一組で密着して透明な筒の中を滑るんだよ。」 シュリンプクレープを差し出しながら言う光に昇は慌てる。 そんな、密着するだなんて!今この千晶と密着するだなんて!あ、そうだ!別に千晶と組むとは言ってないじゃないか! 「照、一緒に組もう!」 「背の高い同士で組んでどうするんですか。千晶と組んでください。」 ああ、希望がついえた。 頭を抱える昇に、千晶は眉を寄せる。 解せない。まったく解せない。奴の行動が理解できない。時折甘い雰囲気になるのに、拒絶される意味が分からない。千晶は違う意味で頭を抱えたくなった。 千晶と昇に順番が回ってきた。ソリに似たそれに千晶を後ろから抱き込むようにして乗り込む。濡れた布の向こうに感じる体温が生々しい。 消えろ煩悩。消えろ煩悩。消えろ煩悩。 再び呪文を唱えるが、高鳴る鼓動が抑えられない。 「後ろの方は、安全のため、前の方をきちんと抱き寄せてください。」 キャストのお姉さんに、微笑まれて、覚悟を決めた。 これは不可抗力だから仕方ないんだ、良いんだ。今このときは彼を感じてて良いんだ。開き直った昇は千晶をぎゅうっと抱きしめる。 一方千晶は、背中越しに彼の熱と鼓動を感じてしまい、妙な期待をしてしまう自分を戒めていた。 ルービッツエリアとリンビッツエリアは海中トンネルで繋がっていて、トンネルの周りは水槽になっていて、いつでも魚が見られるようになっている。 あまり深くない水中に、屈折した太陽の光が淡く差し込んでいて、とても幻想的だ。 千晶が、筒状のガラスの向こうに泳ぐ魚を見ていると、照がにやりと笑った。澄ましている彼からは想像つかない嫌な笑いだ。 「なに、千晶?魚が羨ましいですか?」 「ほっとけ。」 ほーら、きた。と、千晶は憮然と答えるが、隣の昇が興味を持ってしまっだ。 「なんで?」 「千晶は金槌なの。」 聞いた昇に光が律儀に答えて、千晶は舌を打つ。 「黙れよ。」 そう言うのに、昇は千晶をまじまじと見て、 「千晶って、泳げないの?」 って、 「馬鹿にしてんのか。」 ぎろっと睨みつけると、やっと昇が慌てだした。 「違うよ、千晶にも苦手なものがあるんだなって、思っただけで。」 「それ、馬鹿にしてんだろ。」 「そうじゃなくて、だから、可愛いなって思ったの!あ…」 慌てすぎて失言した昇が真っ赤に顔を染める。つられて千晶も真っ赤になった。 「なんでお前が照れてんだよ!」 「照れてない!今の無し!」 なんともいたたまれない空気を二人して大声を出して誤魔化した。 ****** リンビッツエリアには、コーヒーカップやメリーゴーランドなどの可愛らしいアトラクションが集まっている。 そんな少し落ち着いた空間に、身を置いて、照はほおっと息をついた。 「なんかちょっと疲れましたね。」 「ここ、リラクぜーションルームがあるみたいけど。アロマの部屋とかあって、マッサージも受けられるの。」 そう言う光に全く疲れた様子はない。光と千晶は体力馬鹿だ。でも、二人とも、自分が人より体力があることを分かっているから、誰かが疲れたと言えば、それに合わせてくれる。照は、良い子良い子、とその金髪を撫でて微笑んだ。 「それより、もうそろそろお昼にしない?」 シュリンプクレープごときでは腹は膨れない。 照の提案に光はパっとパンフレットを開いた。 「プルビッツがフランス料理で、ルービッツがイタリアンで、リンビッツが和食で、レンビッツがバーベキューで、レドビッツが韓国料理で、ピンビッツが香草料理だよ。」 「いろいろあるね。」 横から加わった昇に光が続ける。 「あ、あと、センターにフードパークがある。」 「でも、ここに来てフードパークってのもねー。」 「ここで食えばいいだろ。」 千晶の意見で決定。 「やったー、和食だー。」 そう言って光は喜んでいるが、きっと他のものが良いと言っても同じ反応をしただろう。照はまたその頭を優しく撫でた。 レストランではみんながみんな別の物を頼んだ。そうして、光と照は、恋人同士のように、お互いの食べ物を「あーん」と交換し合っている。いつもの光景だ。 少しは周りを気にしたらどうかと思うが、他のテーブルも、テーマパークにテンションが上がっているのか、気にする人はいなかった。 というか、この二人だと、カップルにしか見えないから、意図的に見ないようにしているのかもしれない。 照といちゃいちゃしながら、光は唐突に思いつき、楽しそうに笑う。その意図に気が付いた照は少し機嫌を損ねつつも、彼の邪魔をする気はないと、自分の食事に戻った。 光は思い付きを実行すべく、茶わん蒸しを一さじ掬うと、千晶に差し出した。 「千晶ちゃん、あーん。」 千晶はその行動に、あーあ、と思う。こいつの奇行はいつものことだ。そして、これはこちらが受け入れるまで終わらない。 千晶は、さじを持つ光の手を掴んで引き寄せ、食べる。 「おいしー?」 「うまい。」 ニコニコ笑顔満点の光にそっけなく答える千晶。そんな二人に昇はショックを隠せなかった。 まるで、恋人同士ではないか、と。 二人は本当に仲が良い。千晶だってまんざらではないのだ。悲しい。寂しい。こんな気持ちになること自体間違っているのに。 「どうした?昇?」 はっと気づくと顔の前で千晶が手を振っている。 「な、何でもないよ?」 怪訝な顔で覗いてくる彼に、無理やり作った笑顔で答えるしかなかった。
蕩けていちごミルク
柵の向こうで背の低い車がブンっと通り過ぎる。千晶と光のサーキット一騎打ちだ。 食事を終えて、元気が戻った一行は、レンビッツエリアに来ていた。ちなみに、ジャングル探検を追えてのサーキットである。 「二人とも速い!すごい!」 昇は口ではそう言いながらも、そうやってやりあえる二人を羨ましいと思った。 そんな昇の頭を、照るがべちっと軽く叩いた。 「?」 昇が振り向くと、照はこちらを見ては居なくて、光の応援を続けている。照が光を応援するから、昇は千晶を応援した。 一方、光ばかりを応援する照に、良い気持ちがしない千晶は、昇が自分の名前を呼んだ時、いっそう胸がきゅんと苦しくなったりしていた。 「勝ったぜ!」 そう言って帰って来た千晶が笑う。 「応援サンキュー。」 自分に向けられた笑顔と言葉にきゅんとする。昇は、目を逸らして「どういたしまして」と小さな声で言った。 そうやって、覗いたの昇の耳が赤いことに千晶は気が付いた。下から顔を覗くと目元も心なしか赤いようだ。それを見て、口元が自然と綻んだ。 続いてのアトラクションは、サイクルモノレールで、千晶と昇チーム、光と照チームに分かれての勝負になった。サーキットで寂しそうにしていた昇に対する、照の粋な計らいかと思われる。 「お前も精いっぱい漕げ!」 「漕いでるよ!」 しかし、そこで交わされる千晶と昇の会話は殺伐としたものだった。しかも、結果は自分たちの負け。 パイナップルピザを食べながら、「くっそー。」と千晶は悔しげだ。 「え、と…ごめんね、千晶。」 そんな千晶に、昇は本当に悪いと思って謝った。だって、さっきの勝負は照と昇の実力差で負けたようなものだったのだから。 丸まった昇の背中を千晶が蹴りつけた。 「謝んな!」 「痛ったー。」 何すんのー、と振り返って見た千晶は楽しそうに笑っていて、昇もつられて笑った。 次にやって来たレドビッツエリアは、絶叫系のオンパレードで、年齢制限つきの、バイキングの進化系みたいなアトラクションで、照がダウンした。 ベンチで光に膝枕をしてもらって、照が唸っている。 そんな彼の頭上で光るは辛むーちょポップコーンを食べていた。 「照も食べる?」 「今食べたら、戻す…」 白い肌を更に青白くして、細かな汗を浮かべた照に、光はフム、と頷く。 「ちーあき、のーぼる。」 「なんだ?」 「なに?」 「照は僕が見てるから、二人は他回ってきてよ。」 「え、悪いよ。」 「みんなでいたってしょうがないし、照だって大勢で待ってたら気を遣っちゃうよ。ね?」 「そう、ですね。俺は、光が居れば良い…。」 そう言って無意識に光に手を伸ばす照に、その手を取って微笑む光。盛大に惚気られた千晶と昇は、うわぁと思って、さっさと退散した。だって本当にお邪魔虫みたいだったから。 ****** と、言う訳で別行動。 しかも場所は何の因果か、愛のビッツ・ピンビッツエリアだ。 レースやリボンのモチーフで飾られたピンクの空間は、乙女チック全開。 男二人でこの空間はどうだろうと、昇は一瞬思ったが、千晶は小っちゃくて可愛いし、ピンビッツの帽子をかぶった姿など、女の子だと言われれば、そうかと納得してしまうくらいに嵌っている。 ああ、本当に、女の子だったら良かったのに。そんな理不尽な考えを、昇は首を振って追いやった。 「鏡の館」は鏡の壁の迷路だ。たくさんの鏡にたくさんの自分と昇が映っている。通路なんだか、壁なんだか分からなくて千晶はゴッと鏡に突っ込んだ。 その上一瞬気がそれたことで、どれが本物の昇かも分からなくなってしまった。 「どれが本物の昇だよ」 一枚一枚鏡に触れて、確認する千晶に、昇が声をかける。 「千晶、ちょっと動かないで。」 すると、正面から昇が近づいてきた、と思ったのに、実際には後ろから肩を叩かれた。 「見ぃつけた。」 なんですぐに分かるんだよ、なんて、本当はちょっと考えればすぐに分かることだったのだが。相手の前に立って、自分が映らなければ本物なのだ。でも、やっぱり、見つけてもらえてことは嬉しくて、 「見つかった。」 振り返って、そう答えた。 そうしたら何故か昇がピキッと固まる。実は振り返った千晶の笑顔に射抜かれて硬直したのだが、そんなこと千晶は思いもしない。不思議に思いつつも、はぐれないようにその手を取って歩き出した。 占いの館に入った。 「あら、カップルですか?」 キャストの占い師は、黒い布を頭から被っており、顔は見えない。その人は、千晶と昇のつないだままの手を指してそう言った。 その言葉に二人して飛び退くように手を離すと、占い師はふふっと笑う。そうして昇の方を見た。 「あなた今、恋愛で悩んでいますね。」 「え、あ、はい。」 それを聞いて、千晶は、例の女か、と気持ちが沈んだ。 「大丈夫、貴方の悩みに問題なんてありません。」 「…それは、どういう?」 「糸が絡まってしまったのですね。すべては思い違いです。すぐに解決します。」 占い師はふふ、と笑って次に千晶を見る。 「あなたは、想い人との関係をどうにかしたい。友達とも言えない微妙な現状を何とかしたい。今日は一緒に来たんですね。でも、貴方の方もすぐに解決します。」 二人の出て行った館で、占い師は黒い布を外した。その下から現れたのは、ふわふわと豊かな長い髪と、美麗な面。愛場明だった。 折角いい雰囲気になったのに、なんだか、占いの館から空気がおかしくなってしまった。 だって、昇の恋がうまくいくということは、つまり、そういうことだから。 千晶はもうそろそろ自分の気持ちに気付き始めていた。自分はこの男が好きなのだろう、と。だからこそ、さっきの占いは受け入れがたいものだった。占いがすべて当たるとは思わない。現に、昇の占いと、千晶の占いが同時に当たることは不可能なわけだから。でも、気持ちが沈んでしまうのはしょうがない。 一方昇は、千晶と光の関係を、先の占いで完全に誤解してしまっていた。千晶が好きなのは光なのだろう、と。 二人はぎくしゃくとしたまま、観覧車に乗り込んだ。残す乗り物はこれだけだったのだ。今更、これだけ外すのも、おかしいと思って。 「ごめんね光と別行動になっちゃって。」 申し訳なさそうに言う昇を、千晶は不思議に思う。 「なんでここで光が出てくんだよ。」 「だって…」 言い渋る昇のうしろに水平線が見えた。大きな夕日が沈んでいく。 茜色に染まった空に、雲の輪郭が映えた。 千晶は、夕日をもっと近くで見るという口実で、昇に近づく、そうすると、彼は目に見えて身構えた。 今日彼が何度も見せた拒絶の反応に、千晶はもとの席に戻り、目を伏せる。 「なあ、昇。おれ、何かしたか?お前に、嫌われるようなこと…」 俯くその顔に西日が当たって、常より長い睫の影が、その表情をより一層儚げに見せる。 「千晶は何もしてないよ!悪いのは僕だ!」 ほら、そうやって誤魔化す。 「…千晶?」 昇は、動かない千晶に、声をかけて、その肩が震えていることに気が付いた。 膝の上で握った拳の上に、ぽた、ぽた、と水滴が落ちる。 「え、うそ、どうしよう…」 千晶は、近づこうする昇を手で制して、腕で顔を隠した。こんな、女々しい所、見せられない、と思って。 「なん、だよっ!…あんなに、好きだって、可愛いって、…言って、た、のに……っ。こんなんっ、俺…ばっか」 でも、出てきてしまう言葉はやっぱり女々しい。千晶は、悔しくて、唇を噛みしめた。 「ち、千晶!違っ、お、俺。」 「なんだよ!もういいよっ!!」 腕を剥がして、顔を覗こうとする昇に、暴れて、抵抗するも、どうにもならなくて、ついに、顔を上げて濡れた瞳で睨みつけると、そこに切羽詰った昇の顔があった。 「俺、二股かけてるんだ!!」 「…は?」 叫ばれた言葉がすぐに理解できなくて、返事が一拍遅れる。 「この前言ってた女の子とは別に、もう一人好きな子がいるんだ。」 「…それ、俺に関係ないじゃん……」 「いや、でも。なんていうか、二人の人を同時に好きになった自分が許せないというか、千晶に合わせる顔が無いというかなんというか…」 本当は好きな子の一人が千晶本人なわけだけど…… 昇が千晶の顔を窺っておろおろとしていると、千晶の顔にじんわりと笑みが広がっていった。 「ばっかじゃねぇの。」 浮かんだのは、嫌われていないという安堵の笑みだ。そして、二股をかけているのなら、自分にもチャンスがあるかもしれないという期待の笑みだ。 その、いつになく柔らかな笑顔を至近距離で見て、昇はもう、だめだと思った。 その顔は反則だ…。 ****** 観覧車を降りると、出口で光と照が待っていた。 「ああ!昇が千晶泣かした!」 「うっせー、泣いてねぇよ。」 騒ぐ光に千晶はそう返したが、目元が赤くなっているからバレバレだ。 「じゃあ、泣かせた悪い子は俺たちみんなにかき氷を買ってきてください。」 「だから、泣いてねぇって言ってんだろ!」 照に言われてまたそう言うも、取り合ってはくれない。 「分かった、買ってくる。味は?」 「だ、か、ら~」 「僕と照はいちごミルク。有名らしいよ。千晶は?」 「…いちごミルク。」 ついに諦めて大人しくなった千晶のリクエストを聞いて、歩き出した昇に、照がついていく。 「一人じゃ持てないでしょうから、俺も行きます。」 「いってっらしゃーい。」 光は二人が見えなくなるまで見送って、そっと千晶を窺った。 「仲直りできた?」 「ばーか」 千晶は照れくさそうにそう言ってそっぽを向く。 「…………………………ありがとう」 そうして何拍も開けて呟いた小さな感謝の言葉が、いちごミルクのかき氷みたいに甘く溶けた。 「ただいま!」 戻ってきた昇は、光と千晶の空気がに何やらほんわかしていることに慌てて駆け寄り、躓いた。 「うわっ!?」 べちゃっ かき氷が千晶の顔面にヒットした。 「ごめん!」 慌てて見た千晶の顔は、練乳に塗れていて、昇は鼻を押さえて蹲ってしまった。 センターエリア名物の七色マカロンを食べながら、園内を路線バスで回る。 すっかり日が落ちたパーク内で、キューブの傘を被った羽根つきの街灯が光っている。 バスでしか行けない路地に入って、窓や壁から出てきた人形たちが繰り広げるキュービッツたちの日常がを見ながら、なんだかんだあったけど、ここに来てよかったな、なんて千晶は思った。髪がべたつくのはご愛嬌だ。 センターエリアを囲むようにして立っているビッツ達の家はお土産屋さんだ。 お土産を物色しながら、パレードの時間を待った。四人で、帽子と同じビッツのキーホルダーを買った。 時間になると、パーク内の電気が全部消えてパレードが始まる。キラキラとカラフルな光のパレードの中でピンビッツとリンビッツが手を繋いでる。それを見て千晶と昇も手を繋いだ。 こいつを、この子を、諦めるなんてできそうにない。
二股じゃありませんでした
絵に描いたような天色の空と太陽の下、陽炎が揺れる真夏日。プールの無い山百合高校の体育は、炎天下の中での野球。 ジージーと命を削って、五月蠅く蝉が鳴いている。体育会系とは言えない自分に、滴る汗はけして気持ちのいいものではない。 水道の前、列を成すクラスメイトを前にして、白鳥昇は限界だった。 水を求めた。グランド横、体育館の水道は込み合っている。向かったのは中庭。そこには、公園の水飲み場に近い、小さな水道があった。 そこには先客がいた。校舎によって長方形に切り取られた空の下、見慣れた赤い髪が揺れている。 「ちーあき。」 こちらを見たその人に息を呑む。呼びかけに顔を上げたその人は、今呼んだ可愛い男の子ではなく、件の少女だった。 大きく開かれた瞳に心臓を射抜かれる。あんなに五月蠅かった蝉の声が意識の外に追いやられる。時間が止まったようだった。 「あ…」 数拍後、昇の漏らした声で、時間が動いた。その瞬間、少女は走り去る。 「あっ!」 言葉が出なくて、馬鹿みたいにそんな声が漏れる。昇は、それだけ発してその場に留まった。 一瞬の逢瀬。それは、陽炎の見せた幻のような一瞬だった。 ****** 「やべー、やべー。」 中庭から離れてすぐ、少女はポケットから取り出したヘアバンドとメガネを装着する。小さすぎる水道にこいつらを置くスペースが無くて良かった。おかげで多分ばれなかったと思う。 何を隠そう、この少女、昇が人違いしたと思っている愛馬千晶その人である。彼女は小学一年の夏から男として生活していた。当初それなりに意味を持っていたこの行動だが、今ではする必要もない。でも、今更ライフスタイルを変える気もしないし、嘘がばれるのは何となく怖い。 でも、千晶は昇が好きだった。それを叶えるには男よりは当然、女の方が都合が良くて。 「どーうすっかなぁ。」 言いながら首と肩を回した。 更衣室で普通に着替えて(男物のタンクトップと、パンツの上にトランクスを重ね着しているのでばれない)千晶が教室に戻ると、何やら昇が呆けていた。 「何、ぼけっとしてんだよ。」 「え、――うわっ!千晶っ!」 声をかけたら、やたらと大げさな反応をされてしまった。 「なんだよ。」 「あ、いや、別に…なんでもない……。」 半目で問うと、おどおどと目を逸らされて、これじゃビッツランド前に逆戻りじゃねえか。 そこで、千晶は昇にだけ効く最強の脅し文句を使うことにする。 「言え。泣くぞ。」 「えええええ!?」 叫んだ昇の方が泣きそうな顔になった。 「ほら。」 吐いちまえ、楽になるぞと顎で示す。 「…うぅぅ。実は、さっき、中庭でぇ…」 「中庭で?」 「あの女の子に会った…。」 その言葉に千晶は固まる。それって…まさか… 「…千晶?」 「え、あ、いや…その……」 顔に熱が集まる。どくどくと心臓が五月蠅く鳴る。 「どうしたの?」 心配した昇がその手を千晶の頬に伸ばした。その手を思わず振り払う。 「お、俺に触るんじゃねぇ!!」 千晶は走ってそこから逃げ出した。 「うそぉ…」 教室に残された昇は、茫然と呟いた。 振り払われた手が熱い。どうして?もしかして、俺の気持ちがばれたから?男に好かれて、しかも二股されて、恋愛相談まで受けて?ばれたんだとしたら、そりゃそうなるな。 千晶の出て行ったドアを見る。彼は隣のクラスに駆け込んだようだ。――光のところに行ったのかな…。 知らずため息が零れ落ちた。 「ど、どどどどどどうしよう!?」 「落ち着いて、千晶。意味が分からない。」 昇の予想通り、千晶は藤本光の元に来ていた。助けを求めに、だが。 「昇、昇が…。」 「昇が?」 「好きなの、俺だった…」 千晶の言葉に光の顔がぱあっと華やぐ。 「良かったじゃない。」 「で、でも。あいつはそれを俺だって気づいてないし、それに…もう一人好きな奴がいるって言うし…」 「つまり女の状態の千晶を見て千晶だと認識しないままに好きになっていたと。そして昇は二股をかけていると。」 「そうだ。」 「じゃあ、告白すれば?」 「?」 「どっちも好きなんでしょ?そんなの、告白してきた方と付き合うんじゃないの?もう一人のことなんて、付き合ってるうちにどうにかなるよ。」 「ん?そう、か?」 「そうそう。」 話は済んだとばかりに、光は筆箱を持って席を立った。 「次、移動か?」 「何言ってるの?次は千晶のクラスと合同のワークショップの特別授業でしょ?」 ああ、そういえば特別講師が来るとか言ってたな、と思いだし、一緒に行こうという光と図書館棟の二階にある講義室Dに向かった。 ****** 「昇、さっきは悪かったな。」 そう言いながら光と講義室に入ってきた千晶に、昇は表情を曇らせる。やっぱり光と… 「昇?」 「ううん。何でもない。あ、先生来たみたいだよ。並ばなきゃ。」 「あ、ああ。」 背の順で並んでしまえば、千晶と昇は一番前と一番後ろだ。しかし、昇が息をつけたのは人数確認の点呼の間だけだった。 「じゃあ、ワークショップを始めますが、ちょっとスキンシップをしてもらおうと思うので、男子同士、女子同士で組んでください。」 ス、スキンシップ、…だと? 「昇――」 千晶に声をかけられそうになって、慌てて照の腕を掴む。 「照!一緒に組もう!」 「いや、俺は光と組むので。」 しかし、勢いのままに誘った言葉は無下にあしらわれてしまった。 「千晶が呼んでますよ?」 (そんなぁ…) 周囲が凍りつくほど美麗な笑顔で言われたら、従わないわけにいかないじゃないか… 今、俺の理性は試されている。 昇は、千晶を背中から抱え、床にべったりと座っている体勢である。 ワークショップは、二人一組で、ペアを組み、一人が一人を背中から抱き、抱かれた方が、抱いている方の十本の指のうちどれかを押して、抱いている方がそれに合わせて抱いている方をくすぐったり、抱きしめたり、軽く叩いたりするという、幼児向けの遊びだったのだ。 高校でやるワークショップなんだから、高校生向けのをやってよ――っ!! ああもう、千晶小さい可愛い。柔らかい、何か良い匂いがするぅぅうっ 内心身悶えるが、そんな事を考えていても、終わらない。早速千晶が指を叩いた。 ああ、もうどうにでもなれ! とりあえず脇腹をくすぐってみると… 「ひゃんっ!」 いやぁぁぁぁあああっっ 千晶の漏らした声に、昇の心が悲鳴を上げる。やられた側よりもやった側の方がダメージが大きいのはどういうことだ。 「の、ぼる…っ、やぁ…っ」 くすぐる手を止めるのを忘れていた。そこで昇の意識はぷっつり途絶えた。 くすぐり攻撃を止めない昇に、千晶は次の指を押した。そうすれば止めると思ったから。 そして、昇は確かに昇はくすぐり攻撃を止めた。しかし、問題は次の攻撃だった。彼はあろうことか千晶の耳に熱い吐息を吹きかけたのだ。 「ひ…っ!」 千晶は息を詰めて彼の腕から逃れようとするが、すぐに抱き寄せられて、動きを封じられてしまう。遂には耳に舌を入れられて―― 「ギャ――ッ!」 気づいた時には肘が彼の鳩尾にめり込んでいた。 ゴスッと重い衝撃が腹部を襲ったことでハッとする。真っ赤な顔で肩を怒らせた千晶が震える拳を抑えて必死で息を整えていた。 「…てんめぇ、分かってんだよなぁ?」 「ち、千晶…ごめ」 「問答無用!」 座ったままの昇に強烈な蹴りをお見舞いして(拳を抑えていたくせに。ここらへん千晶も混乱している)、怒ったままの千晶は次のパートナー探しに行ってしまった。 痛みに悶える昇の肩を誰かが叩く。顔を上げれば綺麗に微笑む照の顔が。 「自業自得。」 そこはせめてドンマイ、とか言って欲しかった。 次のパートナー探しに出たと思われた千晶だが、実は講義室から出て、非常階段の前に来ていた。 鼓動が速い。身体が熱い。 「責任とれよ、ばかやろう…っ」 濡れた感触が離れない。耳を押さえて蹲った。 ****** 裏校舎一階隅の第二理科室は今は使われていない。 その日の放課後、千晶に呼び出されたそこで、昇は赤毛の少女に会った。 そこに来いと言ったのは千晶だった。だから昇はてっきり千晶が待っているものだと思っていた。 でも、目の前にいるのは件の少女で… 「好きだ。」 「え?」 言われた言葉が理解できない。 「白鳥昇、お前が好きだ。」 「ええ!?」 少女は今、自分を好きだと… 「あ、あ、え、と……」 昇は意味の無い言葉を紡ぎながら必死にとるべき行動を考えた。 自分は彼女を好きだ。そして彼女も自分を好きだと言っている。でも、自分は… 真摯な瞳が見つめていた。ああ、俺はどうしてこの子に応えることができるだろう… 「ごめんなさい……」 そうだ。断るのが正しい。だって、自分はこの子と同じに千晶のことが好きなのだから。 「っ、なんでだよ!もう俺のことは好きじゃないのかよ!?」 泣きそうな顔で責められて、どうして良いか分からない。 そうだ、ここに呼んだのは千晶だった。もし、千晶が俺が好きなのがこの子だと知って、とりもってくれたのなら、彼女は俺が彼女を好きなことを知っている。 でも、それってなんて残酷なんだろう。 「違う!俺は、君を好きだ。」 「じゃあ、なんで?」 「だって、俺は――」 昇はぎゅっと目を閉じる。 「――最低の二股野郎なんだよ!!」 「知ってる。」 予想外の言葉に閉じた瞳を開いて、まじまじと彼女を見た。 「その上で俺はお前が好きだと言ってるんだ。今、お前は俺と、もう一人好きな奴がいる。でも、俺は絶対そいつより好かれて見せる!」 強い意志のこもった言葉にぐっときてしまう。しかし、ダメだ。 昇はぐっと唇を噛みしめ、静かに息を吐く。 「無理だよ、選べないんだ…。今日だって、ワークショップで組んで、どきどきが止まらなくて、心臓が壊れるかと思った。結局理性も飛ばすし、しかも、その子男だし…。気持ち悪いでしょ?」 少女の瞳が見開かれた。 ああ、やっぱり驚いてる。目が零れ落ちそうだよ… これで終わった、とすぐに来る絶望的な未来を予想して、昇はゆっくりと瞼を閉じた。 でも、予想した馬頭は耳に届くことは無く、代わりに腰にあたたく重い何かがぶつかってきた。 「え?」 驚いて目を開ければ、件の少女が腰に抱きついている。 「ええ!?」 「……。」 慌てて放そうとしても、黙ったままびくともしない。 「ちょ、え!?」 「……俺だよ。」 「はい!?」 「愛場千晶は俺だよ!」 「……へ?」 少女は昇の腰にしがみついたまま見上げてきた。 よくよくその顔を見てみれば、この大きな瞳は千晶のメガネの奥のものと同じではないだろうか、 この小さな鼻は、ふわふわの赤毛は、彼のそれと同じではないだろうか… 「うそ…」 「…男だってのは嘘。」 だって、そんな自分に都合の良いことって… 「昇。」 千晶の手が、伸ばされる。それに惹かれるように昇は身をかがめた。千晶のその手が、彼の頬を霞める。 「ち、千晶?」 大きな瞳が自分を映して揺れた。 「好きだ。」 「俺も。」 二人の影がそっと重なった。 ****** 「だいたいさー。好きだとか言って、同一人物だって気付かないってどうなんだよ?」 「しょうがないじゃん!男子と女子がまさか同じ人だとは思わないじゃん!」 「ま、バレたらダメなんだけどな。」 そう言って千晶は笑った。 駅までの道を自転車を押して歩く。乗っていかないのは気分だ。決して、昇との時間がもっと長く続けばいいのにとかそんな甘いことを考えたんじゃない。まじで。 「そういえば、なんで千晶は男の恰好してるの?」 「…さて、どうしてだったかな……」 そんなの、今はもうどうでも良いことだ。ただ今はこのスタンスが楽なだけ。 「お前は、どっちの俺が良い?」 聞けば昇は楽しげに笑った。 「俺はどっちの千晶も好きになったんだよ。」って、 最高の口説き文句だな、なんて。お互いに顔が赤いのは、多分きっと、夕日のせいだ。
恋愛成就 編 <完>