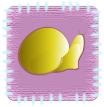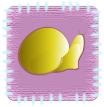
芸術奇行
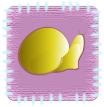
芸術奇行
![]() でんでんむし
でんでんむし ![]()
僕は綺麗な顔が好きだ。性別は関係ない、可愛い子ももちろん好きだけど、やっぱり綺麗な子が好きだ。それに気が付いたのは小学5年の夏。それまではただキラキラ光るビー玉や、太陽を反射して白く煌めいて揺れる水面なんかがたまらなく好きだった。 一目惚れって、何を見て惚れるんだろう。顔?雰囲気?僕の場合は顔だけど、中身も良い人だったなぁ。まあ、惚れたのも一人だから運が良かっただけなのかもしれないけどね。 ****** 「でーんでん、むーしむし、かーたつむりー」 ペタンコの靴を履いた小柄な彼女は女性より少女という言葉が似つかわしい。少女が歩くのは、まだ蕾の目立つ桜の並木道。カタツムリが顔を出しそうなアジサイの花などは無い。 「おーまえーの、あーたまは、どーこにーあーるー」 これは季節の歌ではなく、彼女を象徴する歌だ。 モウエヤマト、馬上大和と書いてモウエヤマトと読む。今年山百合大学に入学する彼女は、賃貸のカタログをいくつも持って、歌いながら途方に暮れた。入学式は来週に迫っていると言うのに、未だに住む場所が決まらないのだ。学生寮、学生アパート。国立の大学があるのだから、賃貸なんてより取り見取りで、普通ならこんな時期に住む場所が決まらない、なんてことは無いのだろう。しかし、いかんせん条件が細かすぎた。大家が一緒に住んでいなくて、学生が居なくて、家賃月三万円以内。そんな物件はありませんか? 「角出せ、やい出せ、目玉ー出せー」 歌い終わると、意識の外に追いやっていた景色がすうっと視界に入ってくる。いつの間にか、桜の並木道ではなく、赤レンガの高い塀に挟まれた一本道に立っていた。帯状の空間を風が抜けると、塀をくりぬいた窓から覗く植物が揺れる。 「あれ…?」 方向音痴の自覚はあるので、また迷ったのかと納得して元来た道を戻ろうとくるりと方向転換した。大きくカーブを描く道では、先が見えないが、すぐに元いた通りに出るだろう。ヤマトは緩い下り坂を歩き出した。 「あら、あなた。不思議の気配がするわね。」 すると、後ろから声を掛けられる。艶やかな声に振り返ると、ふわふわの巻き毛の美女が坂の上に立っていた。 彼女を知っている。大好きだったあの子との思い出の中に居た。嬉しくて、幸せで、その分思い出すのが辛い、もう大丈夫だと自分に言い聞かせた、思い出の中に居たその人。 「明ちゃん…」 掠れた声で名前を呼ぶと彼女は大きな瞳をキョトンと瞬いた。 ****** 身体測定や、新入生のオリエンテーリングなどを終えて、やっと授業が始まった昼休み。美術棟に近い講義棟の一室では、様々な学科の人が昼食をとったり、雑談をしたりと好きに過ごしていた。C棟一階のこの教室は、来るもの拒まずの独自の体系を持っているらしく、誘われて入ってきた新入生も、間違えて入ってきた新入生も例外なく歓迎される。 秘密を守るために、学科の同級と友達になるのを避けたいヒロカズにとって、他学科の人や先輩と関われるこの場所は、とても都合が良かった。 「浪人したから、同じ年の子少ないだろうと思ってたら、思わぬところで小中の同級生に再開して嬉しかったのになぁ。折角同学年だと思ったのになぁ。」 そんな和気あいあいとした空間で、猫毛短髪の背の高い男が、向いに座る小柄な男に向かって言った。大柄な男の名前はマガミヒロカズ、馬上大和と書いてマガミヒロカズと読む。文句を言われた背の低い方、三反田巧太郎はゴメンゴメンと明るい声で形だけで謝った。 二人が再開したのは、入学式後の学科の新歓パーティーだ。ヒロカズは日本画、巧太郎は服飾と、専攻こそ違うものの、美術科で一まとめにされたその空間で鉢合わせた。 ヒロカズの顔を見ると、巧太郎はありえないものを見たかのように茫然とその顔を見つめ、「ヤマト!」と叫んだ。 「ヒロカズだよ。」 ヒロカズがそう冷静に返すと、彼はおっとと口を押える。 「わり。」 「どうかした?」 口を押さえつつも何か言いたそうに見つめてくる彼にそう言うと、小柄な彼はヒロカズの手を引いて屈ませ、耳に口を寄せて声を潜めた。 「いや、大学なんて通って大丈夫なのかよって思ってさ…もしかして、もう決まったのか?」 彼はヒロカズの秘密を知っている。だから、心配してくれる。 「いや、変わるよ。でも、大学って人との繋がり薄いし、気を付ければ何とかなるんじゃないかな。」 「そうなんだ…――あのな!」 「ん?」 「えっと、俺はもうお前のこと知ってるわけだし。何かあったら相談乗るから!」 「ありがとう。」 「同じ一年だしな!」 ――なんて、真ん中分け外はねの髪を元気に跳ねさせて、何とも頼もしいことを言ってくれたのだ。まあ、最後のはウソだったわけだが。 ここ、国立山百合大学には偽一と呼ばれる新入生歓迎イベントがある。入学式が4月1日のエイプリルフールなことに便乗して、何人かの上級生が一年生に紛れ込むというものだ。偽の一年生だから偽一。由来はこうだが、今では一年に紛れ込むだけでは飽き足らず、様々なウソで新入生を翻弄して上級生が楽しむものになっている。聞いた話だと、どこの学科だか知らないが、ベジータとフリーザが廊下ですれ違ってあわや一発触発!?になっただとか。誰をどう騙そうとしてそうなった。 「でも、他学科には歳一緒なのに白鳥財閥に内定決まっている人がいるらしいぞ。」 「え、どういう事?」 「大手じゃないですか。」 巧太郎の言葉にヒロカズと共にその隣に座っていた円佳香清が反応した。楊枝が3、4本乗りそうな長い睫毛に大きな黒々とした瞳の綺麗な顔立ちの青年で、ウルフカットなんて洒落た髪型までしているものだから、ヒロカズの好みにドンピシャ過ぎてまいってしまう。いや、嬉しいのだが。 美術科洋画専攻の彼とは、同じく件の新歓パーティーで知り合った。同学年同学科とは当たり障りのない関係を築こうとしていたヒロカズだが、彼だけは別だ。だって、どうしようもなく好みの顔をしていたのだから。まあ、専攻が違うからどうにかなるだろう。 「ああ、それナルナルだ!彼氏が白鳥に入って、ちょくちょく手伝いに行ってたら気に入られたらしいぞ。」 心理学部の院生である坂本圭斗が会話に混ざってきた。 「すごいですね。知り合いですか?」 合いの手を入れるのは法学部三年の羅門薫。 「ああ。彼氏の方とよくつるんでたし、ナルちゃんとも友達だし。」 坂本はさらっとした癖の無いイケメンで、羅門は優しい笑顔の王子様系正統派イケメンだ。 今のところ仲良くなったのはこの四人。みんなイケメンばかりで嬉しいが、ほんの少し劣等感も感じる。イケメン三人が少しずつ瞳の大きさを分けてくれたらこの三白眼もどうにかなるだろうに、とヒロカズは思った。 フツメンは俺とお前だけだよ、巧太郎。 「羅門さんのところは何しました?」 ヒロカズにそんな失礼なことを思われているとはつゆ知らず、巧太郎は薫に話を振った。 「僕のところ?大変だったよー。うちは普通にすごいのを抱えてるからさ、うそで飾るんじゃなくて、逆にうそで隠してたんだよね。」 「なにをですか?」 「白鳥財閥跡取り。」 「うぇええええ!?」 『白鳥財閥に内定決定』に驚いてたところに跡取りの登場ときて、ヒロカズは何とも言えない声を上げた。しかし、先輩たちにとっては周知のことらしく、そう言えばいたなぁなんて頷いているし、唯一同じ一年の香清は涼しい顔で「じゃあ、ネタばらしの反応すごかったんでしょうね。」などと合いの手を入れている。これでは驚いている自分がバカみたいだ、とヒロカズはすぐに持ち直した。 「…それがさ…違うとこまでバラしちゃったんだよね。」 もったいぶって話を切る羅門に、4人はなんだなんだと視線を向ける。すると羅門は身を乗り出し、声を潜めてこう続けた。 「一人ホモ役の偽一がいたんだけど、新入生に本物がいてさ。泣いちゃったんだ。」 「う、わあ。」 セクシュアル・ マイノリティ、所謂セクマイは中々ナイープな問題だ。もし、新入生が、セクマイであることを隠して生きてきたのだとしたら、同氏を見つけてその子はどう思ったのか、心を開いて自分の性癖を晒したのだろうに、裏切られてどう思ったのか。4人は顔を歪めた。 「そしたら、白鳥が廊下に出てって、超絶綺麗な男子生徒連れてきて、その場でキスしたんだ。」 「え!?」 「おお!」 ヒロカズ、香清、坂本が驚きの声を上げ、巧太郎一人が感嘆の声を上げた。 「そいつがホモなのは嘘だけど。俺はホモで間違いないぞって。」 「衝撃ですね…」 ヒロカズはそれだけ言ってもう言葉が出ない。 「てゆうか、白鳥さんはそれで良いわけ!?」 食ってかかる坂本を羅門は手を振って落ち着かせる。 「いやぁ、相手の男があんまり綺麗だったものだから、こう、違和感なくて。というか男勢みんなポーッと頬染めてたから大丈夫なんじゃないかな。」 「薫さんがそんなに言うほど美人なんだ…」 ちょっと会ってみたいかも…、とヒロカズがふわわんと思っている隣で巧太郎がにぃっと笑った。 「いや、でも。衝撃ならこっちも負けてないですよ。」 「え、なにかありましたっけ?」 キョトンと尋ねる香清に、巧太郎は「はぁ?」と顔を歪め、彼とヒロカズの背中を無駄に器用そうな手でバンッと叩いた。 「お前らだよ、お前ら!円佳はヒロカズを見るなり抱きつくし、ヒロカズは抱きつかれて引きはがすどころか、円佳の顔を引き寄せるし!挙句お互い言った言葉が『すげー好み』って、どういうことだよ!」 「何それ笑える。」 長台詞を一息で言い切った彼に坂本が言った。 「そうそう!すっげー、笑った!ってばか!」 それにノリツッコミで反す巧太郎。今までうざいと思ってたけど、実は笑いのセンスのある奴だったのかも知れない。香清以外の三人は彼の認識をほんの少し改めた。 「笑ってたのは俺だけだよ。他はぽかーんだよ、ぽかーん。菓子落として奴もいたっつーの。」 「だって綺麗くない?好みなんだからしょうがないってー。ちなみに好きなアイドルはNGのTEL。」 それにのほほんと答えるヒロカズ。 「芸能科の生徒だね。」 「俺仲良いよ。高校の同級。」 羅門の言葉に巧太郎が答える。それを聞いてヒロカズが慌てる。まさかこんなところで繋がるとは。彼がこの学校に居るだなんて知らなかったし、それが巧太郎の知り合いだったなんてことも知らなかった。 「ああ、観賞用なんで紹介はいいです。」 極力動揺を悟らせないように、平坦な声でそう返した。 ****** 「でーんでん、むーしむーし」 青年は、満開の桜並木の道を抜けて、住宅街に入る。緩やかな坂を上がるごとに、高くなる両脇の塀。 カタツムリは、雌雄同体。だから、同じ種に出会えば雌雄関係なく繁殖活動ができるから便利だ。でも、僕は人間、カタツムリじゃない。進化した一族なんだって言われても困ることの方が多い。 馬上大和は日毎に男女を行き来し、性行為をして初めて相手の望む性別に固定される、という体質を持つ血筋の元に生まれた。生まれた時は女だったが、その体質が現われたのは、小学校6年に上がろうという春休み。大和は転勤族だった父親と離れ、そのころ通っていた小学校を転校し、母親と一緒に本家のある田舎に戻った。それから、大和は男と女で異なる人間関係を築いてきた。今更片方の自分を消すことなんてできない。 緩くカーブを描く坂を上った正面に、円柱と四角柱を繋げたみたいな煉瓦の壁の、赤い屋根の建物がある。パリのオシャレなアパートというか、こじゃれた図書館のような見た目だ。 ――世界の不思議研究会 ここの二階がやっと決まった大和の住居だ。 バーバナ、ベゴニア、アリッサム、ロベリア。玄関前のアプローチの両脇のプランターの小さな春の花の間を通って、アンティーク調の木の扉を開ける。 「あら、お帰りなさい。」 「お帰りなさいませ。」 「ただいま、明ちゃん、まゆちゃん。」 ふわふわ巻き髪の美女とツインテールの少女が大和を向かい入れた。
H2Oサークル
未だ大学の授業は始まっていないが、家主の明は毎日忙しそうに家を空け、まゆはもともと坂の上に住んでいるわけではなく、そうなると部屋に一人で居てもすることの無いヒロカズは、いつでも誰かしらがいるC棟に入り浸っていた。 「ヒロカズ!」 教室に入ってきた香清が一目散に駆け寄ってくる。ヒロカズは席から立ち上がり、両手を広げて彼を迎えた。ヒロカズの体を愛してやまない香清はヒロカズの体に抱きついているのが通常運転だ。 毎回繰り広げられるバカップル顔負けの光景に、C棟の仲間はうわぁと、呆れたり、興味津々に眺めたり。 ヒロカズが長身である上に、厚底の下駄を履いているため二人の身長差は15cm。香清はヒロカズの肩口にぴったり頬を寄せて斜め下から見上げて言った。 「お前もサオリに行くだろう?」 サークルオリエンテーション、略して「サオリ」今週の金・土に行われる学内サークル紹介のイベントである。香清に誘われずともヒロカズもそれに行くつもりだった。土曜日はヤマトでも、金曜日はヒロカズだ。彼と一緒に行くのにも問題は無い。しかし、香清がヒロカズの体が好きなように、ヒロカズは香清の顔が好きだった。だから色々な表情が見たくてつい意地悪をしてしまう。 「どうしようかな。」 「なんだよ、行かないのかよ。」 焦らせば唇を尖らせて拗ねた顔になる。 「行かないかも。」 「え~、行こうぜ。」 どんどん不機嫌になって、整った眉がだんだん下がっていく。 「ほんとに行かないのかよ?」 う~ん、と苦笑いで応えれば上目使いで 「…だめ?」 はい、今日も超絶可愛い。 これを至近距離で見てよく鼻血を出さないな、とヒロカズは毎回自分を誉めている。 「金曜日なら良いよ。」 「やりぃっ!約束だからな!」 満足して了承すると、香清は満面の笑みでヒロカズに抱きついたままピョンピョン跳ねた。 それを見ていた坂本圭斗は慣れてしまったのか無反応。羅門薫は「彼、とぼけた顔してるくせに案外黒いよね」とそれこそ黒い笑みを浮かべ、三反田巧太郎は食かけの菓子パンをそっと机に置いた。 他ギャラリーは糖分の過剰摂取で青息吐息。甘党男子女子は彼らのおかげでダイエットに成功したと言う。 ****** 「H2Oサークル」の部長、影木幻十郎はがらんとした教室で相棒(カメラ)の手入れをしていた。 勧誘の声があちこちで飛び交うのサオリの中にありながら、一切の勧誘活動を行う気配がない。割り当てられた教室の机を適当に寄せて、何年か分の部誌を並べて、あとは相棒(カメラ)の手入れにいそしむ。 上級生が卒業して現在部員は、部長と他大学の幽霊部員二人の計三人。最低あと二人は入ってもらわないとサークル存続の危機なわけだが、幽霊部員二人が、「もし誰も入らなかったら、心当たりが2、3人、いや3、4人、いや、4、5人居るから大丈夫!」と言っていたので危機感は無い。結局心当たりが何人いるかは分からないが、あまり増えて欲しくはないなぁと思った。 「あ、これ巧太郎の絵じゃない?」 「あの人絵描くのか?」 「いや、テキスタイルだって絵描くからな?」 のんびりしていると、教室の前で話す声が聞こえて、すぐに声の主が入ってきた。 「こんにちは。ここ、何のサークルですか?」 「…水?」 やって来た男二人はやけに距離が近くて、腐男子幻十郎は早速当たりを引いたと、死んだ魚のような目に光を宿した。 「ようこそ、H2Oサークルへ。ここは『human observation お腐れサークル』の略で、人間観察を主な活動とする変人のサークルだよ。外の看板を見て入ってきてくれたみたいだけど、君たちの言った通り、あれは三反田巧太郎くんが描いてくれたものだけど、彼はここの部員じゃないんだよね。彼は高校の後輩で、頼んで描いてもらったんだ。」 話ながら二人を席に誘導し、用意しておいた菓子の盛り合わせを差し出す。 「お茶とオレンジと炭酸のどれがいい?」 「あ、じゃあオレンジでお願いします。ありがとうございます。」 「俺は炭酸でお願いします。」 二人の向かいに座って、紙コップに飲み物をついで話を続ける。 「活動は週一回の部会と文化祭で部誌を発行してる。部会はただの雑談で終わるかな。最近こんな人がいただとか、そんな。部誌は一人何ページでも良いし、いっそ書かなくても良い。内容もバラバラ、文章を書く人もいるし、イラストや漫画を描く人もいるし、僕は写真。共通点は人がメインなところ。まあ、なんでもありの緩いサークルだよ。」 そこまで説明して二人の表情を窺う。三白眼の方は興味ありげに幻十郎の顔を見つめているが、美青年は勝手に部誌を捲っていた。 「興味ある?」 三白眼の方に狙いを定めてそう尋ねると、 「あります!あなたに。すごく可愛い顔立ちをしていますね!」 予想外の反応に「え」とひくと、美青年が三白眼の頭を持っていた部誌でスコンと叩いた。 「え、えーと。じゃあ、活動内容も紹介し終わったし。自己紹介しようか。僕は影木幻十郎。医学部三回生。活動は写真。」 「マガミヒロカズです。美術科1回生です。男女構わず美しい人の顔が好きです。大学に入ってから見目麗しい方々に何人も出会ってウハウハです。特に香清の顔が好きです。」 「円佳香清、美術科1回生です。男女構わず美しい肉体が好きです。マガミの体は至高だと思っています。」 「なるほど。」 変人だ。しかし美味しい。 「うちは今部員が三人しか居ないんだ。それも、僕以外は他大学の幽霊部員。最低あと二人は入って欲しい。特に活動を強制しようとは思わない。好きな時に好きなように使える部屋が学内にできると考えて欲しい。」 「入ります。」 予想外に香清の方が先に入部を希望してきた。さっきまで部誌は見ていても、特に興味は無さ気だったというのにどういう風の吹き回しか。 「俺は、ヒロカズの絵が描きたい。」 「ああ、C棟だとポーズが限られるもんな。――僕たちお互いの容姿が好きなんで、お互いの絵を描きあってるんです。」 「ああ、なら部誌もそれで良いよ。マガミ君も入るよね。」 「はい。宜しくお願いします。」 「こちらこそ。」 今後のために手早く連絡先を交換する。 新入部員ゲット。しかもなかなか美味しい二人組だ。幻十郎は上機嫌に笑いながら何の気無しに言った。 「ところで、円佳君はNGのTELに似てるね。」 その言葉を聞いて、何故か二人がピシッと固まってしまった。 ――ここでもその名前が出るのか。 香清は、別に自分が誰に似ていようが構わない。TELは美形だからなお構わない。しかし、大学に入ってから、その名前を聞き過ぎている。TELが有名になり始め、彼と自分の顔が似ているのだから、名前を聞く機会が増えたのは当然なのだろう。しかし、そう何度も言われると俺は俺だと反発したくなる。それにTELの名前を聞くと、何故かヒロカズが悲しそうな目をする。 「…この睫毛を毟ってしまおうか。」 長い睫毛を摘まんで香清がボソッと呟くと、慌てたヒロカズがその手を掴んで止めようとする。 「え、え、止めて!?」 しかし、そのせいで数本睫毛が抜けて、はらはらと床に舞い落ちて行った。 「いやぁぁぁぁぁああああっ!!!!!」 ヒロカズがその場に泣き崩れると、幻十郎がおずおずと尋ねた。 「え、ごめん!誉めたつもりだったんだけど、似てるって言われるの嫌だった?」 「いえ、大丈夫です。でも、俺は俺なんで。」 それを聞いたヒロカズが立ち直り、香清の顔に自分の顔を引き寄せる。 数本抜けても睫毛は長い。睫毛同士がぶつかるほどの近距離で、見つめ合う。 「うん。香清は香清だよ。香清の方がTELより目が青みがかってるし、ちょっとベビーフェイスだよ。」 え、そうかな?と思いつつ幻十郎は二人を連写した。
ヤマトって知ってる?
文科系サークルの集まるサークル棟の最上階、一番奥の部屋はH2Oサークル部室。『human observation お腐れサークル』の略で、人間観察を主な活動とする変人のサークル。床一面タイルカーペットで覆われた八畳間には、大きな本棚とそこに詰められたOBの持ち寄った漫画や小説と毛布やタオルケット、旧式のパソコンと炬燵机が置いてある。 現在部員数女子2人、男子3人の計5人だが、実際に使っているのは男子3人のみ。女子の目が無ければ、やれることの範囲が広がる。マガミヒロカズはトランクス一枚でチョコ―レートを摘まみ、ウーロン茶を飲んだ。現在デッサンモデルの休憩中だ。 香清は春とはいっても裸ではさすがに寒いだろうと、ヒロカズの背中に張り付いている。しかし、彼の手がヒロカズの腹筋を撫でまわしているから、親切心より、自身の欲のほうが勝っているようだ。 腹筋を撫でていた手が太股に下がってきた。内腿の際どい部分を撫でられてびくっと体が跳ねる。ヒロカズは反射でその手を叩いてどかした。 「お前もか。」 「いや、何がだよ。」 「虫刺されがある。」 言われてみれば内腿がぽつんと赤くなっていた。 「言われたら痒くなっちゃっただろ。」 「毒吸おうか。」 「手遅れだし!」 後ろから手が伸びてきて、またそこを撫でられる。虫刺されのせいでより敏感になったそこを触られるのは宜しくない、何かに目覚めそうでやっぱりだめだ。 「だーっ!もう、触るな!」 今度は手を退けるだけでなく、席も移動して離れると、香清はやっと大人しくなってその場にごろんと寝転んだ。 「なあ、ヒロカズ。モウエヤマトって知ってっか?」 ヒロカズは飲んでいたウーロン茶を吹き出しそうになるのを堪え、盛大に咳き込んだ。 山百合大学には一般教養科目なるものがある。専門の括りなく選択必修で受ける科目だ。その中に体育がある。体育はその中でも、水泳、テニス、空手、ゴルフ、ボーリング、と選択肢が様々あり、ヤマトはそのうちお金がかからないかつ、趣味に合ったランニングを選択した。 151㎝の小柄な体型。二の腕、足首はきゅっと閉まって、お腹もペタンコ。でもお尻と太股には良い感じのお肉がついて、バストサイズはFカップ。ふわふわロングを団子にまとめて動くたびに残した横髪がふわふわ揺れる。大きな目は白目が大きすぎて三白眼。少しタレ目でとぼけて見える。 「馬上大和」と書いて「モウエヤマト」はポリエステル60、コットン40の水色しましまホットパンツに、胸に大きなヒヨコのプリントがしてあるTシャツを着て、大学敷地内を走っていた。 隣で一緒に走るのは生活科学部院生の斉藤聡美。この授業でお近づきになった、ヤマト好みのスラッとした体型のさばさばしたイケてる女性、イケ女である。 初めての体育の授業で、選択を決める際、ランニングのコースの列に聡美は居た。男女混合なために目立たないが、170の長身で、長い手足。モデル顔負けの体型はヤマトの理想で、ふらふらと彼女に引き寄せられていった。 何とか彼女の前に回って顔を覗くと、ショートカットの似合うボーイッシュな美人さんで、それこそヤマトのストライクゾーンど真ん中だった。 ヤマトが彼女の目の前で大きな目を大きく見開いて放心すると、聡美は白くて長い指をヤマトの顔にひらひらと翳して「おーい。ねえ、君、大丈夫?」と優しく声を掛けてくれた。 「ひゃい!大丈夫です!あ、あの。僕モウエヤマトって言います!僕もランニングをとるので、えっと、宜しくお願いします!」 と、ヤマトは盛大にテンパりつつガバッと頭を下げて彼女の隣を走る権利を勝ち取ったのだ。 はわーん、ヤマト幸せ―。美人の隣を走る幸せに浸っていると、視界にイケメンを捕えた。粟色のセミロングの髪をバレッタで纏めた、顔立ちも服装も姿勢もシュッとしたイケメンだ。ヤマトの好みは中性的な美少年なので、別段好みと言う訳ではないが、かっこいいなぁと思う。 「あの人カッコいいですね。超バレッダ似合ってます。」 ヤマトが呟いたので、聡美もその視線を追って、その人を見つけた。 「ああ、山田さんか。同じ学科の子よ。親に短髪禁止令出されてるらしいわ。」 「ええ!?長髪禁止は分かりますけど、短髪禁止なんですか?」 ヤマトの疑問に聡美は一瞬キョトンと目を瞬いて、「ああ!」と納得の声を上げた。 「ああ!あの子、女の子よ。――て、ちょっとヤマトちゃん!?」 その言葉を聞くや否や逆走してイケメン改めイケ女に突撃するヤマトを、聡美の声が追いかけた。 「あああああああの、あの、すごく好みです!お友達になってください!」 そう、好みなのだ。シュッとしたイケメンは好みではないと言ったが、女子なら別だ。大好物だ。 「え…」 「待ちなさいよ、ヤマト!」 「あ、斉藤さん。」 聡美は、山田にいきなり詰め寄り、困惑させたヤマトの頭をぺちっと叩いた。 「ごめんね。この子、カッコいい女の人が好きらしくて。」 「うきゃぁ、カッコいい女の人が目の前に二人も…」 「変な子だけど悪い子じゃないのよ!」 「ヤマト幸せ…っ」 両手を頬に添えて恍惚のヤンデレポーズをするヤマトは悪い子じゃないと言われても危ない人にしか見えない。 山田はそんなヤマトの顔をまじまじと見つめた。初対面で胸ではなく顔をこんなにまじまじ見られたのは久しぶりのヤマトである。あ、でもやっぱり胸も見られた。 「ヤマト?もしかして、馬上大和?」 「え、は、はい。そうですけど?」 「うわぁ!久しぶり、私、小5の時同じクラスで、一緒に下校してた山田太陽(さん)だよ。覚えてる?」 覚える・覚えているとも。思い出したとも。彼女は小学5年の、ヤマトが一番青春していたあの頃、下校を共にした友人の一人だ。 「ヤマト?」 「あ、いや。覚えてるよ。茶色いランドセルだったよな、あのころから格好良かった。」 「あはは、男によく間違えられたな。今もだけど。」 「あのころは僕も男に間違えられたよ!あははっ…はは……」 明に続いてまた会ってしまった。照に淡い恋をしていたあの頃の友達… 場面は冒頭に戻ってH2Oサークル部室。 「で、モウエヤマトさん、知ってるか?」 ヒロカズは香清からわざわざ離れた筈なのに、彼がじりじりと詰め寄って来ていた。 「し、知らない、なんで?」 「すごく好みなんだ。小柄で細身なのに、胸と太股に肉がついてて、挟まりたい!」 それをどうして僕に言うのか。いや、間違ってはいないのだが、今僕はヒロカズだ。 「昨日ランニングをしてるところを見たんだ。それで、近くに居る奴片っ端から捕まえて名前を聞いた。」 「直接行かないんだ?」 「直接行ったら最後ドン引かれて終わりだろうが!女の子なんだからな!」 「なるほど。」 「胸が大きくてな、たゆんたゆん揺れるんだよ。」 「お、おう。」 「胸にヒヨコの絵の入ったTシャツだったんだけどな、胸がでかいからイラストが横に伸びちゃってるんだよ。」 「お、おう…」 「で、足の付け根に虫刺されがあってな、白い肌の中ぽつんと花びらが散ったみたいにそこだけ淡いピンクに染まって心底嘗め回したいと」 「もう止めてくれ!」 香清がヒロカズに馬乗りになるという体勢で熱く語られて、いたたまれなくなる。それ、僕です!もう止めて!大和のHPは0よ! 「て、――ひゃわ…っ!」 「そうだよ、ここに同じように虫刺されがあったんだよ。」 「止めろ触るな。僕はヤマトじゃない、柔らかくない、硬い!」 「これはこれで…」 「――っ馬鹿やろう!!」 ****** 「――と、言うことがありまして…」 坂の上の赤い屋根の家に帰ったヒロカズは、ぐったりとカウンターテーブルに懐いた。 ここ、世界の不思議研究会は、ここ自体が不思議の塊。利用者の気持ちや用途によって内装が変化するとんでも屋敷だったのある。 今日の内装はオシャレなバー。未成年しか居ませんが。 「相談事と言ったらバーでしょ?ね、ママ。」 ママと呼ばれて、カウンターの向こうでまゆが胸を叩いた。 「どんとこいです。」 そう言って底に赤い色の沈んだ白いカクテルをコン、と置いた。 「桃のノンアルコールカクテルです。」 ツインテールの高校二年生のどんと来い。可愛い。頼もしい。美味しい。 「で、要領を得ない話だったわけだけど。纏めると、昔の男のことなんて思い出したくないのにまた当時の友達に会っちゃったよ、ウワー(汗)。と、友達にセクハラせれるよウワー(泣)。で良いのかしら。」 カクテルの味に感動していると、明が傷に塩を塗りたくって来た。棒読みで「ウワー」って言っちゃうよ、この美女は。 「『友達にセクハラせれる』は今更、はっ!って感じだけれど。当時の友達は…」 はっ!と言いつつ笑ってもくれない、悲しい。と思っていると、言葉を切ってヒロカズを見て楽しそうににんまりと笑った。 「他の子にも会う?ねぇ、会う?」 「止めてよぉ!」 このお姉さん怖い! 「ねぇ、今どんなお気持ちですか?ねぇ、今どんなお気持ちですか?」 頭を抱えると、カウンターのまゆまで煽ってきた。 このお嬢さんも怖い! 「うわぁあん!味方が居ないよぉ!」 ヒロカズは美味しいカクテルを飲み干してから、部屋に逃げ帰った。 翌日。 昼休みにヤマトと聡美と太陽が、カフェテリアでランチをしていると、明がやって来た。 「まーぜーて。」 って弾んだ声で。 ちょうど四人席で椅子が余っていたので、それを差し出して聡美に明を、明に聡美を紹介した。テーブルの元から高かった顔面偏差値が、また上がって周りの人たちがちらちら見てくる。 「明、いつも研究室で食べてるんじゃないのか?」 太陽の質問に明はうふふと楽しそうに笑った。 「今日は、太陽に慰めてもらいに来たのよ。」 慰める必要皆無に見えますが。 明以外が頭上に?を浮かべると、すぐにカフェテリアの入口の方がざわめき始めた。見ればジブリに登場しそうな、レース編みの襟元がどこか懐かしい、ターコイズブルーと白のボーダーのワンピースを着た、可愛らしい少女が怒涛の勢いで走り込んできた。 それも、「あかりぃぃぃいい!!!???」の怒号付き。 すぐにヤマト達のテーブルを見つけ、そのままの勢いで詰め寄る少女に、当の明は 「あら千晶、どうしたの?」 なんて涼しい顔だ。 「どうしたもこうしたもこうしたもねぇよ!何だよ、なんで俺の男装セット無いんだよ!俺の着替えふりふりのスカートにしたのお前だろ!ばかぁ!!」 赤いふわふわのショートヘアをふり乱して、大きな目に涙を溜める女の子可愛い。じゃなくて、これは――もしかして。 「千晶、落ち着いて。みんな見てる。」 席を立った太陽が千晶を抱き寄せた。千晶は彼女の胸に顔を埋めて「うう~っ」と唸っている。 「明。」 太陽が明を目で叱ると、彼女はふんと肩を竦めた。 「だって、千晶可愛いんだから、ふりふり着て欲しいじゃない。」 「千晶は、慣れない場所で頑張ってるんだぞ。昼間は男装して外に出る昼休みだけが素を出して息を吐ける時間なのに。」 「素は出せても、本音は出せないでしょ。千晶が一番甘えられるのは貴方じゃない。」 「…お前、慰めるって…」 「誰も私を慰めて、だなんて言ってないわ。」 「双子の妹によくもまぁ…いや、妹だからこそか……。千晶お疲れ。」 太陽は大きくため息を吐いて千晶の頭を撫でた。 ヤマトは「双子の妹」発言に泣きそうになった。 明の双子の妹と言えば小5のあのころ一緒に下校した友人の一人である。彼女は昨日言っていた、「他の子にも会う?ねぇ、会う?」を実行したのだ。 当時の友人あと二人+照。 ごめんね千晶。望んだわけじゃないけど、これの原因の一端僕みたい……
合コン野郎
昼休みのC棟空き教室。マガミヒロカズ、円佳香清、三反田巧太郎、羅門薫、坂本圭斗の5人は、窓側一番後ろの一角に集まって喋っていた。 「それでさー、円佳のやつマジで笑えるんだけど――」 「坂本さんって円佳が好きなんですか?」 「は?」 巧太郎の疑問に圭斗は絶対零度の声音で答えた。 その一瞬周囲から音が消えた。 円佳とは、男女関係なく人の体に大したこだわりを持っており、その執着の仕方は気に入ったものから離れないという、変人際まりない人物円佳香清のことである。 顔はイケメンの癖に毎日お気に入りのヒロカズニにべったりくっついている、その変人ぷりに、入学したばかりだというのに関わらず、結構な範囲に顔と名前が浸透している変人。 対する相方マガミヒロカズもこれまた変人で、二人の出会い頭の言葉は「お前の体が好きだ!」「顔が好きだ!」のある意味相思相愛状態。今現在も香清の腕はヒロカズの腕に絡みついて、体もべったりくっついている。 この香清に濃い?いや恋? ライバルが強すぎるし何より変人だし、 「――ありえない。」 迫真。 圭斗がそう答えると、静まり返った教室が元のようにざわめきを取り戻した。 「だよね。」 「びっくりした。」 「また巧ちゃんの暴走かー」 などという声と共に、時折こちらを窺う視線を感じるが、それはもう仕方ない。巧太郎のせいだ。 圭斗がちらりと円佳の顔を見ると、きらきらした美少年面を迷惑そうに顰めている。こっちだって迷惑だ。 「俺はもっと大人しい顔が好みだ。」 「――ぶふっ」 圭斗が言うと、薫がくぐもった息を吹きだした。それまでも文庫本で顔を隠しつつ、体がぴくぴく動いていたから、笑いを堪えていたのは知っている。 「だって、坂本さんいつも円佳の話するじゃないですか。」 皆に一蹴されて、薫に笑われた巧太郎は、ぶー、とふてくされてそう言った。 「あー、分かる。」 「え」 「~~っ!」 それにヒロカズがとぼけた声で賛同してしまうと、香清が彼の肩口からその顔を悲しげに見上げ、薫は文庫本を放して机に突っ伏し、バンバンと机を叩いた。もう笑いを隠すことを諦めろ。 「あいつの行動が可笑しいからつい話すんだよ。だからって好きじゃねぇよ。絶対人と違う行動するんだぞ。他人と一緒に居ても、一人で違う行動とるんだぞ。」 「うんうん。心理学部の実験楽しそうですね。~~っ」 薫は冷静に相槌を打とうとしているのだろうが、最後に笑いを堪えきれていない。 「そうだよ。一昨日だって、意味もなく道にブルーシートを敷いたら、何人が避けるのかって統計取ってたら、一緒に居たマガミは避けて通るのに、円佳はわざわざ真ん中を歩いて行ったんだ。いっそっ遠回り!」 学生食堂の入り口前のスペースにシートを敷いていたため、食堂に入るには、ブルーシートの四分の一を斜めに横切るのが最短だったのに、彼は角から角まで歩ききったのだ。 「子供心があって可愛いんですよね、~~っ!」 「だから、好きじゃない!」 強く否定すると今までぼうっと話を聞くだけだったヒロカズが今更話に入ってきた。 「え、坂本さん香清のこと嫌いなんですか。」 ややこしくなるから止めろ。 「嫌いじゃねぇよ!そうじゃねえよ!」 「すみません、俺はちょっと…」 香清が気持ちヒロカズの影に隠れるように身を引いて、申し訳なさそうにそう言った。 「なんで俺がフラれたみたいになってんだよ!いつものふてぶてしい態度は何処行ったよ!」 立ち上がってバンバンと机を叩いて抗議すると、入口側から、 「あー、何、兄浮気?優ちゃんに言いつけちゃうよ?」 第三者、いや第六者が話しかけてきた。 「あ、川島。馬鹿か、変な脚色付けて言いつけてみろ。泣くからな、優斗が。」 「俺も混ぜろ混ぜろ。」 「おめーの席無ーからー」 「お誕生日席で良いわよん。」 入口から見て左に手前から、マガミ、香清。右に手前から圭斗、薫。一番窓側の奥に巧太郎、とグループを組んでいたところの、巧太郎の正面に椅子を持ってきて座る。巧太郎がいるから別にお誕生日席でもない。 「やあ、諸君。数学科OBの川島直哉だ。いやー、マジで居るなぁ!バカップル。昔の兄にそっくり。」 「兄?」 川島は軽く手を挙げて勝手に自己紹介をすると、ヒロカズと香清を見て言った。弘太郎がキョトンと兄?を反復する。 「おお、そうそう。俺、こいつと同期なんだ。」 バンッと圭斗の背を叩いて説明を始める川島。痛い、うるさい。 「学生時代は俺もここ(C棟空き教室)使ってたんだけど、その時こいつの従弟の坂本優斗ってやつがいて、どっちも坂本だから『兄』『弟』って呼んでるんだ。なー、兄!」 うるさい。 「ああ、浮気を言いつけられる優ちゃん。」 薫がポンと手を叩いた。 「坂本さんもこんなんだったんですか?」 ヒロカズと香清を指さして巧太郎。 「こんなんもそんなんも、べったりだったぜ。なー、兄!」 「おまえ、相変わらずうるせぇな。」 圭斗は馴れ馴れしく肩を組んでくる川島の腕を払いのけた。しかし、彼は全く気にした様子もなく、全員に問いかける。 「ところで金曜日合コンいかね?」 「うっわー、そう来ると思った。」 こいつは、根っからの合コン魔なのである。 こいつが在学中だった頃から、圭斗が何度合コンの誘いを断ったことか。そろそろめげろ。 「みんなイケメンじゃん、丁度いいじゃん。」 「何がちょうどいいのか分かんね。」 川島は四人の顔を見渡して言った。あ、巧太郎を除いた四人である。 「というかだな、兄と円佳と羅門をどうしても連れて来いって言われてんだよ。」 圭斗は川島の頭をペシンと叩いた。大げさに痛がっているが、さっき俺が背中を叩かれた時の方が絶対痛かった。 「俺はともかく、お前こいつらと接点無いだろ、適当言ってんじゃねぇよ。」 「それがさぁ、女の子の代表が、俺と圭斗が知り合いで、お前とこの子たちが仲良いって何処からか調べてきてな。無理だって言ったんだよ?お前には優ちゃんが居るしな?でも、どぉぉおしても!って言うから。」 「断る。」 「そこを何とか。」 「嫌だ。」 パンと手を叩かれて拝まれても嫌なものは嫌だ。 「えー、他の人は?」 とりあえずターゲットを変えた川島が圭斗から目を離した。あくまでとりあえずだ。諦めたわけじゃない。 「俺行きたい!」 「あー、うん。」 唯一元気よく答えた巧太郎を適当に流す。もっと相手をしてやれ、かわいそうだろ、いくら巧太郎だって。え?笑ってないぜ?笑ってるのは薫だ。 「冷たい!羅門さんも坂本さんもヒロカズも笑うなんてひどい!」 「あっははははは!」 「羅門さん!」 いっそう声を上げて笑う薫に弘太郎が猛抗議した。 「羅門君はどうだい?」 「他の、人の、答えに、寄りま、っふ~~っ!」 落ち着け。 薫は今はこんなだが俺らや気を許した一部の相手の前でしか笑い上戸にはならないらしい。彼を上品で品行方正な美青年だと思っている法学部の皆さん、見てほしい。これが彼の本当の姿です。顔面崩壊。 次に川島は香清を見る。 「俺パス。興味ない。」 答えはすげない。 「全滅!!じゃあじゃあ、君は?イケメンだし、来てくれたら首が繋がるかも。」 頭を抱えた川島はヒロカズを誘った。 ただの合コンの人集めに首切りも何もないだろう。 「え、僕イケメンじゃないですよ。」 場を白っとした空気が満たす。特に巧太郎は、はぁぁああ、と重く呆れたようにため息を吐いた。 それだけ背が高くて足が長くて、筋肉ついてて、輪郭がシュッとしていたら充分イケメンだ。 「は、何言ってんの?イケメンでしょ。」 「いえいえ、ありえませんって。お世辞言ってもその日は無理です。」 川島の怪訝な声に、ヒロカズは本気でそう思っているのか、ぶんぶん首を振って否定し断った。 「えーーー!!死ぬ、殺される。」 もう良い!と言って川島は席を乱暴に立った。 「え、諦め早くね?」 いや、万々歳なのだが。しかし、圭斗が拍子抜けしたのも束の間、携帯電話を取り出した彼はすぐに誰かに電話をかけた。数秒待って、 「もしもし優斗君ですか、金曜日圭斗君を合コンに連れてい――」 「ふざけんな!殺すぞ!」 圭斗はすぐに彼を蹴り飛ばして絞め技をかけた。 「ギブギブギブギブ」 『もしもしー?川島―?』 「優斗!何でもねぇから!」 『あ、圭斗!合コン行くの?』 「行かねぇから!!」 それだけ言って通話を切り、川島を睨みつける。 「あー、でも三人のうち誰も連れてけないなんて…」 川島はがくんと肩を落とした。しかし奴はすぐに復活する。 「あ、そうだ!君たち、学内に気になっている異性はいないか?この際同性でも良い!呼んでやる!」 また悪足掻きを…と思ったが、予想外の奴がそれに反応した。 「名前しか知らなくても良いですか。」 「「「「え!?」」」」 現在もヒロカズの背に腕を回し、細マッチョな彼の胸筋を撫でまわしている円佳香清だ。 香清と川島以外の四人が驚きの声を上げた。 「円佳お前、マジか。」 圭斗が詰め寄り。 「マガミ君はダメだよ?行けないって言ったからね。」 薫も乗り出す。 香清は違うとかぶりを振った。 「ヒロカズは名前しか知らなくない。」 「え?お前マガミ以外に気にしてるやつとかいるの、え?」 「誰だ、誰だ!」 困惑する中、川島が俄然やる気で聞きだした。 「モウエヤマトです。」 その名前を聞いてヒロカズが「えっ」と声を上げた。 同時に巧太郎がぷくっと片頬を膨らませたが、別に意味は無いだろう。 「知ってるのか!?」 「い、いえ!この前香清が話していたので!」 その人物を探さなければならない川島はすぐにヒロカズに食いつくが、彼は慌てて否定した。確かに川島の剣幕はすごいが、それにしても慌てすぎじゃないだろうか。 仕方なく川島は香清に向き直る。 「どこの学科だ?」 「だから、名前しか知らないんです。」 「むしろなんで名前だけ知ってるんだよ。」 「見かけたときに周りに片っ端から聞きました。」 「じゃあ、見た目は分かるんだな。」 「身長151㎝、手が綺麗で、キャミソールが似合うくらい肩まわりと腕がスラッとしてて、足首もウエストもきゅっと締まってて、それでいてお尻と太股に良い肉がついてて、バストサイズはFカップ。色白の肌はきっとマシュマロみたいに柔らかいはず…」 「体だけ!」 思わず巧太郎が口を出した。薫?あいつは死んだ。 「てかなんでそんなに詳細に知ってるんだよ。」 「見ればわかります。」 圭斗が聞けば当然だろうと、そんな答えが帰って来た。 「…っ、安定の、円佳…。」 何とか復活した薫がそれだけ言った。もう良いよ、お前は机とお友達になってろよ。 「安定の円佳。でもそれは探せない。」 弘太郎は冷静に返す。 「怖ぇよ。」 圭斗はドン引いて返す。 「顔の特徴も頼む。それから何処で見たか。あと、誰かと一緒に居たならその人の特徴も。」 香清に耐性の無いくせに冷静に質問を重ねる川島の合コン野郎根性は流石と言わざるをえない。 「三白眼で、ぼけっとした顔。髪はヒロカズくらいの茶髪で癖毛ロング。団子にしてたけど、ランニング中だったからかもしれません。木曜四限の時間に正門の方で見かけました。選択体育のランニングだったんだと思います。一緒に居たのは身長170㎝Bカップ、手足の長い細身のショートカットの女生徒です。」 「他に情報は。」 「もうありません。」 「分かった。どうにかして調べてやる。」 「え、マジですか。」 「やると言ったからにはやる!そしたら来るんだな!?」 「その子が来るなら。」 川島は「よし!」と拳を握った。 「羅門君は?」 「円佳君が行くなら。」 「よっしゃ、分かった。じゃあ、早速探しに行くからじゃあな。」 彼はそう言い残すと、さっさと椅子を片して去って行った。
酔いどれ
「何でもってんの?何でもってんの?飲みたりないからもってんの?は~い、飲んで飲んで飲んで飲んで~♪」 コールに促されて、円佳香清はかれこれ何杯目になるか分からないジョッキを煽った。 C棟での暴走のあったその日のうちに、川島からヤマトに連絡があった。熱烈な勧誘に若干引いたが、特に断る理由もないので了承した。それにしても特定が早い。 そして次のランニングの時、何処からか合コンのことを聞きつけた聡美に「ヤマトちゃんぼけっとしてて危なっかしんだから、一人で行ったらダメよ!」と、一緒に行くと宣言された。 合コンの男側幹事は当然のごとく川島で、男は川島・香清・薫・巧太郎、それから川島と同期でOBの佐々木と小堀。女は幹事の百瀬と新垣・中野、そしてヤマトと聡美と太陽。 当然まずは自己紹介!となるところが、巧太郎が太陽を見るなり、 「山田さん!?彼氏いるのにこんなところ来ちゃだめじゃん!」 と、叫んだために一悶着あった。 どうして彼が彼女を知っているのかと、ヤマトは疑問に思ったが、そういえば巧太郎は照と同じ高校だったと言っていたな、と思い出した。ならば彼と幼馴染の太陽とも接点があっても不思議ではない…か? 「俺の親友泣かしちゃダメ、絶対!」 巧太郎がきゃんきゃん吠える。照とは関係無かったようだ。 それはともかく、山田さん…彼氏いたのか、こんなに男前なのに。 「いや、どうしてもと言われて。」 どうしてもと言って誘ったのは聡美だ。一人じゃヤマトを守り切れるか心配だと思ったらしい。彼女の目にはヤマトがどう見えているのか。 「光には言って来たんだけど…。」 「光?」 ヤマトは聞きの覚えのある名前を反復した。 「ああ、ヤマトも知ってるよな。私、光と付き合ってるんだ。」 ――藤本光、照の弟だ。巧太郎と太陽の繋がりに照が関係無いなんて誰が言った。 「ヤマト?」 「ヤマトちゃん、大丈夫?」 「――あ、うん!大丈夫だよ!」 固まってしまったヤマトを心配した太陽と聡美に慌てて返事をすると、川島が仕切り直しだ、と手を叩いた。 「おい、ちょっと飲み過ぎじゃないか?」 喉を鳴らしてビールを飲み干し、ジョッキを置いた香清に声を掛けた。 彼はすでに手まで赤く染めあげて目をトロンと潤ませている。 合コン会場は個室の座敷で、開始時の男女向かい合わせだった席は崩れて、ヤマトは香清の隣に居た。 川島はおっとりした美人の新垣に狙いを定め、佐々木と小堀はタッグを組んで百瀬と中野を口説いている。 お調子者の弘太郎は相手がいるか心配だったが、太陽と楽しげに話していた。合コンの楽しみ方としては間違っているが、まあ良いのだろう。 聡美は教授からの電話で席を立っているが、先ほどまで薫とのんびり飲んでいた。 香清は安定して開始時からヤマトを視界から離さず、気が付けば隣に居た。香清を呼んで来いと言った人が居る筈だったが、あまりに彼がヤマト一直線だったため諦めたようで見当たらなかった。それか、薫もフリーの様だし、目の保養が欲しかっただけかもしれない。 「ヤマトちゃんに良いとこみせたいんだろ~?」 「なになに?やっぱりヤマトちゃん狙いな訳?」 すでに酔っぱらった様子の川島と新垣が話しかけてきた。 「え~ショック~!」 まだ誰も答えていないのに新垣はそう言って赤い頬を両手で挟んでショックを受けた仕草をする。 「いや、モウエさん狙というか、モウエさんの体が好きと言うか。」 「あはは!冗談おもしろ~い!」 一瞬何が起こったか分からなかった。 香清の言葉に、何を思ったか新垣は、彼の手を取って、えい!とヤマトの胸に押し付けたのだ。 ゆっくりと掌が動く。 ――あ、柔らか… 彼の口元が小さくそう動いたように見えた。 やわやわと乳房を揉まれ、ブラジャーがずれる。ブラから出てきてしまった突起を服越しに触られて…ヤマトはやっと正気に戻った。 「~~~っ、い、やぁぁぁあああ!!」 彼を突き飛ばして、胸を押さえて泣きじゃくる。 「あ、悪い!無意識で!」 「うぐ…っ、ぐす…っ」 混乱した頭では、謝っている彼に何を言って良いか分からず、ただ溢れてくる涙を拭った。 「ちょ、お前何女子泣かせてんだよ!」 「あー、泣かせたいけないだぁ!」 それをおちょくる酔っぱらい二人。香清もヤマトも混乱しているのだから止めて欲しい。 「元もとはと言えばお前が…っ!」 口論になりそうなところで、ヤマトは香清を止めるために手を伸ばそうとするが、後ろから肩に手を置かれて止まった。 「ヤマトちゃん、大丈夫?」 佐々木と小堀だ。こちらも首まで赤くなってるが、川島程酔ってはいないようだ。 「あ、あの僕…」 「痴漢野郎は置いて、こっちおいで俺達と一緒に飲もうぜ。」 こっちと示された方を見ると、百瀬と中野がにこやかに手を振っている。 「こっちこっち」 佐々木に腕をとられて引っ張られる。ヤマトは「あ!」と慌てて手を伸ばしてきた香清の手を掴んだ。目がって、ほっと息を吐く。佐々木もその様子をみて腕を引くのを止めた。 「あ、あの。びっくりしただけです。大丈夫です。」 「なんだよ、ヤマトちゃんもまんざらじゃないんだ?」 「胸揉まれても良いんだ?」 「いや、そうじゃなくて。酔っぱらいのやることだし…」 香清をかばうヤマトに二人はじりじりと詰め寄った。やはり相当酔っているようだ。 「俺も酔っぱらいー」 「や!」 二人が勢いで抱きついてくる。 「あ!」 巧太郎と太陽が短く声を上げた。聡美と共にヤマトを守るために参加した太陽だが、佐々木と小堀が助けに入ったために静観していたのだ。 二人を避け、香清に抱きつく。半分立った状態のまま抱きついたために、香清の顔が豊満な胸に埋まった。 「ちょっとあんたたち!」 この状況をどうしようと思っていると、ふって来た天の声。 「私の居ない間にヤマトちゃんに何してんのよ!」 電話を終えて帰って来た聡美が帰って来た。 「ヤマトちゃん大丈夫?――って…」 彼女の存在にヤマトがやっと冷静になって香清を放すと、 「香清!」 彼はグラッとそのまま倒れた。 ****** 個室完備の居酒屋の前の長椅子で、背の低い女性が綺麗な顔の男性の頭を膝に乗せている。若者向けの店が立ち並ぶ通りは、店の明かりと街灯の明かりで夜でも明るく、二人を隠すものは無い。通りかかる独り身の誰かは、運悪く二人を視界に入れると舌を打って足早に通り過ぎた。 五月半ばにしては低い気温の外気を、気持ちが良いと感じつつ、ヤマトは膝上の温もりに手を伸ばす。滑らかな頬を撫で、セットの乱れた髪を梳いて、耳にかけてやる。 「う…ん…」 彼は、その感触に軽く身じろぎし、目を開けた。 程よく弾力のある枕に、胸に置かれた暖かな手。安心する。また、違う手でそっと頬を撫でられた――手? 香清が重たい瞼を持ち上げると、ヤマトが顔を覗いていた。 「!」 すぐに状況を確認する。 頭の下には枕があった。しかし、枕は枕でも膝枕だ。 私服姿のヤマトは、ストラップをきつく絞ったキャミソールに、大きな襟がふわふわと波立つ、透ける素材のブラウスを重ねて、綺麗な肩周りを見せつつ、胸をがっちりガードして、下半身はふわりと広がる超ミニの花柄のフリルスカートを履いていた。 こちらは何も言っていないのに、聡美が「この子、この下にぺチパン履いてるんだからね。パンチラとか期待するんじゃないわよ!」と牽制してきたのを思い出す。 ペチパンの意味が分からなくて、仲良くなってきた頃にヤマトに直接聞くと、「パチパンツっていうフリルの付いたショートパンツだよ。」と、スカートをめくって見せてくれた。裾の方が透けていることに少し興奮したのは内緒である。 長くなったが、何が言いたいかと言うと、彼女は今、生足でミニスカートだということだ。香清の頭の下に、白く柔らかな、触りたい衝動を必死でこらえた生の太股があるということだ。 覚えている、正座をした彼女の太股の、柔らかそうなあの輪郭を、ふくらはぎの輪郭を。 「気分どう?」 訊ねてくる彼女を仰ぎ見る。豊満な胸の向こうに見える彼女の顔は、夜の光を反射して、キラキラと光って見えた。なにこのアングル、すごい。 「最高です。――え、いや、モウエさん?」 呆けてつい本音を漏らしてしまった香清は、慌てて彼女の名前を呼んで誤魔化した。 「うん。水飲む?」 ペットボトルを頬に当てられる。正直まだ起き上がりたくなくて、香清はそのままの体勢で受け取り、彼女を見つめた。 「あれ?」 まだ頭が混乱しているふりをする。 「円佳君酔いつぶれちゃって、誰も家知らないって言うから、起きるの待ってた。」 「悪い。」 「ううん。」 彼女は柔らかな声と表情で言った。安心する。ヒロカズと一緒に居る時みたいだ。 彼にするように甘えたくなって、ふと、こんな時に邪魔に入りそうな聡美が居ないことに気づく。良く見れば自分とヤマト以外のメンバーの姿が無かった。 「え、モウエさんだけで?」 「みんな二次回に行くか、帰ったよ。でも、ちょっと前まで巧太郎もいたんだけど。」 香清の眉間に皺が寄った。すっと胸が冷えて、痛みを感じる。 「…弘太郎?」 いつの間に下の名前で呼ぶまで仲良くなったのか。 「あ、えっと。彼とは中高が一緒だったんだ。」 そんなの、聞いて無かった。何でだ、三反田さんも言ってくれたら良かったのに。 「三反田さんは、用事?」 「電車無くなるって。」 「…何時?」 「ん?今12時。」 終電終わったな。 香清はゆっくりと身を起こした。 「起きて平気?」 「平気。ていうか起きないとだろ、重いし。」 そうは言ったが、ぐらりと眩暈がした。強く目を瞑ってやり過ごす。すると、肩を押されて、トスンと膝に戻された。 「え?」 「どうせ終電終わっちゃったんなら、良いじゃん。」 見下ろして笑いかけられる。 酒のせいではなく、ぼーっと顔が熱くなるのが分かった。居た堪れなくなって、「うう…っ」と呻いて視線を逸らす。 「…あ。」 「ん?」 「さっき、ごめん。」 泣かせてごめん。 「え、ああ、うん。大丈夫。ちょっとビックリしただけだから。」 ヤマトはふふっと笑って、脂肪が少ない割に柔らかな掌で香清の頬を撫でた。 「…ん」 「あっごめん、つい。」 心地よかったのに、気づいた彼女はすぐに手を放してしまった。 「…なんでモウエさんが残ってくれたんだ?」 ふと疑問に思ったことを聞いてみる。 「だって、一人で放置しておくわけにはいかないし…、」 「他の人も任せられただろ?」 「うん。――いや、僕が、他の人には任せたくないな、って。」 「え」 はにかみながらの台詞にどきりとした。しかし、続けて耳に入ってきたのは、ときめきの余地のないこの台詞。 「円佳君の顔、すごく好みなんだ!」
連絡先が知りたい
合コンのあった金曜日から週末を挟んだ月曜日、東の門から続く並木の緑が濃くなって、高く淡く頭上に広がっていた空が、低いが眩しい青色に変る季節。5月はもう夏で良いよ、暑いもの。ヒロカズは小生前で配られた試供品の苺アイスを口に含んだ。 「木のスプーン、良い…!」 「そっち!?アイスじゃないんだ!?」 向かいでチョコアイスを食べる巧太郎が言った。 「試供品アイスは良いね。タダだから余計に美味しく感じるね。」 抹茶味を食べながらそう言う薫は、いつも上質な布を使っていることが分かる、作りの良い服を着ている。お金持ちなんでしょ?良い所の坊ちゃんなんでしょ? 「んー、俺もチョコが良かった…」 チーズ味を食べながら圭斗が言う。圭斗が行った時にはチーズとキウイしか残っていなかったらしい。 大学生活が本格的に始まってもうしばらくするが、この4人に香清を加えた5人は午前・午後と跨いで授業のある日の昼休みは、ほぼ毎日ここC棟空き教室に集まっていた。 そう言えば、香清は今日は午後からの日だけど、ここには来ないのかな、ヒロカズがそう思うと丁度入口の戸が開いて彼が入ってきた。 「ヒロカズ!」 速足で近づいてきた彼は開口一番ヒロカズを呼ぶ。 「なに?」 「ヒロカズヒロカズヒロカズヒロカズ!」 「う、おう。」 そのまま名前を連呼しながらヒロカズの肩を掴んでガシガシと揺すってくる香清。 「どうしよう、ヤマトちゃん可愛い!」 「え、お前金曜はモウエさんって」 なされるがままになっていたヒロカズが彼のヤマトちゃん発言につい口を出すと揺さぶる動きが止まった。 「なんで知ってるんだよ。」 「あ、いや巧太郎から聞いた。」 本人だとは言えない。 「胸揉ませて!」 「は?」 ヒロカズが香清の純粋な眼から視線を逸らすと、彼は胸を弄って来た。 その感触にヒロカズの中にむず痒い何かが込み上げる。彼が体に触ってくるのはいつものことだ。しかし、今日は勝手が違かった。 先日ヤマトの時に彼に触られたのが、原因かもしれない。いや、確実にそれだ。男の時と、女の時では感覚が違う。ヤマトは胸が大きいから、女子にふざけて触られたことはあるが、あんなブラを介さない生に近い状態で、それも、その…突起まで触られたのは初めてで…、だから困るのだ。 香清の手を掴んで慌てて引きはがすと、彼はなんで?と不思議そうにヒロカズを見た。靴底の違いも入れて、身長差15センチ。自然と上目遣いになるヒロカズ好みの顔が見つめてくる。可愛い、可愛すぎる。しかしダメだ。 「無理、耐えらんねぇ!」 「おいおいおいおい、ちょ、まっ!」 ヒロカズは駄々っ子のように暴れる彼の手が使えないように背中に回して抱きしめた。 「どうどう。落ち着け。」 「う~、う~、」 唸ってる香清可愛い。美形は歯を食いしばって苦悩の表情を浮かべても崩れないんだな… 「何そいつ、どうしたの。」 一連の流れを見ながらひとり状況がつかめない圭斗が言った。 「…っいろいろあって、…っ、例のモウエさんの~~~っ!!胸揉んじゃったん、ファー…っ!ですよ。ね。」 笑いを堪えながら羅門が答える。香清が登場したあたりから死にそうだ。 「はぁ?」 「あっはは…っあ、事故ですよ。」 「羅門さん、その時は起きてたんですね。」 巧太郎が言った。薫はその日、寝落ちして迎えが来たのだ。モノトーンで纏めたノーブルな雰囲気の背の高い人で、薫をお姫様抱っこして帰って行った。あの人は誰だ、執事か。やっぱりこの試供品アイスで喜んでいる御人は金持ちなんじゃないのか。 「はー…、いや、寝てたけど。」 笑いを収めた彼はけろっとした顔で答えると、うふふと笑った。さっきまでとは違う意味深な笑みだ。 「すげーな。ラッキーすけべじゃん。でも気まずくなっただろ。」 そういう圭斗にまた薫が答える。 「いや、それが。彼女、胸を揉まれた時は泣いてしまったんですけど、そのあと酔いつぶれた円佳君と一緒に店に残って介抱していたみたいですよ。ね、三反田君も一緒に残ったんだよね。」 「いや、だからなんで知ってるんですか。」 「笑い上戸の上サトリって、設定盛りすぎじゃありませんこと?」 「そんなことないよ。」 巧太郎につっこまれて、圭斗におどけて言われて、薫は肩を竦めた。 そうこうしている間に香清が大人しくなったので、手を開放するとヒロカズの背中に手が回ってきた。よしよしと頭を撫でてやる。 「いや、でも俺は終電で帰りましたけどね。」 「おまえ、この変態と女の子残して帰ったのかよ!」 巧太郎の発言に、圭斗が思わず椅子から立ち上がった。 「いや、円佳なら大丈夫だと思いまして。」 「こいつだからダメなんだろうが!」 指をさしての猛抗議だ。まあ、普段の彼を見ていればその反応も仕方ない。 「円佳君、手出してないよね?」 薫がふると、香清はほわんと頬を染めて表情を緩める。 「ヤマトちゃんに膝枕されたまま話して、朝が来て…幸せで…」 そして言いながらヒロカズの尻に手を伸ばす。 「ちょっとちょっと、胸がダメだからって、尻を揉むな!」 「うわぁ…」 圭斗が引き攣った顔で引いた声を出した。 「あっはははは!」 薫の笑い再び。 「う~、硬い。」 「怒るよ。」 男の尻なのだから硬くて当たり前だ。ヒロカズが叱ると香清は大人しくまた背中に手を戻した。 「うまくいきすぎだろ。」 「あーまぁ、ヤマトだしなぁ…」 彼らの周囲の目をはばからない過剰なスキンシップにはもう慣れたものだ。圭斗はそれを軽く流して話を戻した。 「そうだ三反田さん!」 巧太郎の言葉に、思い出した!と、香清が叫んだ。 「ヤマトちゃんと中高一緒だったらしいじゃないですか!」 聞いて無い!聞いて無い!と、ヒロカズに抱きついたまま抗議する。 「うお、おう!中高っていうか、小学校の途中から高校の途中までだけどな。いや、別に隠してたわけじゃなくて!えっと、連絡なんて取ってないし、この大学に居るなんて知らなかったし!あげられる情報無いから良いかなって!な!」 そう言ってヒロカズに話をふった。何故ふった。 「そうなの?マガミ君。」 と、薫。この人は秘密を知らないはずなのに。 「あげられる情報、大いにありますよ!中高時代どんな子だったとか!」 ヒロカズが何も言わないでいると香清が続ける。 圭斗は合コンの話が出て、香清がヤマトの名前を出した時に巧太郎が変な顔をしていたのを思い出した。あれは笑いを堪える顔だったのか。じゃあ、こいつ確信犯じゃねぇか。でも、面倒くさくなりそうなので指摘はしないことにした。 「そそそそ、そんなことより!あれだ、俺が帰った後どうなったんだよ?」 「すごく優しく介抱してくれました。」 「どうなってんだよ。」 圭斗が冷静にツッコんだ。胸を揉まれて泣いて、一緒に残って、介抱して。その女がどういう思考なのか分からない。 「マガミ君、実際のところどうなの?」 「いや、あれは手のかかる弟の面倒を見ると言うか、母性本能と言うか…って、あっ、ぼ、僕に聞いたってし、知りませんよ!」 ヒロカズは薫に自然にふられて思わず答えてしまい慌てる。 「えー?」 それに不満そうに声を上げる薫。この人本当に何者なんだ…、ヒロカズは冷や汗をかいた。 「でも円佳君のその様子じゃ、すぐにメールとかしたんでしょ?」 続けて薫に言われてヒロカズと香清は二人して間抜けな声を上げた。 「「あ」」 慌ててヒロカズは手で自身の口を塞ぐ。 「メアド交換するの、忘れた。」 ヒロカズを除く一同、香清の言葉にぽかんと静止した。 「あっははははは!」 一拍おいて薫の笑い声が響いた。 ****** その週の木曜日、ヤマトは聡美と一緒に校内を走っていた。 ヤマトは時折モスグリーンのアメリカンスリーブ姿の聡美を仰ぎ見る。彼女は私服でもランニングの時でも、いつもアメリカンスリーブを着ていた。首の根元から袖ぐりの下まで斜めに大きくカットした、肩を大きく露出するデザインは、モデル体型の彼女に良く似合う。ヤマトは見るたびにうっとりした。 「モウエさん!」 正門のあたりで良く知った声に呼ばれる。ヤマトが返事をする前に、聡美がヤマトを庇うように前に出た。 「ちょっと、円佳香清!」 ああ、仁王立ちする後ろ姿もかっこいい。 「貴方、私が居ない間にヤマトちゃんにあらぬことをして泣かせたらしいじゃない!」 ああ、そういえばそんなこともあった、とヤマトは呑気に思った。 「それはもう謝りましたよ。」 「そういう問題じゃないわよ!貴方みたいな変態にヤマトちゃんは渡しませんからね!」 「な!あんたには関係ないだろ!?俺はヤマトちゃんと話しに来たんだ!」 「ヤマトちゃんですって!?いきなり馴れ馴れしいわよ!」 呑気に見ていたヤマトだが、二人して喧嘩腰になっているのでさすがに慌てだす。 「ちょっと待って斉藤さん!僕は気にしてませんから。」 「ほら、ヤマトちゃんだってそう言ってるじゃないですか。関係ない人は引っ込んでいてください。」 「香清!」 聡美を宥めにかかった大和だが、この香清の発言はいただけない。 「さっきから、斉藤さんは僕を心配してるのに失礼だぞ。」 「え、いや俺は…そういう意味じゃなくて」 ヤマトに叱られた香清は母親に叱られた子供のようにたじたじと語尾を濁した。 「どういう意味よ。」 「斉藤さんも、僕は気にしていないので、そんなに香清を責めないでください。」 「…なんでヤマトちゃんまでこいつのこと名前で呼ぶのよ。」 「あ」 しまった。ヒロカズの時の癖がでてしまった。 「もう、ヤマトちゃんは優しいんだから…。貴方、ヤマトちゃんがぽやぽやしてるからって、付け上がるんじゃないわよ。」 「あー、あー、」 香清につっかかる聡美を制してヤマトは香清に向かった。 「かす…円佳君。僕、今授業中だから、終わったらラウンジで会わない?」 「あ、はい!」 良い返事を聞いてふわりと笑う。 「じゃあ、また。」 香清はそう言って走り去る大和をほわほわとした気持ちで見送った。 「ヤマトちゃん!」 ヤマトがラウンジに着くと、すぐに香清が速足で迎えてきた。すっかりヤマトちゃん呼びになっている。 「今日も可愛い服だな。」 今日のヤマトは落ち着いた色合いのベリー柄のタンクトップとショートパンツのオールインワンに、薄手のピンクのカーデガンを羽織って、足元はローヒールのエメラルドグリーンのパンプスだ。ヒロカズの時は長ズボンに高い靴、ヤマトの時は足を思い切り出してペタンコの靴と決めている。だってその方がかっこいいし、可愛いし。どうせ変わってしまう性別ならと、ヤマトも楽しんでいる。 「ありがとう。安物なんだけどな。」 「安物に見えないよ、センスが良い。」 お礼を言うと、肩に触れようとしたのか彼の手が不自然に上がって、下がった。自重したらしい。それが可笑しくてヤマトはくくっと笑った。 「あ~~~~~」 金曜日のC棟。机に突っ伏した香清が悲鳴を上げる。 「今度はどうしたんだよ。」 「モウエさんに説教されたそうです。」 圭斗が聞いてきたので事情を知っているヒロカズが答えた。彼は口調はぶっきらぼうだが、なんだかんだ面倒見が良い。 「恰好悪い所を見せてしまった…」 「あはは、円佳君が格好良かったことなんて無いでしょ。」 項垂れる香清を薫がえぐる。 「羅門さんきっつ!」 巧太郎がツッコむがこちらも笑っている。 「顔だけだもんな。」 「坂本さんまで!」 またしても笑いながら巧太郎がツッコむ。 「う~~~~」 味方が居ないと香清が唸った。 「モウエさんは気にしてないんだろ?唸るなよ。」 「ヒロカズ~~~~~~」 唯一優しい言葉を掛けるヒロカズに抱きついた。 「で、メアド交換してメールはしたの?」 「「あ」」 薫に言われてヒロカズと香清は二人して間抜けな声を上げる。 「忘れてた。」 「あっははははは!」 一拍おいて薫の笑い声が響いた。
香清とヒロカズ
それは香清と二人きりになったH2Oサークルの部室でのこと。 「っちょ、香清…っ」 部屋に入るなり香清はヒロカズの背中に抱きつき、逞しい胸を揉みしだいた。 それを引きはがそうと手をと掴み、体を捻ると、足が縺れて二人でその場に倒れてしまう。香清に上に乗られて、強かに腰を打ち付けたヒロカズは痛みに眉をしかめた。 「触らせて、お願い。俺の顔、好きにして良いから。」 ヒロカズ好みの綺麗な顔の香清が切羽詰った表情で、至近距離で見つめてくる。 「は、ぁん…っ」 少しぼうっとしてしまうと、シャツを捲られて胸を直に触られた。普段はヒロカズより体温の低い、さらっとしている手が、今は熱を持って汗ばんでいる。 「待って、香清…っ」 「ヒロカズ…」 別に彼に胸を触られるなんて初めてのことではないし、今まで何とも思っていなかった。しかし、前にも言ったがヤマトの時の後遺症でどうも変な気分になってしまうのだ。それにその場の雰囲気というものがある。「胸筋かっけー!」と言いながらぺたぺた触られるのと、鼻息荒く弄られるのでは訳が違う。 「止めろって!」 引きはがそうと顔に手を伸ばす。あ、顔可愛い…っ。 触られてるのはヒロカズのはずなのに、そんな恍惚の表情って何なの?赤い顔に潤んだ瞳、可愛くて突き放せるわけないじゃないか。 超至近距離の彼の、熱い吐息が顔にかかってくる。 「~~っ」 無理、無理です!色々無理です! 「ふ…っ、ん!」 胸全体を手のひらで擦るから、突起もくにくに転がされる。ヒロカズの口から甘い吐息が漏れた。 「ヒロカズ、可愛い…」 「可愛いのは香清でしょ、」 そう言って頭に手を回して引き寄せ、唇を合わせる。――あ、一線超えてしまった。 「どうやらヤマトへの欲望をヒロカズにぶつけているらしいんだ。」 白い壁にピンクの家具たち。ハートのモチーフが散りばめられた本日の世界の不思議研究会は、萌え萌えメイド喫茶風。 ヤマトはピンクのレースのクロスのかかった丸いテーブルにプリンを置いた。明とまゆと、空席の前に一つずつ。空席分はヤマトの分だ。 置いてから、ハート形の背もたれの、ハート形のピンクチェックのクッションの椅子に腰かける。 プリンはヤマトの手作りプリン。ご飯茶碗で丸く形を作って、半分に切ったクランベリーを乗せたおっぱいプリン。わざわざキッチンを借りた力作だ。 「どうして私に堂々と猥談ができるのかしら。」 明が白い皿に乗った白いプリンを木製のスプーンでつついた。ぷるるんと震えるおっぱいプリン。 「いや、ヤマトだから良いかと思って。」 ほら、ヒロカズだとアウトっぽいけど、ヤマトならセーフじゃない? ヤマトはおっぱおプリンを掬って食べる。甘い。おっぱいってこんな味がするのか。 「それ、プリンだから。」 「心読まれた。」 でもプリン美味しい。もうひと掬い口に運んでヤマトは続ける。 「それだけじゃないんだよ…」 ****** 選択体育の時間は学科によって異なる。美術科のヤマトと生活科の聡美は木曜日の四限目だが、法学部の薫は水曜日の四限目だった。 その週の四限の時間、香清と弘太郎と一緒にとっていた授業が休講になったので、三限が終わると三人でC棟に行った。 「あれ?羅門さん?」 一番に教室に入った巧太郎が先客の名前を呼ぶ。薫は手提げから運動着を出していた。 「次体育ですか。」 「更衣室で着替えないんですか?」 口々に言うと薫は整った顔に苦笑いを浮かべた。 「更衣室で着替えるのは、大勢に見られるから嫌だな。君たちなら良いけど。」 「?」 「だって、君たちは僕に欲情しないだろ?」 そう言ってふわりと笑う正統派イケメン。 更衣室なのだから男しかいないはずなのに、欲情されることを恐れる。これがイケメン。 「あ、でも。三反田君は目を瞑っててくれるかな?」 「欲情しませんよっ!?」 巧太郎の反応にアハハと軽やかに笑い着替えるために薫は服を脱ぎだした。それを見て三人が固まる。 ――全身キスマークだらけだ。 「――こんなの学科の人たちに見せられないでしょ?」 彼は艶のある笑みで言った。 ****** 「――そしてそれに触発された香清が…」 ヤマトは遠くを見つめる。 「なるほど。だから珍しくタイツを履いてるのね。」 「暑いのに…」 タイツだけでなく、肩も出していない。ヒロカズの服装で外に出ていない箇所すべて、ちょっと人には言えないところまで、くまなく吸い付かれたのだ。あの時のことを思いだすと全身がむずむずする。 熱くなった頬に、まゆの淹れてくれた水出し煎茶のグラスを当てる。あー冷たい。 「それから――」 「まだあるの。」 明が呆れた声を出した。 ****** その日ヒロカズはぼけっとして何もない所で足を捻り、いつも履いている下駄で鼻緒ずれをした。 これくらいのドジは良くあることで、擦ったところも大したことは無かったので、気していなかったのだが、香清と共に部室に行って裸足になると、目ざとく彼がそれに気づいた。 「ヒロカズ!?」 座っていたヒロカズの足を持ち上げて、叫ぶ香清。そのせいでヒロカズは後ろにひっくり返った。 「どうしたんだよこれ!」 「ちょっと鼻緒ずれして。」 「あー、あー…、――筋張って血管の浮いた甲と土踏まずのくっきり抉れたメリハリのある足底から続く外に開いた存在感のある五つの指。がたついていない形の良い爪を付けたそれらは理想的な厚みのある皮に包まれていたというのに、こんな、こんな…」 香清は説明口調で一気にまくしたてた。ヒロカズの足を持つ手が震えている。 「フェチすげぇ。」 「こんな赤く…っ」 そのまま彼は何を思ったかその微かに赤くなった親指と人差し指の間を舐めた。 「うひゃぁっ!?」 尖らせた舌で舐められて思わず変な声が出る。 「やめ!それは汚いから!!」 慌てて彼を引きはがしたが、今度は押し倒された。押し倒されたというか、抱きつかれた勢いで倒れた。 「お前の体は至高なんだ!お願いだから傷つけないでくれ!」 そう言って体を弄りだす香清。 「分かった!分かったから!これから気を付けるから!落ち着いて!」 襲われていると、部屋のドアが開いた。幻十郎だ。 「助けてください!」 ヒロカズが言うのに、彼はカメラを構えてカシャカシャとその様子を撮りだした。 騒いでいると、隣の文化祭実行委員室から薫が助けに来てくれて、やっとヒロカズは解放された。 ****** 「影木さん、何で助けてくれないの…」 「彼は根っからの腐男子なのよ。」 「お知り合いですか…?」 「巧太郎の先輩なら、私の先輩でしょ。」 「そういえば…」 「ご愁傷様。」 「う~」 ヤマトは唸って机に懐いた。そんな彼女に明は追い打ちをかける。 「これから“も”頑張って。」 「う゛~!」
ふわふわる
いちふわ:歌声がふわふわ 授業が一コマ開いたうららかな午後、円佳香清はH2Oサークルの部室にて、うとうとと眠気に誘われた。 「香清眠いの?」 こくこくと赤べこになる香清にヒロカズが聞いた。 「う~ん…」 「子守歌うたった歌ったたげようか。」 「う~ん…」 彼は良いとも言っていないのに歌いだす。普段から彼の口調は間延びしていて空気が抜けたみたいな発声をするから、話していると眠くなる。そんな彼の歌う子守唄はきっと魔法のように香清を眠りに誘うのだろう、と思いきや。香清は彼が歌いだすと同時にガクッと、寝ながら器用にずっこけた。 「お、まえ…、クソ音痴だな。」 「えー。でも音は合ってるよ。テンポがずれるだけで。」 自覚はあるのか。 「眠気覚めたんだけど。」 「えー。でもこのテンポの悪さが癖になるって言われたのに。」 「誰に。」 「巧太郎。」 香清の眉間にむっと皺が寄る。 「やっぱり歌え。」 「おう。」 再び始まった彼の歌に耳を傾ける。確かに、テンポの悪さにふわふわした気持ちにさせられる気がした。 にふわ:注意力がふわふわ ヒロカズと、遊びに行ったとき、彼は信号が青なのに止まった。 「青だぞ。」 「あ、本当だ。」 「ヒロカズ、いつもそうなのか。」 「うーん。青信号一回分見過ごしちゃうのはもう仕方ないよね。」 「仕方なくない。」 ヤマトと画材を買いに行ったとき、彼女は曲らなくて良い道を曲がった。 「そっちじゃない。」 「あ、ごめん。無意識だ。」 怖い。 ヒロカズは目的を忘れる。 この前、トイレに行ってくる、と教室を出て行った彼は、帰ってきて「あ」と間の抜けた声を出した。 「どうした?」 「トイレ行ってくるの忘れた。」 「どういうことなの。」 そういえばヤマトちゃんも忘れっぽい。この前はしまったばかりのペンを探していた。 二人は結構似ている気がする。どっちも何もないとこらでこけるし、ヤマトちゃんなんてペタンコの靴で足を挫くし。ヒロカズもヤマトちゃんも至高の体をもっと大事にしてほしい。 さんふわ:警戒心がふわふわ ヒロカズとヤマトちゃんは二人とも、お酒飲むと膝枕をせがんでくる。しかも、何処でも寝られるし、寝起きはゆるゆる。ヒロカズはともかく、ヤマトちゃんは女の子なんだからもっと警戒心を持ってほしい。そう言ったら、 「んー?でも、ちゃんと友達がいる時選んでるよ?」 「男友達じゃダメなんだよ。」 「巧太郎と香清君は良いじゃん。」 「……」 巧太郎の名前が先に来たのが気に入らなかった。 よんふわ:メールがふわふわ ヒロカズとヤマトちゃんは、メールの絵文字が基本これ→♪\(´▽`*)ノ 香清はそんなメールに身悶える。香清は普段、二人がふわふわした行動をとると、なぜだかそのふわふわの髪をもふもふしたくなるのだが、メールではすぐにもふもふできない。困る。だから、次の日にヒロカズかヤマトのどちらを見つけたら、すごい形相で突進して無造作ヘアーをぐちゃぐちゃにする。 ****** 幻十郎「馬上君って、キスするときはべろ出して待ってるんだよって教えたら律儀に守ってくれそうなくらい世間ずれしてるよね。」 香清「ヒロカズは俺が守るから!」
外堀埋まった
ヤマトは日本画の研究室の匂いが好きだ。でん粉から作る糊の匂いも、裂を染める染料の匂いも、箔を張るのに使うベビーパウダーの匂いも、一般に臭いと言われる膠の匂いも全部好きだ。 紅躑躅の仕上げに入る。繊細なように見えてダイナミック。細かな描写よりも構成に時間をかけた作品は、空間を大事に描いた目に映えるものに仕上がった。しかし、何か足りない気がする。 コンコン 作業室の扉が叩かれる。 「はい。」 「呼ばれて飛び出てジャジャジャーン!新作のネタをいただきに参上しました!」 「巧ちゃんだ!」 「巧ちゃんです!」 テンション高く部屋に入ってきた巧太郎はヤマトの手元を見て声を上げた。 「あ!!これ、傘に描いて!」 ****** 昼休みのC棟は、最近いつもよりも静かな気がする。それは何故か?一際賑やかな三反田巧太郎が居ないからかもしれない。 「制作に夢中なんだよ。彼のモデル近々CD出すのにジャケ写で彼の服着るんだって。そりゃ張り切っちゃうよね。」 薫が言った。 「あれ、服飾科のモデルって、モデル志望がやるんじゃありませんでしたっけ。」 香清が言う。 「普通はな。モデル専攻には話が通ってて頼みやすいから。でも、別にモデル科以外に頼んじゃいけないわけじゃないぜ。それに、モデル科は服飾科に比べて人数が少ないから何人かの服飾科で一人のモデルをってことにもなる。でもそれを嫌うモデルも服飾科もいる。だから仕方なくモデル科以外を捜さないといけない事もあるし。」 「「へぇー」」 圭斗の説明にヒロカズと香清の後輩コンビが納得した。 「三反田君は最初からそのこしかいないっていうか、その子のために服作って二つ返事でOK貰ったらしいけど。どこだっけ?」 「芸能・アイドル・音楽。」 薫の質問に圭斗が答える。この人は割と細かいことまで覚えてるんだよね。 「みんなー!!見て見て可愛くねぇ!?ヒカリ最高じゃねぇ!?」 噂をすれば影。いつも通りテンションの高い巧太郎が、美女をひきつれてやっていた。 「巧太郎うざい。」 「巧ちゃん!」 巧太郎は、美女の辛辣な言葉に嬉しそうに返す。Mか。 「巧ちゃんうざい。」 嫌そうな顔をしながらもちゃんと言い直すヒカリ、ツンデレか。 艶やかな黒髪に、赤いリボンが映える。真っ白な面の中、頬と唇が桃色に染まり、くっきりした二重の大きな瞳のベビーフェイスは西洋の人形のように整っているのに、きつすぎる印象は無く、和の空気がとても似合う。顔立ちだけでも十分視線の吸引力となる彼女は、巧太郎のドレスを着てより一層輝いていた。 和柄のドレスは、紅躑躅・花山吹の色目を使った華やかな春の装いだ。浅紅の繻子織のボレロに、ドレス自体は黄色のちりめん。柄は細かい桜紋様。型は上半身はタイトに、下は逆お椀型のショート丈、ちりめんを断ち切りにしたふわふわレース。足元は紅躑躅のヒールの付いた下駄。 「ヒロカズと合作の傘は壊れるとまずいので展示と撮影の時だけ出します!」 自慢げに胸を逸らして巧太郎が言う。これだけ綺麗な友人が居たら自慢もしたくなるだろう。うらやましい。 「…男?」 教室中が彼女に見とれ、ほうっと息を呑む中、香清が眉を顰めた。 はあ? と、周囲が彼と彼女に交互に視線を向ける。 「ああ、ばれちゃった?」 彼女改め彼は、あはは、と笑った。 「ほんとお前気持ち悪いな。」 ヒカリを一目で男だと気付い香清に圭斗がドン引いた声を出した。 「綺麗…」 そんなやり取りには目もくれず、ヒロカズはふらふらとヒカリに近づく。 「あ、ヤマトだ。」 しかし、彼の言葉に固まった。 「え」 ヒロカズと香清が同時に声を上げ、動きを止める。 「ひ、光何言ってんだよ!ヤマトは女の子だろ!」 「光!?」 慌てた巧太郎が彼に言った言葉にヒロカズはさらに驚いた。 「あ、そっか。でも似てるなぁ。兄弟とか親戚にモウエヤマトって子居ない?というか僕のこと知ってるの?」 ヒロカズは首をぶんぶん振って否定する。 「こ、巧太郎に光は金髪蒼眼だって聞いてたから。」 「うん!これ、ウィッグとコンタクトだもん。」 「うぇえ、そうなんだ…そうなんだ…可愛いね…」 「良く言われる。」 「そう、ですか。そうだよね…」 ついに照の兄弟に直接会っちゃった。外堀がじわじわ埋まっていってもうフラグでしかない。ここまで来たらあと二人も来るよね。もしかして明とか糸引いてるの?偶然じゃないでしょ、これ… ****** モデルの写真と共に飾られた作品軍群はどれも輝いて見えた。巧太郎の作品は、大和との合作であるため、服飾科の展示と日本画の展示の両方で飾られることになっている。あの時感じた何か足りないという気持ちは、実用性という点にあったのだと、彼との共演を通して分かった。 ライトアップされた赤い傘を見て、意識せずに口角が上がる。にまにまと満足そうに笑うヤマトは、隣の香清が悔しそうに同じ作品を睨んでいるのに気が付かなかった。 丁度受付担当だった巧太郎を捕まえて、スゴイスゴイと連呼すると、彼は香清をちらちら見ながら気まずげに説明してくれる。何で気まずそうかって?何でか香清が巧太郎を睨むんだよね。何でろうね。 「いやぁ、照明とか会場はデザイン科に協力してもらって作ってるから作品も一層素敵に見えちゃうよねぇ…、明日のショーも演出はイベントプロデューサー志望の子たちと一緒に作るから豪華だよ。現役アイドルのヒカリも出るしね!というか、俺の去年の作品評判良かったから今年も出すことになって、それをTELと陽、あ、TELの双子のお兄さんね!が着てくれることになったから超豪華!!」 ヒカリの話を始めた途端元気になる彼は本当にヒカリが好きで仕方ないようだった。 夏休み間近。この時期になると日が落ちても蝉が五月蠅い。 「汗ばむ~」 「ヤマトちゃんは汗ばんでもなおそこが良い!」 「香清ちょっと黙ろうか。」 「分かった!」 放課後に芸術館で行われていた服飾科の展示会の帰り。すっかり日が落ちた校内はぽつぽつと街灯があっても薄暗い。圭斗の従弟は草陰から出てきた猫に驚いて「ぴゃぁっ!?」と叫んだとか。それが圭斗には可愛くて仕方ないんだとか。 そんなことを考えていたら出てきた。草陰から人間が。 「うわぁっ!」 「ヤ、ヤマトちゃん…っ!」 びっくりして香清の腕にしがみつくと、嬉しそうに腰に手を回された。こいつ本当に僕の体が好きなんだな。 それは置いておいて、草陰から出てきたのは、グレーの猫を抱いた―― その姿を見て、ヤマトは目を見開いて硬直する。いつかは出会うと思っていた。でも、いざその時が来るとこんなにも動揺して、こんなにも… 「――照。」 彼を呼ぶ声が震えた。 こちらに気が付いて彼が歩み寄ってきた。ヤマトの肩が震える。香清が庇うようにヤマトの前に出た。 「誰?俺は照じゃなくて陽の方なんだけど…あ!ヤマトだ!!」 その言葉を聞いてヤマトは慌てて香清の後ろから顔を出す。 「え、あ!陽さんか!ごめんなさい、暗くて分かりませんでした。」 「いや、明るくてもだいたいの人が間違えるから。」 「でも、僕は分かります!」 「うん。知ってる。」 照と同じ綺麗な顔が優しく微笑んだ。綺麗だ。ヤマトの世界で一番好きな顔だ。そんな表情を見たら、感極まって泣きそうになる。 「もう、照とは会ったの?」 「いいえ。」 「そう、――ねえ、君。」 陽の視線が香清に向かう。 「はい。」 「ヤマトのこと、宜しくね。」 猫の背を撫でながら彼は去って行った。 「あの人、誰?」 「――照の、NGのTELの双子のお兄さん。」 その名前に香清の胸が騒いだ。 ――また「TEL」だ。 大学に入学してからというもの、どうしてこんなにも付きまとう。 「ヤマトちゃん、知り合いなの…?」 「…昔、付きあってた。」 「え」 「本当に昔、小学生の時だけど、付きあってて…。でも、親の転勤で遠距離になって、そのまま自然消滅。ありふれてるでしょ。」 「ヤマトちゃんは…」 「でもね、僕…っ、未練たらしんだけどね…っ」 それより先を聞きたくない。でも、彼女の口を塞ぐこともできなくて。 「本当は、諦めたくなかったんだ…っ!」 男泣きする彼女の肩を黙って抱いた。彼女が泣いていることが切なくて、彼女が泣いている理由が悔しくて―― こんな時に、体だけではなく、すべてが愛しいのだと気が付いた。
思い出
「皆もう、大和に会ったんですね。」 香清によく似た顔立ちの男は、対峙する女に切り出した。 「貴方が最後よ。」 「貴女は、割と人の恋愛にちょっかいを出しますよね。」 「あら?そうかしら。」 女はおどけた声で答えて、ティーカップに指を掛ける。 「不思議が一つ減るかもしれませんよ。」 「前にも同じようなことを言われたことがあったのだけど…」 カップに口づけると、遠く過去を見る様に瞳を眇めた。 「結局私はやりたいようにやっているのよ。」 そんな彼女に男はフンと鼻を鳴らせる。 「まあ、こんなじわじわ追い詰める様なやり方、弄んでいるようにしか思えませんしね。」 「ちょっとした余興よ。楽しいでしょ?」 「悪趣味な。」 ふふっと楽しげに笑う彼女に侮蔑の目を向けた。 「でも付きあってくれるんでしょう?」 「逆らったら何をされるか分かったものではありませんからね。」 女の視線を負けない目力で返して、長い足を組み替えた。 ****** 「今日は転校生を紹介します。」 「親の仕事の都合で転校してきました。馬上大和(もうえやまと)です。宜しくお願いします。」 小学五年の春、短い髪があちこち跳ねて、ちょっととろそうな印象を受けるその子は、そう挨拶した。 「席は、そうね。照さんの隣が空いてるわね。二の川の一番後ろ。照さん。」 「はい。」 照が返事をすると、その子は途端に瞳を輝かせた。大きな瞳は黒目が小さいわけじゃないのに、白目の部分が大きすぎて三白眼になっている。 すぐに机の隙間を縫って進んでくるが、背中の古いデザインの黒いランドセルが邪魔そうだった。 「照くん!すごく綺麗な顔してるね!」 「え、うん。ありがとう。」 拳を握って感動しているその子に戸惑ってしまう。 綺麗だとか、可愛いと言われることはよくあるけど、嫉妬とか、羨望とか、下心なしに、こんなに純粋な目で言われたのは、家族以外に初めてだったのだ。 三日ぐらいたって、体育の時間にある事実が発覚した。当然自分と一緒に教室で着替えるものだと思っていたのに、大和が着替えを持って外に行こうとしたのだ。 「男子は教室で着替えるんだよ。」 そう言うと、大和は、目をぱちぱちさせてから言った。 「あ、えと。僕、女だよ。」 大和は女の子だった。 ちょっとビックリした。ちょっとね。だって身近に事例が3人いるから。逆に、大和の方が千晶と太陽が女だって知って驚いてた。 大和は、他の女の子(幼馴染を除く)みたいに媚びてこないし、俺を特別扱いしないし、さばさばしていて、一緒に居て楽だった。でも、最初の印象通り、どこか抜けていて、何回も校内で迷子になったり、何もない所で転んだりするから、なんだか目が離せなかった。 ところで、その頃、光とは別のクラスだったのだが、このクラスに幼馴染(明を除く)が集合しているからか、休み時間になる度に遊びに来ていた。 もちろん大和とはすぐに仲良くなった。大和は光に初めて会った時も、 「すごくかわいい顔してるね!」 が第一声だった。 でも、最初の頃は仲が良かった二人は、日がたつほどに変な感じになっていった。光はいつも通りなのだが、大和の元気が無いのだ。 特に俺と光がくっ付いているとき。俺は光が好きだから、光にぎゅうするし、光は俺が好きだから、光は俺にぎゅうする。そんなとき、大和は暗い表情になった。もしかして、大和も仲間に入りたいのかな、と思ったが、大和は女の子だからぎゅうできない。光も、太陽以外の女の子にはぎゅうしない。 照と光と陽と千晶と明と太陽と大和は毎日一緒に帰った。 照のランドセルと陽のランドセルは紺色で、光のランドセルは水色。千晶と太陽のランドセルは茶色。明は灰色。大和は黒。 いつも照・光・陽は並んで手を繋いで歩いているから、大和はそんな三人をいつも後ろから見ていた。 最初のころは「仲良いなー」「かわいいなー」と思っていたが、夏を過ぎるころには、何だろう、あの繋がれた手を見ているのがすごく辛かった。 前に、 「大和、最近どうしたの?元気ない?」 って、照に聞かれたときは嬉しかった。でも、病気ではないし、自分がどうしたのか、自分でもわからないから、「なんでもない」以外に答えようが無かった。 照と光が仲良くしていると、頭が重くなって、悲しくなる。逆に照が自分に笑いかけると、嬉しいのに、泣きたくなった。 「恋ね。」 「恋?」 大和の気持ちに名前を付けたのは明だった。 でも、名前がついても何の解決にもならなかった。 だって、光に勝てる訳もないし、自分は三白眼だし。余計に辛くなっただけだ。 「…光は、照のことどう思ってるのかな。」 いや、態度を見てれば好きなんだな、って分かるんだけど。 って思ってたら、何処からともなく光が来た。 「大好きだよ!」 どこで聞いてたの。 てか、やっぱり、そうなのか…。 大和が照を避けるようになった。 あからさまに無視されるんじゃなくて、会話が続かなかったり、ふとした時に接触して、振り払われたり。視線が合わなかったり、移動教室で一緒に移動しなかったり、他の友達と仲良くしていたり。 それがすごく寂しかった。でも、決定的なことが無いから彼女を責めることもできない。どうしようもなかった。 それからしばらくしたある日、帰り支度をしていると、いつものように光が来た。萌え袖の白いセーターが可愛くて、 「可愛い。」 って言ったら、 「ありがとー。照大好き!」 って抱きついてきたから、 「俺も―。」 って言って、ほっぺにキスした。 ら、背後で「あ」って声がして、次の瞬間風が横をすり抜けていった。 「大和!?」 二人で彼女を追いかけた。 大和はすごく足が速い。 照は全然追いつけなくて、光と照の間に結構距離ができてしまった。でも、光は異様に運動能力に優れているから、何とか大和を捕まえることができた。 「やだっ、放して!今日は人で帰るからっ…」 俯いてしまった彼女の顔は見れないけど、声が震えていた。 「大和!」 照は、光に代わって彼女の手を取ると、そのまま抱きしめる。 「何で逃げるの、何で俺のこと避けるの、何で一人で帰るなんて言うの、何で泣いてるの…っ」 感情が爆発して、ずっと心の中でもやもやしていたものを全部吐き出してしまった。喉が震えて、大和を抱く手にやけに力が入って、なんかもうどうしようもなかった。 「…っ、ごめん、僕。…僕、照のことが好きなの。…ごめん。照には光が居るのに、ダメだって、思って…諦めようと思ったのに、僕…」 照に抱きしめられたせいで、訳が分からなくなって、言わないでいようと思っていたことをつい言ってしまった。ハッとして、照を見ると……あれ、顔が真っ赤だ。 「……や、大和?が?え、…ええ!?」 真っ赤な顔で、すごく慌ててて、こんな照初めて見た。 「ねえ、大和。」 話しかけられて、光がこの場にいたことを思い出した。というか今まで忘れてたなんて、慌てすぎだ。 「僕、照の弟だよ?」 「え?」 「だよ?」 「え?」 ちょっと何言ってるのか分かりません。 「大和。俺も大和が好きだよ!」 光の衝撃発言に続いて、照にまでこんなことを真剣に言われて、意味が分からない。 「大和。」 「はいっ」 「付きあってください。」 「はいっ」 家の間に田んぼがぽつぽつあるような住宅街は、人が少なくて、少し離れた大通りから自動車の走る音が聞こえていた。 そうして初めての交際が始まったが、幸せな時間は長くは続かず、大和は家の都合で、またその年度いっぱいで転校していった。 ――携帯を持っていなかった当時、パソコンメールでのやり取りが手間だから、自然に連絡の回数が減ったのだと思っていたのだけど… 男は席を立ちその場所を後にする。三白眼の男と女、二枚の写真を懐に入れて。
比重
窓とカーテンを閉めても蝉が五月蠅い。建物の外は眩暈がするほどに暑くて、冷房の効いた部屋では頭が痛くなる。でも、絵を描いている間は全てを忘れられる。頬を伝った汗が、顎先から画面の外に落ちて、はっとする。 「…お腹すいた……」 ヤマトは筆を置いて、コンビニ袋からおにぎりをとり出す。「ヤマト」はもう、しばらく彼に会っていない。 夏休みに入ってからも、盆の数日実家に顔を出せばいいと考えていた大和と香清は、だらだらと学校に通って、部室やC棟に入り浸っていた。 入学から4か月、毎日べたべたと周囲に砂糖を吐かせる二人は学内でも二個一扱いをされている。圭斗や薫や聡美の話だと、他学科にまで知れ渡っているというのだから、すごい話だ。 冷房の無い部室で、窓を開け放って、扇風機を回す。その日も、ヒロカズと香清は部室でお互いの絵を描いて、だらだらして、日が暮れるころにサークル棟を出た。 日中に比べれば気温が落ちるが、それでも汗が滲んで、湿気た空気がべたべた肌に纏わりつく。 真夏日でも、過剰なスキンシップを止めない香清に、圭斗が気持ち悪くないのか聞いたことがる。 「ことヒロカズとヤマトちゃんに関して言えば、汗ばんでしっとりした肌はそれはそれで良い!暑さはスパイスです!」 香清の答えに薫が笑い死んだのは記憶に新しい。 今日も今日とて、彼はヒロカズの腕を胸に抱いて寄り添う。サラサラの髪が肩に当たって、くすぐったい。ヒロカズだって、暑い日にむさくるしい男に引っ付かれたら堪ったもではないが、香清は別だ。汗をかいても、彼の汗はさらさらと澄んでいて、嫌な匂いもない。名前の通り澄んだ香りは、彼の体臭なのか、春よりも芳しく香って、彼に寄り添われるのは寧ろ心地良い。そんな風にして駐輪場に向かう途中、二人は、息を呑んで固まった。 ――照がいた。 ずっと覚悟していた。10年ぶりの想い人との再会。今はヤマトではなく、ヒロカズだからだろうか。その顔を見ても思ったよりショックが無かった。寧ろそれがショックだった。彼と同じ顔の陽と再会した時は、あんなに取り乱したのに。 照は、ゆっくりとこちらに近づいてきた。香清が、ヒロカズの手を離して距離を取る。 照は、ヒロカズの顔をじっと見つめると、すぐに香清を向いて言った。 「お前、この男と、ヤマト、どっちが好きなんだ?」 その言葉にヒロカズが慌てる。 「ちょっと照、香清と俺はそんな関係じゃ…あ」 思わず彼を名前で呼んでしまい、慌てるが、二人とも気にしていないようだ。 「お前にそんなこと言われる筋合いねぇんだけど。」 香清が、彼の視線を真っ向から受け止める。 「中途半端な気持ちでヤマトに付きまとうな。」 彼はそれだけ言うと、背を向けて行ってしまった。 「――恋と友情は別物だろ?」 照の背中が見えなくなって、香清がぼそりと呟いた。ヒロカズが目を見開く。三白眼の白目部分が広がって、ちょっと見れない表情になっただろう。 「香清、モウエさんのこと、好き…なの…?」 彼が微かに眉を寄せ、目を伏せると、睫毛の影が、柔らかな頬に落ちる。暗がりの中で見ても、その頬が染まっていくのが分かって、――すっと心が冷たくなった。 ****** 大和は、恋ができない。 大和は日毎に男女を行き来し、性行為をして初めて相手の望む性別に固定される。でも、今更片方の自分を消すことなんてできない。 今日の世界の不思議研究会の内装は、赤と青にくっきり分かれていた。 壁は上下に二色、テーブルと椅子も一つ一つが縦に二色。ヤマトの席も彼女を境に赤と青に真っ二つに分かれている。右目側は赤、左目側は青。色の境界にグレアが走るビビットカラーが目に痛い。 「僕は、僕のすべてを好きになっててくれる人じゃないとだめなんだ…。どっちの僕も好きでいてくれないと、消えちゃうんだ…」 「消えたら、何が悪いのかしら。」 まゆちゃんの用意してくれたベリーのタルトを口に運びながら、明が聞いた。 「男の時と女の時って、感覚も違うんだよ。」 ヤマトも彼女にならってタルトを頬張る。甘酸っぱくてきゅっと鼻が痛くなった。 「よく男女の友情は成立しないって言うじゃない。じゃあ、男でも女でもない俺は、誰と友情が成立するのかって。女のときは女の子と友達で、男は男って意識しちゃうんだ。男のときは男の子と友達で、女は女って意識しちゃう。」 明はふーん、と相槌を打つ。 「向こうが意識してると思って、態度を変えてるだけじゃない?女だから男にくっ付いたら、誤解されるだろうとか、男だから女にくっ付いたらまずいだろう、とか。」 「…なるほど。」 ヤマトはティーカップを回して間を取った。気持ちが苦しくて、なかなか言葉が出てこない。 「でも、どのみちどっちかに固定されたら変わるよ。」 夏は、フレーバーティーが美味しい。すっきりとした柑橘の香りが清涼な空気を運んでくれる。カップに口を付けると、思考も少しはクリアになる気がした。 「それに、絵を描くのもちょっと、感覚が違うんだ。ものの感じ方が、女の方が幻想的で、男の方が現実的なの。 女の方は質感と色。白が白じゃないって言うか…一つの色の中にいろんな色が見えてくる。たくさんの色を合わせるとその色になるって言うか…。男の時は黒みがかってしか見えない影の部分が、紫だったり、緑だったりが混ざって見える。逆に男の時は、形の奥行や重さ。 だから、二つを合わせて、夢でも現実でもない絵を描く。僕の絵は、女だけだとふわふわしすぎて、男だけだと、面白味が無いんだ。」 大和の生は何でできていると思う? 大和は何で生きていくと思う? この体質のために何を取って、何を諦めた? 「じゃあ、ダメね。」 熱くなった頭が一瞬で冷める。彼女の声はどうしてこんなに、するっと心に入ってくるのだろう。 ――ダメね ――ダメか、またダメなのか… どっちの僕も、好きになって欲しかったな……
面食い
歴史ある学校の中では建て替えられたばかりと言われても、私立大の綺麗な校舎と比べれば薄汚れ、アンティークと言っても差し支えないような他の棟よりむしろみすぼらしい服飾科研究室棟。 お盆明け、巧太郎が研究室に向かうと、思ってもいなかった他学科の後輩が待ち構えていた。入口の柱に、モデルさながらのポージングでそいつ、円佳香清は佇んでいた。 「三反田さん。」 「香清じゃん。何してんの?」 「三反田さんに聞きたいことがあって。」 「良く俺が来るって分かったな。」 「ツブヤイターで来るって言ったのを見たので。」 「ふーん。」 炎天下で光以外の男と話し込む趣味は無い。話しながら研究室に入る。今日はまだ誰も来ていないようだ。二年の鍵担当が自分で良かった。 「三反田さんは、藤本照のことを知っていますか。」 「知ってるも何も高校の同級だって。」 作業台の一つの横に荷物を置いて、彼にも適当に荷物を置けと促した。しかし、彼は考え込んでしまって動かない。どうしたのかと、巧太郎が近づくと、彼は他に人が居ないことを確認して、巧太郎の腕を引き、その端正な顔を耳に近づけ、 「…照とヤマトちゃんがつきあってたのは?」 爆弾発言をしてくれた。 「はぁぁあああ!?」 「まあ、小学生の頃の話ですが。」 廊下まで響く大声を出した巧太郎は、うそー、マジでー…?あの照が?と無意味に部屋をうろついた。 「それ、誰が言ったの?」 「ヤマトちゃんが。」 「まじかー…知らなかった。俺が照と知り合った時にはもう他の人と付きあってたから。」 「じゃあ、もうヤマトちゃんのことは好きじゃないのか?」 「そりゃぁそうだよ。だって、彼には中学から付きあってる恋人がいるもの。」 「はあ!?」 今度は香清の方が声を荒げる。 「だったら尚更あいつにとやかく言われる筋合いないじゃないか!」 「何を?」 「俺、明日彼女に告白する。」 「え」 巧太郎には全くついて行けないが、彼は何やら決意してしまったらしい。 その日も暑くて、タピオカジュースがとても美味しかった。 一緒に出掛けて、腕を組んで買い物をして、公園の露店でジュースを買って、傍から見たらデートだと思うだろう。でも、二人は恋人なんかじゃない。 男の方は、大きな瞳に長い睫毛の華やかな容姿をして、道行く女たちは隣を歩く女を羨ましいと思う。女の方は、顔立ちこそぱっとしないものの、大きな胸にくびれたウェスト、惜しげもなく晒されたもちもちの太股は、道行く男たちの視線を集める。 手漕ぎボートの浮かぶ池に、彼女は笹船を浮かべて笑った。シースルーのシャツから透ける、柔らかな曲線を描く肩を抱いて、男が言った。 「ヤマトちゃん。俺、君のことが好きだ。恋人になって欲しい。」 ヤマトは香清の真剣な顔を見ると、頬を染めて、俯く。 彼女が、彼に未練があることは分かっている。でも、スキンシップを拒まれないことに期待した。この反応に、期待した。 「…ごめんなさい。」 それでも答えは悲しいもので、 「僕は、僕のすべてを好きになっててくれる人じゃないとだめなんだ…。だから、ごめんね。」 彼女は辛そうに笑った。 ****** 夏休みで良かった。ヤマトが告白されたその日から、大和は香清から距離をとった。ヤマトはだめでも、ヒロカズとして友達でいたい。でも、今は普通の顔をして会える自信が無い。今は――そう考えているうちに休みも開けてしまったのだけど。 「ヒロカズ!」 「…香清。」 ヒロカズを見つけた香清は弾丸のようにとんでくると、その胸ぐらを掴んで縋った。 「なんで、急にサークル来なくなったんだよ!」 「それは、えーと。」 「ヒロカズ…?」 身長差で自然と上目遣いになった瞳が揺れる。その頬を撫でて強張った体を抱きしめた。香清はすぐにヒロカズの背中に腕を回して、嬉しそう笑う。 どうしよう、何だこれ、可愛い。香清は全然変わらないのに、胸が苦しい。 久しぶりに香清に会うのだと緊張して、寝不足だったヒロカズは、教授の声を子守唄に、こっくりこっくりと頭を揺らし、とうとう机に沈んで動かなくなる。 そんな彼を見て、香清もほっとした。夏休み後半、ヤマトに振られたと報告してから、急に彼が冷たくなった。C棟にもサークルにも顔を出さなくなって、メールの返信もそっけない。何かをした記憶はないが、嫌われてしまったのかと思って気が気じゃなかった。ヤマトだけでなく、ヒロカズまで離れて行ってしまうのかと、不安で仕方なくて。 隣で気持ちよさげに眠る彼の項に手を掛ける。 「うわぁっ!?」 ヒロカズは声を上げて飛び起きた。項を押さえた彼は、顔を真っ赤に染めて、皆に注目される中、教室から逃げ出した。 H2Oサークル部室に滑り込んだヒロカズは、項を押さえてその場に蹲る。なんでだ、なんでだ。どうしてこんなに、心臓が痛いくらいに高鳴ってる。 「どうしたの?大丈夫?」 「ふ、ぇ…」 顔を上げると、おかっぱ頭の可愛らしい顔がヒロカズを除きこんでいた。声を掛けられるまで気づかったが、確かに鍵は開いていた。部長、影木幻十郎は、間抜けな声を出したヒロカズを見て、苦笑いを浮かべる。 「何があったか知らないけど、誰にでもそんな顔を見せたらだめだよ。」 どんな顔ですか。 見つめ合っていると、背にした扉が勢いよく開いて、名前を叫ばれる。 「ヒロカズ!」 「香清!?」 肩で息をする彼に、胸がきゅんとした。 「なんだよ、お前、講義は?」 「お前が逃げるから、追いかけてきたんだろうが。」 当然のように言われてまた胸が苦しくなった。どうしよう、僕。死ぬのかな。 迫る香清。後ずさるヒロカズ。カメラを構える幻十郎。 香清に肩を掴まれて、綺麗な顔が間近に迫る。触られた箇所が甘く疼いた。身体全部が性感帯になってしまったみたいだ。顔が熱い、もう――無理だ。 ヒロカズは香清を突き飛ばして逃げだした。 ****** カウンター席のみのコーヒーの香ばしい香りが漂う喫茶店。昼休み、C棟に行かなくなったヒロカズは、学校近くの明おすすめのこの店で明と食事をとっていた。 「それは、彼があなたを好きだと理解してしまったからそうなったのよ。」 ヒロカズは、ここ最近の香清への過剰反応について彼女に相談していた。 「本当は好きなのに、てね。」 ヒロカズのもったサンドウィッチからトマトが綺麗に滑り落ちた。 ――え? 「あなた、いつから彼のことが好きなの?」 「――僕、香清のこと…好きなの?」 「僕は――」 ヒロカズが居ない。部室居ない、C棟に居ない、研究室に行っても逃げられる。隣にヒロカズが居ない。 最近、ヒロカズに噂がたった。理学部の才女、愛場明と付きあっているらしいという噂だ。なんでも若くしていくつもの特許を持ち、幼い頃から大手財閥のスポンサーがついた天才。頭だけでなく容姿もばつぐんに優れ、世界中に信者いるとかいないとか。女子大学生に信者って…。彼女の噂自体も過剰で、鵜呑みにできるものではないし、もしそんな人が実在したとしても、そんな天の上の存在がヒロカズと付きあっているだなんて信じられなかった。それを見るまでは。 腰までのびるふわふわウェーブの豊かな髪を揺らし、黒目がちな瞳が妖艶に微笑む。一目見て他と違うと分かった。そんな彼女隣に、彼が居た。 ぎゅっと胸が締め付けられるみたいに痛くなる。そこは、俺の居場所だったのに…。もやもやする。もやもやってなんだ。 ――お前、この男と、ヤマト、どっちが好きなんだ? なんだ、あいつの言ったとおりじゃん。 講義が終わると、ヒロカズは速攻で教室を出ていく。香清を避けるように離れた席に座って、そうやってまた避けて。 香清はその背を追って捕まえた。 「え、ちょ!?香清?」 彼の手を掴んでそのまま部室に連行する。 「何、どうしたんだよ。痛いから放せって。」 無言で腕を引く香清にヒロカズがおびえた声を出すが知ったことではない。放せって、放したら逃げるんだろう…? 部屋に入ると、ヒロカズに抱きついて、床に倒す。逃げられないように腕を押さえて仰向けになった彼に跨った。 「香清…?」 見上げてくる瞳は困惑していても嫌悪は無い。全力で抵抗すればすぐに逃げられるだろうに、そうしないのは何故? 「何で避けるんだよ。」 「何でって…」 「美人な彼女に誤解されたくねぇから?」 「はあ!?なんだよそ、れ…って、もしかして明様のことか!?」 「様?」 「超の付くナイスバディで巻き毛の、きついくらいの美人のことだろ?」 美人という言葉を聞いて、香清の眉間に皺が寄る。 「お前の一番は俺だろう。あの顔より、この顔の方が良いんだろう?なんでそんな奴のことを誉める。俺を綺麗だと言っただろう!?」 「待った、香清!それは大家だ!」 「大家!?おまえ、住むところまで顔で選んでんのかよ!?」 取り乱して叫ぶ香清の手をヒロカズが払う。まずい、逃げられる、嫌だ。 「そんなわけないだろ。ふつうに良い所で安いんだよ。」 ヒロカズは払った腕を掴んで引き寄せ、香清をぎゅっと抱きしめた。 「てか、までってなんだよ。」 逃げられると思ったのに、抱きしめられて、もう戻ってこないんじゃないかと思った温もりを与えられて、香清の瞳が見開かれる。 ヒロカズはそっとその頬に指先で触れる。自分のことで、彼がこんなに追い詰められると思わなかった。 「香清。」 名前を呼ぶと、胸いっぱいの好きが溢れてくる。 香清は、じわじわ瞳を濡らして、ヒロカズの手に頬擦りした。 「だって、おまえ。俺の顔が好きで一緒にいるんだろ?」 可愛い、何でこんなに必死なんだよ。香清が一番に決まってるのに。 「馬鹿だなぁ。顔だけで良いんなら、遠くから見てるか、それで足りないんなら、ここで描いていれば済む話じゃない。」 ぽかんと口を開いた彼の頬がぼっと染まる。ヒロカズは笑いが止まらなくなった。 「な、何がおかしい!?」 「ご、ごめん、無理。あはははっ」 「ヒロカズ!?」 もうダメだなぁ、香清のこと好きなんだもの。
カタツムリ
ヒロカズとヤマトちゃんが気になりすぎて、ストーカー行為に及んだ香清です。 ストーカーとか犯罪じゃん、とか思ったか。愛ゆえだほっとけ。で、だ。ここ数日で分かったことがある。いや、分かったことで余計分からなくなったと言おうか… ヒロカズとヤマトちゃんの絵は似ている。画材も同じで、メーカーも同じなら、汚れ具合まで似ている。それに…ロッカーが同じ? 香清はそれを見てついに動いた。ずっとおかしいと思っていた。でも、これは決定的だ。 「ヤマトちゃん。」 割烹着姿の彼女が振り返る。 「その絵…」 ヤマトは描きかけの絵と画材をそのままに逃げさった。 窓に向かって大きな木の机が数個と、間隔をあけて工作室のような作業台が数個並べられた作業室。壁沿いの棚にはミシン、引き出しには裁縫道具が綺麗に整頓されている。ちなみに巧太郎のお気に入りはミシン糸の棚。綺麗な色糸がグラデーションで並べられている。 作業台の一つにクッキーと、淹れたてのコーヒーを置いて、巧太郎は香清と向き合う。ちなみにこのクッキー、巧太郎のお手製である。 「今日はどうしたの?またヤマト?」 巧太郎がヤマトの名前を出すと、彼は途端に不機嫌な顔になる。 「やだなぁそんな睨まないでよ。付きあってるんでしょ?俺なんかに嫉妬すんなよ。」 巧太郎はお茶らけて手を振った。しかし、香清は不機嫌な顔を崩すことなく、むしろさらに憮然とする。 「付きあってません。ふられました。」 「は、」 巧太郎はクッキーを一つ摘まんで口に運ぶ。我ながら香ばしくていい出来だ。こりこりと良い音をさせて咀嚼し、一泊おいて、 「うそぉ!?」 叫んだ。 「はぁ!?うそぉ!?」 もう一度叫んだ。 その反応に香清は舌を打つ。この人がうざいと言われる訳が分かった。 「三反田さん、ヒロカズと幼馴染でしたよね?ヤマトちゃんとヒロカズってどういう関係なのか知ってますか。」 巧太郎は何も言わない。しかし、その顔を見て、何か知っていると確信した。というか、瞬き多すぎだ。 「ヤマトちゃんとヒロカズの絵が同じなんだ。ロッカーも同じで、モウエさんが、ヒロカズの絵の続きを描いてたんだ。」 「それは…」 「それは?」 黙り込んでしまった巧太郎の目をじっと見つめる。彼は目を逸らすとマグカップに手を伸ばした。そうだ飲め、喉を潤して吐け。 「…俺からは言えない。」 「三反田さん!」 潔く吐けよ! 「――ヤマトも悩んでる。ヤマトには秘密がある、人に知られたくないんだ。親しい人には特に。俺は、ヤマトから何も聞いて無い。だから、それを円佳に話して良いのか分からない。でも…、ヤマトが揺れてるのは見てれば分かる。」 巧太郎はふっと息をはき出し、少し笑った。 「円佳は、ヤマトにとって、特別なんだと思う。」 「ヒロカズは?」 「あ」 「さっきからヒロカズが出てきてないし、なんで三反田さんがヤマトちゃんを名前で呼ぶんですか?中高一緒だったのは知ってますけど、悔しい、気に入らない!!」 「いや、だって。円佳がヤマトのこと好きだって言うから、ヤマトの話がメインなんだと思って。と言うか、ヒロカズの方が気になんの?」 「~~…っ」 慌てて口を出た言葉だが、香清は巧太郎を問い詰める体制のまま耳まで真っ赤に染まった。人の顔が赤く染まるのを正面から見たのは初めてだ。 「へ、マジで…?」 「どっちも気になるに決まってるだろ!?片方には恋してて片方は親友だぞ!?というかだ、二人がどういう関係なんだって聞いてるんだから、だから――ぁあ、もう!!」 取り乱すから彼は、これはひょっとしてひょっとするかもしれない。 「円佳!」 「何だよ…っ!?」 綺麗にセットされた髪を振り乱して涙目で睨みつけてくる香清。敬語が外れてるぞ。別に良いけど。 「わかった。直接聞いて。ヤマトでも、ヒロカズでも良いから。知りたいこと全部、本人に直接。はぐらかされても、拒否られても諦めないで、しつこいって言われても、聞いて。」 そうしたらきっと分かるから。 ****** 数日後、香清はヤマトを呼び出した。 「ヤマトちゃん!」 「…香清くん」 学校の敷地の端にある広場は、池や水車のあるちょっと良い場所なのだが、いつも人が居ない穴場だ。一番暑い時期は過ぎたが、まだまだ残暑が続く。水車から跳ねるしぶきが恋しくて、二人してすぐ傍に立った。 「あの、この前は画材とか片づけてくれてありがとう。」 「あ、ああ。」 「あの絵はね、最初から合作しようって言ってたんだ。だから」 ヤマトの細い髪に飛沫が掛かってきらきら光る。 会うごとに好きなる。玉砕してからも、気持ちが終わることなんて無かった。 「この前、ヤマトちゃんは、ヤマトちゃんのすべてを好きになってくれる人じゃないと付き合えないって言っただろ?」 ヤマトは目を細めた。 「ヒロカズはヤマトちゃんの全部を知ってるのか?」 「違う、そんな関係じゃない。」 「分からなくなった。」 ヤマトにとっても、香清は眩しい。飛沫が掛かった彼は、全身で光を反射して、輝いて見える。 「ヤマトちゃんのことを知ろうとしたら、ヤマトちゃんのことも、ヒロカズのことも分からなくなった。」 最近、彼の辛そうな顔しか見ていない。大好きな顔なのに、大好きな表情を見ていない。 「ヤマトちゃんとヒロカズが仲が良いなんて知らなかった。好きな人のことどころか親友のことも、肝心なところ何も知らなくて。それに気づいたら、もう二人とも俺のそばに居なくなってた。」 「……」 「ヤマトちゃんのすべてを好きになるなんてできない。だって、おれは貴方のすべてを知らない。だから、知りたい。」 「――分かった。」 本当はもう覚悟は決まっていた。 高い塀を額にして、星空が帯状に広がる。秋を控えて、空が高くなってきた。 レンガや木の塀をくり抜いた窓から草花の覗く、どこか異国の香りのする坂を上る。その先には、煉瓦造りの家があった。 「世界の不思議研究会?」 「今、ここの二階に住まわせてもらってるんだ。」 香清は、花壇に挟まれたアプローチを上がるヤマトに続く。アンティークの木の扉を開けると、ペンションのロビーのような落ち着いた空間で、美女と美少女が白いソファに座ってくつろいでいた。 「ただいま、明、まゆちゃん。」 「お帰りなさい。」 「お帰りなさいませ。」 どうして、彼の才女がここにいるのか。 「いらっしゃい。」 「…お邪魔します。」 「知りたいことは、彼女に聞けばいいわ。」 明は意味深に微笑んだ。 二階の住居には、建物の裏の外階段を登って入る。アパートのように同じ扉が二つ並ぶが、奥の扉はさっきの美女と美少女の相部屋らしい。 一階と同じ、防犯よりも見た目を重視した扉を開けると、すぐにフローリングの6畳間に出る。カントリー調の家具で統一された部屋は女の人の部屋と言われても、男の人の部屋と言われても納得できる、落ち着いた雰囲気だ。 彼女は部屋に着くなり、ベッドの下の衣装ケースからシャツとズボンを出して香清に渡した。 「汗でべたべたするでしょ。とりあえずシャワー使いなよ。」 なんでだよ。 おかしいだろう、恋人でもない男を部屋にあげてシャワー貸すっておかしいだろう。独り暮らしの女の部屋から男物の服が出てくるっておかしいだろう。出てきた服が俺の服より一回りサイズがでかくて彼シャツ状態になるっておかしいだろう。服のサイズもデザインも見覚えがあるっておかしいだろう。 今はシャワーを浴びるヤマトを待っている。先にシャワーを借りた香清は、見覚えのある服を着て彼女を待っている。柔らかい生地で、リラックスできるが、これはヒロカズが普段着にしているものと同じだ。 ベッドを背に、緑のチェックのクッションに座り、出された麦茶を啜って悶々としていると、脱衣所のベージュのカーテンを潜ってヤマトが帰って来た。その恰好にぎょっとする。香清が借りたものと同じサイズの男物のパジャマだ。 「どういうつもりだよ。」 「言葉じゃ説明できないんだよ。」 髪を拭きながら正面に座る彼女から香清は必死で視線を逸らした。湯気を纏って、火照った頬。サイズの大きい服から覗く柔らかな胸元。気持を捨てようとは思っていても、目の前に好きな子がそんな恰好でいたら、何をしてしまうか分からない。否、捨てることはもう諦めている。 彼女が何を求めているのか分からなくて、混乱する。訳が分からず悲しくなる。 「おれ――」 帰るよ、と言おうとした。しかし 「あと五分。」 と止められる。 「五分?」 「あと五分すれば分かるから。」 二人で無言で壁の時計の針を見つめる。一分一秒が長い。カチ、カチ、秒針が12を指せば今日が終わる。 00:00 ヤマトの周りの空間が歪んだ。次元が変わったかのように姿を捉えることができなくなり、再び二回り大きい形で集束した。 「お、まえ…」 「なあ、香清。僕のすべてを受け入れてくれる?」 半分諦めたみたいに笑う彼は、さっきまでいた少女ではなく、親友のヒロカズで、それでも、香清は力いっぱい彼を抱きしめた。 「――と言う訳で、僕は日毎に男と女を行き来する体質で、両方を愛してくれる人以外と契りを交わすと、どちらかの存在が消えてしまうんだ。だから――」 すべてを話した大和は、だからこそ香清が良いのだと言おうとした。しかし、それを香清本人に遮られる。 「俺はどっちのお前も好きだ。でも、自分でも分からないうちに気持ちがどちらかに偏ってるかは分からない。だから、お前を抱けない。でも、今まで通り、俺と一緒に居てくれるか?」 大和はそっと横に首を振る。香清が絶望的な顔をしたけど、そうじゃない。 「もう、覚悟はできてるんだ。」 照を諦めたのは、体質のせいだった。 絵の道を目指したのは体質のせいだった。 恋を諦めたのは体質のせいだった。 でも、今は―― 「どちらかが消えても、そうしたのがお前なら、良い。」 恋のために諦めても良いと思った。 絵は好きだけど、趣味でも良い。 どちらかが消えてもまた友達になる。 「一番欲しいのは、香清だ。」 ねえ香清、笑って。僕をあげるから。 潤んだ目元にそっと口づけると、やっと香清が緩く笑った。ずっと、彼の辛そうな顔ばかり見ていた。大好きな顔なのに、大好きな表情を見れなくて、寂しかった。でも、やっと笑ってくれた。 「香清、可愛い。」 「ヒロカズ…っ」 香清はぎゅっと大和に抱きついて、そのままベッドに押し倒した。 ****** 翌日、一階の扉を開けると、クラッカーの弾ける音と、火薬の匂いが二人を迎えた。 「大和に円佳!おめでとう!」 巧太郎がむせび泣く。 「あんだけべたべたしておいて今更くっつくとかふざけてんじゃねぇぞ。」 圭斗が香清に蹴りを入れる。 「僕に隠し事とかできると思ったの?」 薫が黒く微笑んだ。 「ヤマトちゃん、これからは隠し事は無しだからね!」 聡美が大和の背をたたき、 「お二人さん、視線お願いしまーす。」 幻十郎がカメラを構える。 5人だけじゃない。色紙の輪っかや、ティッシュの花で飾られた室内には、大和の幼馴染の太陽に光に陽に千晶、もちろん明もいて、 「おい、お前!」 香清が照に食って掛かった。 「俺、あなたより先輩なんですけど。」 「全部知ってたのかよ!」 プンプン怒る香清に、照はツンと横を向いてしまった。 「騒がしいわねぇ。」 明が呆れたように言うが、その口元は笑っている。大和はカウンターに座って騒ぎを一望する彼女に近づいた。 「ありがとう。」 「別に、私はただ彼らをここに呼んだだけよ。」 それでも最初から最後まで見守ってくれたのは、明だよ。 またその翌日、ヒロカズは無事にヤマトになり、香清は「やるじゃない。」と聡美に背中を叩かれて、大和と香清の背中に一足早い秋が来た。
芸術奇行<完>